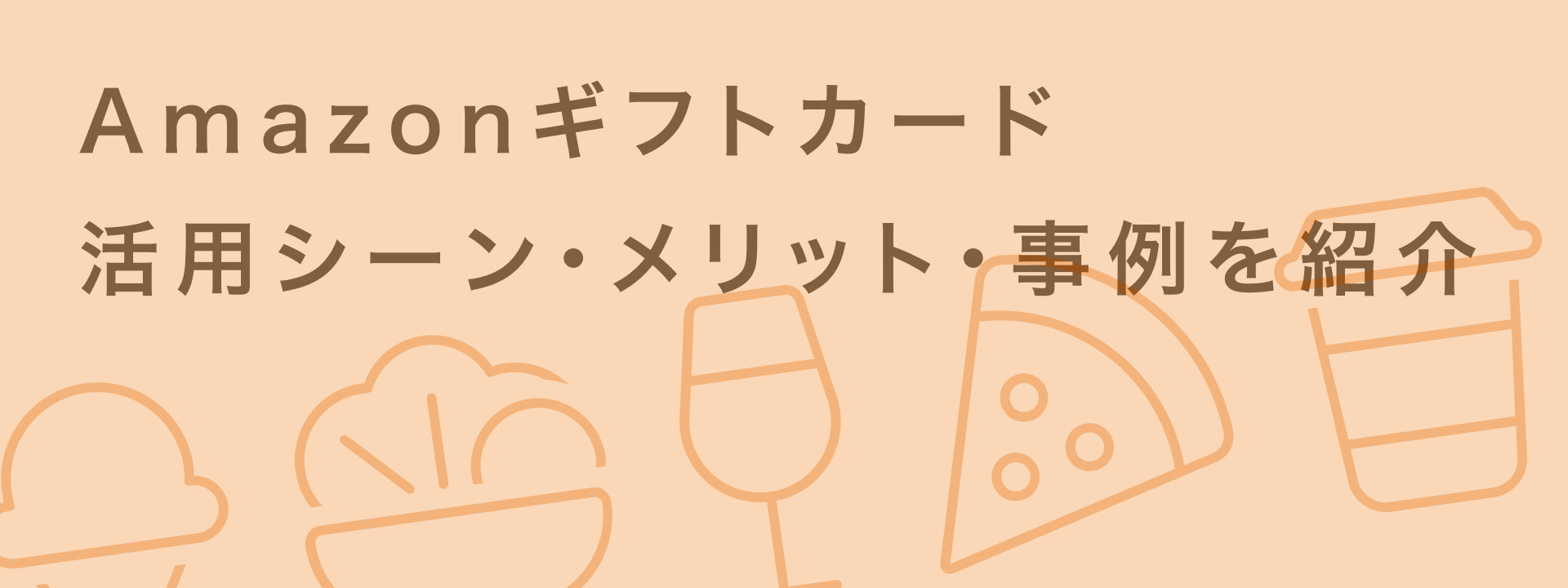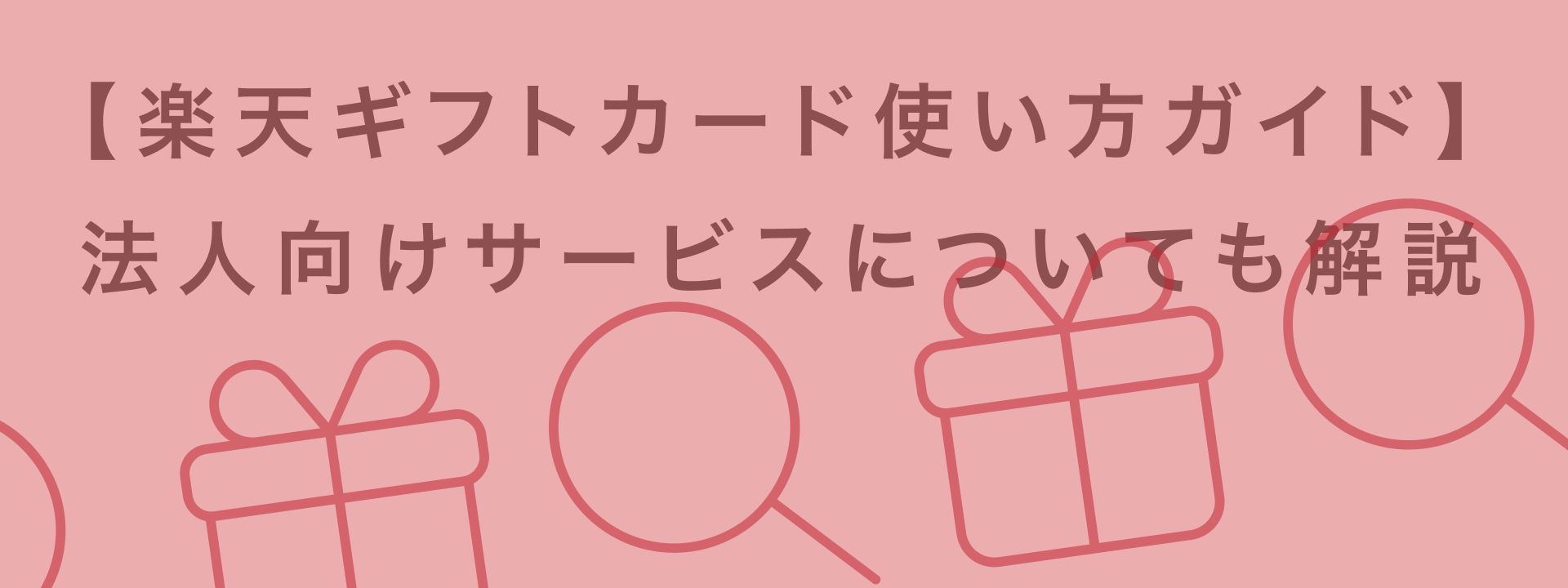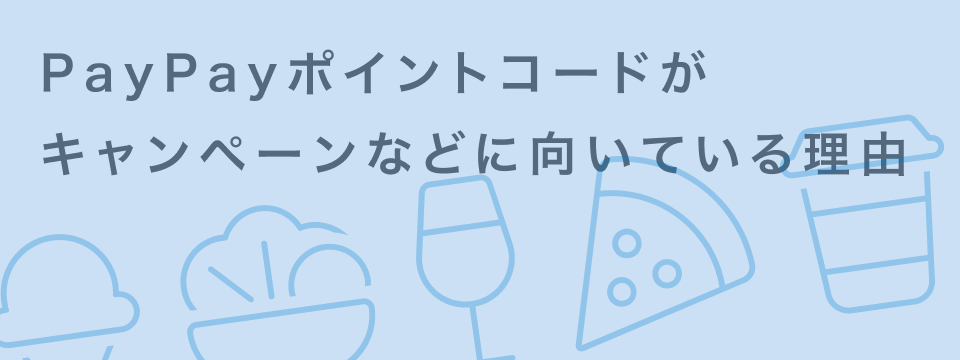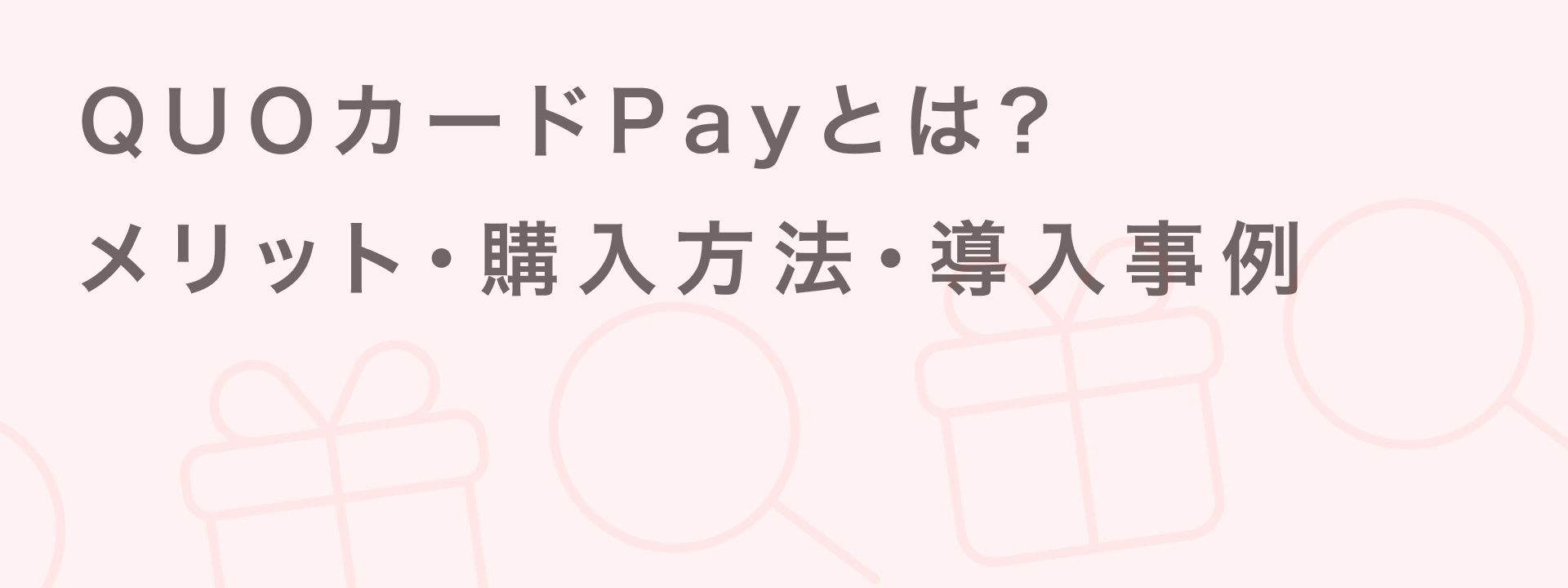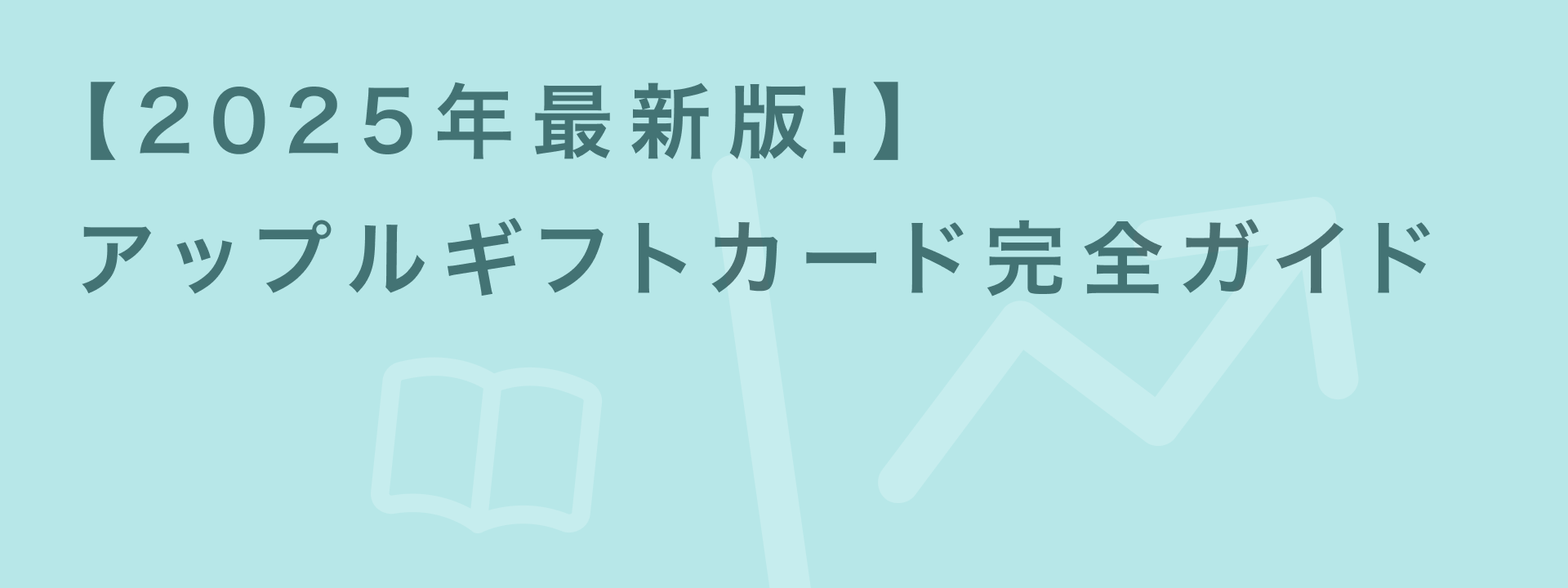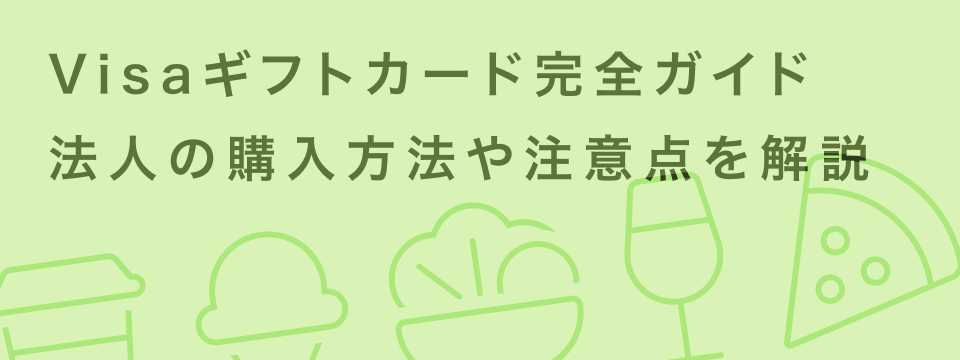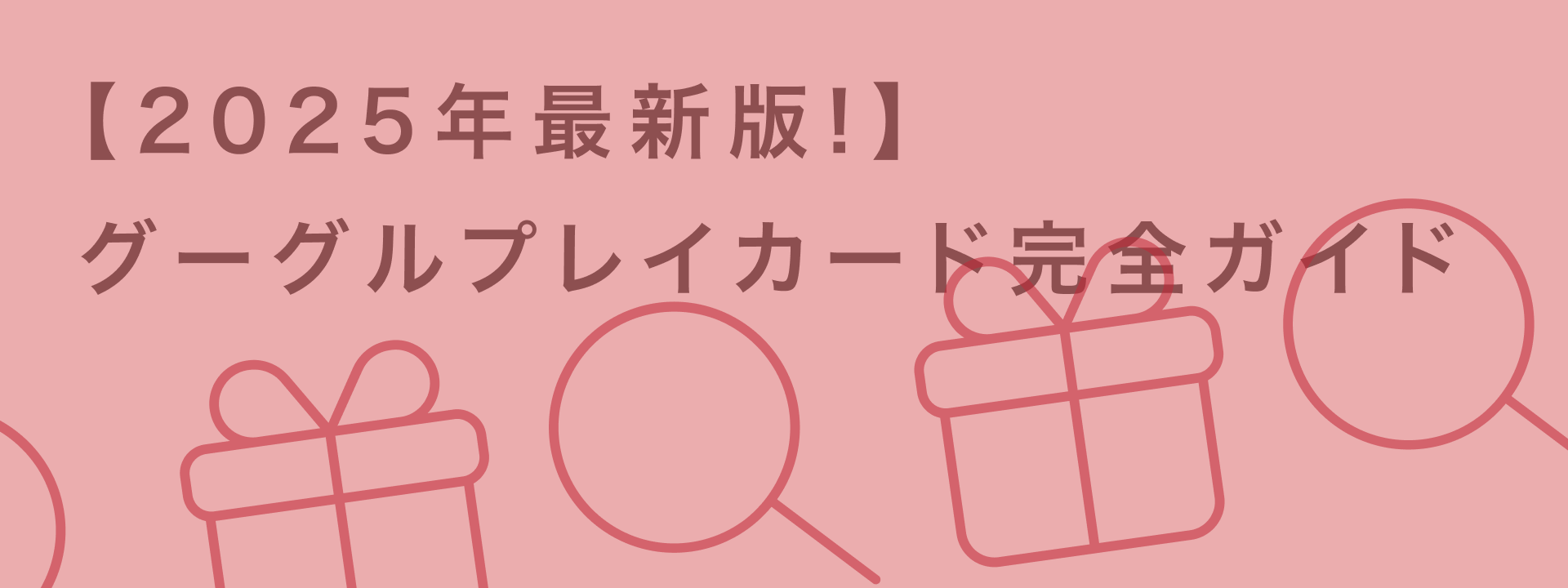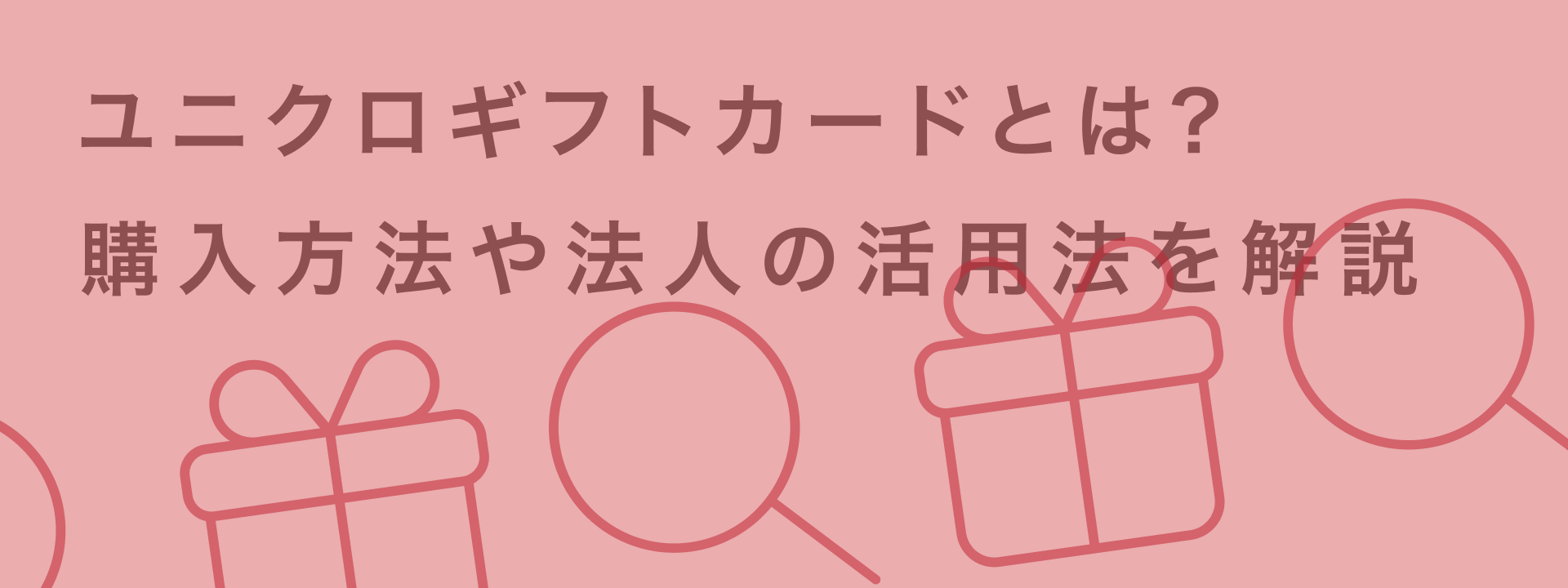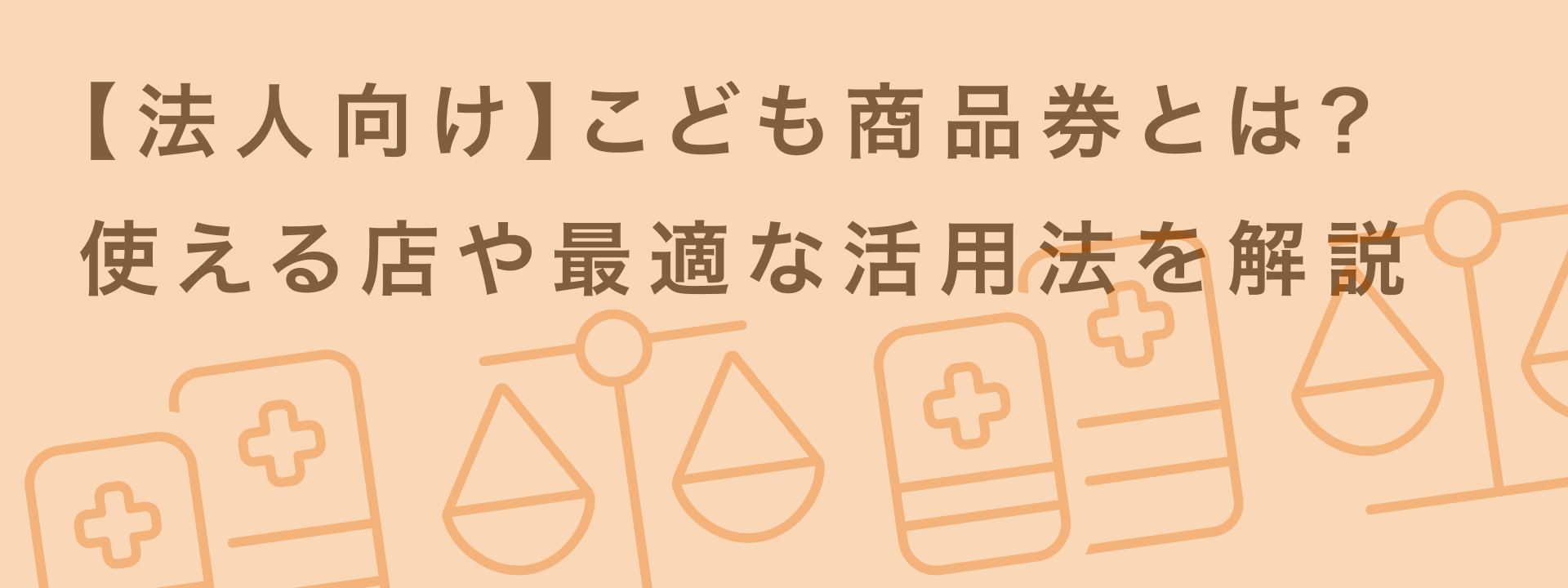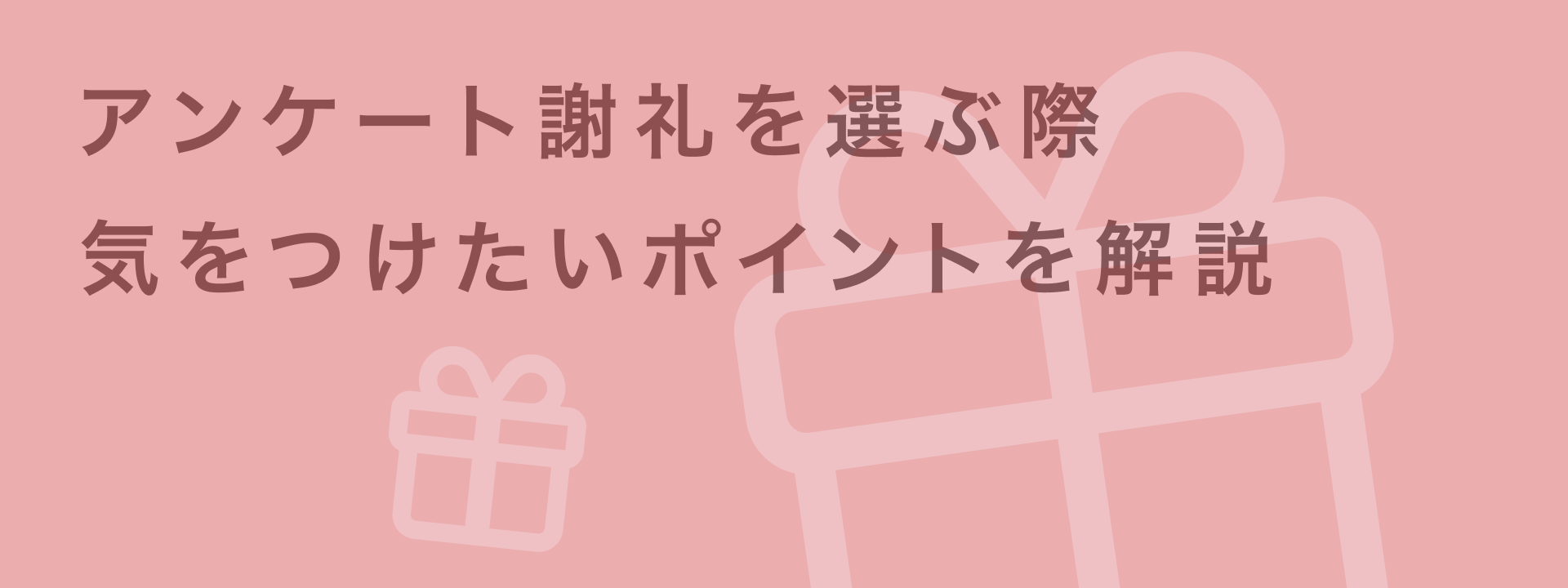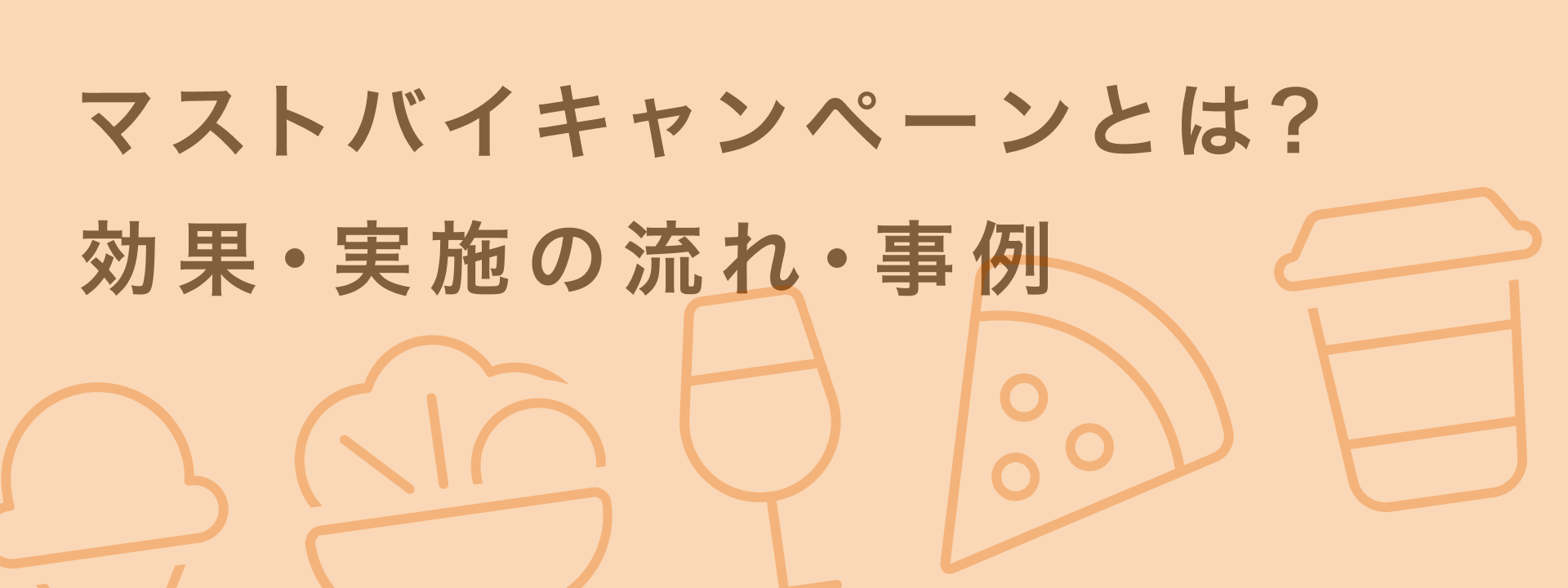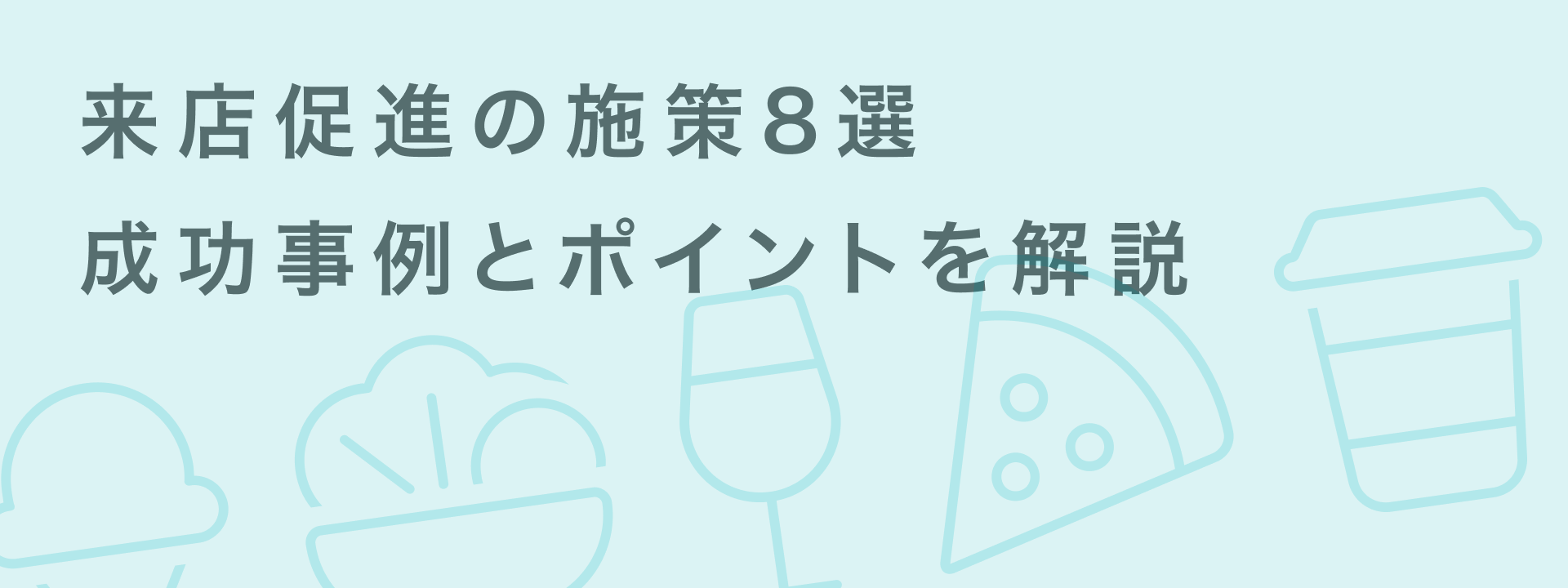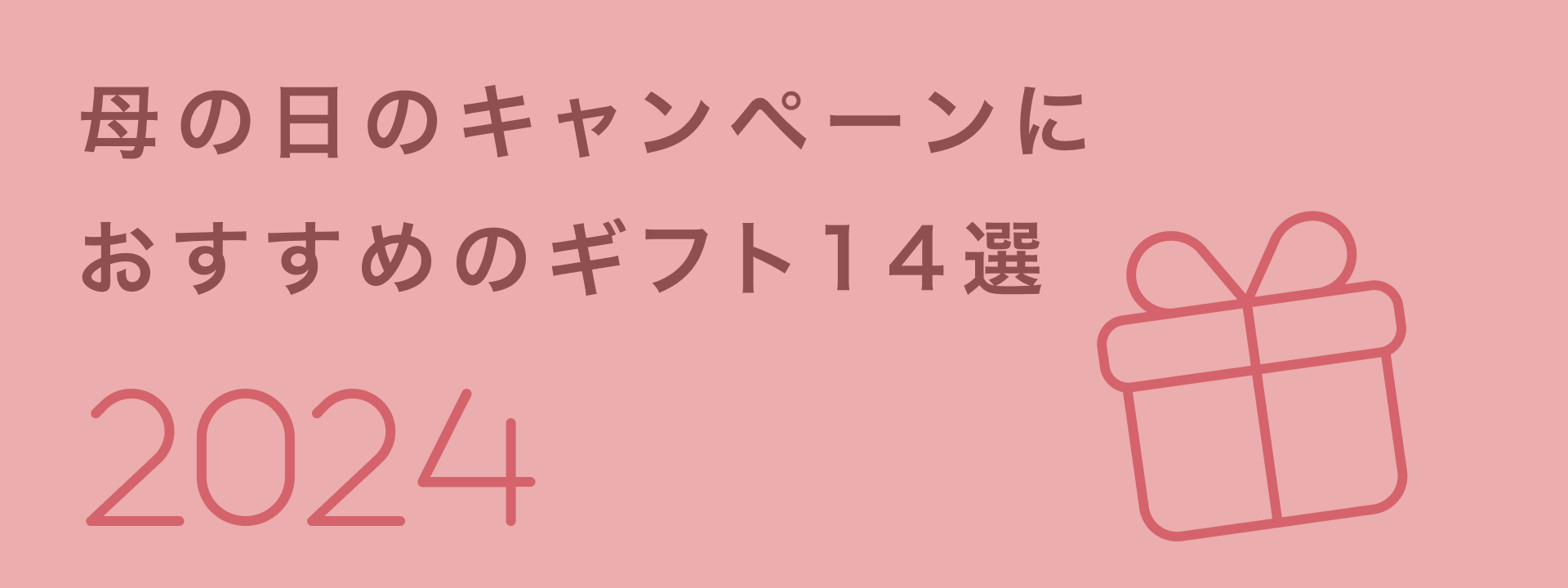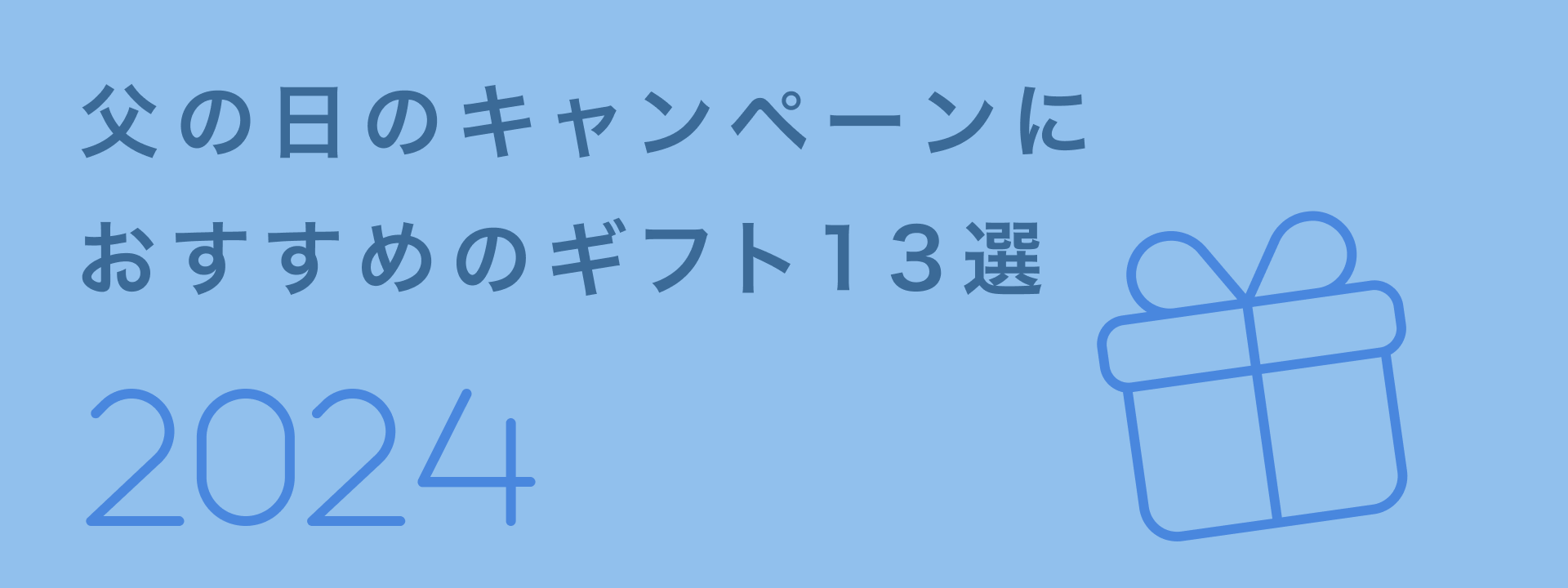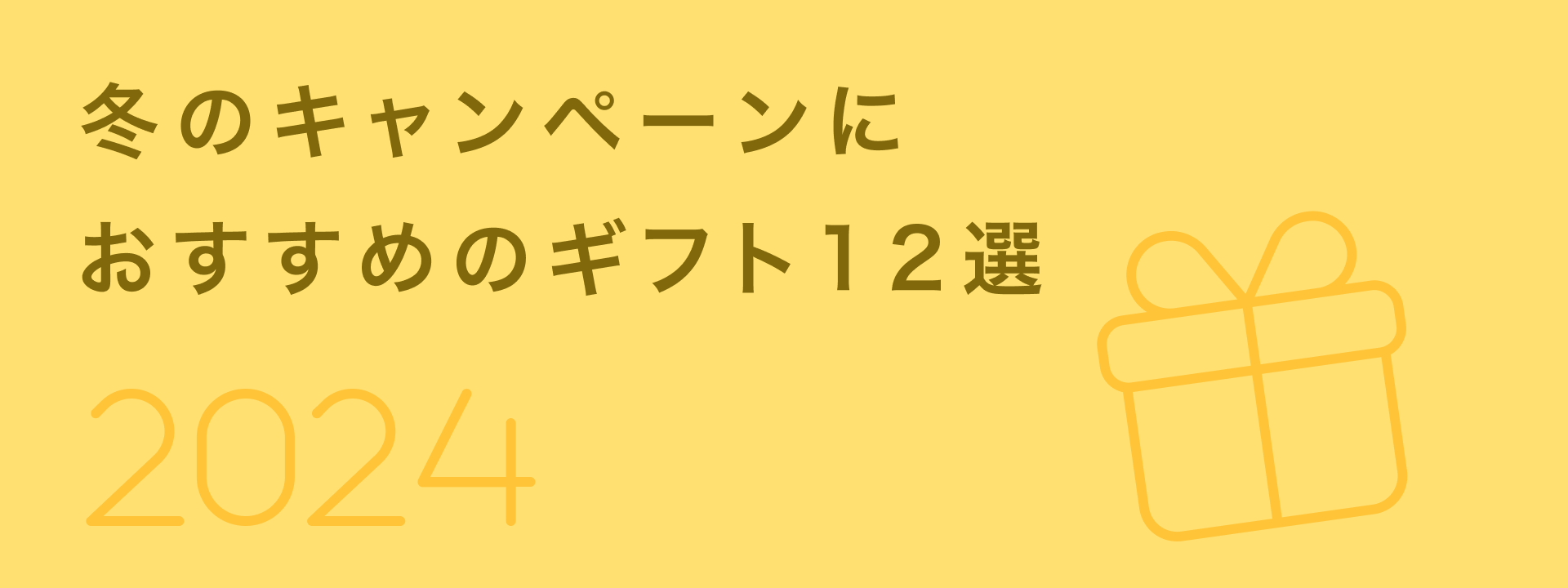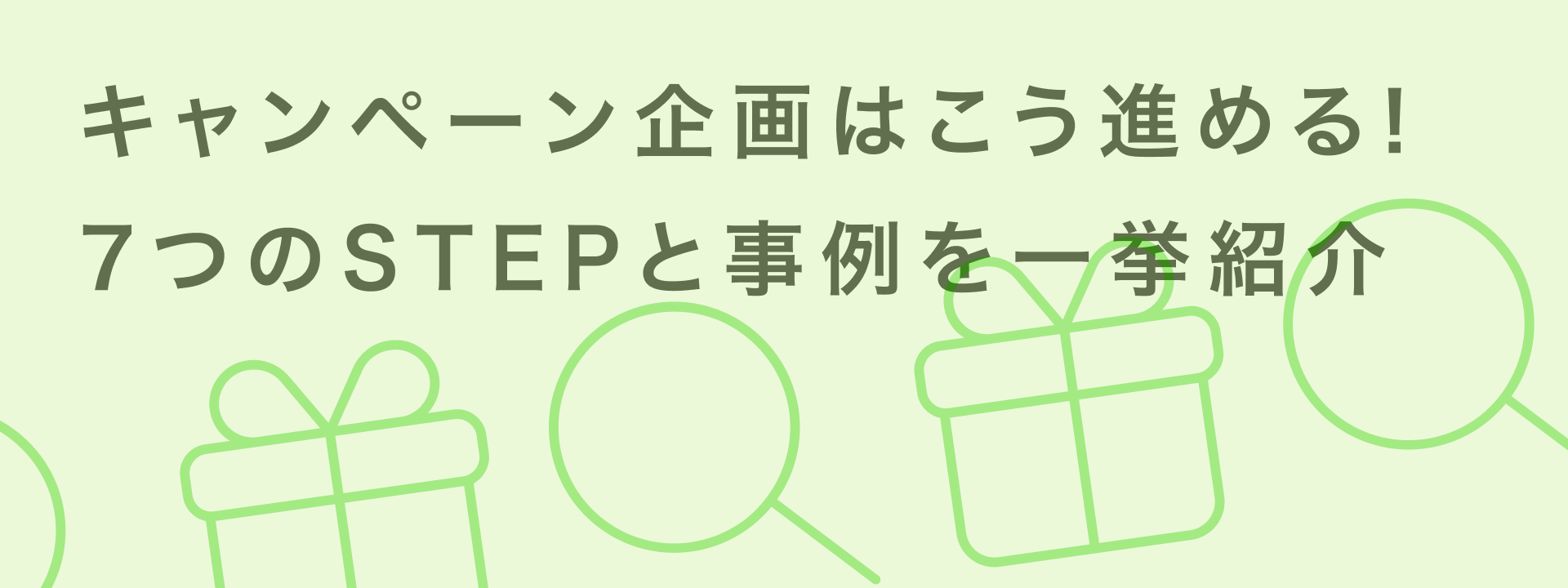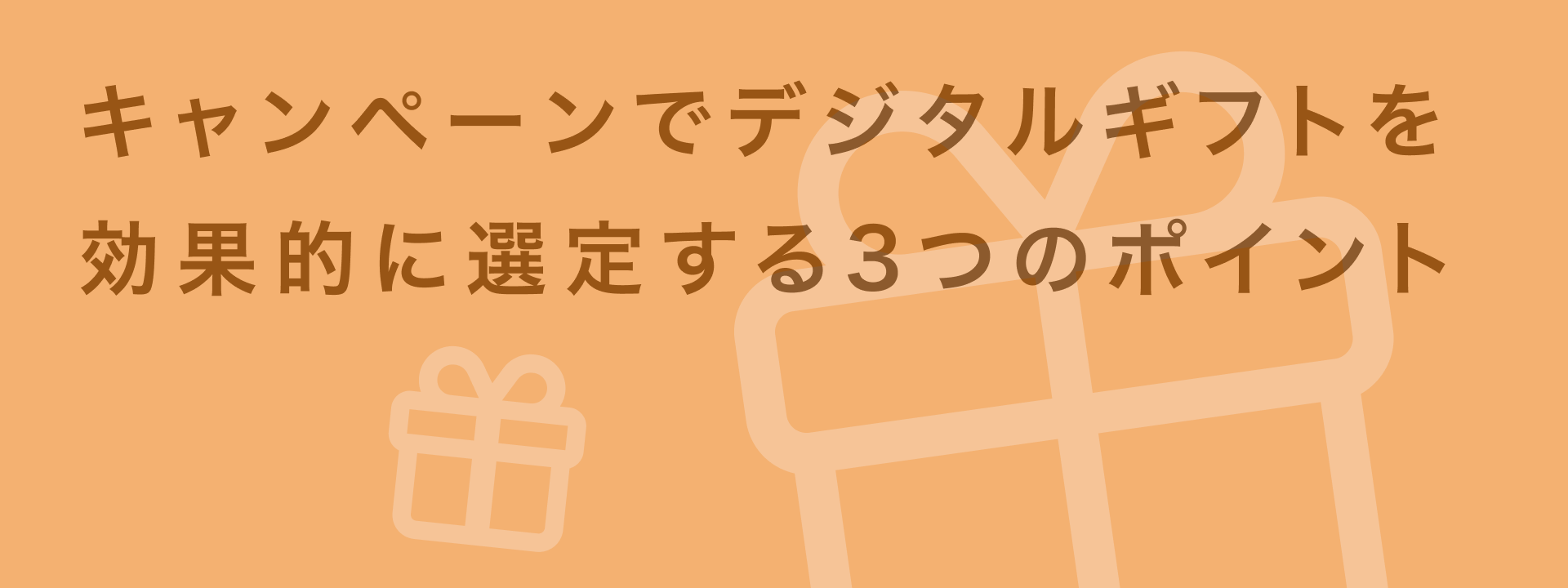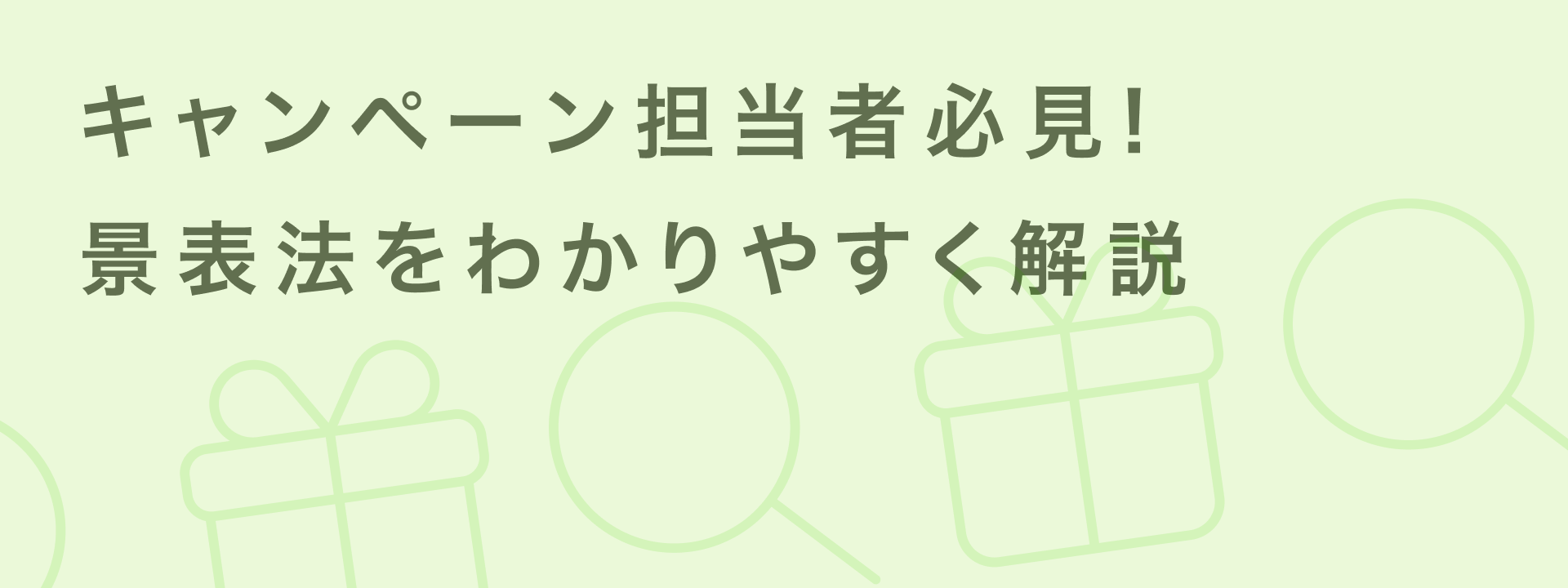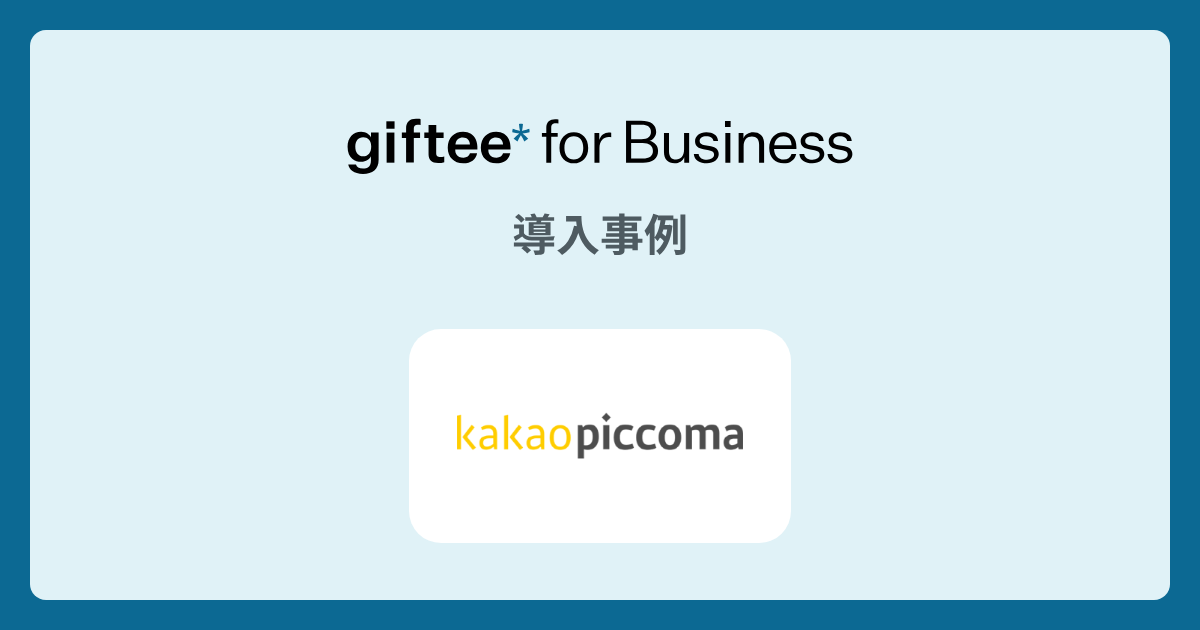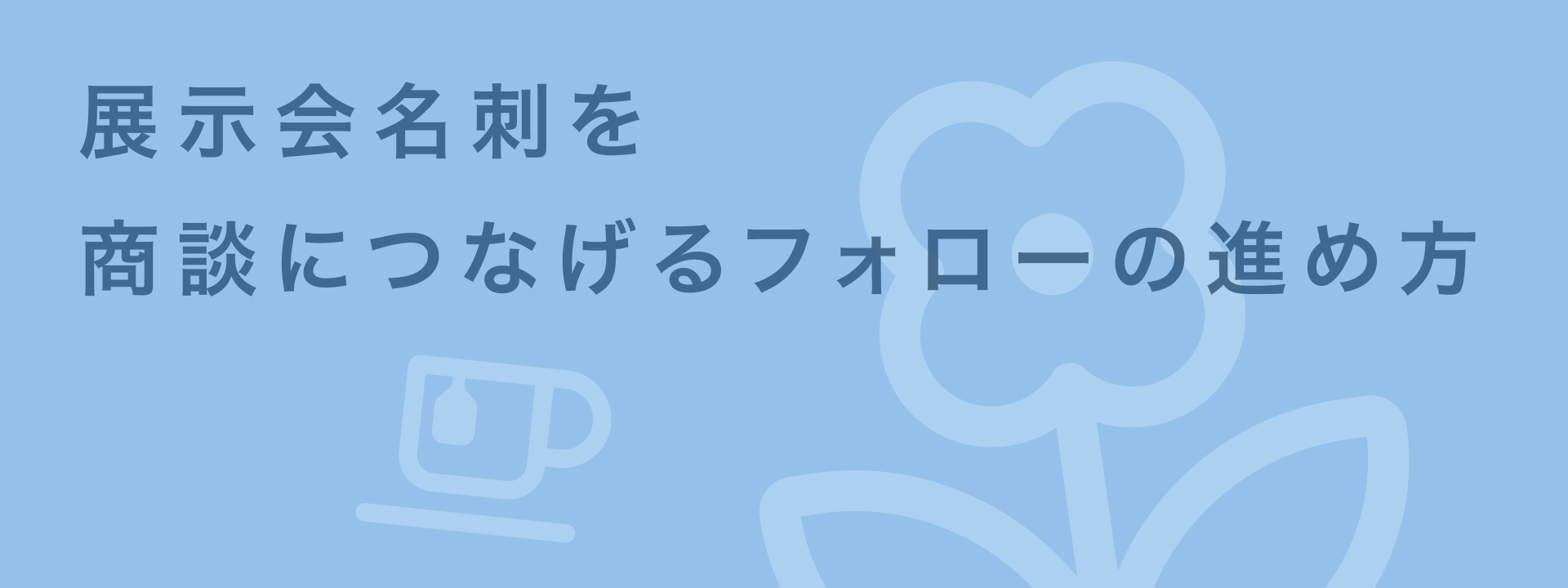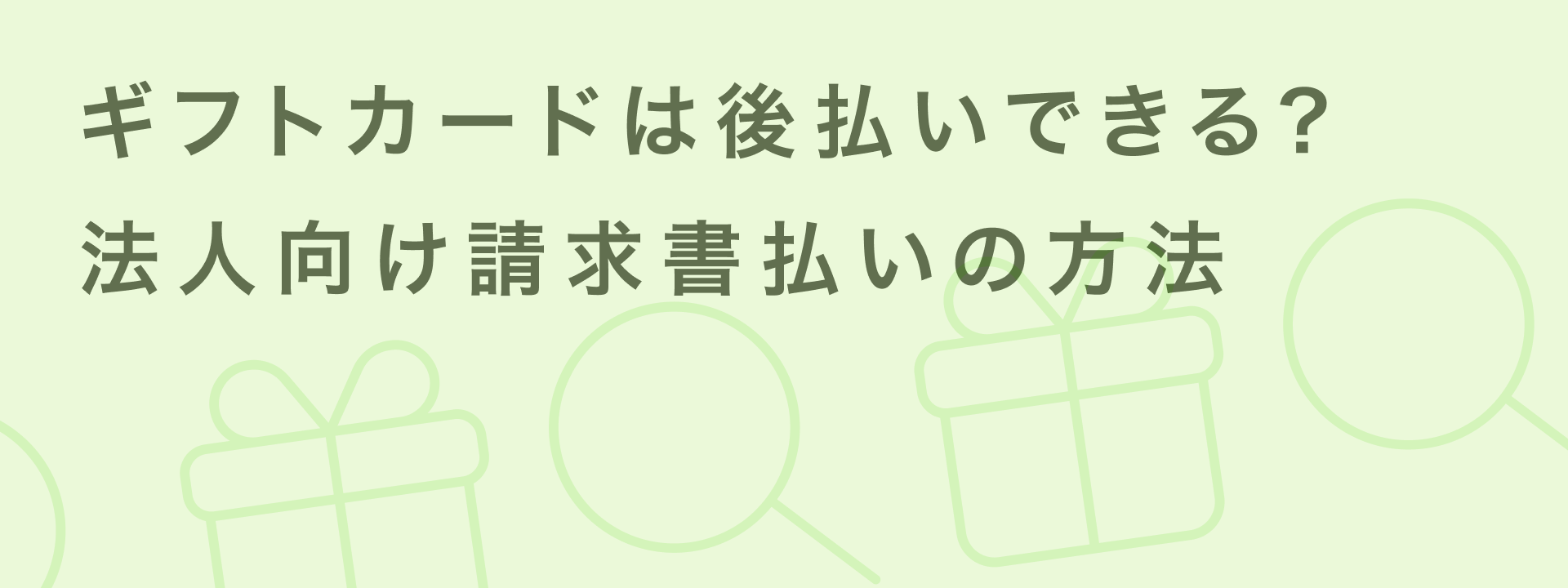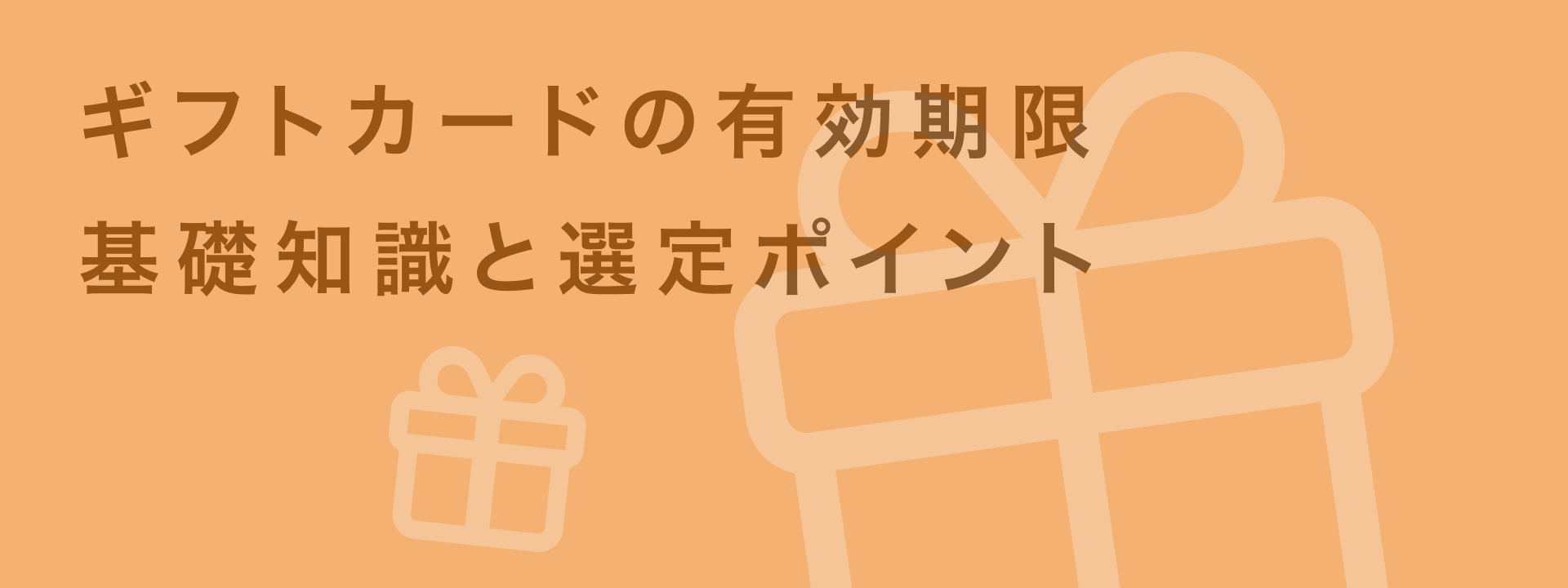デジタルギフトとは?法人利用で人気の種類と導入メリット・活用シーン
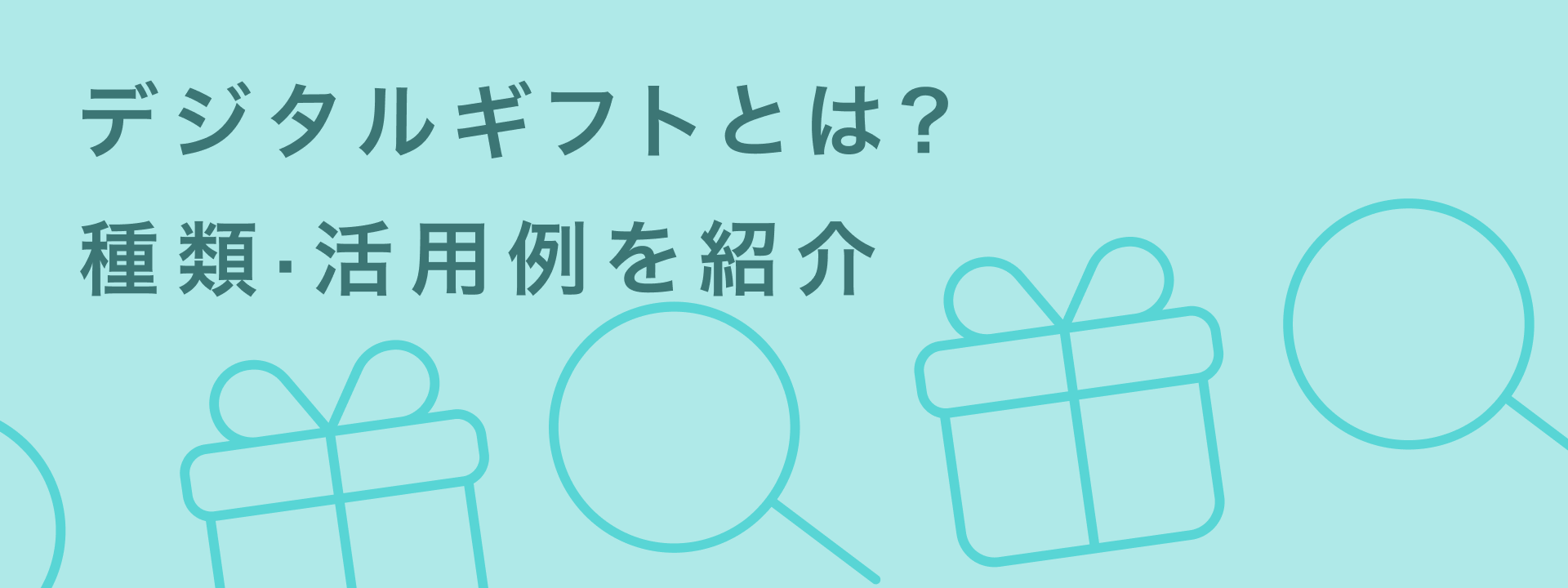
近年、自社のマーケティングやキャンペーンの効果を高める目的で、デジタルギフトを活用する企業が増えています。
デジタルギフトはオンラインで贈れるギフトの一種です。物理的なアイテムではなくデジタル形式で提供され、ユーザー側もスマートフォンで簡単に利用できます。また、目的や施策に応じてギフトの内容をカスタマイズできるほか、受け取り手が好きなギフトを選べる仕組みもあり、幅広いビジネスシーンで活用されています。
また、その利便性の高さから受け取るユーザーの満足度も高い傾向にあります。結果として、企業への信頼感や親しみやすさが高まり、顧客との関係性を深めるきっかけにもなります。
本記事では、デジタルギフトの種類や活用例、活用するメリットや注意点などを解説しています。また、すでにデジタルギフトを活用している企業の事例も紹介しているので、キャンペーンの景品や福利厚生などでデジタルギフトを検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
デジタルギフトの活用を検討中のご担当者様へ
もし現在、このようなお困りごとがありましたら、ぜひ「ギフトマーケティングの基本」をご覧ください。
・そもそもギフトを活用したキャンペーンでどういった成果が得られるのか? ・ターゲットが本当に欲しい、魅力あるインセンティブ設計をしたい
本資料では、インセンティブ施策の変遷とギフトマーケティングについての基本やこれからの可能性について活用事例と合わせて紹介しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
デジタルギフトとは
デジタルギフトとは、オンラインで贈れるギフトの一種です。物理的なアイテムではなくデジタル形式で提供され、ギフトカードやクーポン、電子マネーなどが含まれます。
「主な顧客層が高齢者の場合、デジタルギフトは使いにくいのでは?」と不安に思う担当者の方もいるかもしれませんが、実際にはスマートフォンがあれば簡単に利用できます。
スマートフォンでメールなどからURLをタップ
(選べるタイプの場合)ギフト一覧から交換したいものを選択
表示された引換券を店舗で提示
このように簡単な手順で利用できるため、高齢者を含む幅広い層にとって活用しやすいギフトです。また、コロナ禍で直接物を贈ることが難しくなった背景もあり、より一層キャンペーンや福利厚生などのインセンティブとしての利用が増え、多くの企業に採用されています。
個人向けサービスと法人向けサービスの違い
まず、デジタルギフトサービスは、個人向けサービスと法人向けサービスの2種類が存在します。
個人向けサービスの場合、お祝い事などのプレゼントとしての利用が想定されており、メッセージ機能が充実していることも多いです。たとえば、メッセージの背景のイラストの種類が豊富だったり、現物のギフトカードにして名入れや熨斗を付けられたりもします。
一方、法人向けサービスは、キャンペーンへの活用や福利厚生としての利用を想定しているため、顧客への一斉送信や大量発注などに対応しているサービスが多くあります。
施策支援としてギフト配布ソリューション(即時抽選システムやポイント管理システムなど)を提供しているサービスもあるため、そのようなサービスを選ぶとより施策を効果的に実施できるでしょう。
デジタルギフトと現物ギフトの使い分け
ギフト施策には、デジタルギフトと現物ギフト(従来のギフト)の2つの形があります。それぞれに適したシーンが異なるため、目的に応じて使い分けることが重要です。
デジタルギフトが適しているシーン
スピードや効率を重視する施策では、デジタルギフトが最も効果的です。たとえば、SNSキャンペーンやアンケート謝礼など、多くの人に一度に配布したいときに便利です。住所や氏名を取得する必要がなく、メールやLINEだけで送れるため、個人情報の扱いもシンプル。発送や在庫管理の手間もありません。
また、「今すぐ配りたい」「その場で当選を知らせたい」といった即時性が求められる企画にも強みがあります。突発的なキャンペーンにも対応でき、発送費や梱包費を抑えられる点も大きなメリットです。少額のインセンティブを効率的に配りたい場合にも、コストパフォーマンスが高くなります。
ポイント
- 大量配布やスピード重視のキャンペーンに強い
- 個人情報の取得・管理がシンプル
- 発送や在庫管理のコストを削減できる
現物ギフトが適しているシーン
一方で、「特別感」や「記念性」を重視するシーンでは現物ギフトが効果的です。高額商品の購入特典や、永年勤続表彰、VIP顧客への贈答など、“モノとして残る価値”を伝えたいときに向いています。実際に手に取れることで満足感や感動が生まれやすく、ブランドの世界観を体験してもらう演出にもつながります。
また、ターゲットが高齢者層などデジタルに不慣れな場合は、実物を受け取る安心感が大切です。ギフトの“体験”そのものがメッセージになるシーンでは、現物の存在感が活きてきます。
ポイント
- 特別感を演出したい施策に適している
- ブランドや商品の価値を直接伝えられる
- デジタル操作が苦手な層にも安心
このように、デジタルギフトは「スピード・効率・利便性」を重視する施策に、現物ギフトは「特別感・記念性・実物の価値」を重視する施策に適しています。目的に応じて使い分けることで、より効果的なギフト施策を実現できるでしょう。
デジタルギフトの種類

冒頭でもお伝えしたように、デジタルギフトはターゲットや目的に応じて選ぶことが大切です。そのためには、どのような種類があるのかについて理解しておきましょう。
▼デジタルギフトの種類
電子マネー
ポイント
商品引換券(コーヒーチケットなど)
ギフトカード(図書カードなど)
体験型ギフト(レジャーチケットなど)
カスタマイズ型ギフト
電子マネー
電子マネーは、デジタル上で管理・使用できる通貨の一種です。
利用可能な店舗であれば、実店舗とオンラインサービスのどちらの決済でも使用できます。そのため、受け取った人が自分の欲しいものを購入するといったように、自由に使用することが可能です。たとえば、nanaco、WAON、交通系ICカードなどのようなものがあります。
また、現物の商品やギフト券と異なり、メール・LINE・SNSなどで瞬時に送付でき、受け取った人もすぐに利用できます。管理や配布も簡単です。
ポイント
ポイントは、電子マネーと同様に即時性と利便性が高く、どのような施策にも幅広く活用できます。一口にポイントといっても、PayPayポイントやdポイント、楽天ポイントなど、種類はさまざまあります。
そのため、受け取った人が利用しやすいポイントに交換できるように、複数の交換先からポイントの使用先を選択できる方が便利です。また、受け取った人の利便性を考慮し、有効期限などを事前に確認しておきましょう。
商品引換券
商品引換券は、オンライン上で商品引換券を表示し、実店舗で使用できるデジタルギフトです。たとえば、カフェ、コンビニエンスストア、ファストフードなどの商品と交換できます。受け取った人はコードを店舗で提示することで、引換券の商品を受け取れます。
しかし、受け取ったものの利用できないといったことがないように、商品引換券を利用する際は以下の点を確認しておきましょう。
引き換えできる商品のニーズ
有効期限
使用可能な店舗
幅広いニーズに対応したい場合は、複数の店舗から選べるサービスがおすすめです。
ギフトカード
ギフトカードは従来も紙チケットの形で贈られていたギフトですが、デジタルギフトでいうギフトカードはそれをデジタル化したものです。デジタル化することで、現物のギフトカードの持ち歩きが不要になります。
また、対応している店舗であれば、実店舗以外にオンラインショップでの利用も可能です。
提携店舗が多いギフトカードを選べば、受け取った人が好きな物を購入したり、スーパーでの買い物など日常的な支払いに利用したりできます。
ギフトカードを選ぶ際には、利用できる店舗数や有効期限をあらかじめ確認しておきましょう。
体験型ギフト
体験型ギフトは、受け取った人が指定のサービスを体験できるギフトです。たとえば、以下のような種類があります。
ホテルや旅館の宿泊
クルージング
乗馬体験
陶芸
スパ
エステ
アフタヌーンティー
1つに限定された体験ギフトもありますが、受け取った人が自分で選べる体験ギフトもあります。福利厚生や高額商品をプレゼントしたい場合に活用しやすいギフトと言えるでしょう。
カスタマイズ型のデジタルギフト
カスタマイズ型のデジタルギフトとは、そのギフトサービスの中で利用できるポイント内で、好きなギフトに交換できるサービスです。
たとえば、1,000ポイントを受け取ったら、数ある商品の中から500ポイントを電子マネーに、300ポイントをよく利用するポイントに、200ポイントを商品引換券に交換するといった使い方ができます。
複数の商品と交換できるため、ここまで紹介したギフトの中でもっとも利便性が高く、どのようなシーンでも活用しやすいデジタルギフトと言えるでしょう。
人気のデジタルギフトの一例

実際によく利用されているデジタルギフトには、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。個人向けでも企業向けでもよく利用されているデジタルギフトには、以下のような種類があります。
Amazonギフトカード
Amazonギフトカードは、法人キャンペーンにおいて最も人気の高いデジタルギフトです。ECモールのAmazonでの商品購入はもちろん、Amazon Pay利用可能店舗での決済にも利用でき、幅広い世代に対応できる汎用性の高さが特徴です。オンラインとオフライン両方で利用可能なため、参加者の居住地や年齢を問わず高い満足度が得られます。
こんなシーンにおすすめ
- 幅広いターゲット層にアプローチしたい
- まずは集客、参加率の底上げを行いたい
- 景品選びに悩まず、安定した効果を求めている
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、Amazonギフトカードの活用方法や法人向けの購入方法について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
楽天ギフトカード
楽天ギフトカードは、楽天市場での商品購入や楽天グループ各サービスでの支払いに利用可能なギフトです。楽天ポイントとの相性が良く、楽天経済圏ユーザーに特に人気があります。楽天カードや楽天銀行利用者への訴求力が高く、ECサイトでの購買促進キャンペーンに効果的です。
こんなシーンにおすすめ
- 楽天経済圏ユーザーがターゲット
- ECサイトでの購買促進を目的とするキャンペーン
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、楽天ギフトカードの特徴や実施方法について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
PayPayポイントコード
PayPayポイントコードは、PayPayで利用できるポイントギフトです。コンビニ、飲食店、オンラインショップなど幅広い店舗で使用可能で、特に若年層からの支持が厚いのが特徴です。キャッシュレス決済の普及とともに利用者が拡大しており、現代的なキャンペーンには欠かせないギフトとなっています。
こんなシーンにおすすめ
- 20~40代をメインターゲットとするキャンペーン
- キャッシュレス決済の利用者にアプローチしたい
- トレンド感のあるデジタル施策を重視する
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、PayPayポイントコードの特徴や法人活用事例について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
QUOカード(QUOカードPay)
QUOカードPayは、全国のQUOカード加盟店(コンビニ、書店、ファミリーレストランなど)で利用可能な定番ギフトのデジタル版です。実店舗での利便性が高く、年齢を問わず使いやすいため、法人の福利厚生や謝礼として、また自治体でも長年愛用されています。デジタル版の「QUOカードPay」も誕生し、より配送コストの削減と即時配布が可能となりました。
こんなシーンにおすすめ
- 安定した認知度と信頼性を重視する
- 実店舗での利用を想定したキャンペーンを企画する
- 地域住民への給付を想定している
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、QUOカードPayの特徴や法人での効果的な活用方法について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
Apple Gift Card
Apple Gift Cardは、App StoreやiTunes Store、Apple Musicなどのデジタルコンテンツの購入に利用できるギフトカードです。iPhoneやMacユーザーにとって魅力的なギフトであり、特にアプリやゲーム、音楽コンテンツを楽しむユーザー層への訴求力が高く、デジタルネイティブ世代をターゲットとしたキャンペーンに最適です。
こんなシーンにおすすめ
- Apple製品ユーザーをターゲットとするキャンペーンで活用したい
- デジタルコンテンツ関連のマーケティングのインセンティブとして
- 若年層向けのエンターテインメント系キャンペーンでの利用を想定している
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、Apple Gift Cardの特徴や法人での活用方法について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
図書カードNEXTネットギフト
図書カードNEXTネットギフトは、全国の図書カード取扱店舗で利用でき、書籍・雑誌の購入や一部のオンライン書店・電子書籍にも対応したデジタルギフトです。教育関連企業や知的好奇心の高いターゲット層に特に人気が高く、学習支援の意味合いも持つ価値の高いギフトとして評価されています。
こんなシーンにおすすめ
- 教育関連企業やサービスのキャンペーンに活用したい
- 知的好奇心の高いターゲット層にアプローチしたい
- 自己研鑽やスキルアップを促進したい
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、図書カードネットギフトの特徴や効果的な活用方法について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
Visaギフトカード
Visaギフトカードは、国内外のVisa加盟店で利用可能な汎用性の高いデジタルギフトです。クレジットカードと同様、使い勝手が良く、オンライン・オフライン問わず幅広い用途に活用できます。高額景品としても人気が高く、特別感のあるキャンペーンに適しています。
こんなシーンにおすすめ
- 高額景品を用意したい
- 受け取り手の自由度を重視する
- 越境ECでの利用を想定したキャンペーン
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、Visaギフトカードの特徴や法人での購入方法について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
Google Play ギフトカード
Google Play ギフトカードは、Google Play ストアでのアプリ購入、ゲーム内課金、映画レンタルなどに利用できるデジタルギフトです。Androidユーザーにとって価値の高いギフトであり、特にモバイルゲームやデジタルコンテンツを楽しむユーザー層への訴求力が高く、エンターテイメント系キャンペーンに最適です。
こんなシーンにおすすめ
- Androidユーザーをターゲットとするキャンペーンに利用したい
- ゲームやエンターテインメント関連のマーケティングに活用したい
- モバイルアプリの利用促進を図りたい
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、Googleプレイギフトカードの特徴や活用方法について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
ユニクロeGift Card
ユニクロeGift Cardは、全国のユニクロ店舗や公式オンラインストアでご利用いただけるプリペイド式のデジタルギフトカードです。シンプルで使いやすいアイテムが揃い、老若男女から愛されるユニクロだからこそ、幅広い層に喜ばれるギフトとして活用されています。
こんなシーンにおすすめ
- ファッションアイテムをギフトとして贈りたい
- 幅広い世代にアプローチできるギフトを求めている
- 日常的に使える実用的なギフトを提供したい
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、ユニクロギフトカードの特徴や法人での活用方法などについて解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
こども商品券e-Gift
こども商品券e-Giftは、1987年から長年にわたり、個人の贈り物や企業・自治体の景品や配布物として利用されてきた商品券のデジタル版です。子ども用品だけでなく、タクシーや家事代行にも使えるため、妊婦さんにも喜んでもらえるギフトです。
こんなシーンにおすすめ
- 子育て世代や妊婦さん向けの支援施策を実施したい
- 出産応援や育児支援の意味を込めたギフトを贈りたい
- 家族向けサービスや企業のファミリー層にアプローチしたい
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、こども商品券の特徴や活用シーンなどについて解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
デジタルギフトの価格帯・予算感
デジタルギフトを活用する際、「実際にどれくらいの予算が必要なのか」は多くの企業が気になるポイントです。ここでは、デジタルギフトの価格帯や予算設定の考え方について解説します。
最小金額・ロット
デジタルギフトは、1円単位から設定できるサービスもあり、少額のインセンティブにも柔軟に対応できます。
主な価格帯
- 少額:50円〜500円(Webアンケート、資料請求謝礼など)
- 中額:500円〜3,000円(SNSキャンペーン、来店促進など)
- 高額:3,000円〜10,000円以上(福利厚生、永年勤続表彰など)
また、最小ロット(最低購入数)もサービスによって異なります。即時購入制のサービスでは1件から発行可能なものもあれば、アカウント登録制のサービスでは一定金額以上の購入が必要な場合もあります。
手数料の有無
デジタルギフトサービスを利用する際、サービスによって手数料体系が異なります。主な料金体系は以下の通りです。
主な料金体系
- ギフト額面のみ:手数料なし、ギフトの額面金額のみで利用可能
- ギフト額面 + 発行手数料:1件あたり発行手数料が発生
- 月額利用料 + ギフト額面:月額の基本料金 + ギフト額面
利用頻度や規模に応じて、最適な料金体系のサービスを選ぶことが重要です。少額・単発利用なら手数料なしのサービス、大規模・継続利用なら月額制のサービスが適している場合が多いでしょう。
デジタルギフトの活用例
ここまでデジタルギフトの種類を紹介しましたが、企業がどのように活用するのかについても見てみましょう。デジタルギフトは、以下のように活用できます。
アンケート・資料請求・見積もり謝礼
SNSやマストバイキャンペーンの景品
来店促進キャンペーンのインセンティブ
自治体の市民向け施策の交付物
福利厚生・社内インセンティブ
シーズナルキャンペーン
では、具体的な活用方法を解説します。
アンケート・資料請求・見積もり謝礼

アンケート・資料請求・見積もりをしてくれた謝礼としてデジタルギフトを活用できます。デジタルギフトは数十円・数百円から利用できるため、条件を満たした人が必ず受け取れるような、数を用意しなければならない場合にも活用しやすいです。
また、謝礼を用意することで、多くの人にアンケート回答や資料請求、見積もりをしてもらえる可能性が高まります。
たとえば、アンケートなら回答してくれた人に対し、後日メールなどでデジタルギフトを送付します。また、デジタルギフトサービスの中には、アンケート回答後にその場でデジタルギフトを贈れるツールを提供しているところもあります。
アンケート謝礼に関しては、下記記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
SNSやマストバイキャンペーンの景品

SNSでのフォロー&リポストキャンペーンや、対象商品を購入することで応募できるマストバイキャンペーンなどの景品としても、デジタルギフトが役立ちます。
たとえば、Xのフォロー&リポストキャンペーンの場合は、期間内に条件を満たした人の中から即時抽選する形式のほかに、条件を満たしたらその場で全員当たる形式にもできます(どちらも基本、抽選ツールが必要となります)。キャンペーンを実施することで、効果的にフォロワーを増やしてリポストで情報を拡散させられるでしょう。
また、マストバイキャンペーンの場合は、商品写真やレシートなどを提示することで応募できます。景品を用意することで、購買行動を促進できるでしょう。
来店促進キャンペーンのインセンティブ

来店促進キャンペーンのインセンティブとしてデジタルギフトを活用することも可能です。
特に、受け取り手が選べる形式のギフトを利用すれば、参加者の居住地・性別・年齢などを問わず、満足度の高いギフトをインセンティブとして提供できます。
デジタルギフトは少額でも設定できるため、上限数がないインセンティブとして取り入れやすいでしょう。
自治体の市民向け施策の交付物
自治体の「子育て支援」や「地域復興」などの施策の交付物としても、デジタルギフトを活用できます。
たとえば、子育て支援として出生届を提出した家庭に、実用的なベビーグッズを取り揃えて、受け取り手がその中から自由に選べるギフトを交付するケースがあります。
また、マイナンバーカードの申請割合が少ない年代を対象に、マイナカードを発行したら地域のお店で使えるデジタルギフトを付与するといった活用方法もあります。
福利厚生・社内インセンティブ
デジタルギフトはギフトの種類や価格帯が幅広いため、福利厚生や社内インセンティブとしても活用できます。たとえば、以下のようなケースで利用できるでしょう。
永年勤続表彰
営業優秀者へのインセンティブ
社内イベントの景品
周年記念のプレゼント
社員の記念日のプレゼント
従業員との関係性・満足度向上のためにも気軽に活用できます。
デジタルギフトはさまざまなビジネスシーンで活用できます。では、これらの活用例を踏まえて、実際にデジタルギフトを使ったキャンペーンを企画する際にはどのようなステップで進めればよいのでしょうか。
シーズナルキャンペーン
シーズナルキャンペーンとは、季節や特定の時期に合わせて実施される広告キャンペーンのことです。春夏秋冬のイベントや祝日、セール期間などに焦点を当て、消費者の需要を喚起することを目的とします。
これらのキャンペーンにおいては、季節ごとの特性やイベント内容に合わせたデジタルギフトを活用することで、効果を大きく高めることが可能です。たとえば、母の日・父の日・クリスマスなど、年間を通じて行われるさまざまなイベントでは、それぞれに適したギフトを選定することが成果向上の鍵となります。
母の日キャンペーン
5月の母の日は、中でもフラワー・雑貨、食品・レストラン、リラックス系の3つのカテゴリーが人気を集めています。花キューピットの全国共通eチケットやFEILERのハンカチ・タオルギフト、ゴディバのチョコレートギフト券などが一例としてあるでしょう。
母の日キャンペーンでは、女性向けの施策設計と季節感のある演出が重要です。特に感謝の気持ちを表現できるメッセージ機能付きのギフトや、ハンドケアセットのような実用性の高いアイテムが好まれる傾向にあります。
母の日キャンペーンのポイント
- 感謝のメッセージを添えられる仕組みの導入で感情的価値を向上
- フラワーギフトと食品の組み合わせなど季節感を重視した商品選定
- 4月下旬からの早期実施で参加率と認知度を最大化
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、具体的なギフト選定方法や実施タイミングについて解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
父の日キャンペーン
6月の父の日は、母の日と比べて認知度が低い分、差別化しやすい施策となります。スポーツ、ファッション・雑貨、食品、リラックス系の4つのカテゴリーが人気です。ゴルフのギフト券やadidasのeギフトカード、プレミアムモルツやクラフトビールなどが人気を集めています。
父の日キャンペーンの特徴は、実用性を重視する男性のニーズに合わせた景品設計が重要である点です。ビジネスパーソンが多い父親層には、日常生活で活用しやすいコンビニ商品引換券やリラクゼーション系のギフトも好まれる傾向があります。
父の日キャンペーンのポイント
- スポーツやファッションなど男性の趣味に特化したギフト選定
- 平日のランチタイムを狙ったSNS投稿タイミングの最適化
- 子どもと一緒に参加できるファミリー向け企画で参加率向上
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、男性向けの施策設計や具体的なギフト事例について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
クリスマスキャンペーン
クリスマスは年間最大の商戦期であり、多くの企業がキャンペーンを実施する競争の激しい時期です。観葉植物・お花のギフトチケットやLUSHのバスボム、ルタオのドゥーブルフロマージュなど、季節感のある商品が人気です。
クリスマスキャンペーンの特徴は、プレゼント需要と自分へのご褒美需要の両方を狙えることです。11月下旬から12月25日までの期間で段階的にキャンペーンを展開し、両方のニーズに対応することが重要となります。
クリスマスキャンペーン設計のポイント
- 冬の季節感を活かしたおうち時間充実系ギフトの積極的活用
- 高額ギフトと少額ギフトの組み合わせで幅広い層の参加を促進
- SNS映えするビジュアルデザインで拡散効果を最大化
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、季節別の商品選定や実施戦略について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
このように、アンケート謝礼やSNS施策、マストバイキャンペーン、来店促進キャンペーンに加え、自治体の市民向け交付物、企業の福利厚生、シーズナルキャンペーンまで、デジタルギフトは幅広いビジネスシーンで活用できます。
では、これらの活用例を踏まえて、実際にデジタルギフトを使ったキャンペーンを企画する際にはどのようなステップで進めればよいのでしょうか。
デジタルギフトで、キャンペーンや福利厚生をもっと手軽に
・インセンティブとしてどの種類のギフトを選べば、満足度が高いのかわからない ・選択肢の一つとしてデジタルギフトも検討したい
などのお困りごとがありましたら、ぜひ「デジタルギフト簡単ガイド」をお読みください。
本資料では、デジタルギフトの基本から具体的な活用例、導入メリットまでを詳しく解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
デジタルギフトを活用したキャンペーンの企画ステップ
デジタルギフトを活用したキャンペーンを成功させるためには、計画的な企画プロセスが重要です。以下の7つのステップに沿って進めることで、効果的なキャンペーンの実施が可能になります。
- 自社の目標や課題を明確にする
- キャンペーンの目的やターゲットを設定する
- 目的を達成できるキャンペーンを選定する
- キャンペーンを実施する理由付けを行う
- キャンペーンの景品やインセンティブを決める
- キャンペーン応募の条件と方法を設定する
- キャンペーンの実施期間を決定する
まず、自社の目標や解決したい課題を明確にしましょう。商品認知度の向上なのか、新規顧客獲得なのか、既存顧客の活性化なのかによって、キャンペーンの内容は大きく変わってきます。
次に、具体的な目的とターゲットを設定します。「20代女性の新規会員を前月比20%増加させる」など、数値目標を含めた明確な設定が効果測定の基準となります。
ターゲットと目的が決まったら、それに最適なキャンペーンの種類(SNSキャンペーン、マストバイ、来店促進など)を選定し、実施理由をチーム内で共有します。
キャンペーンを成功に導くために肝心なのは、ターゲットのニーズに合った魅力的な景品やインセンティブの選定です。デジタルギフトは多様な選択肢から選べるため、ターゲット層の好みに合わせた提案が可能です。
その後、具体的な応募条件、方法、実施期間を決定します。これらのステップを丁寧に踏むことで、目標達成に効果的なキャンペーンを企画・実施することができます。
さらに詳しく知りたい方は、キャンペーン企画の進め方についての詳細をお知りになりたい方は、下記記事にて、キャンペーン企画の進め方や、企業の成功事例も紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
キャンペーン企画のステップを理解したところで、次は企業がデジタルギフトを活用する際の具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。
企業がデジタルギフトを活用するメリット
企業がデジタルギフトを活用するメリットとして、以下の五つが挙げられます。
在庫管理の必要がない
マーケティングに有効活用できる
キャンペーンに合わせてギフトを選べる
発送の手間がかからない
予算設定がしやすい
では、メリットについて詳しく解説します。
在庫管理の必要がない
デジタルギフトは現物のギフトと異なり、在庫管理が不要です。そのため、管理しやすいという特徴があります。また、現物のギフトの場合は、どこに何があるのかを細かく管理しなければいけません。対して、デジタルギフトの場合はサービスのシステム上で自動的に管理されることが多く、管理の手間がかかりません。
マーケティングに有効活用できる
先ほども触れましたが、デジタルギフトは顧客向けの贈答品や販売促進キャンペーンのインセンティブなどに活用できます。デジタルギフトをうまく使うことで、自社のマーケティングに有効活用できるでしょう。また、顧客や取引先に贈答品として贈ると、良好な関係を築くきっかけにもなり得ます。自社の経営発展にデジタルギフトをうまく活用しましょう。
キャンペーンに合わせてギフトを選べる
デジタルギフトの種類や金額は幅広く、キャンペーンに適したギフトを選べます。また、ターゲットの好みに応じて選びやすいのも特徴です。デジタルギフトサービスの中には、複数のギフトの中から受け取った人が自由に選べるものもあるため、ターゲット層が幅広い場合にも活用しやすいでしょう。
発送の手間がかからない
デジタルギフトは、オンラインで即座に送信できます。そのため、顧客に住所を教えてもらう必要がなく、個人情報の取り扱いに疲弊する必要がありません。LINE・メール・SNSなどすべてWeb上で完結できます。
現物のギフトは、住所の確認・梱包・発送といった手間がかかるため、その分人件費も発送費も発生しますが、デジタルギフトはそれらの手間も費用もかかりません。
また、急なイベントでインセンティブや景品が必要になった場合でも、すぐに準備ができます。
予算設定がしやすい
デジタルギフトは数百円から高額なものまであります。そのため、柔軟な予算設定が可能です。高額なギフトであれば満足度はもちろん高まるでしょう。ただ、少ない金額でも受け取り手が自由にブランドを選べるタイプのギフトであれば、より満足度を高めることができます。
デジタルギフトでユーザー満足度が高まる理由
企業がデジタルギフトを活用するメリットはさまざまありますが、デジタルギフトは満足度が高い傾向にあります。その理由は以下の3点が挙げられます。
好きな商品を自分で選べる
商品がすぐに受け取れる・すぐに使える
個人情報を開示しなくてもよい
好きな商品を自分で選べる
デジタルギフトの中には、単一のギフトを受け取るのではなく、受け取ったポイントを使って、さまざまなギフトの中から自由に選べるタイプのものがあります。このように、受け取り手が好きな商品を選べる仕組みは、利便性の高さから幅広いビジネスシーンで活用されています。

ギフティが提供するデジタルギフト「giftee Box」では、たとえば1,000円分のギフトカードを送ると、受け取った人が好きなブランドのカフェギフトやアイスクリームギフト、ギフト券などに交換できます。
商品がすぐに受け取れる・すぐに使える
デジタルギフトはオンライン上で手続きを行うとすぐに発送され、商品がすぐに受け取れます。
従来の現物のギフト形式だと、商品受け取りの手続きから企業側の確認、出荷手続きまでの一連の作業が必要となり、ユーザーの手元に届くまで時間がかかってしまいます。受け取りに時間がかかるようだと、自社の評価にマイナスに働く恐れもあります。
ただしデジタルギフトであればすぐにユーザーの手元に提供され、受け取ったその日から利用可能となります。すぐに利用できる点から、ユーザーの満足度向上にもつながるでしょう。
個人情報を開示しなくてもよい
デジタルギフトは、個人情報を開示するリスクが低いというメリットもあります。
従来の現物のギフト形式だと、郵送するためにはユーザーの住所や氏名を開示する必要があります。いくら信頼している企業であっても、個人情報の開示は心理的ハードルが高いです。
ただしデジタルギフトであれば、メールやSNSなどの情報だけ受け取り手続きを行うことができ、ユーザーは個人情報の入力や開示が不要です。ユーザー側も安心してデジタルギフトを受け取ることができるでしょう。
このように、デジタルギフトはユーザーにとって多くのメリットがあります。では、企業側がこうしたユーザー満足度を最大化するには、どのようなポイントに注目してデジタルギフトを選べばよいのでしょうか。
キャンペーンにおけるデジタルギフト選びのポイント
デジタルギフトを活用したキャンペーンやインセンティブ施策が増加していますが、その効果を最大化するには、ターゲットの趣味やニーズに合った適切なギフトを選ぶことが重要です。せっかくの施策も、ギフト選びを誤ればその効果は半減します。以下の3つのポイントを押さえて、最適なデジタルギフトを選びましょう。
多様な選択肢を提供する
金券類に限らず、食品、体験、サブスクリプションなど、幅広いジャンルから選べるデジタルギフトを用意することで、多様なユーザーの嗜好に対応することができます。特にキャンペーンの規模が大きい場合は、ターゲット層の多様性を考慮した選択肢が重要です。
利用のしやすさを重視する
受け取り手が場所や時間を選ばず、すぐに利用できる景品を選びましょう。全国展開の店舗で使えるもの、宅配サービス、大手ECサイトの金券など、利便性の高いギフトは満足度向上につながります。また、複雑な手続きが不要なものを選ぶことも大切です。
キャンペーン内容との親和性を考える
景品がキャンペーンの目的やコンテンツに合致し、自社サービスへの誘導につながるものを選びましょう。たとえば、健康関連のキャンペーンなら運動やウェルネス関連のギフト、エコをテーマにした施策なら環境に配慮した商品などが効果的です。ユーザーの記憶に残るストーリー性のある選択が重要です。
これらのポイントを踏まえて最適なデジタルギフトを選ぶことで、キャンペーンの反応率向上やユーザーエンゲージメントの強化につながります。
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、キャンペーンで人気のデジタルギフトを14種類紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
デジタルギフトを検討するなら、ユーザーが選ぶのを楽しめるギフトも
デジタルギフトは商品がすぐに受け取れる・すぐに使えるという魅力があります。さらにユーザーの関心を引き、エンゲージメントを高めたいのであれば、選べるタイプのデジタルギフトもおすすめです。ユーザーが自分の好みに合わせて商品を自由に選べることで、個々のニーズにぴったりなギフトを提供でき、より高い満足度を実現できます。
gittee for Businessが提供する「gifteeBox」は、1,000種類以上の豊富なラインナップから、受け取った人が自分の好みに合わせて商品を自由に選べるデジタルギフトです。
サービス資料では「gifteeBox」内で選ばれた商品の人気ランキングを公開しているほか、システムの仕様や告知用画像の利用イメージも公開しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご検討ください。
デジタルギフトを活用する際の注意点

活用する企業にとっても、受け取るユーザーにとってもメリットが高いデジタルギフトですが、活用する際には以下の3点に注意しましょう。
目的にあったデジタルギフトか確認する
利用条件や有効期限が決まっているギフトがある
景品表示法(景表法)の規制対象になることがある
では、これらの注意点について詳しく解説します。
目的にあったデジタルギフトか確認する
デジタルギフトは受け取るユーザーの満足度が高いとはいえ、ただ配布するだけでは自社の求めている効果につながらない可能性が高いです。
デジタルギフトを活用する目的やキャンペーンのターゲット層、ブランドイメージなどを考えた上で、適切なデジタルギフトを選定するようにしましょう。
また、ユーザーにとって魅力的なデジタルギフトを選ぶことも重要です。自社の顧客層やキャンペーンのターゲットを踏まえた上で、ユーザーの満足度が向上するものを選びましょう。デジタルギフトを活用する目的とユーザーの満足度に沿っているものを選定できれば、おのずと自社の目的・目標達成につなげられます。
利用条件や有効期限が決まっているギフトがある
デジタルギフトの中には、交換可能な店舗が特定のエリアに限られている場合があります。
たとえば、全国のユーザーを対象としているのに、地域密着型のコンビニのデジタルギフトを送ってしまうと、中には利用できない人も出てきてしまいます。
そのようなことが起こらないように、利用できる店舗はしっかりと確認しておくことが大切です。
また、多くのデジタルギフトは有効期限があるため、その期間内に交換や利用をしなければ、使えなくなってしまいます。デジタルギフトサービスの中には、有効期限が3か月といったように短いものもあるため、注意が必要です。
過大な景品は景品表示法(景表法)の規制対象になることがある
景表法とは、「不当景品類及び不当表示防止法」の略称です。一般消費者の利益の保護を目的として、商品、サービスの品質、内容、価格、取引条件などを偽って不当に表示することを規制したり、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限したりする法律です。
景表法は、消費者が以下のような事態に陥らないよう制定されました。
虚偽の表記に騙されて商品を購入する(不当表示の禁止)
豪華すぎる景品に釣られて、質の悪い商品を購入する(過大な景品類の規制)
企業が景表法に違反すると、
社会的な信用が失われる
課徴金制度(違反行為の抑止と法規制の実効性確保を目的とした行政上の措置)が適用される
といったリスクがあります。そのため、キャンペーンでデジタルギフトを活用する際には、過大な景品類をギフトとして利用しないよう、必ず頭に入れておきましょう。
景表法については、下記記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
人気の法人向けデジタルギフトサービス8選
ここまで、デジタルギフトに関して解説してきましたが、実際にどのような法人向けデジタルギフトサービスがあるのかも見ていきましょう。
▼人気のデジタルギフトサービス
giftee for Business
EJOICAセレクトギフト
デジコ
デジタルギフト
Visaギフト vanilla
SELECTS for Business
yui365
dgift
では、それぞれのサービスの特徴を解説します。
※なお、掲載しているサービスの詳細は2024年12月のものです。現在の情報と異なる場合があります。
giftee for Business
▼おすすめポイント
幅広い価格帯で多種多様なギフトがある
「giftee Box」や「えらべるPay」など、受け取り手がギフトを自由に選べる商品がある
施策を効率化できるツールが多数あり、施策サポート力がある
オリジナルギフトの作成も可能
giftee for Businessは、導入実績50,000件を超えるデジタルギフトサービスです。幅広い価格帯のギフトを取り扱い、SNSキャンペーンや来店促進施策の景品など、さまざまなシーンで活用可能なサービスとして、多くの企業様から選ばれています。
強みとして、メールやLINE、SNSを活用したギフト配布ソリューションも提供している点が挙げられます。これにより、運用の手間を削減しながら、迅速かつ効率的なキャンペーン展開をサポートします。
さらに、株式会社ギフティは、情報セキュリティマネジメントシステム(ISO 27001)およびプライバシーマークを取得しています。個人情報の取り扱いにおいて厳格なセキュリティ基準を守り、安心してご利用いただける環境を提供しています。
また、自治体様からはマイナンバーカードや行政アプリの普及促進などで、さらに企業様からは福利厚生文脈でデジタルギフトをご活用いただくケースも増えております。
施策支援 | X(キャンペーンシステム)、LINE(キャンペーンシステム)、Instantwin(即時抽選システム)、Survey(アンケートシステム)、Auth(認証配布システム)、Direct(対面配布システム)、Mission(参加条件判定システム)、MustBuy(購買判定システム)、Referral(友達紹介システム)、Delivery(商品配送システム) など |
|---|---|
注文方法 | 申し込み・審査制・要アカウント登録 |
利用想定シーン | アンケート謝礼、資料請求・見積もり謝礼、LINEキャンペーン、X(キャンペーン)、福利厚生・社内報奨、販売促進キャンペーン、抽選キャンペーン、ポイント交換、ウェビナー・イベント御礼、自治体 など |
EJOICAセレクトギフト
EJOICAセレクトギフトは、電子マネーとポイントに特化したデジタルギフトサービスです。Amazonギフトカードなど、23種類(2024年12月時点)の電子マネーやポイントが揃っており、受け取った人が自由に選択・交換できます。
そのため、電子マネーやポイントに絞ったデジタルギフトで施策を実施していきたい企業に適しているでしょう。
施策支援 | メール配信サービス、オリジナルカードサービス、外部ツールとも連携可能(SNSキャンペーンシステム、マストバイキャンペーンシステム) など |
|---|---|
注文方法 | 申し込み・審査制、要アカウント登録 |
利用想定シーン | 販売促進キャンペーン、SNSキャンペーン、株主優待、福利厚生、自治体 など |
デジコ

※引用:デジコ公式サイト
デジコは、PayPayマネーライトなど複数の電子マネーと直接交換ができるデジタルギフトサービスです。購入手続きをすればすぐに発行可能なため、手軽に利用できます。
施策支援や機能も充実しており、1円単位でのギフト発行が可能なため、幅広い用途で活用での活用が可能です。受け取ったデジコをPeXポイントギフトに交換すれば、それを利用して幅広いポイントや商品と交換できます。
施策支援 | レシートOCR機能、アンケート機能、ギフトカード印刷、コンビニプリント、ECナビ広告パック など |
|---|---|
注文方法 | 即時購入制・要アカウント登録 |
利用想定シーン | アンケート謝礼、LINEキャンペーン、X(キャンペーン)、福利厚生・社内報奨、販売促進キャンペーン、自治体 など |
デジタルギフト

※引用:デジタルギフト公式サイト
デジタルギフトは、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナの4種類のプランがあるデジタルギフトサービスです。
プランによってできることや発行手数料が異なります。そのため、少額での利用よりも、毎月ある程度の金額を利用する場合に適したサービスと言えるでしょう。
ギフトは29種類(2024年11月現在)あり、電子マネーやポイントが中心です。受け取った人が自由に選んで交換できる仕組みとなっています。
施策支援 | インスタントウィン機能(プラチナプランのみ)、自社商品ギフト(ゴールド・プラチナプラン)、デザインギフト(シルバー・ゴールド・プラチナプラン)、ギフト発行スタンド(全プラン) など |
|---|---|
注文方法 | 即時購入制・要アカウント登録 |
利用想定シーン | 株主優待ギフト、友達紹介キャンペーン、福利厚生・社内インセンティブ、自治体サポート、資料請求・見積もりお礼、会員登録キャンペーン、レシートOCRキャンペーン、ポイント交換、スタンプラリー、キャッシュバック、お詫びの品、オリジナルギフトの作成、イベントやセミナー参加の謝礼、アンケート回答のお礼、YouTubeキャンペーン、Xキャンペーン、LINEキャンペーン など |
Visaギフト vanilla
Visaギフト vanillaは、Visa加盟店で使用可能なヴァーチャルプリペイドカードです。現物のカードタイプと同様に、Visa加盟店で利用できます。
また、実店舗だけでなくオンラインショップでクレジットカードのようにカード番号を入力し、使用することも可能です。そのため、受け取った人が幅広いお支払いに利用できます。
Visaギフト vanillaはアカウント登録などは不要で、購入すればすぐに活用できます。公式サイトからお問い合わせをすれば法人での購入が可能です。
注文方法 | 即時購入制 |
|---|---|
利用想定シーン | 販売促進キャンペーン、謝礼、福利厚生、自治体 など |
SELECTS for Business
SELECTS for Businessは、オリジナルのカタログギフトが作成できるサービスです。
Amazonや楽天市場、Baseなどにある商品のほとんどが掲載でき、自社製品・SELECTS提携ギフト商品も選べます。
掲載できる商品の幅が非常に広いため、オリジナリティを追求したい場合におすすめです。
デジタルのカタログギフトは、オンラインで贈るためのWebページを作成し、URLで贈れます。カタログギフトという形態であることから、最低金額が数千円以上になるため、一定金額以上のギフトを贈るシーンに活用しやすいサービスでしょう。
また、独自のAIや専任プランナーが効果的な掲載商品の選定を支援してくれるサービスも提供しています。
施策支援 | ギフトキュレーション、抽選/先着商品機能、アンケート機能、ポイント交換機能 など |
|---|---|
注文方法 | カタログ作成方式 |
利用想定シーン | BtoB、福利厚生、プレゼントキャンペーン、成約特典、販売促進、ノベルティ など |
yui365

※引用:yui365公式サイト
yui365は、オリジナルカタログギフトが作成できるサービスです。社内従業員向けに特化しているため、福利厚生などでの利用がおすすめです。
用意されている商品リストはありますが、ほかにも自社商品の追加や、リクエストにも柔軟に対応してくれます。そのため、カスタマイズ性が高い点が特徴です。
最も低いプランで1冊あたり4,100円から作成できます。金額に応じて選べる商品が変わります。また、1冊から注文可能で、社員の記念日などに合わせて、その都度利用することも可能です。
施策支援 | オリジナルカタログギフトの提案 など |
|---|---|
注文方法 | カタログ作成方式 |
利用想定シーン | 福利厚生、周年記念、社内イベントの景品、誕生日 など |
dgift

※引用:dgift公式サイト
dgiftは、幅広い種類・価格帯のギフトが揃っているデジタルギフトサービスです。最大の特徴は、キャンペーンの企画段階からサポートを提供している点です。
また、さまざまな種類の抽選機能があるため、福利厚生などに利用するよりも、キャンペーンの景品として活用しやすいでしょう。
施策支援 | 抽選機能、告知機能、オリジナルギフト機能 など |
|---|---|
注文方法 | 申し込み・審査制・要アカウント登録 |
利用想定シーン | 来店促進キャンペーン、Web集客施策、販売促進キャンペーン、会員登録キャンペーン、ARスタンプラリー、アンケート回答の謝礼 など |
デジタルギフトを活用した企業の事例

最後に、デジタルギフトを活用した企業の例として、ギフティの事例をご紹介します。
デジタルギフトを活用したイベントで、新規ユーザー獲得・リテンション向上を達成
ターゲット年齢層 | 10~40代 |
|---|---|
性別比(男性:女性) | 5:5 |
利用ギフト | えらべるPay |
株式会社カカオピッコマでは、全ピッコマアプリユーザーを対象とした、「総額3億円分マンガを読んでポイ活」イベントを約1か月間実施しました。
イベントの内容は、
対象のマンガを読む
作品をX(旧Twitter)にシェア
デイリーボーナスの動画視聴
といったミッションをクリアすることで、マイルを獲得。獲得したマイルは「えらべるPay」か、ピッコマ内で使用できる「コイン」と交換できるというものでした。
結果として、交換先を複数用意したことで、幅広い層のユーザーに参加してもらえました。また、新規ユーザー・復帰ユーザーのボリュームが増加し、リテンション率を向上させることができただけでなく、全体のアクティブユーザーの増加にもつながりました。
当選者数を最大化し、キャンペーン認知の拡大に成功
ターゲット年齢層 | 20~40代 |
|---|---|
性別比(男性:女性) | 4:6 |
利用ギフト | えらべるPay |
株式会社外為どっとコム様は、外国為替取引を専門とする企業です。
同社は20周年記念企画を実施し、キャンペーン期間中、外為どっとコムのXアカウントをフォローし、指定のハッシュタグをつけて対象のキャンペーンポストを引用リポストしたユーザーの中から、抽選で1,000名様に「えらべるPay」をプレゼントしました。
メインキャンペーンの認知拡大をする必要があったため、Xキャンペーンでは200円〜1,000円の低額デジタルギフトを景品に使用して当選者数を合計1,000名に増やしました。そうすることで、メインキャンペーンの情報に触れるユーザーを一人でも多く増やせるようにしました。
結果として、Xキャンペーンをきっかけとした、メインキャンペーンへのエントリー数増加効果があり、社内の担当者からも良いトリガーになったと好評価を得られました。
従業員への誕生日ギフトで満足度アップ
ターゲット年齢層 | 20~60代 |
|---|---|
性別比(男性:女性) | 6:4 |
利用ギフト | giftee Box |
LifeBank株式会社様は、愛知県で運輸・物流業を展開している企業です。
以前から、福利厚生の一環として、各従業員の誕生日当日にギフトとして「Amazonギフトカード」を郵送していました。しかし、毎月5~10人の従業員へのギフト郵送は、担当者の業務負担となっていたため、感謝の気持ちを伝える仕組みは変えずに、業務効率化する方法を模索していました。
そこで、ギフトの内容を「giftee Box」2,000円分に変更。ギフトにコメントを添える文化を大切にしているため、URLを記載したメール内にコメントを書いて送信するようにしました。
その結果、複数の従業員から「ギフトが選べるようになり嬉しい」などの声が上がっているそうです。
販売店向けキャンペーンで特典獲得のハードルを下げて販売意識を醸成
ターゲット年齢層 | 20~50代 |
|---|---|
性別比(男性:女性) | 9:1 |
利用ギフト | giftee Box |
切削工具製造メーカーの国内販売部門である株式会社やまわエンジニアリングサービス様では、販売店の営業担当者を対象に、対象商品を指定本数売り上げた方に500円分、1,000円分、1,500円分の「giftee Box」を贈呈するキャンペーンを実施しました。
従来はオリジナルのポロシャツやジャケットを特典として提供していましたが、マンネリ化が課題に。そこで、1,000種類以上から選べるデジタルギフト「giftee Box」と、一斉配信が可能なギフト配信サービス「giftee Port」を導入しました。
これにより、従来の特典と比べて原価を抑えながら、特典獲得のハードルを下げることができ、営業担当者の販売意識醸成につながりました。
▼この事例の詳細はこちら
出産・子育て応援でデジタルギフトと現金、選べる仕組みを導入
ターゲット年齢層 | 20~40代 |
|---|---|
性別比(男性:女性) | 1:1 |
利用ギフト | giftee Box |
愛知県日進市では、国の「出産・子育て応援交付金」を活用し、妊娠・出産・子育て期を切れ目なく支える事業を展開しています。2025年度からの現金給付義務化に対応するため、現金振り込みかデジタルギフトボックスを選べる仕組みを導入しました。
デジタルギフトボックスには、育児用品店の利用券やタクシークーポン、ECサイトで使えるデジタルコード、電子マネー、さらには市内の産後ケアプログラムや家事支援サービスクーポンなど、子育て世帯が本当に必要とするアイテムを用意しました。
その結果、約6〜7割の利用者がデジタルギフトを選択し、申請書類チェックや口座情報確認などの事務負担が軽減され、職員が本来の業務に集中できる環境が整ったとのことです。
▼この事例の詳細はこちら
LINE友だち登録キャンペーンで目標17万名を約4か月で達成
ターゲット年齢層 | 20~30代 |
|---|---|
性別比(男性:女性) | 5:5 |
利用ギフト | えらべるデジタルギフト |
三井住友海上あいおい生命保険株式会社様では、LINE公式アカウントの新規開設にあたり、LINE友だち追加キャンペーンとアンケートキャンペーンの双方を実施しました。友だち追加キャンペーンでは期間中にLINEの友だち追加をされた方全員に、アンケートキャンペーンでは期間中にアンケートに回答いただいた方全員に「えらべるデジタルギフト」をプレゼントしました。
キャンペーンの企画設計から運用までギフティの担当者と密に連携。ユーザーにとってわかりやすいキャンペーンになるよう、設計を工夫しました。その結果、友だち登録者数の目標であった17万名を約4か月で達成し、お客様だけでなく、商品を案内する代理店からも好評なキャンペーンとなりました。
▼この事例の詳細はこちら
よくある質問(FAQ)
デジタルギフトの導入を検討する際、多くの企業が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q1: デジタルギフトの有効期限は?
デジタルギフトの有効期限は、ギフトの種類やサービスによって大きく異なります。
主なデジタルギフトの有効期限例
- Amazonギフトカード:発行から10年
- QUOカードPay:発行から3年
- こども商品券e-Gift:発行から3年(36か月)
このように、ギフトによって有効期限は3か月から10年ほどまで幅があります。
有効期限が短いギフトを選ぶ場合は、受け取り手に事前に期限を明示し、早めの利用を促すことが大切です。また、サービスによっては有効期限の延長が可能な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
Q2: 受け取り手が使わなかった場合は?
デジタルギフトが有効期限内に使用されなかった場合、基本的に返金や再発行はできません。未使用率を下げるためには、以下の工夫が効果的です。
- 有効期限をわかりやすく明示する
- 受け取り後にリマインドメールを送る
- 利用しやすいギフト(全国展開の店舗、大手ECサイトなど)を選ぶ
- 受け取り手が自由に選べるタイプのギフトを活用する
Q3: 個人情報の取り扱いは?
デジタルギフトは、現物ギフトと比べて個人情報の取り扱いが最小限で済むのが大きなメリットです。
必要な情報
メールアドレス、LINE ID、SNSアカウント、電話番号など(住所や氏名は基本的に不要)
セキュリティ面で信頼できるデジタルギフトサービスを選びたい場合、以下のポイントを確認しましょう。
- ISO 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)を取得しているか否か
- プライバシーマークを取得しているか否か
- SSL/TLS暗号化通信を採用しているか否か
- 個人情報保護方針を明示しているか否か
まとめ
本記事では、デジタルギフトの種類や活用例、企業がデジタルギフトを活用するメリット、注意点などについて解説しました。
デジタルギフトは目的や施策・キャンペーンの方向性に合わせてギフトをカスタマイズできたり、受け取り手で好きなギフトを選べたり、その利便性の高さからさまざまなビジネスシーンで活用可能です。デジタルギフトをうまく活用することで、自社の認知拡大や新規顧客の獲得、顧客との関係性向上につながります。
ただし、ただギフトを渡すだけでは自社の求めている効果につながらない恐れがあります。デジタルギフトを活用する目的やキャンペーンのターゲット層、ブランドイメージなどを考えた上で、適切なデジタルギフトを選定するようにしましょう。