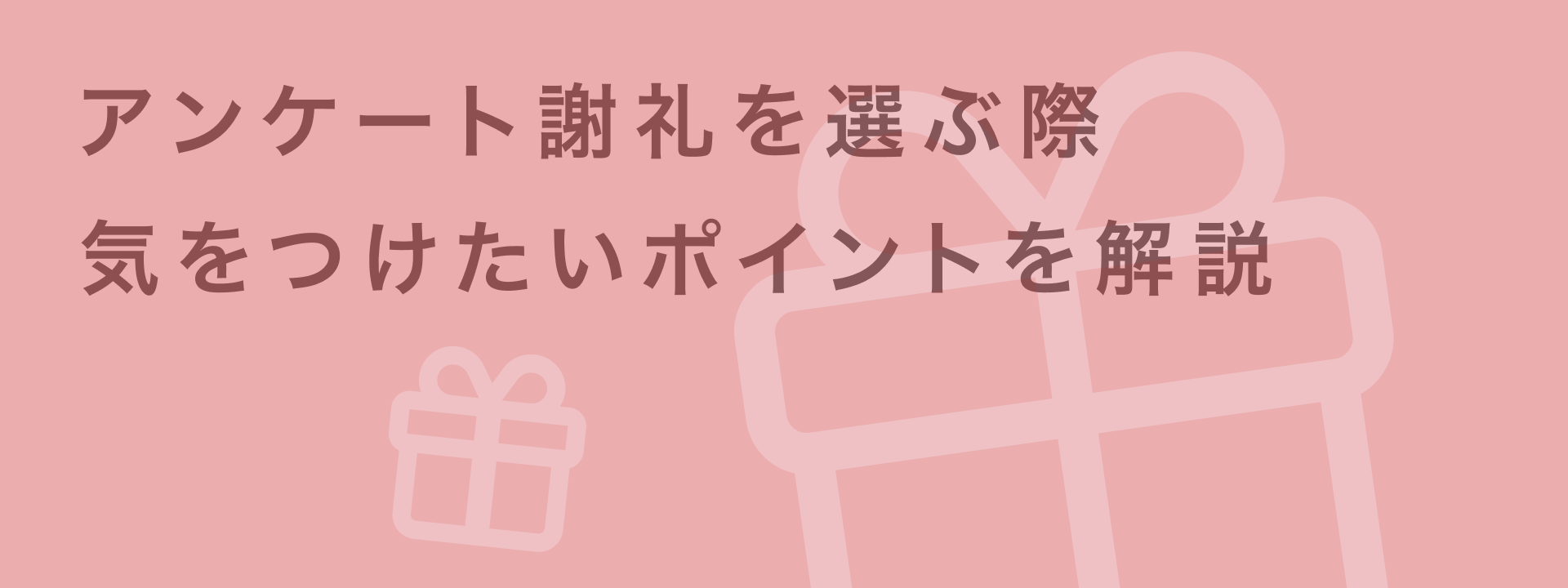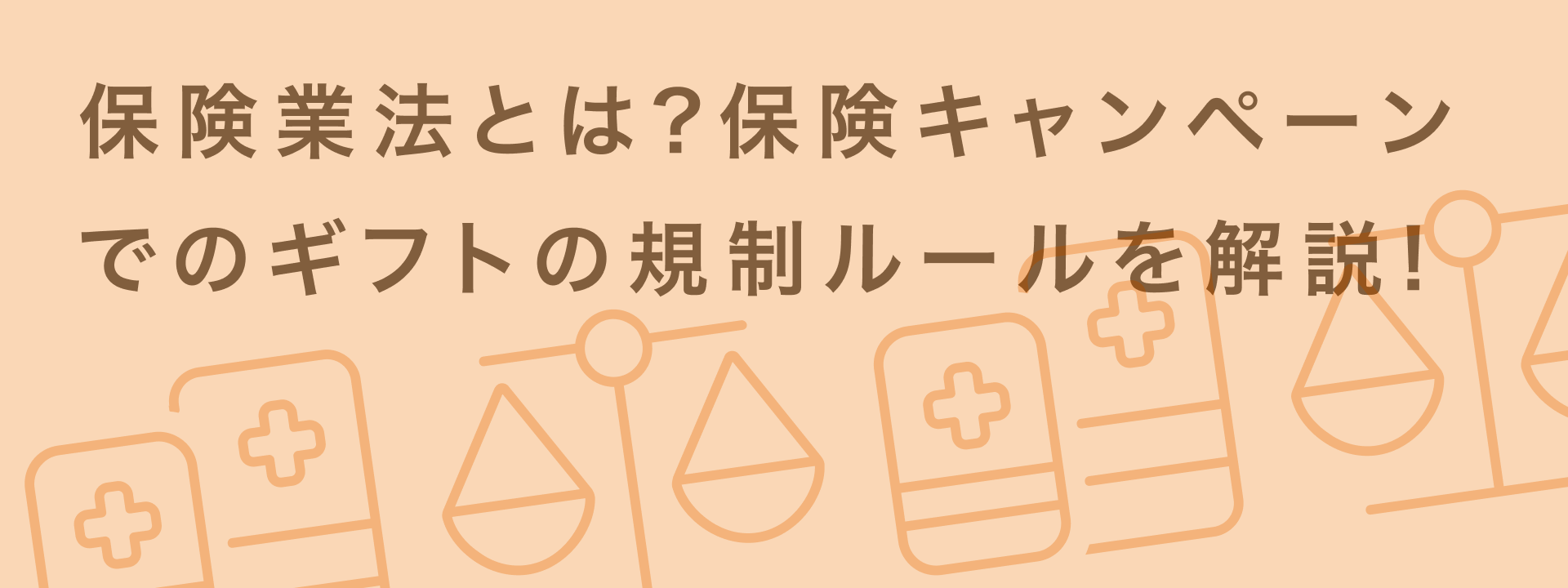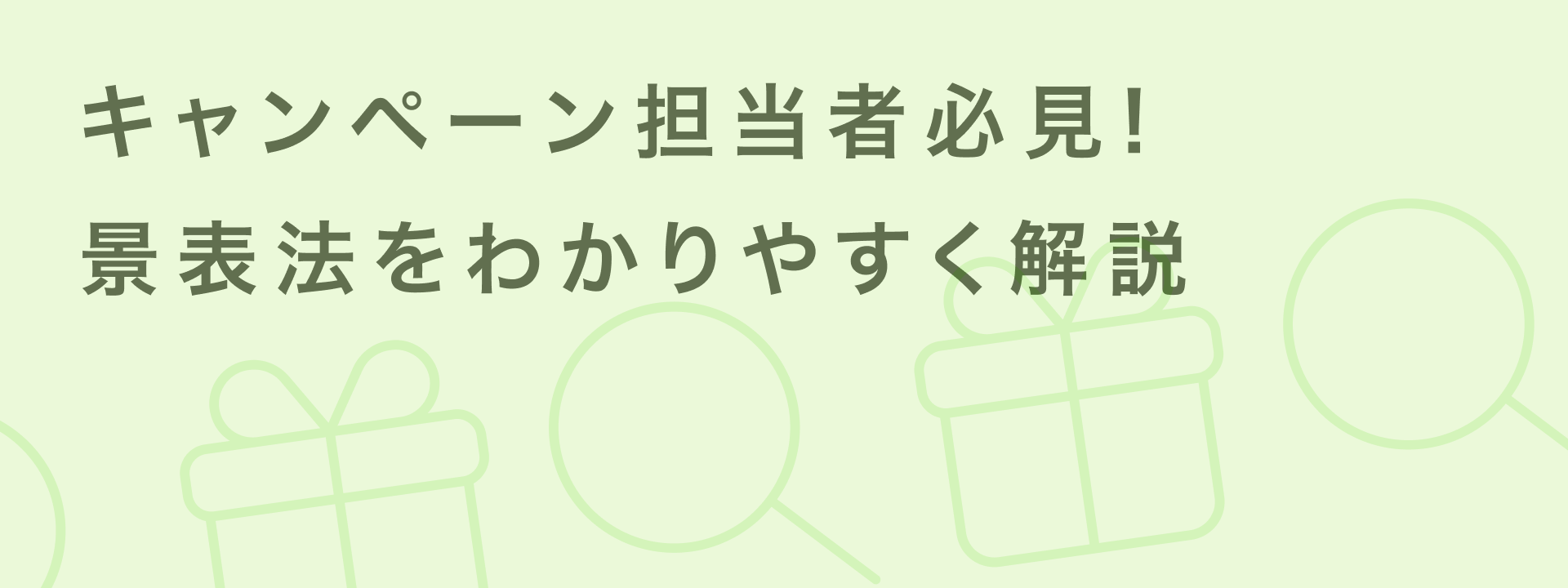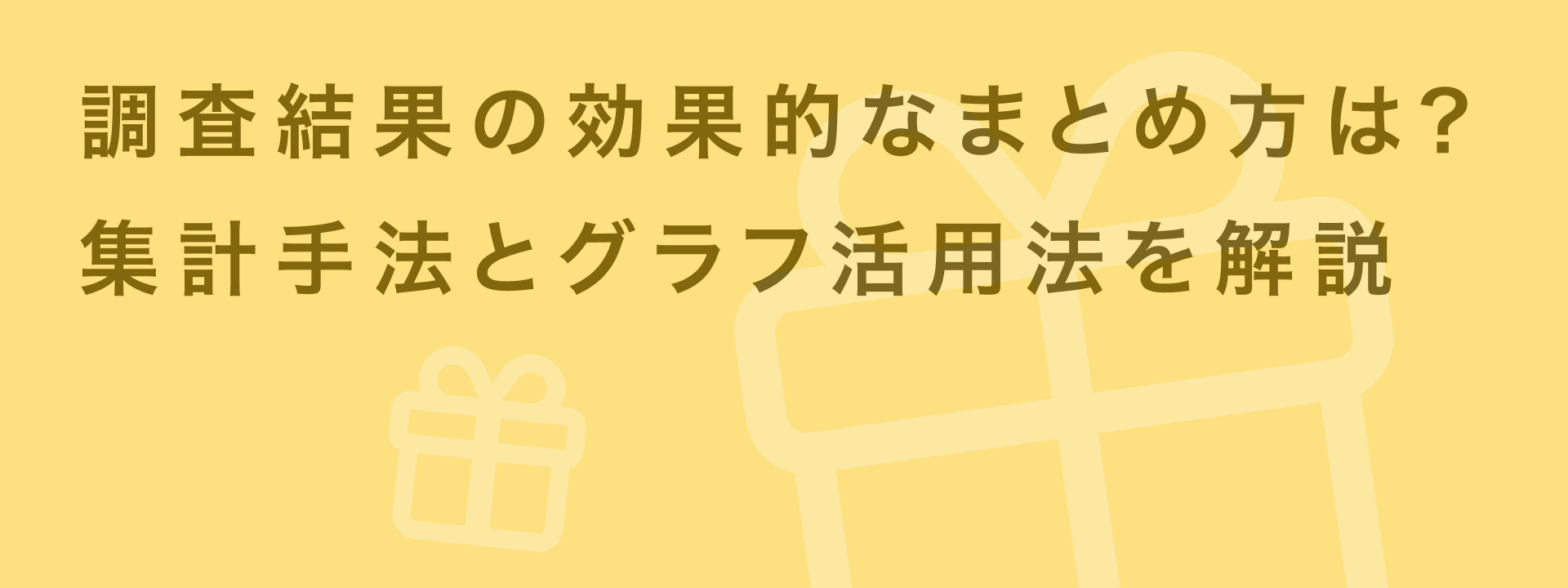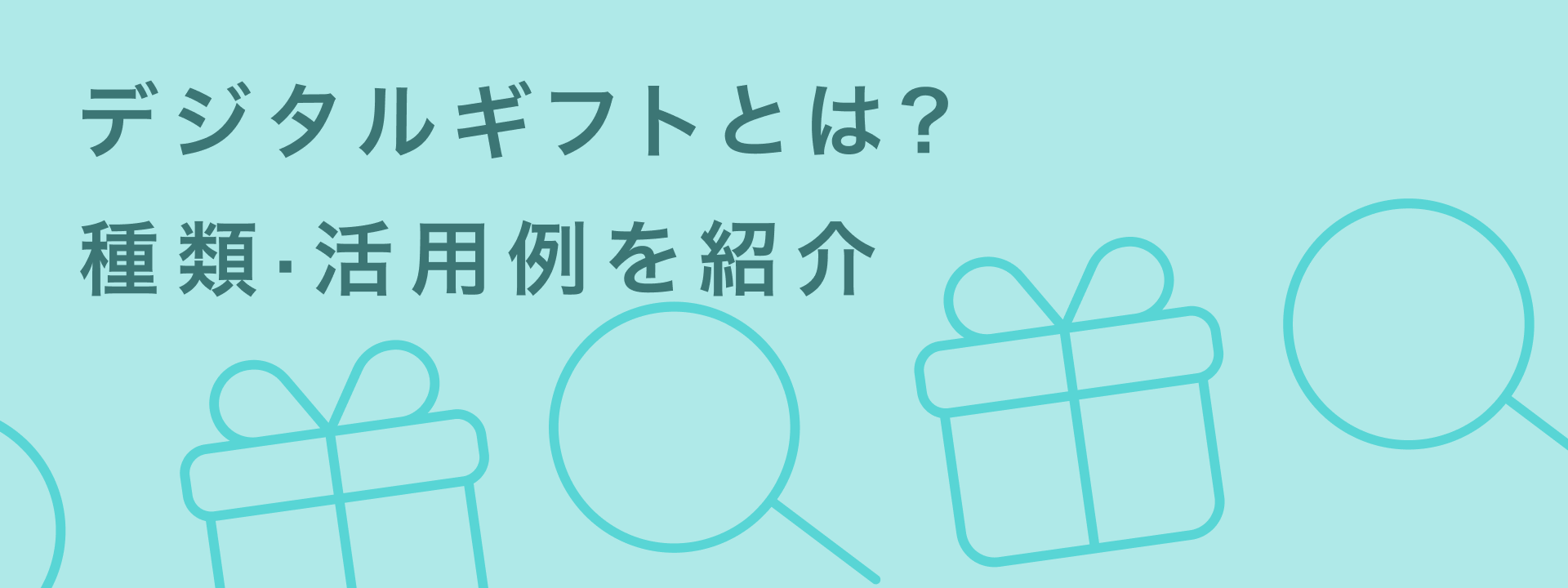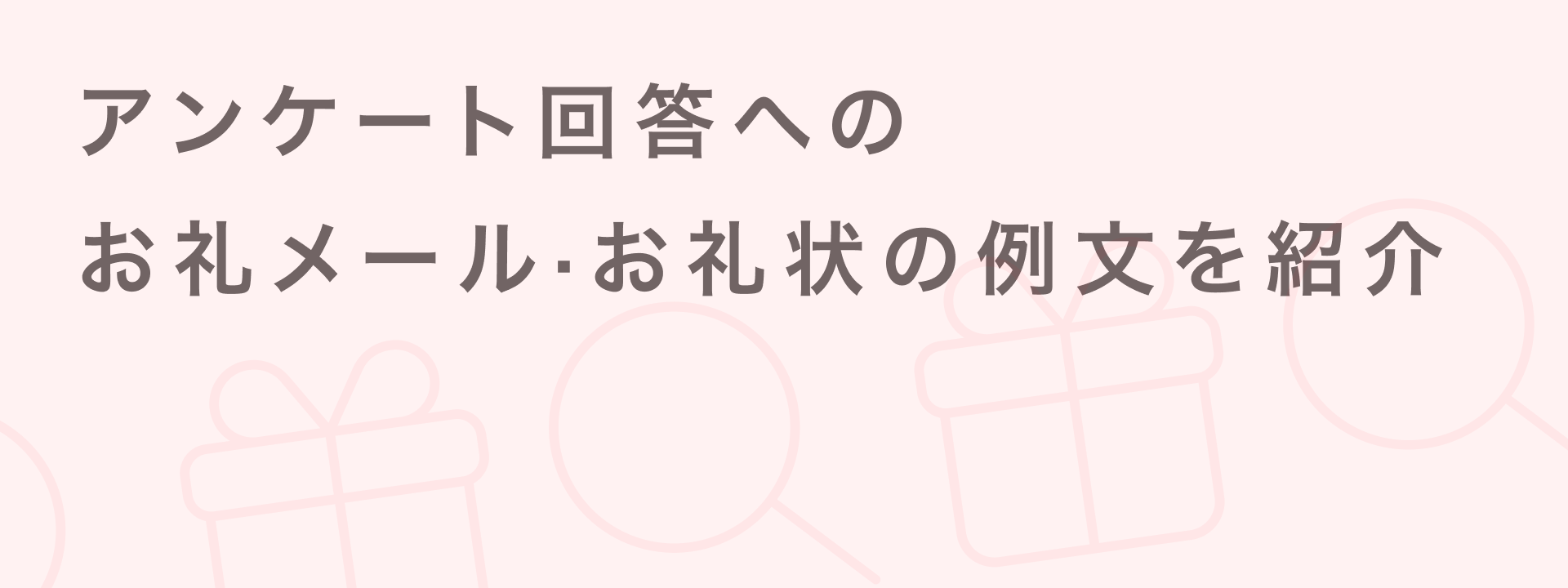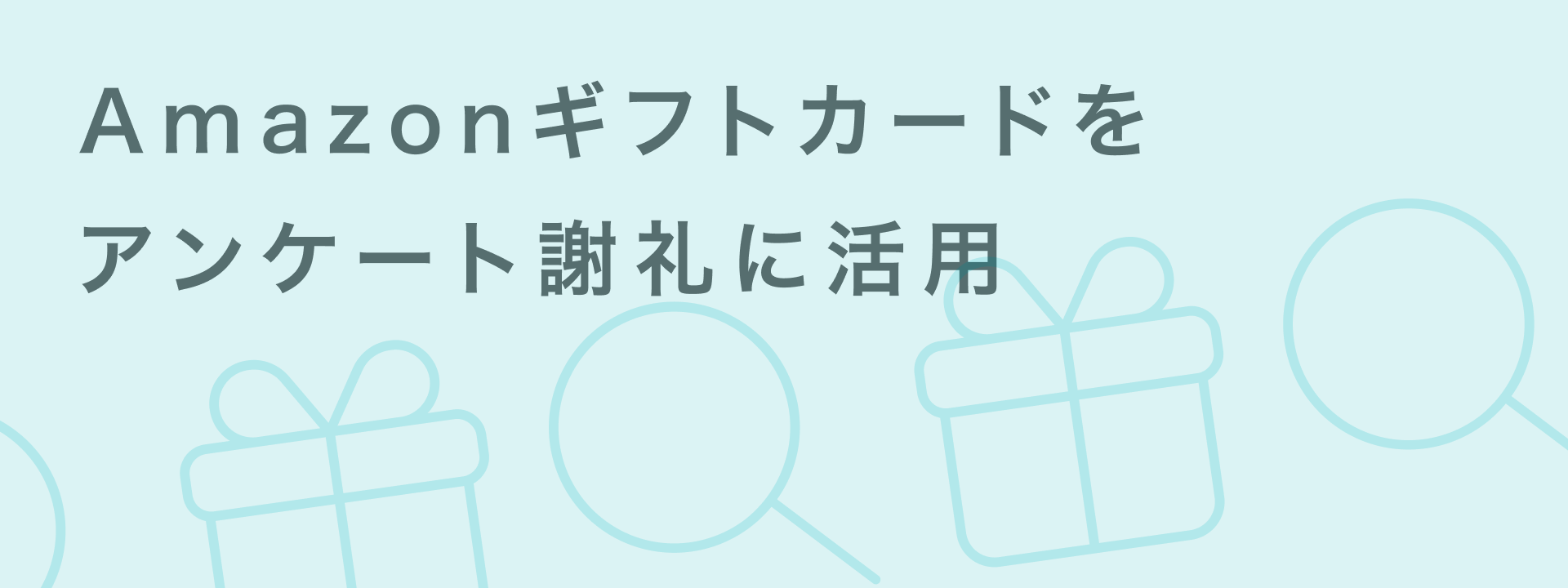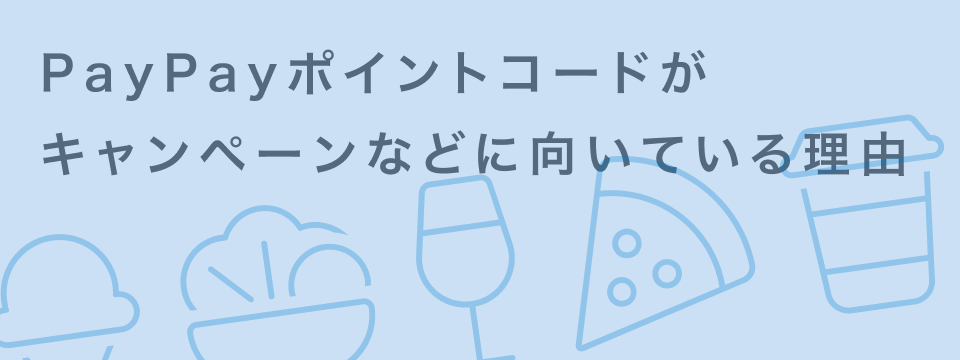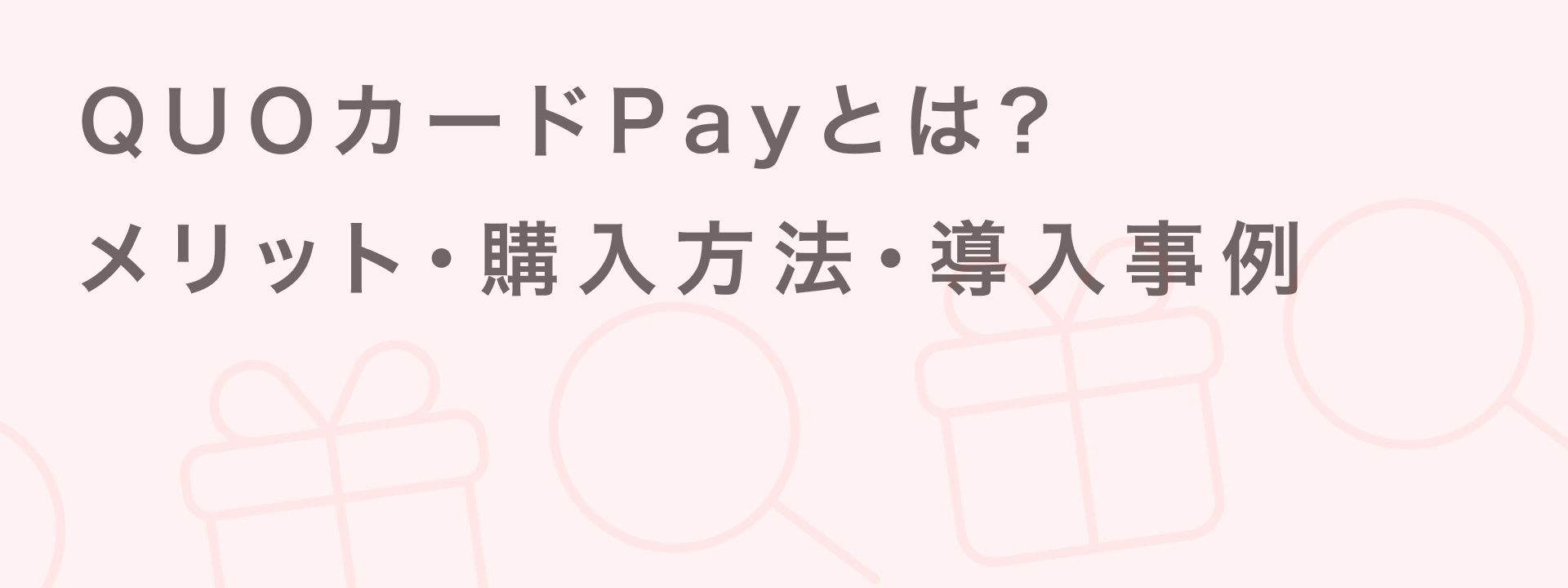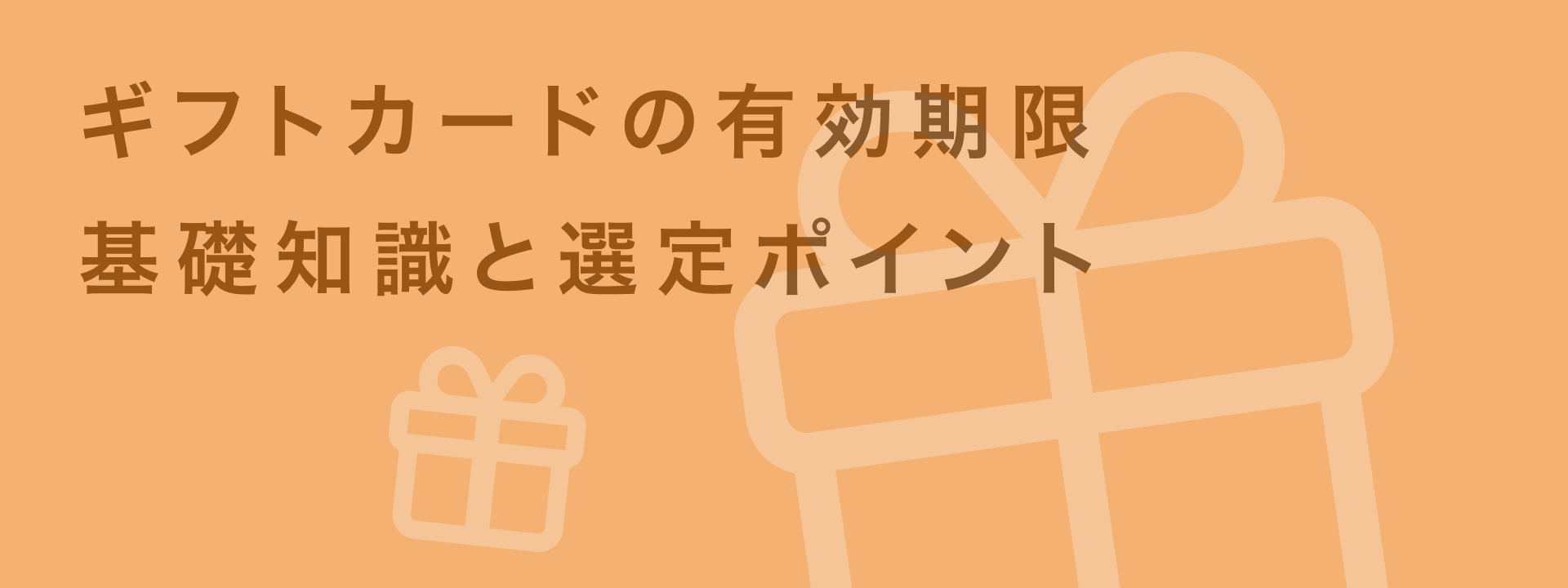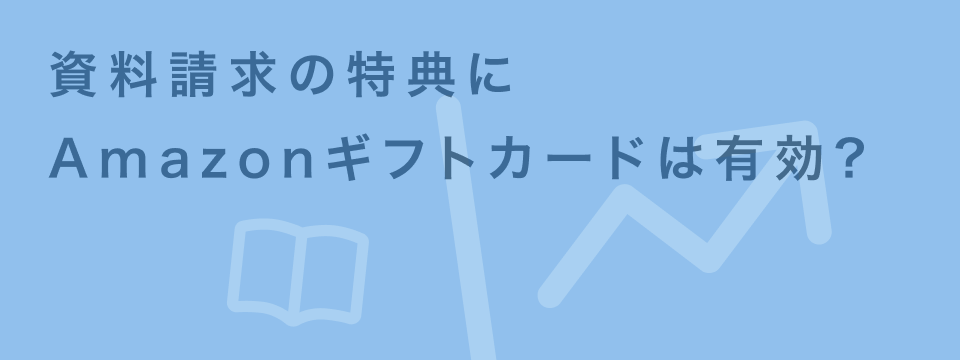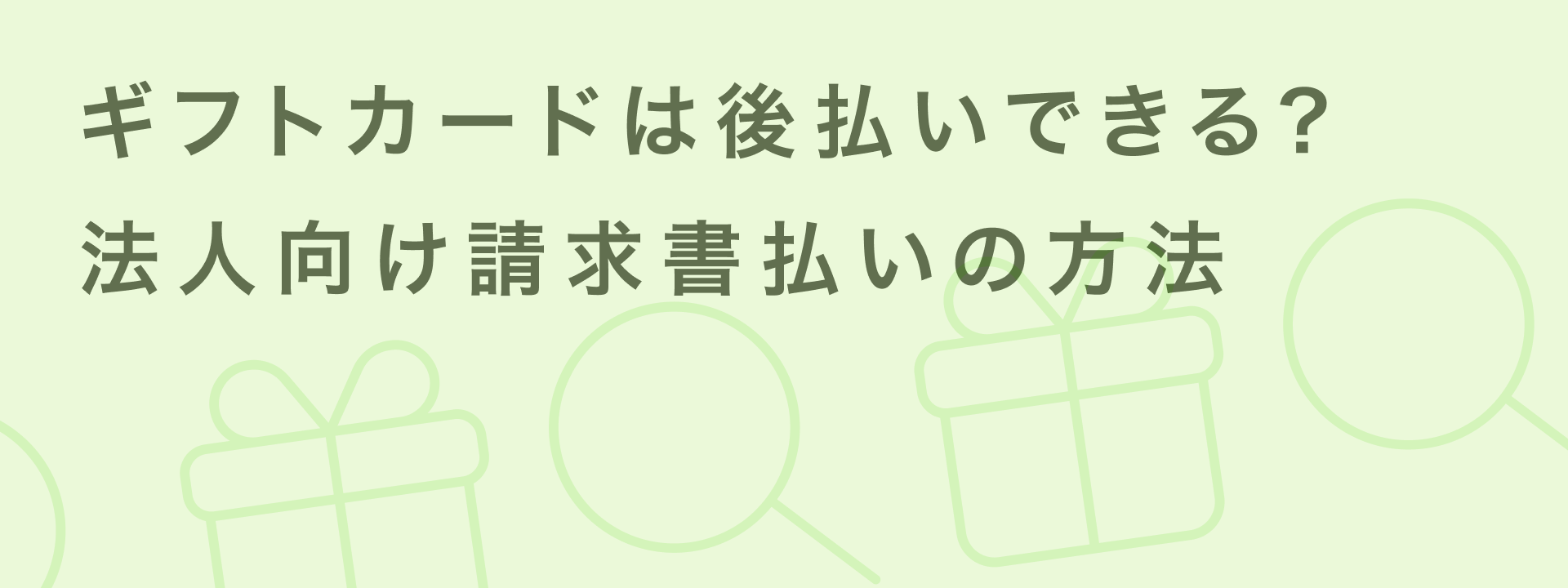アンケート謝礼の相場|ケース別の金額目安と景表法で注意すべきポイントを解説
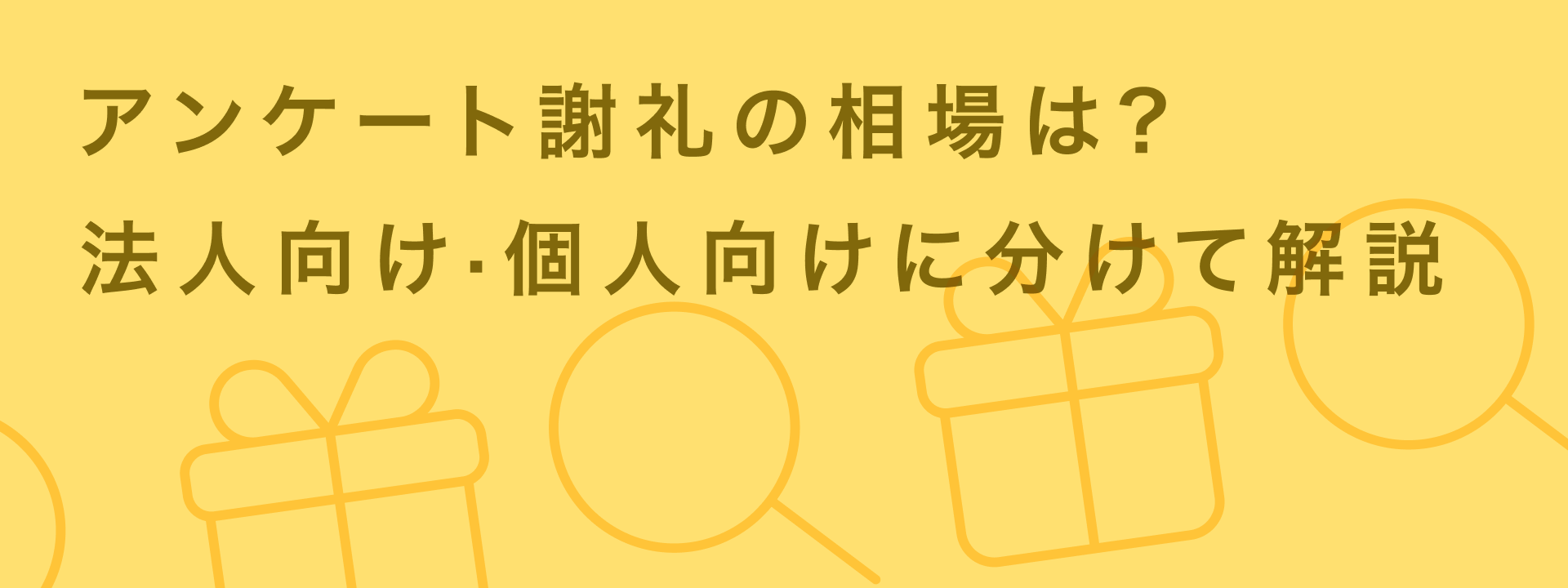
アンケートへの協力を募るために謝礼を用意することがありますが、どの程度の金額感の謝礼を用意するかお悩みの企業様も多いのではないでしょうか。
本記事では、ギフティのデジタルギフトを活用してアンケート施策を実施いただいた企業様の情報をもとに、アンケート謝礼の相場を調査し、シーンごとの謝礼相場の紹介をしています。
もちろん、各社様で予算や目的はそれぞれなので、必ずしも相場通りの謝礼を用意する必要はありません。あくまで一例として、施策検討にご活用ください。
アンケート謝礼の配布を効率化したいご担当者様へ
こんなお悩みはありませんか? ・アンケート謝礼の相場がわからない ・どの程度の金額感の謝礼を用意するか悩んでいる ・謝礼の発送の手間やコストを削減したい ・アンケート実施から謝礼の配布までを効率化したい
アンケート施策では、謝礼の金額設定だけでなく、配布方法や運用のしやすさも成果に大きく影響します。相場を踏まえて適切な謝礼を用意できても、発送や管理に手間がかかると、運用負担が増えてしまうケースも少なくありません。
そこで累計導入件数7万件以上、法人向けデジタルギフト導入実績No.1のgiftee for Businessでは、アンケート実施から謝礼配布までを一元管理できる「Survey(アンケートシステム)」を提供しています。アンケート回答後、その場でギフトを付与するシステムです。アンケートツールやギフト付与など、アンケート施策実施にあたって必要なサービスの包括的な提供が可能です。
「Survey(アンケートシステム)」ついてより詳しくお知りになりたい方は資料も用意しましたので、ぜひご覧ください。ぜひご活用ください。
アンケート謝礼にはどんな種類がある?
アンケート謝礼を設計する際、まず知っておきたいのが謝礼の種類です。謝礼には大きく分けて「現物の商品」と「デジタルギフト」の2種類があります。
現物の商品
現物の謝礼には、商品券、ギフトカード、実際の製品などがあります。
メリット
- 高額商品や限定品で高い満足感を提供できる
- 実物として価値が伝わりやすい
注意点
- 商品の配送に手間やコストがかかる
- 参加者の好みに合わない場合、満足度が下がる可能性がある
デジタルギフト
デジタルギフトは、電子ギフトカード、ポイント、クーポンコードなど、オンラインで提供される謝礼です。
メリット
- 即時提供でき、在庫管理が不要
- 回答者もスマートフォンで手軽に受け取れる
- 発送コストを大幅に削減できる
注意点
- PCやスマートフォンの操作が必要
- 高齢者など、デジタル機器に不慣れな層には不向きな場合がある
謝礼を選ぶ際は、ターゲット層の特性やアンケートの目的に応じて慎重に検討することが重要です。このように謝礼を選んでいくことで、よりアンケートの回答率を向上させましょう。
アンケート謝礼の相場はどのくらい?
アンケート謝礼の予算を決める要因はさまざまにありますが、そのなかのひとつとして、個人向けアンケートか、法人向けアンケートなのかが挙げられます。
その理由として、アンケート回収の難しさがあります。
法人向けのアンケートは、個人向けアンケートと異なり、対象者の母数が少なかったり、顧客接点を持つことが難しかったりと、アンケート回収の難易度が個人向けに比べて高くなります。そこで謝礼単価を上げて、回答率を上げる傾向がみられます。
そこで今回は、「法人向け・個人向け」の2つに分け、それぞれの相場を解説していきます。

ケースごとのアンケート謝礼金額相場をご紹介
それでは早速、個人向け・法人向けそれぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。
個人(toC)向けアンケート謝礼の相場
まずは、個人のお客様向けのアンケート謝礼相場についてです。
新規顧客獲得や顧客情報の獲得など、一人でも多くの方にリーチし、ご回答をいただきたい場合、100円〜300円程度の低単価ギフトを全員にお渡しし、裾野を広げて回答を募る傾向にあります。カフェチケットやコンビニエンスストアで使えるギフトのほか、100円から自由に金額設定ができる「giftee Box」などがよく使われております。
一方、toCサービスの中でも金融・不動産といった顧客単価が高いサービスや、顧客接点を持ちづらいものについては、回答者全員に2,000円〜3,000円のギフトをプレゼントすることをフックに、お客様との接点を生み出す手法が使われています。
また、オンラインインタビューなど、お客様のお時間を長めにいただく場合には、業界を問わず3,000円〜1万円程度の謝礼をお渡しする企業様が多くなっています。
全員にギフトをプレゼントするほか、抽選で対象者を絞るパターンもあります。
購入者や会員向けアンケートなど、対象者は限定しつつもなるべく多くの回答を求める場合、抽選という手法が取られる傾向にあります。いわゆる「目玉商品」として、1等にお肉や旅行券といった5,000円〜1万円程度の高単価ギフトを設定し、ダブルチャンスとして500円程度のデジタルギフトを使用するパターンも頻繁に見受けられます。
法人(toB)向けアンケート謝礼の相場
toB向けサービスのユーザーや、ビジネスイベント来場者など、法人のお客様を対象としたアンケートの相場について解説いたします。
そもそもの対象者数が限られていることや、個人向けに比べるとアンケート回答のハードルが高いこともあり、より高価格、かつ全員にプレゼントとなることが多いです。金額としては500円以上のギフトが使用される傾向があります。
一方で、展示会やセミナー参加者を対象としたアンケートなど、アンケート回収もさることながら、来店・イベント参加の促進を主な目的とし、多くの人数に配布する場合には、100円〜200円程度の低単価ギフトがよく使用されています。
また、抽選とする場合には、業界誌の読者アンケートとして1,000円程度のギフトを用意したり、展示会来場者アンケートの謝礼として3,000円程度のギフトを抽選でプレゼントしたりすることが多いようです。
法人向けのアンケートの場合、回答者属性が広いこともあり、受け取り手が商品を選べる「えらべるPay」などが好まれています。
謝礼金額を決める3つのポイント
ここまで相場を紹介してきましたが、実際に自社のアンケートで謝礼金額を決める際には、どのような点を考慮すればよいのでしょうか。金額設定の判断材料となる3つのポイントを解説します。
ポイント1:回答に要する時間で決める
アンケートの回答にかかる時間が長くなるほど、謝礼の金額も高くなる傾向があります。
たとえば、Webアンケートで数十円の謝礼を設定していたとして、回答に10分、20分かかってしまえば「割に合わない」と感じられてしまい、回答してもらえなかったり、途中で離脱されてしまう可能性があります。
ただし、2択形式などの簡単な質問であれば、設問数が多くても問題ないでしょう。一方で、記述式や全問解答必須のアンケートでは、設問数が少なくても負担が大きくなるため、高めの謝礼を設定する必要があるかもしれません。
ポイント2:対象者の属性で決める
金融や不動産業界のように高単価商品を扱う業界では、顧客の信頼を得て成約に結びつけるために、アンケートを顧客との重要な接点として活用しています。
たとえば、マンションや保険の契約に関連するアンケートでは、謝礼として数千円〜1万円相当のギフトカードや高級商品を提供することがあります。一方で、一般的な消費者向けアンケートでは、100円〜500円程度の謝礼で十分な回答を得られることも多いです。
このように、対象者の属性や商材の特性に応じても謝礼の金額を調整することが可能です。
ポイント3:配布方法(全員/抽選)で決める
謝礼の配布方法によっても、適切な金額は変わってきます。
全員に謝礼を提供する場合は、回答者は確実に報酬を受け取れるとわかっているため、回答するモチベーションが高まります。比較的低単価(100円〜500円程度)でも十分な効果が期待できるでしょう。
抽選方式の場合は、全員に謝礼を用意する必要がない分、魅力的な謝礼や高額な謝礼を用意しやすくなります。「目玉商品」として高単価ギフト(5,000円〜1万円程度)を設定することで、回答数を増やしやすいというメリットがあります。
謝礼金額を決めるにあたっては、景表法などの法規制にも要注意
アンケート施策の内容によっては、景品表示法(景表法)の規制対象になることがあります。もし景表法の対象となる場合、使用する謝礼の金額に制限があるので、施策実施前に各企業様の法務・コンプライアンス部門へご確認ください。
景表法の規制対象となるか否かは、アンケートが「取引に付随するか」がポイントです。商品の購入やサービスの利用、来店の誘引手段としてアンケートが用いられていると考えられる場合、対象となる場合があります。
また、保険業界など、業界によっては、景品の提供に関するルールが別途存在する場合がありますので、アンケート謝礼を用意するときは、自社が属する業界のルールも確認しておくと良いでしょう。
各法律に関しては、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。
アンケート結果を効果的にまとめる分析手法
アンケートで収集したデータをそのまま保管しているだけでは、せっかくの情報資産が活かしきれません。施策や事業戦略に反映するためには、適切な集計・分析・可視化が不可欠です。
まずは回答の全体像を把握できる単純集計から始めましょう。そこから、年齢や性別、業種など回答者の属性ごとに違いを比較するクロス集計を行うことで、より深い洞察を得ることができます。
回答者属性ごとにクロス集計を行い、違いや傾向を把握する
グラフや表をデータに合わせて選び、視覚的にわかりやすく表現する
分析結果を踏まえて、次に取るべきアクションを明確にする
最終的には、こうして得られた分析結果から具体的なアクションプランを導き出し、次の施策に反映することがゴールです。
効果的なデータ分析の詳細な手法について知りたい方は、以下の記事にて、集計方法から可視化のテクニックまで実践的なノウハウを解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
デジタルギフトで実現する業務効率化
一方で、法規制の条件を満たした上で実務面を考えると、謝礼の手段としてはデジタルギフトが非常に有効です。
なぜなら、物理的なギフトを一度発注してしまうと、仕様変更への対応が難しいからです。
たとえば、キャンペーンにおける景品類の上限額は景表法上の形式(一般懸賞=抽選や競技など、総付=参加者全員に配布など)によって異なります。当初は一般懸賞として設計していたものを、途中で「総付」に切り替える場合、上限額の調整が急務となります。しかし、すでに物のギフトを発注していると、金額変更や差し替えが困難なのです。
その点、デジタルギフトであれば、最小1円から金額設定が可能な柔軟性が最大の魅力です。さらに、在庫管理や配送が不要なため、業務効率化にもつながります。
受け取り側にとっても、スマートフォンですぐに利用でき、好きな商品を選べる利便性の高さが好評です。配送先情報が不要なため、個人情報管理のリスクも軽減され、コンプライアンス面でも安心です。
デジタルギフト活用の効果
- 最小1円から金額設定が可能な柔軟性
- 配送・管理コストを削減
- 利便性の高さによるユーザー満足度の向上
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事にて、導入企業の具体的な成果について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
アンケート謝礼の送付に使える!効果的なメール例文
ちなみに、アンケートへの謝礼を送る際、どのようなメールを送れば良いか悩むことはありませんか?適切なお礼メールを送ることで、回答者の満足度向上や企業イメージの向上につながります。
アンケート謝礼のメールには「お礼の言葉」「アンケート内容の活用指針」「謝礼の品に関する案内」「問い合わせ先」という4つの要素を盛り込むことが重要です。さらに、謝礼の種類(デジタルか物理か)や配布方法(全員か抽選か)によって、メールの内容や構成を使い分けることで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。
全員プレゼントの場合と抽選の場合、デジタルギフトと物理ギフトそれぞれの状況に合わせた例文を活用することで、お客様への感謝の気持ちを適切に伝えられるだけでなく、企業としてのプロフェッショナリズムも示すことができます。
アンケート謝礼送付メールを作成する際のポイント
具体的な案内を心がける:どのアンケートに対する謝礼か、いつ頃届くのか、どう使うのかなど、明確な情報提供が回答者の安心感につながります
謝礼の受け取り方法を分かりやすく説明する:特にデジタルギフトの場合は、受け取り方法の手順や注意点を丁寧に説明しましょう
アンケート回答の活用方法を伝える:回答がどのように活かされるかを伝えることで、回答者の満足度向上と今後の協力意欲を高められます
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事にて、アンケート回答のお礼メールおよびお礼状に盛り込むべき内容から、具体的な例文まで解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
アンケート謝礼にデジタルギフトを活用した企業の事例
本章では、デジタルギフトでアンケート回答率向上を実現した企業様の事例をご紹介します。
LINEアンケートで回答数目標120%達成
企業/ブランド名 | 株式会社LIFULL |
|---|---|
目的 | LINE公式アカウントでのユーザーアンケート実施 ターゲット層からの十分なフィードバック収集 |
成果 | 当初の回答数目標に対して120%達成 システム連携による完全自動化で問い合わせ対応工数がほぼゼロに |
株式会社LIFULL様では、不動産情報サービス「LIFULL HOME'S」のLINE公式アカウントを通じてユーザーアンケートを実施していました。従来のアンケートでは回答数が伸び悩み、ターゲット層から十分なフィードバックを得ることが課題となっていました。
そこで、LINEアンケートとgiftee for Businessのシステムを連携。アンケート回答完了と同時に、抽選でAmazonギフトカード500円分を自動配布する仕組みを導入しました。
回答直後に結果を表示し、当選者にはその場でギフトコードを送信することで、参加体験の満足度を大幅に向上。その結果、わずか2週間で回答数が目標比120%を達成し、ユーザー満足度を高めることに成功しました。
▼この事例の詳細はこちら
アンケート謝礼単価見直しで回答数が想定以上に
企業/ブランド名 | アイベックスエアラインズ株式会社 |
|---|---|
目的 | 仙台=広島線PR施策検討を目的とした顧客ヒアリング |
成果 | 謝礼単価を下げ当選者数を増やしたことで想定以上の回答を獲得 景品手配や住所問い合わせ等の運用工数を大幅に削減 |
アイベックスエアラインズ株式会社様では、仙台=広島線のPR施策検討にあたり、搭乗客へのアンケートを実施していました。従来は航空券や産直品などの高額景品を用意していましたが、予算の制約から当選者数を絞らざるを得ず、回答数が伸び悩んでいました。
そこで、1,000種類以上から選べるデジタルギフト「giftee Box」200円分を抽選で200名にプレゼントする施策に変更しました。
謝礼の単価を下げて当選者数を増やしたことで、降機後に想定以上のお客様がアンケートに回答。さらに、デジタルギフト活用により景品の手配や住所問い合わせなどの運用工数も大幅に削減できました。
▼この事例の詳細はこちら
組合員アンケートで1万件の回答目標を110%達成
企業/ブランド名 | ニトリ労働組合 |
|---|---|
目的 | 年次の組合員意識調査における高い回答率の確保 |
成果 | 1万件の回答目標に対し110%(11,000件)達成 イベント会場での即時回答により回収期間を大幅に短縮 組合員からの満足度向上と次回調査への協力意向向上 |
ニトリ労働組合様では、全国に約15,000名の組合員を擁する中で、年次の組合員意識調査において地理的に分散した組合員から高い回答率を得ることが課題でした。従来の紙ベースの調査では配布・回収に時間がかかり、回答率も伸び悩んでいました。
そこで、組合イベント会場で二次元コードを配布し、その場でアンケート回答を促進する仕組みを導入。回答完了後、即座にAmazonギフトカードを含むgiftee Box500円分を配布しました。「その場で回答、その場で受け取り」という即時性により、1万件の回答目標に対し110%を達成。
組合員が普段から集まる場を活用したことで、自然な形でアンケート協力を得ることができました。
▼この事例の詳細はこちら
アンケート謝礼におすすめのデジタルギフト3選
最後に、実際のアンケート謝礼としてよく利用されている代表的なデジタルギフトを3つご紹介します。いずれも法人向けの購入方法が整備されており、大規模配布にも対応できるため、アンケート施策に適しています。
Amazonギフトカード
Amazonギフトカードは、少額から高額まで幅広い金額設定が可能で、アンケート謝礼として最も利用されているデジタルギフトの1つです。全国共通で使いやすく、書籍から日用品まで豊富な商品が揃うAmazonで利用できるため、受け取り側の利便性が非常に高いのが特徴です。法人向けの購入方法も充実しており、大規模な配布にも対応できます。
こんなシーンにおすすめ
- 幅広い年代・属性の回答者がいるアンケートを実施する
- 100円〜3,000円程度の範囲で柔軟に謝礼額を調整したい
- 受け取り側の利便性を最重視したい
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事で、法人での活用方法について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
PayPayポイントコード
PayPayポイントコードは、決済アプリ「PayPay」で利用できるポイントをデジタルで贈れるギフトです。スマートフォン決済の普及により、特に若年層を中心に高い人気を誇ります。コンビニエンスストアからオンラインショッピングまで幅広いシーンで利用でき、即時性があるため謝礼として喜ばれます。
こんなシーンにおすすめ
- 20代〜40代のスマートフォンユーザーがメインターゲット
- 即座に使える謝礼で回答率を高めたい
- 決済アプリの利用が多い都市部がターゲット
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事で、法人での導入事例について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
QUOカードPay
QUOカードPayは、スマートフォンで簡単に使えるデジタル版のQUOカードです。コンビニエンスストアをはじめ、ドラッグストア、飲食店など全国の幅広い店舗で利用可能。アプリのダウンロードや会員登録が不要で、URLを送るだけで贈れる手軽さが特徴です。特に法人向けアンケートの謝礼として人気が高く、500円〜1,000円程度の中価格帯での利用が多くなっています。
こんなシーンにおすすめ
- BtoB企業で、ビジネスパーソン向けアンケートを実施する
- 展示会やセミナー参加者へのアンケート謝礼
- デジタルに不慣れな層も含む幅広い年代にリーチしたい
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事で具体的な活用方法について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
まとめ
今回は、アンケート謝礼の相場感を、法人向け・個人向けに分けて解説いたしました。予算や目的などに合わせて、ギフトの選択肢は幅広く持っておく必要があります。
ギフティでは、コンビニエンスストアで使えるギフトから、旅行やお肉などの豪華なギフトまで、金額も種類も幅広くラインナップを取り揃えております。
また、謝礼の配布方法も、複数ご提案が可能です。
アンケート謝礼の配布を効率化したいご担当者様へ
こんなお悩みはありませんか? ・アンケート謝礼の相場がわからない ・どの程度の金額感の謝礼を用意するか悩んでいる ・謝礼の発送の手間やコストを削減したい ・アンケート実施から謝礼の配布までを効率化したい
アンケート施策では、謝礼の金額設定だけでなく、配布方法や運用のしやすさも成果に大きく影響します。相場を踏まえて適切な謝礼を用意できても、発送や管理に手間がかかると、運用負担が増えてしまうケースも少なくありません。
そこで累計導入件数7万件以上、法人向けデジタルギフト導入実績No.1のgiftee for Businessでは、アンケート実施から謝礼配布までを一元管理できる「Survey(アンケートシステム)」を提供しています。アンケート回答後、その場でギフトを付与するシステムです。アンケートツールやギフト付与など、アンケート施策実施にあたって必要なサービスの包括的な提供が可能です。
「Survey(アンケートシステム)」ついてより詳しくお知りになりたい方は資料も用意しましたので、ぜひご覧ください。ぜひご活用ください。