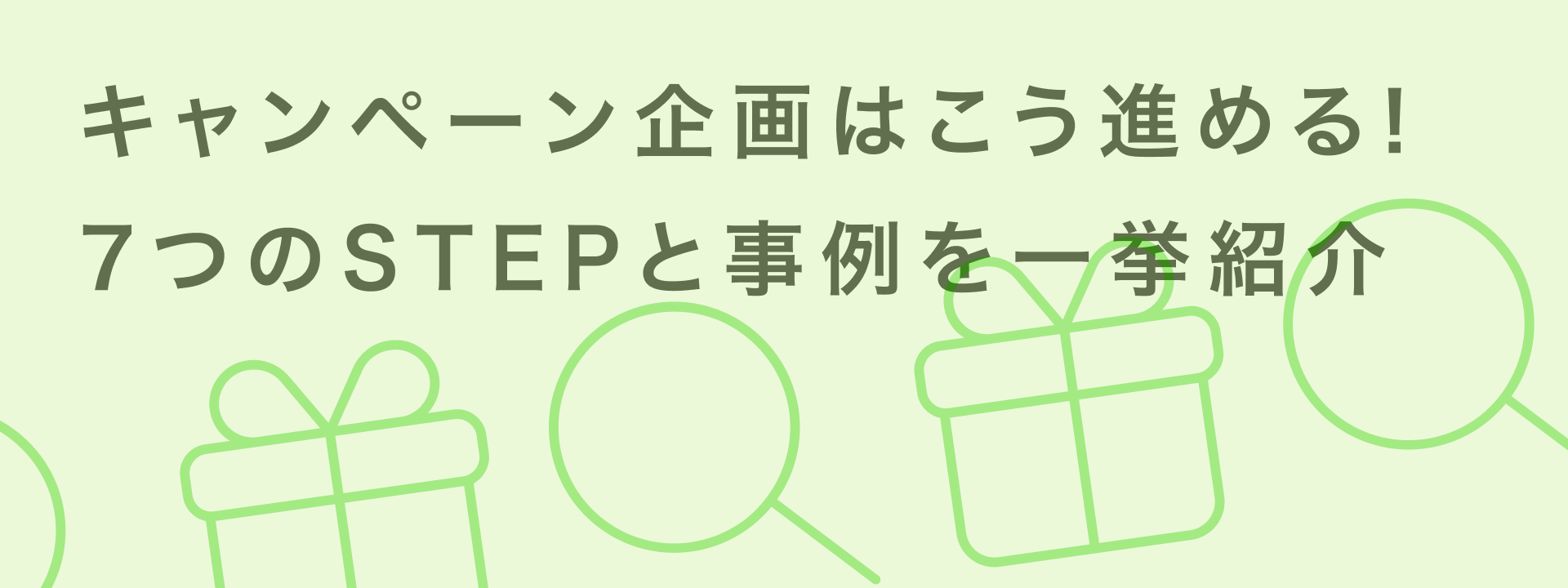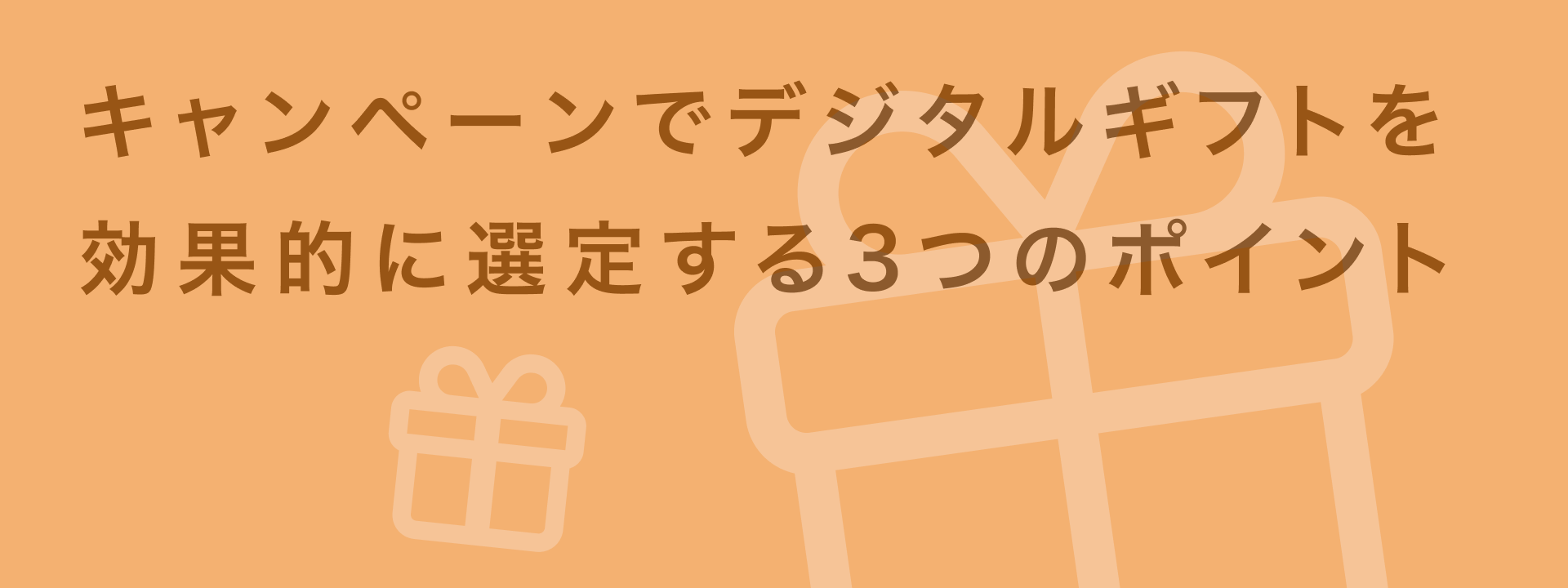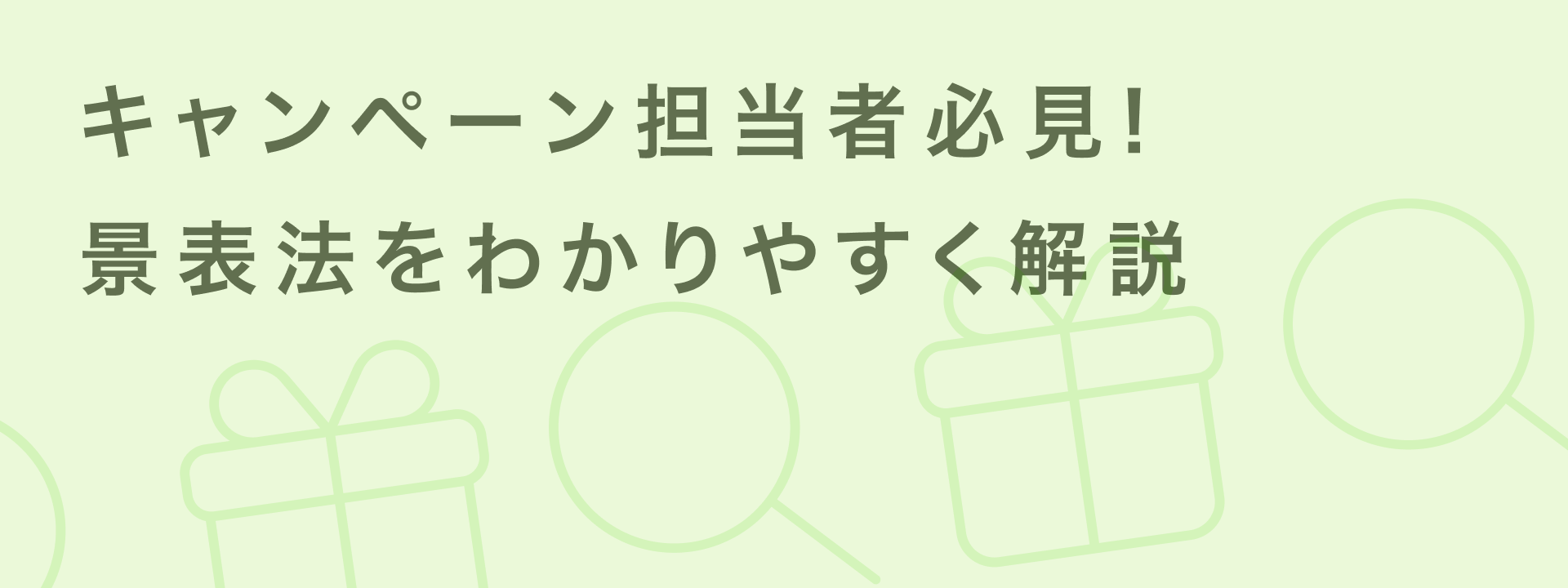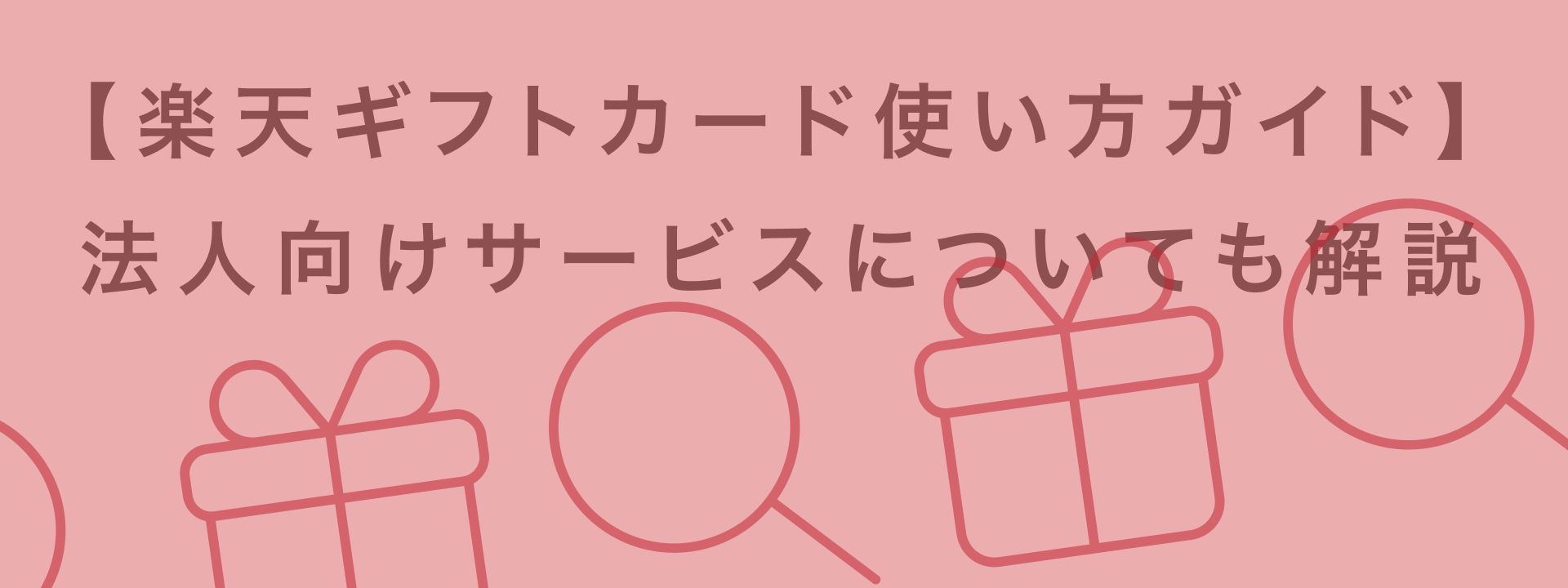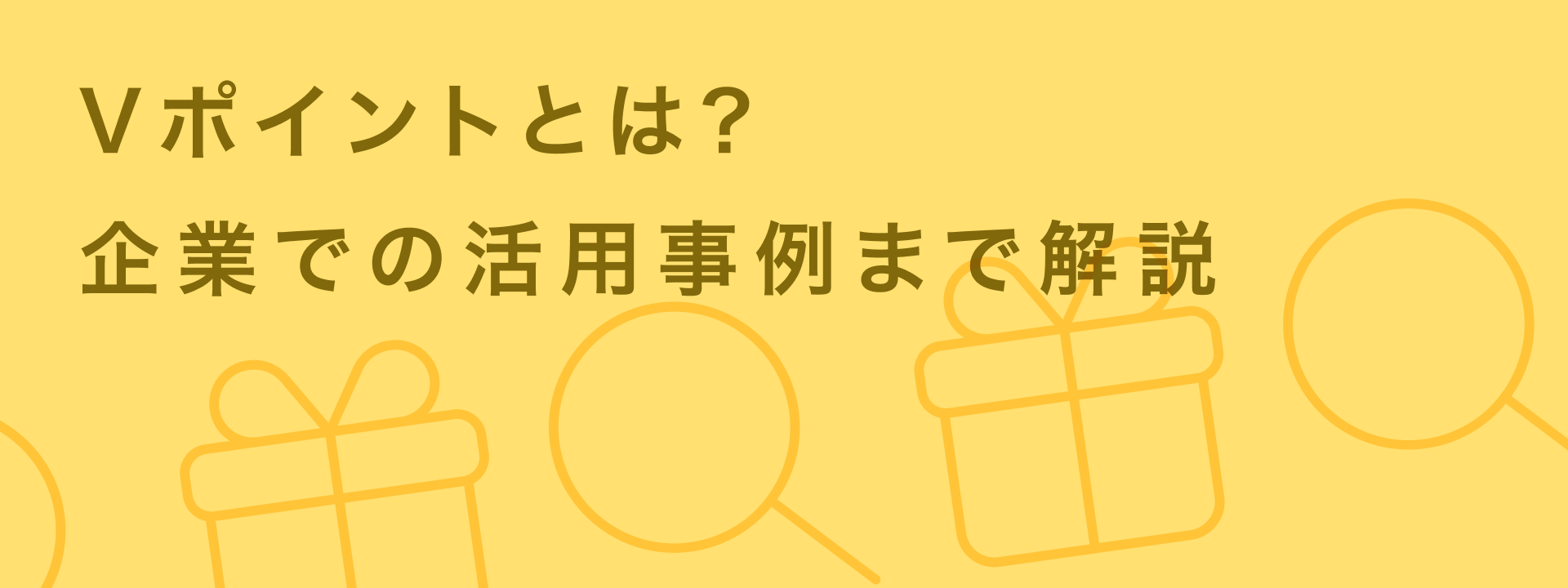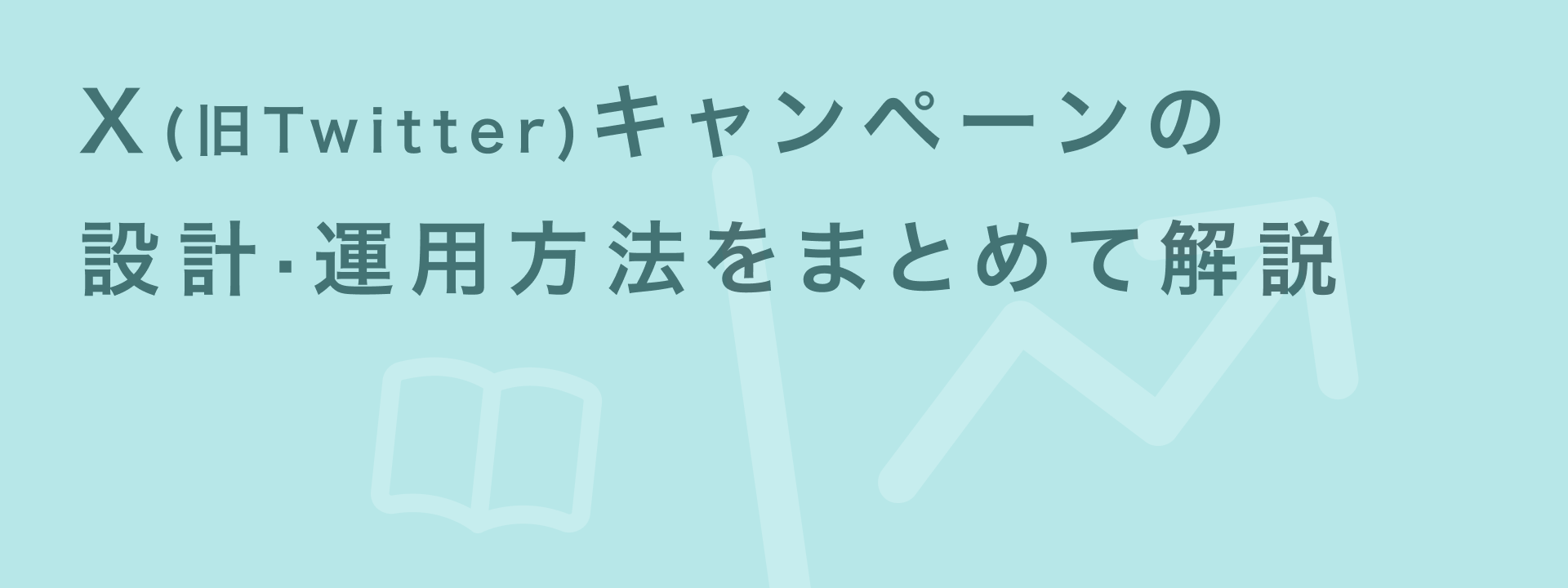Xインスタントウィンとは?フォロワー獲得に有効なキャンペーンの設計法を解説
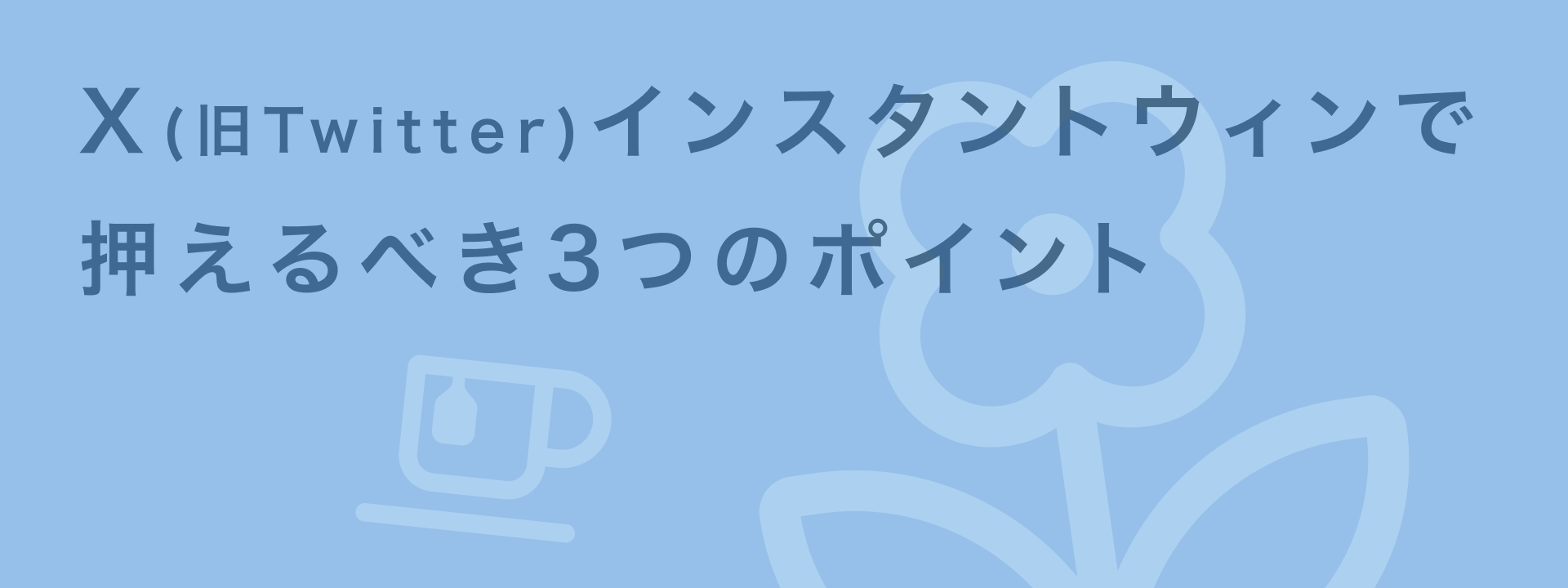
X(旧Twitter)で実施するインスタントウィンキャンペーンとは、フォロー&リポストなどの条件を達成した方が参加できる、即時抽選形式のキャンペーンです。
インスタントウィンで抽選を行うことで参加ハードルを下げ、参加者数を増やす効果があります。また、その場で結果がわかることで、ユーザーに楽しみながら抽選に参加してもらえます。
本記事では、Xインスタントウィンキャンペーンのポイントや実施手順について解説します。また、ツールの選び方についても解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
Xインスタントウィンのキャンペーンの運用にお困りのご担当者様へ
・どの抽選ツールを選べば良いか分からない ・APIの変更に対応したツールを探している ・景表法などのルールを守りながらキャンペーンを運用したい ・手間をかけずに当選者へギフトを送付したい
このような課題を解決する「X (キャンペーンシステム)」では、参加条件を満たした参加者に対し、その場で抽選、当選者にはそのまま景品を付与するキャンペーンの実施が可能です。参加条件の確認や抽選などの作業が自動化できるため、実施の手間を削減できます。
本資料では、Xで実施されるキャンペーンごとのシステムの活用イメージや、料金プランについて詳しくご紹介しています。
そもそもインスタントウィンとは?
Xインスタントウィンとは、X(旧Twitter)上で実施する「即時抽選キャンペーン」のことです。フォロー&リポストなどの参加条件を満たしたユーザーが、その場ですぐに抽選結果を確認できる手法です。
従来の「後日抽選」とは異なり、応募と同時にリプライやDMで当落が通知される仕組みのため、ユーザーにとっての参加ハードルが低く、エンターテインメント性が高い点が特徴です。
Xインスタントウィンの仕組み
Xインスタントウィンキャンペーンは、以下のような流れで実施されます。
【基本的な流れ】
- 企業がキャンペーン告知ポストを投稿
- ユーザーが参加条件(フォロー&リポストなど)を満たす
- システムが自動で参加条件を判定
- その場で抽選を実施
- 当落結果をリプライまたはDMで即時通知
- 当選者にデジタルギフトなどの景品を自動配布
この一連の流れが自動化されているため、従来のキャンペーンと比較して運用工数を大幅に削減できるのが特徴です。
後日抽選との違い|比較表
Xキャンペーンには、インスタントウィン(即時抽選)と後日抽選の2つの方式があります。それぞれの特徴を理解し、キャンペーンの目的に応じて選択しましょう。
項目 | インスタントウィン | 後日抽選 |
|---|---|---|
結果発表のタイミング | 応募後すぐ(数秒〜数分) | キャンペーン終了後(数日〜数週間後) |
参加ハードル | 低い(その場で結果がわかるため気軽に参加できる) | やや高い(結果を待つ必要があり、参加意欲が低下しやすい) |
必要な景品単価 | 比較的低額でも参加者を集めやすい | 高額な景品でないと参加意欲が湧きにくい |
当選者数の設定 | 多数の当選者を設定しやすい | 当選者数を抑える傾向がある |
運用工数 | ツール導入で自動化可能(工数削減) | 抽選・通知作業に一定の工数が必要 |
ユーザー体験 | エンターテインメント性が高い | 期待感を長く持続させられる |
適したキャンペーン目的 | 認知拡大、フォロワー獲得、参加者数の最大化 | 高額景品で話題性を狙う、じっくり検討させたい商品のPR |
【選び方のポイント】
インスタントウィンは、参加ハードルを下げて多くのユーザーに参加してもらいたい場合に最適です。一方、後日抽選は高額な景品を用意し、話題性や期待感を長期間維持したい場合に適しています。
キャンペーンの目的や予算、ターゲット層に応じて、最適な方式を選びましょう。
Xでインスタントウィンキャンペーンを実施するメリット
ほかのSNSではなくXでインスタントウィンキャンペーンを実施するメリットとして、以下の4つが挙げられます。
リポストでの拡散により認知拡大が期待できる
フォロワーを効率的に増やせる
参加ハードルが低く、多くのユーザーの参加が期待できる
リポストでの拡散により認知拡大が期待できる
XはInstagramなどのSNSに比べ、拡散力の高さが特徴です。リポストによって情報が短期間で拡散されやすく、効率的に認知拡大できます。
また、Xのアルゴリズムは、リポストやいいねなどエンゲージメントが高い投稿を優先的に他のユーザーのタイムラインに表示します。そのため、リポストが増えると投稿が「有益」と判断され、さらに拡散されやすくなります。
Xでインスタントウィンキャンペーンを行う際に「キャンペーンポストをリポスト」を条件にすることで、キャンペーンに参加するユーザーがリポストを行い、情報が拡散される仕組みです。
フォロワーを効率的に増やせる
Xでインスタントウィンキャンペーンを行う場合、リポストのほかに「公式アカウントのフォロー」を参加条件とすることが一般的です。参加したいユーザーは公式アカウントをフォローしてくれるため、効率的にフォロワーを増やせます。
フォロワーを増やしておくことで、キャンペーン後の情報発信がより多くのユーザーに届くようになります。また、再度キャンペーンを実施した際にも、参加数の増加が期待でき、より効果的に認知拡大ができるでしょう。
参加ハードルが低く、多くのユーザーの参加が期待できる
インスタントウィンキャンペーンは、後日抽選と比較して、参加ハードルが低く、多くのユーザーに参加してもらいやすいキャンペーンです。
後日抽選は、期間内にキャンペーン応募を行ったユーザーに対し、応募締め切り後にまとめて抽選や景品の配布を行う仕組みです。応募者は結果発表まで待つ必要があるため、魅力的で高額な景品を用意しないと参加意欲が低下しやすいというデメリットがあります。
対してインスタントウィンは、後日抽選と比較して参加ハードルが低く「その場で当たる」というエンターテインメント性があるため、高額な景品を用意しなくてもユーザーの興味を引きやすいのです。
さらに、景品の金額を下げれば、当選数を増やせます。当選数が多ければ当選への期待値が高まり、さらに参加者を増やせるでしょう。
Xインスタントウィンキャンペーンを実施する際のポイント
Xでインスタントウィンキャンペーンを実施する場合、以下のポイントを押さえておきましょう。
キャンペーンの目的を明確にする
参加条件をシンプルにする
当選者数を多くする
適切なツールを選ぶ
景品をデジタルギフトにする
キャンペーンの目的を明確にする
Xでインスタントウィンキャンペーンを実施する際には、目的を明確に設定することが重要です。たとえば、以下のような目的が考えられます。
認知度向上
新規顧客獲得
購買促進
来店・来場促進
会員登録促進
目的を明確化することで、それに応じた応募条件や景品設計ができるようになります。
参加条件をシンプルにする
Xでインスタントウィンキャンペーンを実施するのであれば、誰でも簡単に参加できる条件を設定しましょう。たとえば、代表的かつ参加ハードルが低いキャンペーンとして「フォロー&リポストキャンペーン」などがあります。
特に、認知拡大やフォロワー獲得を目的として、多くのユーザーに参加してもらいたい場合は、参加ハードルはできるだけ下げた方が効果的です。
ただし、目的によって設定すべき参加条件は異なるため、必ずしも「フォロー&リポストキャンペーン」を実施すべきというわけではありません。自社の目的を達成するための参加条件を検討する際に「参加ハードルを下げるにはどうすべきか」を考えることが重要です。
当選者数を多くする
当選者数を増やすことで、ユーザーは「当たるかもしれない」という期待感を持ちやすくなり、参加意欲が向上します。
たとえば、
10,000円分のギフトを10名様にプレゼント
500円分のギフトを200名様にプレゼント
という2種類のキャンペーンがあった場合、前者は「どうせ当たらないだろう」と思われて参加してもらえない可能性がありますが、後者は200名と当選者数が多いため「当たるかも!」という期待感が高められます。
また、
毎日1回参加可能
外れてもダブルチャンス
といったように、よりエンターテインメント性を持たせたキャンペーンにすることで、より参加数を増やせるでしょう。
適切なツールを選ぶ
インスタントウィンキャンペーンを実施するには、ツールが必要不可欠です。しかし、インスタントウィンツールはさまざまな種類があるため、適切なものを選ぶことが求められます。
中には、無料で利用できるツールもありますが、利用できる機能が限られていたり、ノウハウが必要になったりするため、余計にキャンペーン運用の手間が増してしまう可能性もあります。
また、有料ツールであっても対応しているXキャンペーンが異なったり、当選確率を設定できたりするツールもあるため、自社に適したものを選定することが重要です。
実施したいキャンペーンの内容に合わせて、運用を効率化・自動化できるツールを選びましょう。
景品をデジタルギフトにする
景品は現物のギフトではなく、デジタルギフトを活用するのがおすすめです。インスタントウィンキャンペーンは、基本的にツールで以下の工程を自動化できます。
条件判定
抽選
当選結果の発表
景品の配布
しかし、現物のギフトを用意した場合、最後の工程である景品の配布を人の手で行わなくてはならなくなります。景品を梱包して発送する手間が増えるため、その分運用の負担が大幅に増えるのです。
また、現物のギフトでは少額の景品を用意しにくいというデメリットもあります。キャンペーンの運用を効率化し、なおかつ当選者数を増やしたいのであれば、少額にも対応しているデジタルギフトがおすすめです。
Xインスタントウィンのキャンペーンの運用にお困りのご担当者様へ
・どの抽選ツールを選べば良いか分からない ・APIの変更に対応したツールを探している ・景表法などのルールを守りながらキャンペーンを運用したい ・手間をかけずに当選者へギフトを送付したい
このような課題を解決する「X (キャンペーンシステム)」では、参加条件を満たした参加者に対し、その場で抽選、当選者にはそのまま景品を付与するキャンペーンの実施が可能です。参加条件の確認や抽選などの作業が自動化できるため、実施の手間を削減できます。
本資料では、Xで実施されるキャンペーンごとのシステムの活用イメージや、料金プランについて詳しくご紹介しています。
Xインスタントウィンキャンペーン実施のための5つの手順
Xインスタントウィンを成功させるには、思いつきで着手するのではなく、まずは計画を立てることが重要です。
計画は「目的の設定」から「効果測定」までを一貫して設計しておくことで、実施中に改善点を見つけたり軌道修正したりしやすくなり、結果、成功につながりやすくなるでしょう。
キャンペーン企画の具体的な進め方は以下の記事にて解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
キャンペーンを実施する際には、以下の手順で進めましょう。
企画内容を決める
どのツールを利用するか決める
ターゲットを見据えてコンテンツや景品を考える
プロモーション・告知を行う
キャンペーンスタート
1.企画内容を決める
自社の目的から、企画内容を決めましょう。目的を設定した後、以下のような内容を検討します。
参加条件
キャンペーン期間
参加回数(例:毎日参加可能など)
また、参加してほしいターゲット層も明確にしておきましょう。ターゲットによって選ぶべき景品も変わるからです。
2.どのツールを利用するか決める
どのツールを使用するかを決定しましょう。ツールは、以下のいずれかの方法で準備します。
自社で開発する
インスタントウィンツールのASPサービスを利用する
デジタルギフトサービスなどが提供しているツール(SaaS)を利用する
上記いずれかの方法でツールを準備しましょう。
なお、おすすめの外部ツールを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
3.ターゲットを見据えてコンテンツや景品を考える
X上のキャンペーンを見ると、電子マネー、ポイント、家電製品、日用品、旅行券などさまざまな景品が見られます。そのため「どのように景品を選ぶべきか」と悩むケースもあるでしょう。
そして、景品がキャンペーンの成否を大きく左右する、と言っても過言ではありません。単に高価な景品を用意するのではなく、参加者が日常使いしやすく、かつ自社との接点強化につながりそうなものをえらぶと良いでしょう。そうすることで、一時的なキャンペーン参加に終わらず、継続的な顧客との関係構築につながります。
また、受け取った人が自由にえらべるタイプのデジタルギフトを活用すれば、満足度を高めながら配布コストを抑えられます。さらに利用データの取得も可能になり、次回の施策に活かせます。
ポイント
- 参加者のライフスタイルや好みに合う景品をえらぶ
- 自社商品・サービスとの関連性を意識して景品を設計する
- 在庫管理や配送負担を減らし、データ取得も可能なデジタル化を検討する
キャンペーン景品の選び方と人気商品について詳しく知りたい方は以下の記事にて、効果的な景品選定の具体的な手法などを解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
景品を選定する際には、以下のポイントを押さえておきましょう。
ターゲットのニーズを見極める
まず、大前提としてターゲットのニーズに合う景品かが重要です。
たとえば、外食に関するキャンペーンを実施する場合、普段から外食をするユーザーがターゲットとなるでしょう。その場合、レストランで利用できる金券を景品にすれば、喜ばれる可能性は高いと考えられます。
また、旅行関連のキャンペーンなら、旅行券や体験ギフトなどが喜ばれる可能性が高いでしょう。
ターゲットのニーズに合った景品を選べるかは、キャンペーンの参加率に影響するため「どのようなものが景品なら、ターゲットが参加したくなるのか?」を十分に検討しましょう。
当選者がプレゼントを使える場所にいるか
電子マネーやポイントの場合、当選者は場所や時間を気にせず自由に使うことができますが、実店舗を利用する必要がある景品(商品引換券など)は利用できない場合があります。特にXなどのSNSを通じて、さまざまな地域に住んでいるユーザーを対象にキャンペーンを実施する場合は、注意しなければいけません。
キャンペーンとの親和性はあるか
ユーザーがキャンペーンに興味を持ってもらうためにはコンテンツ自体の魅力を作り上げ、コンテンツに触れた際のブランドメッセージを賞品で拡張させる、という形が取れると理想的です。
たとえば、自動車メーカーが宿泊券を贈ることは、コンテンツに接触した際にユーザーが想像する「自動車を持つことで体験できる旅行の楽しさ」を賞品で補完することにつながり、ソーシャルゲームでiTunesやGoogleの電子コードを贈ることは、課金してもっと遊んでもらうことにつながります。
4.プロモーション・告知を行う
より多くのユーザーに参加してもらうために、キャンペーンに関するプロモーションや告知を行いましょう。主に以下のような方法があります。
Web広告
自社Webサイトでの宣伝
キャンペーン専用LPの作成
メルマガやプッシュ通知で告知
実店舗でのポスターやPOP掲示
自社に適した手法を組み合わせ、キャンペーンを周知しましょう。
5.キャンペーンスタート
キャンペーンポストを投稿し、キャンペーンを開始します。
キャンペーンに関する問い合わせがあれば対応し、当選者の投稿をリポストするなど、ユーザーとのコミュニケーションも図りましょう。また、応募数や参加率をリアルタイムで確認し、必要に応じて告知内容を見直すなどしてください。
キャンペーンが終了したら「インプレッション数」や「リポスト数」「いいね数」などのエンゲージメント指標を分析し、次回に活かしましょう。
Xインスタントウィンツール選びの5つのポイント
キャンペーンに合わせて適切なツールを選ぶ必要があるとお伝えしたものの、実際にどうやってツールを選べばよいかわからないという方もいらっしゃるでしょう。そこで、ツールの選び方も紹介します。
ツールを選ぶ際には、以下のポイントを押さえておきましょう。
キャンペーンに必要な機能が搭載されているか
商用利用が可能か
月額制か都度契約か
景品と紐づけられるか
必要な支援が受けられるか
キャンペーンに必要な機能が搭載されているか
Xのインスタントウィンツールにはさまざまな種類があり、それぞれ機能も異なります。そのため、自社の行うキャンペーンにあわせて、最適なツールを選ぶことが重要です。
Xでは、有料のAPIプランがあります。各プランによって、毎月の参加条件の判定数や非公開アカウントの参加可否に制限の設定など、利用できる機能の違いがあります。
また、SNS完結型なのか、URL遷移型なのかも確認しておきましょう。
| 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
SNS完結型 | ・ユーザーがSNS上でキャンペーンに応募すると、リプライやDMで結果が通知される ・SNS内ですべてが完結するため、手軽に参加でき、応募数やフォロワー増加が期待できる | SNSごとの投稿・DMの送信制限がある |
URL遷移型 | ・SNS投稿や広告に記載されたURLにアクセスし、抽選結果を確認する ・キャンペーンと同時に、商品情報の提供や会員登録などの追加アクションを促せる | 応募フォームの入力が必要な場合もあり、参加ハードルはやや高くなる |
商用利用が可能か
無料の個人向けツールは利用規約で商用利用が禁止されている場合があるため、商用利用可能なツールを選ぶことが必須です。これに違反すると、アカウントが停止される可能性もあります。
Xのガイドラインに準拠しているかも確認しましょう。
月額制か都度契約か
ツールが月額制か都度契約化で、ツールの利用にかかるコストが変動します。キャンペーンを毎月実施するかどうかなども考慮して、契約形態を選ぶことも大切です。
景品と紐づけられるか
Xのインスタントウィンツールの中には、自動抽選からギフト付与までがワンセットで実装されているものがあります。これを活用することで、キャンペーン担当者のギフト付与の手間を省けます。
必要な支援が受けられるか
キャンペーンの実施は、企画やクリエイティブ作成など多くの準備が必要であるため、担当者の負荷が非常に大きくなる可能性があります。
そのような場合は、キャンペーンの支援サービスの活用を検討しましょう。たとえば、以下のような作業を任せられます。
キャンペーン全体の企画
バナーやチラシの制作
景品ブランドへの許可申請
どうすれば負担を減らしてキャンペーンを実施できるかも検討し、必要であれば支援サービスを活用しましょう。
Xインスタントウィンキャンペーンに最適なツールを選ぶには
ツールを選ぶ際には、上記のポイントを押さえておきましょう。Xでのインスタントウィンキャンペーンをより効率的に実施するためには、適切なツールの選定が不可欠です。X抽選ツールには、SNS完結型とURL遷移型の2種類があり、それぞれのメリットやユーザー体験が異なります。
市場には多数のツールが存在しますが、以下の点に注目することでより効果的な選定ができます。
API対応状況を確認する:X社のAPIプランは複数あり、ツールによってできることが異なります。参加条件の判定数や非公開アカウントの参加可否など、実施したいキャンペーンに必要な機能が備わっているかをチェックしましょう。
実績ある企業のツールを選ぶ:多数の導入実績を持つツールは、安定性やサポート体制が整っていることが多く、トラブル時も安心です。導入事例や口コミも参考にしてください。
ギフト付与の自動化機能を重視する:抽選から当選者へのギフト付与までをワンストップで提供するツールを選ぶことで、運用工数を大幅に削減できます。
どのようなキャンペーンを実施するか、予算や期間はどれくらいか、自社のリソースで対応できる範囲はどこまでかなどを明確にした上で、最適なツールを選びましょう。
さらに詳しく知りたい方は以下の記事にて、おすすめのX抽選ツールやその特徴、選定時のチェックポイントまで詳しく紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
Xインスタントウィンの事例
最後に、弊社ギフティのギフトやツールをご活用いただき、Xでインスタントウィンキャンペーンを実施した企業の事例をご紹介します。
認知拡大を目的とし、テーマが異なる4つのキャンペーンを実施したゲームアプリの事例
目的 | ・新作アプリゲームの認知拡大・新規ユーザー獲得 |
|---|---|
課題 | ・コアゲームユーザーが対象ではなかったため、「ほしいかも」と思って貰いやすく、ゲームの内容を想起させられるような賞品を用意する必要があった |
成果 | ・想定より多くの方に参加してもらえた ・スクリーンショット投稿キャンペーンでは約2,200件と、想定を上回る数の投稿があった |
株式会社コロプラ様は、アプリゲーム「とらべる島のにゃんこ」のサービス開始にあたり、認知拡大を目的として、以下の全4回のSNSキャンペーンを実施しました。
第一弾(テーマ:旅の準備) | 事前登録キャンペーンとして、公式Xをフォロー&リポスト、公式Instagramをフォロー&いいねした方の中から抽選で、オリジナルデザインのキャリーケース・ハット・ボトルをプレゼント |
|---|---|
第二弾(テーマ:料理) | サービス開始日決定を記念し、公式Xをフォロー&リポスト、公式Instagramをフォロー&いいねした方の中から抽選でそれぞれに、バルミューダのトースターやBRUNOのホットプレート、オリジナルデザインのランチボックスをプレゼント |
第三弾(テーマ:旅行) | Xにて、フォロー&リポストで毎日参加可能なインスタントウィンキャンペーンをリリース開始日から7日間連続で実施し、10万円分の旅ギフトやオリジナルトートバッグ、最大1万円分の「giftee Box」を1,000名様にプレゼント |
スクリーンショット投稿キャンペーン(テーマ:癒やし) | サービス開始後、公式Xもしくは公式Instagramをフォローし、テーマに合ったゲーム内のスクリーンショットまたは動画を撮影のうえ、指定ハッシュタグをつけて投稿した方の中から抽選で、オリジナル刺繍入りオーガニックエアーホイップタオルケット、ティーポット&マグ+オリジナルティータグ付き和紅茶3個セット、ゲーム内アイテム(ふくびきチケット50枚)をプレゼント |
同ゲームは、カジュアルゲーム好き、あるいは普段あまりゲームをしないユーザーがターゲットだったため「ゲームである」というハードルを感じさせないような施策を検討する必要がありました。
景品も、普段使いができ、同ゲームの世界観とリンクしているものを選ぶ必要があったため、弊社にご相談を頂き、オリジナルグッズや旅ギフト、モノのギフト、デジタルギフトといった多様なギフトを用意することができました。
また、キャンペーンを実施する際には、弊社のX用インスタントウィンツールである「X (キャンペーンシステム)」もご活用いただきました。
質の良いオリジナルギフトにしたことで、社内外から「可愛い」「絶対欲しい」などの声が聞けました。さらに、想定を超える参加数となり、スクリーンショット投稿キャンペーンでは約2,200件と、想定を上回る数の投稿がありました。
▼この事例の詳細はこちら
開設まもないXアカウントのフォロワー獲得を目的とした事例
目的 | ・フォロワーの獲得 ・ZEV(ゼブ)という言葉の認知拡大 |
|---|---|
課題 | ・フォロワーの獲得数の見込みがみえず、うまくいくかわからなかった |
成果 | ・開始から4日間で約20,000人ものフォロワーを獲得 |
東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター (愛称:クール・ネット東京)様は、Xの公式アカウントのフォロワー獲得を目的として、フォロー&リポストキャンペーンを実施しました。
フォローと対象ポストをリポストすると、抽選で800名に「giftee Box」200円分がプレゼントされるというものです。
フォロワーがいない状態でのキャンペーン実施だったため、視覚的に訴求できるバナー投稿を実施。giftee Boxのテンプレートをご活用いただき、プレゼントされるギフトの魅力が一目でわかるようにし、投稿を見つけてもらいやすくしました。
また、キャンペーンを実施する際には、弊社のX用インスタントウィンツールである「X (キャンペーンシステム)」もご活用いただきました。
その結果、多くのユーザーにキャンペーンを認知してもらい、開始4日で約20,000人ものフォロワーを獲得できました。
▼この事例の詳細はこちら
イベントの告知と集客を目的とした事例
目的 | ・ライブ配信イベント告知と集客 ・フォロワー獲得 |
|---|---|
課題 | ・従来の実施方法では、運用工数が膨れあがってしまう ・効率的な運用体制を確立できていない |
成果 | ・約32,000件のリポストを達成 ・フォロワーが120%増加 ・従来の施策よりも運用工数を大幅に削減 |
パーソルホールディングス株式会社様は『田村淳が池袋Innovation Council特別編「はたらくって、何だ!?ミライ会議 Powered by パーソル」』というイベントを開催。その告知と集客、さらに公式アカウントのフォロワー増加を目的とし、フォロー&リポストキャンペーンを実施しました。
キャンペーンの実施に際し、11月でもっともXのユーザーがアクティブになる「いいふうふの日」と「勤労感謝の日」に実施することで、キャンペーンの効果を上げるように計画。弊社のX用インスタントウィンツールである「X (キャンペーンシステム)」もご活用いただき、キャンペーン運用の工数も削減しました。
その結果、約32,000件のリポストを達成し、フォロワーもキャンペーン前と比較して120%増加しました。
▼この事例の詳細はこちら
新商品のPRとフォロワー獲得を目的とした事例
目的 | ・新商品の認知拡大 ・Xアカウントの新規フォロワー獲得 |
|---|---|
課題 | ・Xキャンペーンと来店促進を組み合わせるキャンペーンをやるのは煩雑かつコストがかかりすぎていた |
成果 | ・6万以上のリポストによって新商品の認知拡大を実現 ・4.3万の新規フォロワーを獲得 |
ゴディバジャパン株式会社様は、新商品発売記念キャンペーンとしてフォロー&リポストキャンペーンを実施しました。
公式アカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストすることで「GODIVA ギフト券(1,000円)」が抽選で当たり、はずれても「ゴディバキューブトリュフ(1粒)ご試食」がプレゼントされるというものです。はずれを無くすことで、参加モチベーションを高めています。
また、キャンペーンを実施する際には、弊社のX用インスタントウィンツールである「X (キャンペーンシステム)」もご活用いただきました。
その結果、6万件以上のリポストを達成し、効果的に新商品の認知拡大ができました。また、4.3万ものフォロワーも獲得できました。
▼この事例の詳細はこちら
Xでインスタントウィンキャンペーンを実施するなら景表法に注意
景表法とは、正式名称を景品表示法といい、消費者が商品やサービスを選ぶ際に、誤解を招くような広告表示や過大な景品提供を規制する法律です。キャンペーン内容によっては、景表法の規制対象となるため、理解しておかなければいけません。
商品購入やサービス利用を条件とせず、誰でも参加可能な「オープン懸賞」の場合は、この規制の対象外です。Xのフォロー&リポストキャンペーンはオープン懸賞に当てはまるため、基本的には景表法の規制対象外になります。
しかし、キャンペーンの条件に商品購入やサービス利用が含まれる場合は、取引に付随する「クローズド懸賞」とみなされるため、景表法を守らなくてはいけません。つまり、Xキャンペーンの参加条件として、商品の購入や来店などがある場合は、注意が必要です。
クローズド懸賞の規制内容
取引額が100円未満の場合:景品額は最大2,000円
取引額が100円以上の場合:景品額は取引額の20倍まで(上限10万円)
総額規制:キャンペーン期間中の売上総額の2%以内
景表法については、下記記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
キャンペーン景品におすすめのギフトカード3選
Xインスタントウィンキャンペーンでは、ユーザーが「欲しい」と思える景品選びが欠かせません。特に若年層の参加が多いXキャンペーンでは、日常的に使いやすく、知名度の高いギフトカードが効果的です。ここでは、即時抽選と相性の良いギフトカードを3つ紹介します。
1. 楽天ギフトカード
楽天市場をはじめとする楽天のサービス内で幅広く活用できる楽天ギフトカード。実店舗でも利用でき、若年層を中心とした楽天ユーザーにとっては特に魅力的なので、キャンペーンの参加率向上も期待できるでしょう。
楽天ギフトカードの特長
- 楽天市場や楽天グループのサービスに加え、楽天Pay加盟店でも利用可能
- 1,500円〜5万円の間で自由に金額指定ができるバリアブルタイプも存在
- 楽天ユーザーが多く、利便性が高い
楽天ギフトカードについてさらに詳しく知りたい方は以下の記事にて、利用シーンや活用メリットなどを詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
2. nanacoギフト
セブン-イレブンをはじめ全国125万店以上(nanaco公式サイトより)で利用できるnanacoギフトもxインスタントウィンキャンペーンでの活用におすすめです。コンビニでの日用品や飲食で手軽に使えるため、実用性が高く参加者に喜ばれやすいギフトです。
nanacoギフトの特長
- セブン-イレブンなど身近な店舗で利用可能
- 100円単位で細かな金額設定ができ、予算調整が柔軟
- デジタルギフトのため、即時配布が可能
nanacoギフトについてさらに詳しく知りたい方は以下の記事にて、企業でのキャンペーン活用法や導入事例などを詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
3. Vポイント
三井住友カードが提供するVポイントは、VポイントPayアプリを通じてiDやVisaタッチ決済で利用ができます。キャッシュレス決済が浸透した現代において、若年層に好評です。
Vポイントの特長
- Apple PayやGoogle ウォレット経由でiDやVisaタッチ決済に対応
- 1ポイント=1円として幅広い店舗やサービスで使える
- ギフトを受け取った後、すぐに利用できる
Vポイントについてさらに詳しく知りたい方は以下の記事にて、企業でのキャンペーン活用方法や成功事例などを詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q. Xインスタントウィンの費用相場は?
Xインスタントウィンキャンペーンの費用は、ツール費用+景品費用の2つで構成されます。
ツール費用
景品費用
Q. インスタントウィンツールは無料でも使える?
無料で使えるツールもありますが、商用利用が制限されている場合があるため注意が必要です。
個人向けの無料ツールは、利用規約で商用利用が禁止されているケースが多く、企業のキャンペーンには使用できません。また、無料ツールは以下のような制限があることが一般的です。
機能が限定的(抽選のみ、ギフト配布は手動など)
参加者数や抽選回数に上限がある
サポートが受けられない
企業でXインスタントウィンキャンペーンを実施する場合は、商用利用可能な有料ツールの導入をおすすめします。
Q. フォロワーが少なくてもインスタントウィンキャンペーンは効果がある?
フォロワーが少なくても、適切な告知と魅力的な景品設計により効果を出すことは可能です。
フォロワーが少ない段階でキャンペーンを成功させるポイントは以下の通りです。
視覚的に訴求できるバナー画像を投稿する
Web広告やプレスリリースなど、X以外での告知も併用する
参加条件をシンプルにし、参加ハードルを下げる
当選者数を多めに設定し、当選への期待感を高める
フォロワー数が少なくても、戦略的にキャンペーンを設計すれば十分に効果を出せます。
まとめ
本記事では、Xのインスタントウィンキャンペーンについて解説しました。
Xでのインスタントウィンキャンペーンは、拡散力・参加ハードルの低さ・フォロワー獲得効率の高さといった特長から、プロモーション施策として非常に有効です。
成功の鍵は「目的の明確化」と「ツールや景品の設計」です。特にツールに関してはそれぞれ機能や契約形態が異なるため、自社に適したものを選ぶことをおすすめします。
ぜひ本記事で紹介した手順や事例を参考に、目的に合ったキャンペーン設計を進めてみてください。
Xインスタントウィンのキャンペーンの運用にお困りのご担当者様へ
・どの抽選ツールを選べば良いか分からない ・APIの変更に対応したツールを探している ・景表法などのルールを守りながらキャンペーンを運用したい ・手間をかけずに当選者へギフトを送付したい
このような課題を解決する「X (キャンペーンシステム)」では、参加条件を満たした参加者に対し、その場で抽選、当選者にはそのまま景品を付与するキャンペーンの実施が可能です。参加条件の確認や抽選などの作業が自動化できるため、実施の手間を削減できます。
本資料では、Xで実施されるキャンペーンごとのシステムの活用イメージや、料金プランについて詳しくご紹介しています。