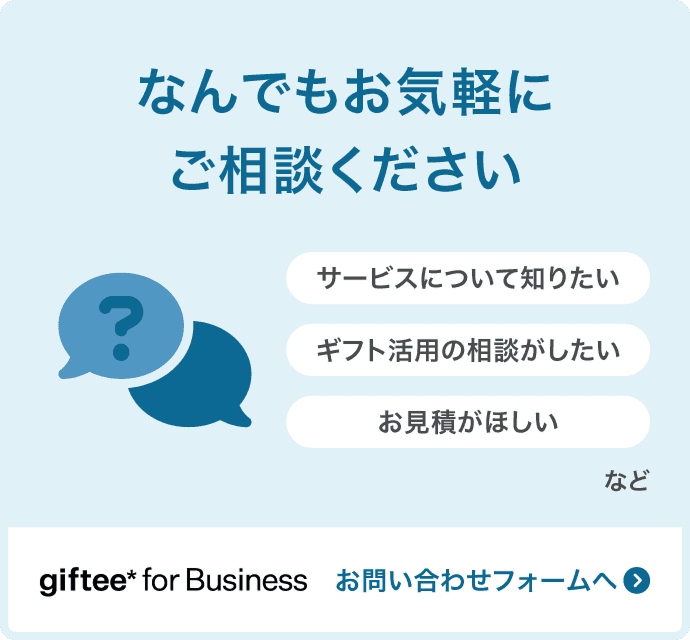表彰の景品に「giftee Box Select」を導入し、辞退率が改善 カード形式で“受け取る実感”を演出&制度のリブランディングにも寄与
日本生命保険相互会社様(以下、日本生命)では、様々な施策・表彰がある中、約4万1,000名の営業職員の中で一定の基準を満たした方を対象とした表彰運営を実施されています。その表彰の景品として、弊社のデジタルギフト「giftee Box Select」を新たに採用いただきました。
今回は、日本生命のご担当者様のご希望により、「giftee Box Select」をカード形式で提供。カードに印字された二次元コードを読み取るとギフトが受け取れる仕様で、デジタルならではの利便性はそのままに“手に取れるギフト”としての手触り感や満足感も重視した形に。こうした“デジタルとリアルの両立”が奏功し、辞退率の改善にもつながったとのことです。
今回は、導入に至った背景や施策ローンチまでのハードル、ギフティのサービスに関しての所感などを、日本生命の瀬古さんと久方さん、ギフティの諏訪さん、國分さんに伺いました。
日本生命保険相互会社

:
-:
-:
全国


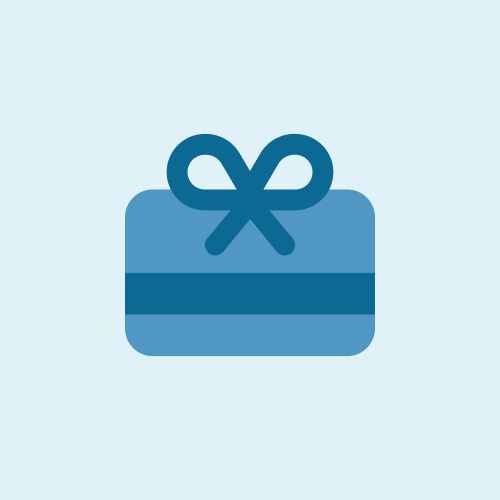
計5種類のカード形式のデジタルギフトを用意
今回、弊社の「giftee Box Select」を採用いただいた貴社の表彰について、概要を教えてください。
瀬古さん:当社では2016年から約10年間、全国の営業職員約4万1,000人を対象に、さまざまな表彰運営を実施してきました。今回「giftee Box Select」を導入した当表彰もその一つです。

日本生命保険相互会社の瀬古佳与さん。2025年3月末まで法人職域業務部に所属し、現在は新宿支社に在籍。
瀬古さん:先ほどもお話した通り、当社には様々な施策や表彰がある中で、今回の表彰は約4万1,000名を対象とした規模の大きいものとなっており、特に優れた成果を上げた職員を表彰しています。
表彰された方には景品を贈呈しています。景品はこれまで、百貨店様から提供いただいた家電製品や美容機器などの中から、受賞者が自由に選べる形式でした。
今回の表彰運営において、ギフティはどのような形で支援させていただいたのでしょうか。
瀬古さん:今回、景品の新たな選択肢として「giftee Box Select」を導入しました。受賞した賞の種類に応じ、デジタルギフトが受け取れる二次元コード付きのカード(プラチナ賞、ゴールド賞、シルバー賞、ブロンズ賞、グッド賞の全5種類)をお渡ししています。
また、カードを挟み込める「受賞おめでとうございます」のメッセージ入り台紙や、その外装となる封筒も含め、すべてギフティ様に制作していただきました。

ギフティが制作したカード、台紙、封筒
表彰の景品選びで抱えていた三つの課題
今回「giftee Box Select」を導入される前に感じていらっしゃった課題について教えてください。
瀬古さん:導入以前、我々は大きく三つの課題を抱えていました。
一つ目は「コストの上昇」です。「giftee Box Select」導入前は、受賞者へのギフトは百貨店様の物に限定されていました。しかし、近年の物流費の高騰により、同じ予算内で同じ内容のギフトを用意するのが難しくなり、受賞者満足度の低下につながりかねない状況でした。
二つ目は「景品のマンネリ化」です。受賞者の中には、長年にわたり活躍され、複数回表彰されている方も多くいらっしゃいます。そうした方々からは、「毎回同じようなカタログギフトでは新鮮味がない」といった声が上がっており、インセンティブの多様化が求められていました。
三つ目は「辞退率の増加」です。これは前述の課題とも関連しますが、配送コスト上昇に伴う“実質的な景品価値の低下”や“内容のマンネリ化”により、特に比較的少額のギフトでは、せっかく受賞しても辞退されてしまうケースが見受けられるようになっていました。
「面白そう」を原動力に「giftee Box Select」導入を前向きに推進
これらの課題を解決する手段として「giftee Box Select」を採用された経緯を教えてください。
諏訪さん:きっかけは、あるイベントで瀨古様の上司の方へ弊社のデジタルギフトをご紹介したことでした。その際にご興味をお持ちいただき、後日、改めてご提案の機会をいただきました。

株式会社ギフティ Corporate Gift Unit 諏訪さん。企業が取引先や顧客、従業員に対して関係性構築・関係性強化を目的に贈るギフトである「Corporate Gift」の提案をしている。
当初から、デジタルギフトの導入を想定されていらっしゃったのでしょうか。
瀬古さん:いえ、最初は「デジタルギフトを景品にする」という発想はありませんでした。当時は、これまでのギフトとは異なる“新しい選択肢”を模索しており、他の百貨店のカタログギフトなども検討していたところでした。そんな中、ギフティ様からご提案をいただき、上司が「これは面白そうだね」と興味を示したことがきっかけで、諏訪様をご紹介いただき、本格的な検討がスタートしました。
元々選択肢にはなかったデジタルギフト導入にあたって、社内調整などのハードルも多かったのではないでしょうか。
瀬古さん:実際、導入にあたってはいくつかの課題を乗り越える必要がありました。たとえば、社内規定に沿った形に整えるため、支払い規定の見直しや関係部署との調整、ギフト内容の精査などが必要でした。
ちなみに、デジタルギフト自体を使用されたご経験はありましたか。
久方さん:個人的な場面ですが、友人への贈り物として有名カフェチェーン店のデジタルギフトを購入したことがあります。その経験から、デジタルギフトのUIや、どのように贈るのかといった流れについては、ある程度イメージは持てていました。

日本生命保険相互会社の久方彩椰さん。2024年度より、法人職域業務部に所属。
瀬古さん:私たち自身もデジタルギフトの利便性をある程度理解していたことに加え「これは新しい取り組みで面白そうだ」という前向きな空気感がチーム内にあったことが大きかったと思います。そのおかげで「できない理由を探す」のではなく「どうすれば実現できるか」を常に意識しながら議論を進めることができました。
表彰に込めたい想いをヒアリングし、デザインに落とし込む
今回は日本生命様のご希望により「giftee Box Select」をカード形式で提供させていただきましたが、その形式にこだわられた理由を教えてください。
瀬古さん:カード形式を選んだ理由は、デジタルギフトの高い利便性が、かえって受賞者に「味気なさ」を感じさせてしまうのではないか、そんな懸念があったためです。
特に、当社の表彰運営では、朝礼の場などで上司が受賞者へギフトを直接手渡すというコミュニケーションの時間を大切にしており、そうした「贈る体験」そのものにも価値を置いています。だからこそ、リアルで手渡せるカードは、デジタルギフト導入にあたって必ず取り入れたいと考えていました。
さらに、我々が受け渡しのシーンや「贈る体験」を重視している旨をお伝えしたところ、カードだけでなく「台紙」や「封筒」もギフティ様にはご用意いただけました。こうした細やかなご対応は、本当にありがたかったです。

「贈る体験」そのものにも価値を置かれ、カード形式を導入されたのですね。今回のクリエイティブはどのように制作されたのか、教えてください。
國分さん:今回はまず、クリエイティブの制作に取りかかる前に、日本生命様にヒアリングするところからスタートしました。

株式会社ギフティ クロスファンクショナル推進室 Design Unit 國分結香さん。giftee for Businessのクリエイティブ制作を担う。
國分さん:というのも、クリエイティブ制作においては、まずはデザインのコンセプトを決める必要があるのですが、そのためにもこの表彰運営に込めたい想いやターゲット層、届けたいメッセージ、表現したいイメージなどについて、時間をかけて丁寧にお伺いしました。
その中で「明るい」や「応援」といったキーワードが浮かび上がってきたため、それらを手がかりにムードボードを作成し、イメージを徐々に具体化していきました。
ムードボードでは5つの方向性のビジュアルイメージを提示しながら、トーン&マナーのすり合わせを実施。対話を重ねる中で方向性を1つに絞り込み、その後、実際のデザインへと落とし込み、最終的に3案をご提案しました。
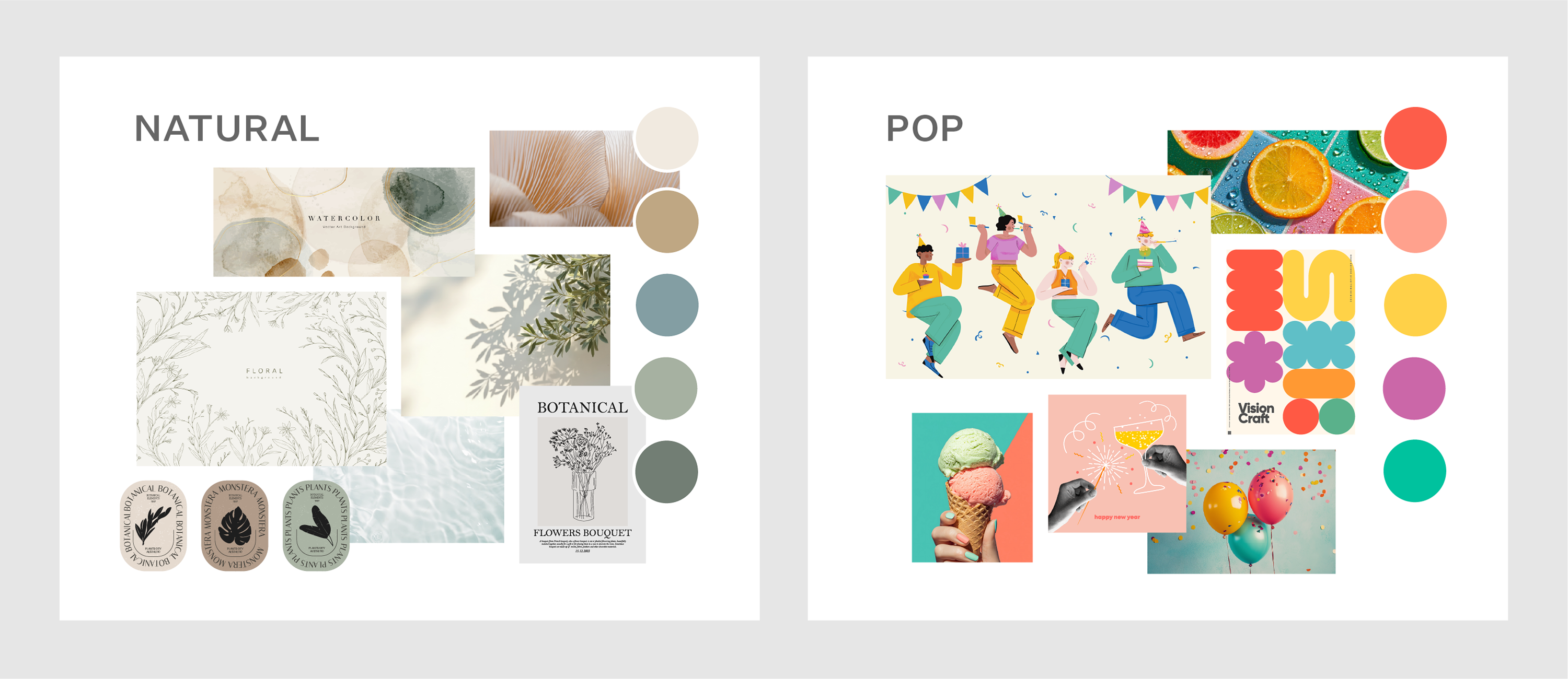
ムードボードのイメージ。ギフティでは、「ナチュラル」や「ポップ」など、ご希望のトーン&マナーに合わせて、さまざまなクリエイティブの制作が可能です。※こちらの画像はイメージであり、日本生命様の案件とは関係ございません。
國分さん:このように、初期の段階から日本生命様とは密にコミュニケーションを取り、共通認識を醸成できたことが、スムーズで精度の高いクリエイティブ制作につながったと感じています。
諏訪さん:今回の取り組みでは「デザイン定例」という形で定期的な会議の場を設け、制作のスタートから完了まで一貫して密な連携を図ることができました。これは、営業チームにとっても非常にありがたい取り組みだったと感じています。
日本生命様には工数的にご負担をおかけした面もあったかと思いますが、それでも丁寧に進めていただけたことで、より完成度の高いアウトプットにつながったと感じています。
ギフティとの対話を通じて、表彰の世界観をリブランディング
日本生命様にとって、弊社が提案した今回のような「デザイン定例」を通じたコミュニケーションはいかがだったでしょうか。
瀬古さん:我々としても、非常に有意義な機会だったと感じています。デザイン定例を通じて、日頃の表彰運営において私たちが無意識に行っていたことや、これまで明確に言語化できていなかった想いやゴールを、改めて整理して捉え直すことができました。
ちょうどその頃、前回の表彰運営から当表彰運営へと、名称や基準も含めて変更するタイミングでもありました。これまでも制度の見直しは重ねてきましたが、これまで以上に「表彰の世界観をもっと際立たせたい」という気持ちが芽生えていました。
そうした背景もあり、今回のギフティ様との対話を通じて「この表彰で我々はどんなメッセージを打ち出したいのか」といった本質に立ち返り、全体を整える良い機会になりました。
また、各制作物のデザインクオリティも非常に高く、当初はお願いしていなかった告知用のポスターのデザインについても「それならポスターもお任せしよう」と自然に話が進みました(笑)。
結果として、カードや台紙、封筒に加え、ポスターのデザインにも統一感が生まれ、私たちが大切にしている空気感や世界観を、より的確に表現できたと感じています。
制作物の中で、特に「これは良かった」と感じられた部分はございますか。
瀬古さん:景品ラインナップを掲載したパンフレットの背表紙には「giftee Box Select」の中身や使い方を解説した紹介ページを掲載しています。受け取った方がギフトの内容を直感的に理解できる構成になっていて、とても良かったと思います。
諏訪さん:パンフレットに掲載していただけたことは、我々としても非常にありがたかったです。新しいギフトを導入するにあたっては、まず受賞者の方にその存在を認知してもらい、興味を持ってもらうための導線設計が非常に重要です。その点で、裏表紙に紹介ページが掲載されたことで、パンフレットを開かずとも自然と目に留まりやすく、デジタルギフトにご興味を持っていただく上でより効果的だったと思います。

今回の表彰運営の景品一覧を掲載したパンフレットの裏表紙
「giftee Box Select」導入で辞退率が改善
「giftee Box Select」導入により得られた成果はありましたか。
瀬古さん:導入させていただいたことで、課題であった景品取得の辞退率が改善しました。
特に顕著だったのは、グッド賞を受賞された方々の辞退率が大幅に下がった点です。従来の物のギフトでは、送料が差し引かれることで選べる品目が限られ、受賞者にとって魅力が伝わりづらいという課題がありました。
その点、デジタルギフトの「送料がかからない」という特性が大きな強みとなりました。さらに、「giftee Box Select」だと、たとえ500円〜1,000円の範囲でも、有名カフェチェーンのドリンクチケットなど選択肢が豊富にあるため「金額が少ないから要らない」といった印象を持たれにくくなり、結果として辞退率の改善に大きく寄与したのではないかと思います。
日本生命様が今後ギフティに期待していることがあれば教えてください。
瀬古さん:「giftee Box Select」は、今後1年間にわたり景品ラインナップへ掲載していく予定です。その運用を通じて、今後さらにさまざまな改善点や新たなニーズも見えてくると思います。その際には、これまでと同様にギフティ様と協力し、制度そのものをより良い形にブラッシュアップしていきたいと考えています。
また現在は、百貨店様のカタログギフトと「giftee Box Select」の両方を選択肢として用意していますが、受賞者の皆さんの反応や満足度によっては、将来的に「giftee Box Select」の選択範囲を広くしていきたいと思っております。
久方さん:私個人としても、従来の紙のカタログギフトと比較して、スマートフォン一つで簡単にギフトを選べるデジタルギフトの利便性は非常に高いと感じています。今後も、受賞者の皆さんの声を参考にしながら、デジタルギフトの導入比率をさらに高めていければと考えています。
一方で、このような新しい取り組みを社内に根付かせるには、制度そのものの認知拡大や、意識のアップデートも不可欠です。乗り越えるべき課題はまだまだありますが「giftee Box Select」にはそれだけの価値と可能性があると信じていますので、今後は社内での浸透にも力を入れていきたいと思います。

最後に、お二人の話を踏まえて、ギフティとして今後どのような支援をしていきたいと思いますか。
諏訪さん:ギフティとしては、より多くの受賞者の方々に「giftee Box Select」を選んでいただけるよう、今後も情報提供を継続的に行っていければと思います。最終的には、受賞された方々が「表彰されて本当に良かった」と感じていただけるような体験をお届けすることが目標です。
また、デジタルギフトは表彰に限らず、福利厚生や販促キャンペーンといった幅広いシーンでもご活用いただける柔軟性があります。また、我々はデジタルギフトの提供にとどまらず、体験ギフトやオリジナルのモノのギフトなど、さまざまな選択肢を提案できます。
こうした支援の幅広さや柔軟性を活かしながら、何かお悩みがあれば、まずはお声がけいただけるようなパートナーでありたい。そんな想いを持って、今後も伴走させていただきます。