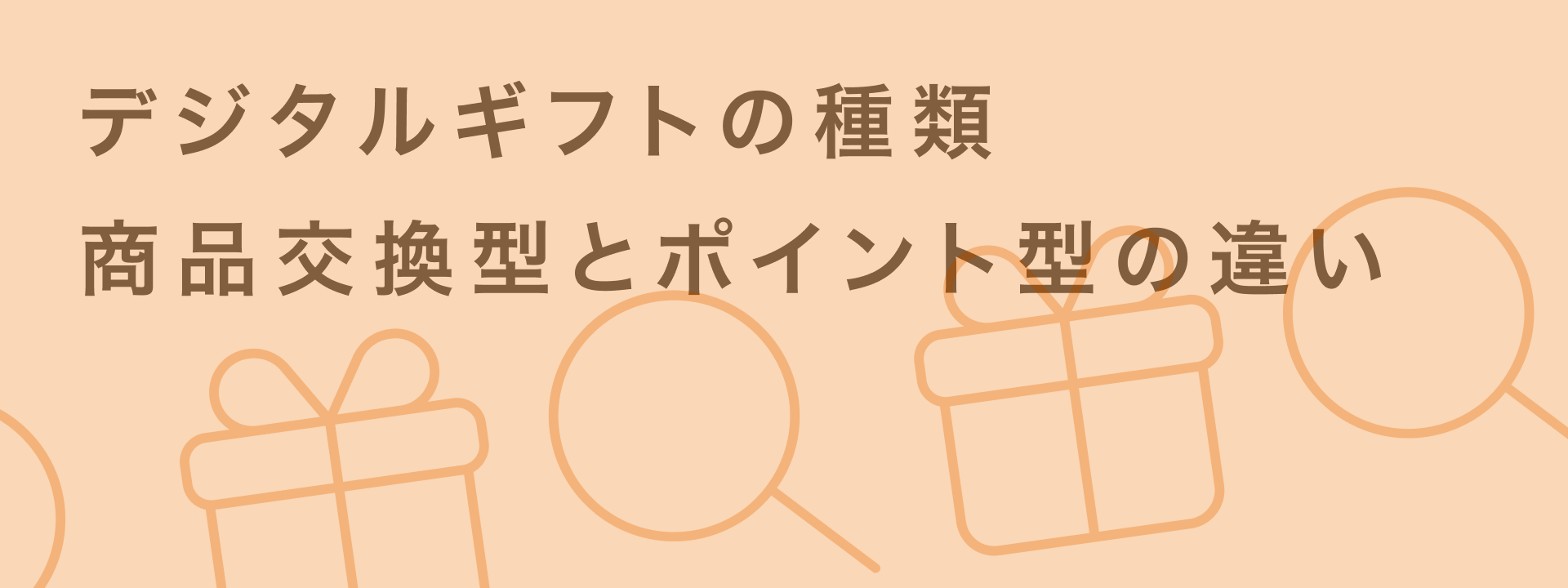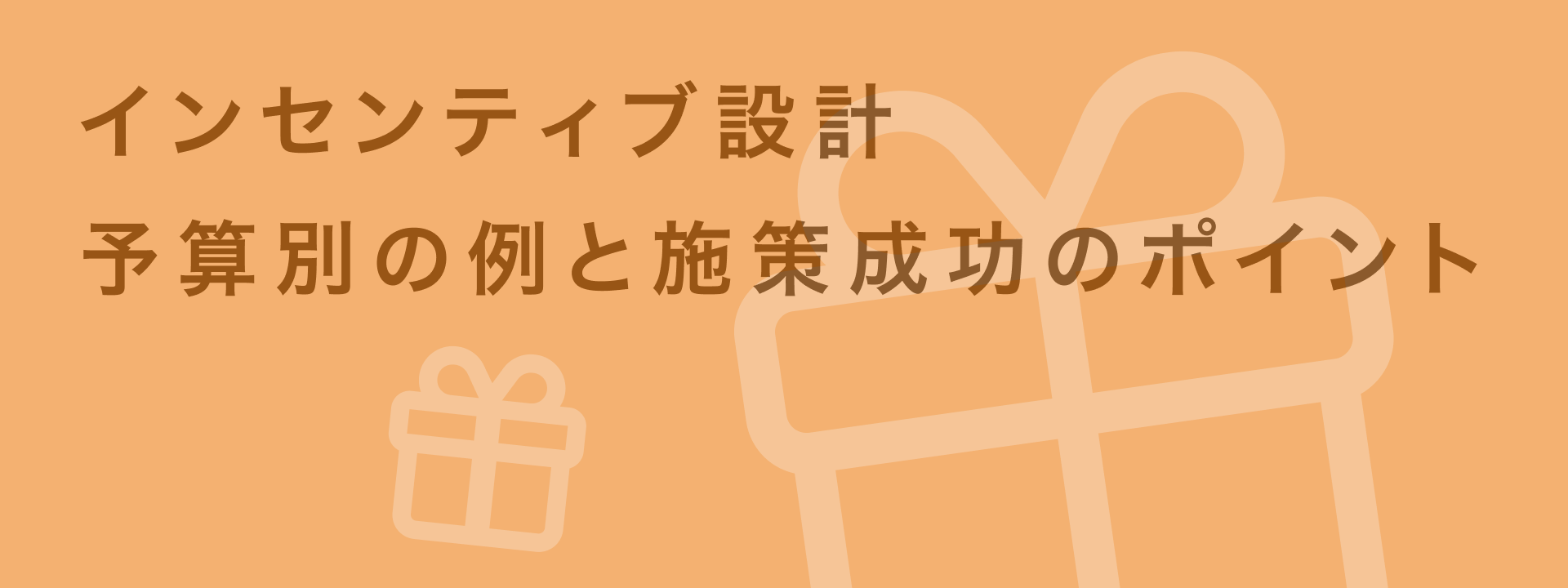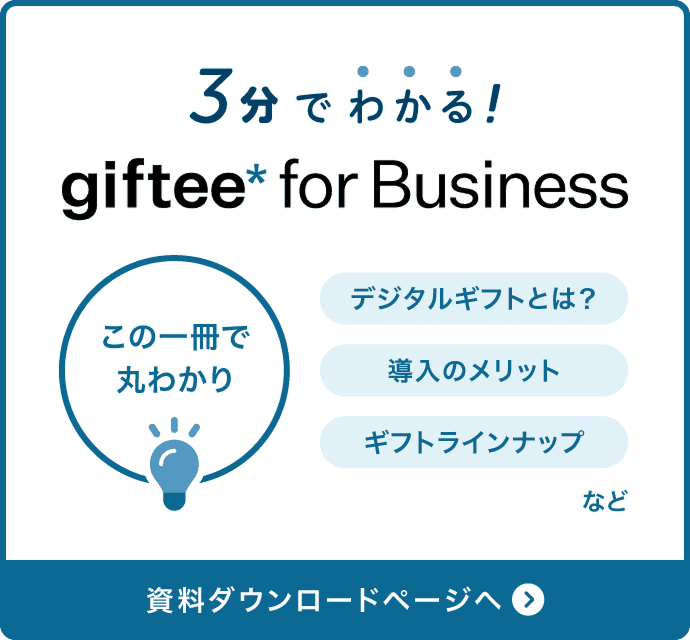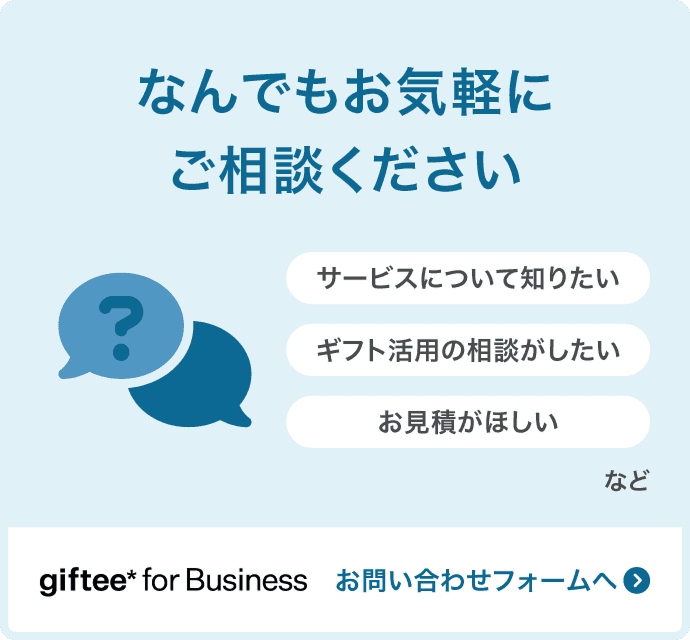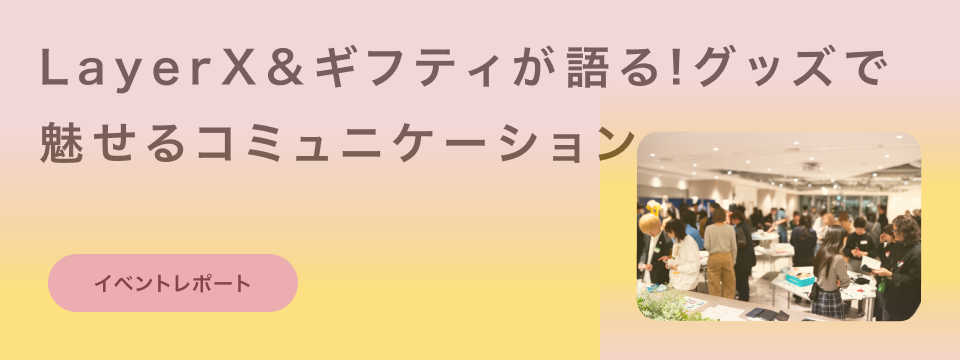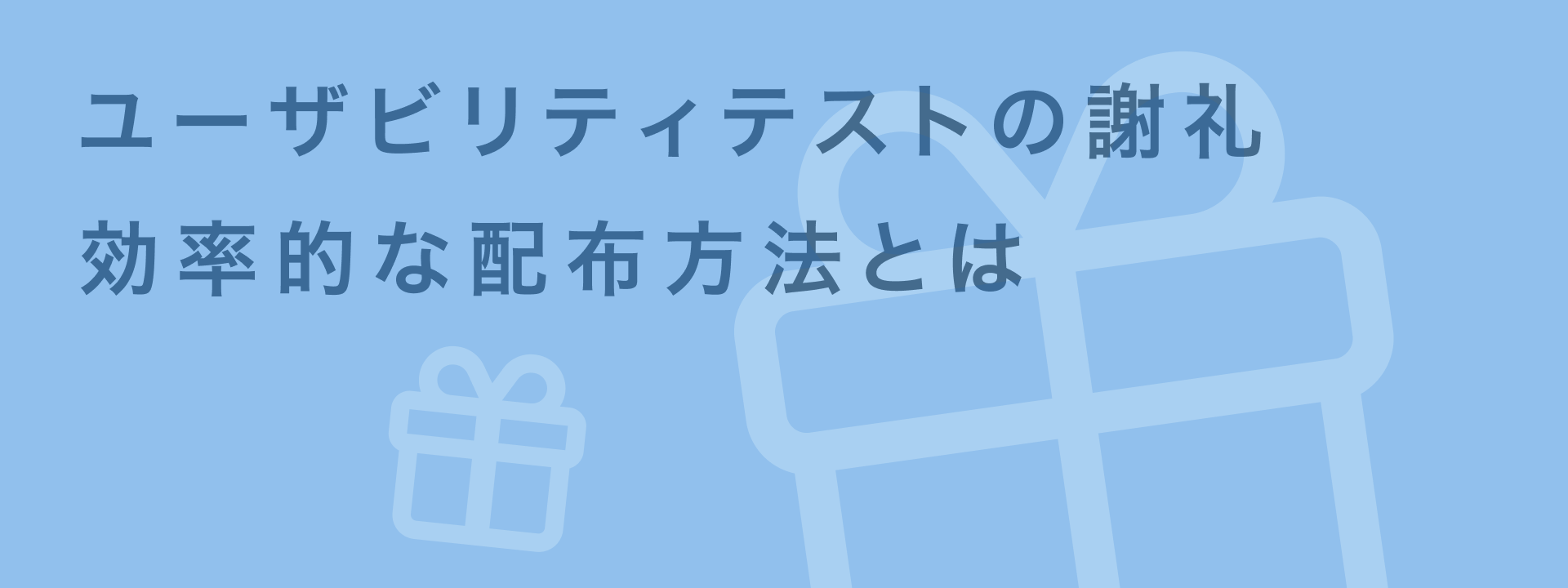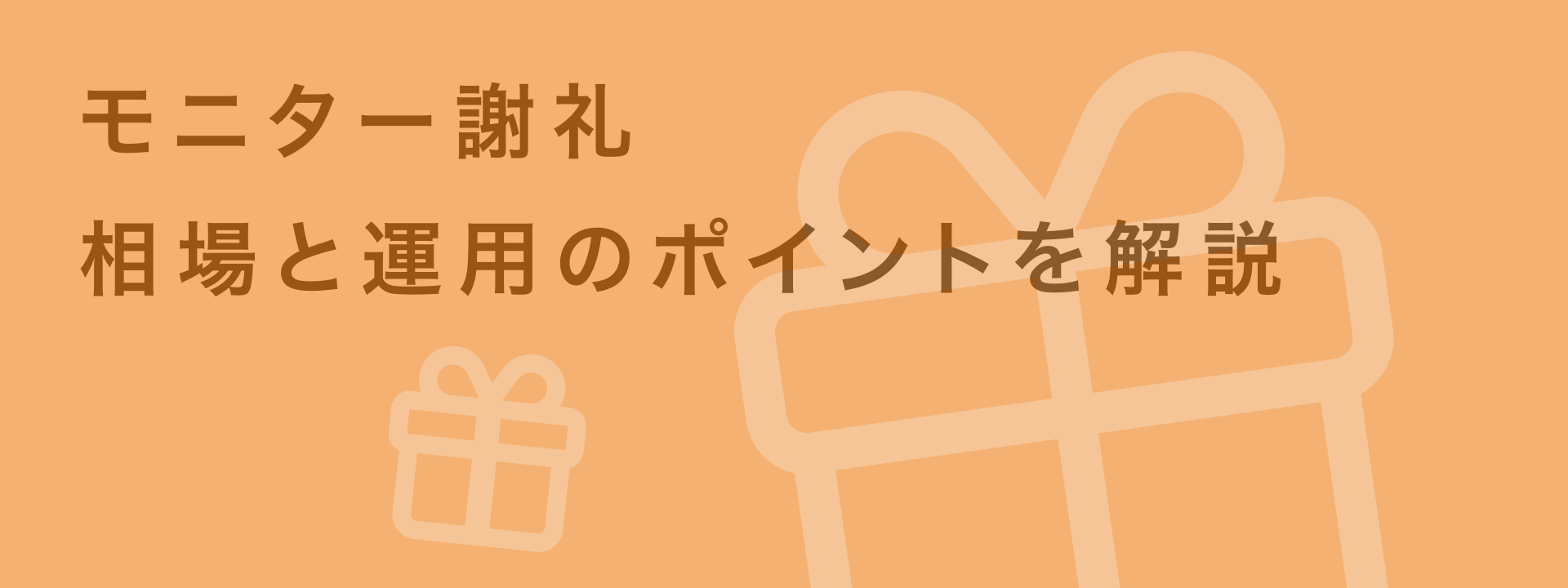アンケート回収率を向上させる10の施策|BtoB企業向け完全ガイド
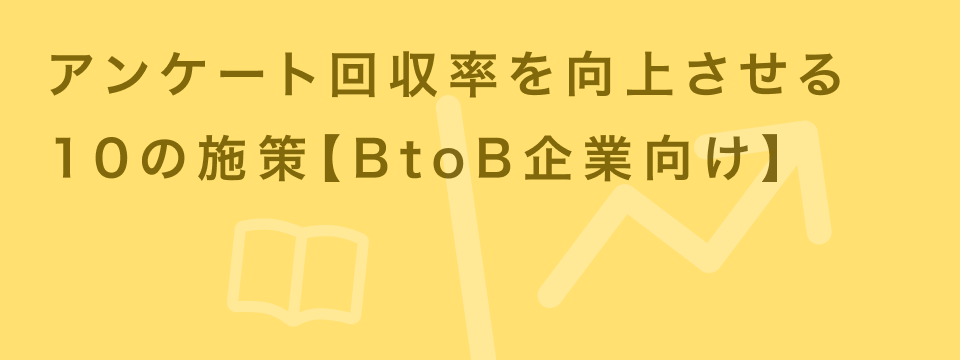
アンケートを実施しても回答が集まらず、「回収率が10%以下で施策の判断ができない」「せっかく配信したのに反応が薄い」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
顧客満足度調査やNPS調査は、重要な判断材料ですが、多くの企業が低い回収率に直面しています。
回収率が低くなる原因は明確で、「アンケートが長すぎる」「インセンティブがない」「配信タイミングが適切でない」といった共通の問題があります。これらの要因に適切に対応すれば、回収率は確実に改善できます。
本記事では、アンケート回収率が低くなる5つの原因と、すぐに実践できる10の改善施策を具体的に解説します。ぜひアンケート施策の改善にお役立てください。
アンケート施策の運用にお困りの方へ
アンケートの実施には、質問の設計や回答の収集、結果の集計・分析、そして謝礼の発送など、多くの手間がかかります。これらを手作業で行うのは非常に大変で、特に大量のデータを扱う場合は時間や労力がかかります。
そのため、アンケートの運用を効率化するためには、システムの活用が非常に効果的です。「Survey(アンケートシステム)」を使うことで、これらの手間を軽減し、スムーズに運用を進めることができます。
例えば、既にお使いのアンケートツールとも連携できるので、システムを大きく変更することなく、今の運用のままでアンケートの実施やギフト配布が可能です。
本資料では、アンケート実施から回答者へのギフト付与までをシステム上で完結させる方法や、料金プランについて詳しくご紹介しています。
アンケート回収率が低くなる5つの原因
アンケートの回収率が上がらない場合、必ず原因があります。回収率を向上させるためには、まず「なぜ回答されないのか」を理解することが重要です。
ここでは、アンケート回収率が低くなる代表的な5つの原因を解説します。
- アンケートが長く回答に時間がかかる
- 質問内容が複雑でわかりにくい
- 回答するメリットが伝わっていない
- 配信タイミングが適切でない
- 心理的な回答ハードルが高い
原因①アンケートが長く回答に時間がかかる
アンケートの回答時間が長すぎると、回答者は途中で離脱してしまいます。一般社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会の調査によると、アンケートの回答時間が10分を超えると離脱率が急激に上昇することが示されています。
特にBtoBの顧客や取引先は、業務の合間に回答するケースが多く、長時間のアンケートは敬遠されがちです。
質問数の多さ、自由記述欄が多い、選択肢の複雑さなどは、回答者に心理的な負担を与えます。
アンケート設計の段階で、「本当に必要な質問だけ」に絞り込むことが重要です。
改善のポイント
- 質問数を10〜15問以内に抑える。
- 回答時間を5分以内に設定し、所要時間を事前に明記する。
原因②質問内容が複雑でわかりにくい
質問文が複雑だったり、専門用語が多かったりすると、回答者は質問の意図を理解できず、回答を諦めてしまいます。特に避けるべきなのは「二重質問」です。
たとえば、「当社の製品の品質と価格についてどう思いますか?」という質問は、品質と価格という二つの要素を同時に聞いているため、回答者は答えにくくなります。
また、「やや満足」「満足」「とても満足」などの曖昧な選択肢は混乱を招き、回答率を下げる要因になります。
改善のポイント
- 一つの質問では一つの内容だけを尋ねる。
- 専門用語を避け、日常的な言葉を使う。
- 選択肢を具体的で明確にする。
原因③回答するメリットが伝わっていない
回答者にとって「アンケートに回答する意味」を理解していないと、回答意欲は高まりません。
アンケートの目的が不明確だったり、回答してもメリットがないと感じられたりすると、回答率は大きく低下します。
特に、インセンティブ(謝礼)がない場合、回答者は時間を割いて協力する理由を見出しにくいです。
「あなたの声を聞かせてください」だけでは、回答者の協力を得ることは難しいでしょう。
改善のポイント
- アンケートの目的を明確に伝える。
- 回答結果の活用方法を説明する。
- 可能な範囲でインセンティブを用意する。
原因④配信タイミングが適切でない
アンケートを配信するタイミングが悪いと、どんなに内容がよくても回答率は上がりません。
BtoB企業の場合、月末月初や年度末は業務が繁忙になるため、アンケートへの回答優先度が下がります。
また、金曜日の夕方や月曜日の午前中も業務対応に追われることが多いため、回答率が低下しがちです。
さらに、不定期で頻繁にアンケートを配信すると「アンケート疲れ」を招き、回答が避けられるようになります。
改善のポイント
- 火〜木曜日の午前10〜11時に配信する。
- 繁忙期を避けて配信する。
- 少なくとも3か月の間隔を空けて配信頻度を管理する。
原因⑤心理的な回答ハードルが高い
アンケートに回答する際、個人情報の入力が求められると、回答者の心理的負担が増し、回答率は大幅に下がります。
氏名や所属、役職、連絡先などの情報は、「個人が特定されるのではないか」という不安を生み、本音を記載しづらくします。
また、匿名性が保証されていないアンケートでは、本音を書きにくいと感じる回答者も多いため、情報取り扱いへの配慮が欠かせません。
改善のポイント
- 取得する個人情報は必要最小限にする。
- 匿名性を保証し、個人が特定されない旨を冒頭で明記する。
アンケート回収率を向上させる10の実践施策
アンケート回収率が低くなる原因を理解した上で、次は具体的な改善施策を紹介します。
すぐに実践できる方法は以下の通りです。
- 回答時間を5分以内に設計する
- パーソナライズされた依頼メッセージを送る
- 魅力的なインセンティブを提供する
- 配信タイミングを最適化する
- リマインドメールを2回送る
- 経営層からのメッセージを入れる
- 匿名性を明確に保証する
- 回答結果のフィードバックを約束する
- モバイル対応を必須にする
- 進捗表示で完了までを可視化する
施策①回答時間を5分以内に設計する
アンケートの回答時間を5分以内に抑えることは、回収率向上の最も基本的かつ効果的な施策です。質問数は10〜15問に絞り込み、回答者の負担を最小限にしましょう。
また、アンケートの冒頭で「所要時間:約3分」のように明記することで、回答者は完了までの見通しを立てやすくなり、取り組みやすさが向上します。
質問を厳選する際は、「この質問は本当に必要か」「この回答で何がわかるのか」を判断基準とし、優先度の低い項目は思い切って削除することが重要です。
実践のコツ:質問数は10〜15問に絞り、自由記述欄は最小限にし、「約3分で完了します」というような所要時間を冒頭で明記する。
施策②パーソナライズされた依頼メッセージを送る
定型文のアンケート依頼メールではなく、パーソナライズされたメッセージを送ることで、回答率が上がる可能性があります。
「お客様各位」ではなく、「〇〇株式会社 〇〇様」と社名や担当者名を記載するだけでも、回答率は向上するでしょう。
さらに、過去の取引内容や利用サービスに触れることで、「自分に向けられた依頼だ」と認識してもらえます。
たとえば、「先日ご購入いただいた△△について、ご意見をお聞かせください」という具体的な文面は、回答者に特別感を与え、回答意欲の向上につながる可能性があります。
実践のコツ:担当者名や社名を記載し、過去の取引内容に言及するなど、定型文を避け、一人ひとりに向けたメッセージにする。
施策③魅力的なインセンティブを提供する
アンケートにインセンティブ(謝礼)を用意することは、回収率向上につながるでしょう。
特にデジタルギフトは、配送不要で即時配布が可能なため、アンケート謝礼に適しています。
相場は500〜1,000円程度で、Amazonギフトカードやコンビニで使えるギフトなど、使い勝手のよいものを選ぶと効果的です。
インセンティブの有無は回答率に大きく影響するため、予算が許す限り導入することをおすすめします。
実践のコツ:500〜1,000円のデジタルギフトを用意し、受け取った人が使いやすいギフトを選んで、アンケート依頼文に明記する。
施策④配信タイミングを最適化する
アンケートを配信する曜日と時間帯を工夫すると、開封率・回答率が向上する可能性があります。
最も効果的なのは火〜木曜日の午前10〜11時と言われています。。この時間帯は、始業時の処理が一段落し、午後の業務前で比較的余裕があるため、回答されやすくなるようです。
一方、月曜日の午前中や金曜日の午後は、業務が集中し、回答が後回しになりやすいため避けた方が良いでしょう。月末月初や繁忙期も同様に回答率が下がる傾向にあるようです。
実践のコツ:火〜木曜日の午前10〜11時に配信し、月曜午前・金曜午後および繁忙期の配信は避ける。
施策⑤リマインドメールを2回送る
アンケートは初回配信だけでは回答されないケースが多いため、適切なタイミングでリマインドを行うことが効果的です。
ただし、リマインドを過剰に行うと、ブランドイメージを損なう可能性があるため注意が必要です。
実践のコツ:(一例)初回配信の3日後と期限前日の計2回に留め、3回以上のリマインドは控える。
施策⑥経営層からのメッセージを入れる
アンケート依頼文に経営層や部門長からのメッセージを添えると、回答率の向上が期待できるでしょう。
「マーケティング部の〇〇です」という依頼よりも、「代表取締役の〇〇です」という文面の方が、重要性が伝わりやすく、協力を得やすい傾向があります。特にBtoBの取引先アンケートでは、経営層からのメッセージが効果的です。
ただし、毎回経営層の名前を使うと特別感が薄れるため、重要度の高いアンケートに限定して活用することをおすすめします。
実践のコツ:重要なアンケートでは経営層名義で依頼し、社長や部門長の名前を冒頭に明記する。
施策⑦匿名性を明確に保証する
アンケートが匿名であることを明確に示すと、回答者の心理的ハードルが下がり、回答率の改善につながる可能性があります。
特に顧客満足度調査や従業員調査など、本音を収集したい場合は匿名性の保証が不可欠です。
「個人が特定されることはありません」「回答内容は統計的に処理されます」といった文言をアンケート冒頭に記載し、安心して回答できる環境を整えましょう。
また、IPアドレスの記録をオフにするような、技術的な匿名化も重要です。
実践のコツ:匿名性を冒頭で明確に示し、個人の特定につながる質問を避け、技術面でも匿名化を徹底する。
施策⑧回答結果のフィードバックを約束する
アンケート結果をどのように活用するかを明示し、集計結果を回答者にフィードバックすることを伝えると、回答率向上に寄与するかもしれません。
「皆様の貴重なご意見をサービス改善に活かします」という一般的な文言だけでなく、「集計結果は〇月中にメールでお知らせします」と具体的に伝えることが効果的です。
実際にフィードバックを実施することで、次回以降のアンケートでも協力を得やすくなり、長期的な関係構築にもつながります。
実践のコツ:結果のフィードバック時期を明記し、実際にフィードバックを必ず行い、活用方法を具体的に伝える。
施策⑨モバイル対応を必須にする
多くのビジネスパーソンがスマートフォンでメールを確認しているため、アンケートのモバイル対応は必須です。
PCでしか回答できないアンケートは、スマートフォン閲覧時に操作しにくく、回答の離脱につながります。
レスポンシブデザインを採用し、スマートフォンでもストレスなく回答できる環境を整えましょう。
また、選択式の質問を中心に構成し、自由記述欄を最小限に抑えることも、回答者の負担軽減に有効です。
実践のコツ:レスポンシブデザインを採用し、スマートフォンでの操作性を確認し、選択式の設問を中心に構成する。
施策⑩進捗表示で完了までを可視化する
アンケートの進捗状況を視覚的に表示することで、回答者に完了までの見通しを持ちやすくなり、途中離脱を防げます。
進捗バーや「残り3問」のような表示は、回答者に「もう少しで終わる」という感覚を与え、最後まで回答する動機を高めるでしょう。
質問数が多い場合は特に効果が大きく、複数ページに分けて1ページあたりの質問数を少なくする方法も有効です。
実践のコツ:進捗バーの表示や「残り〇問」の明示を行い、ページごとの質問数を抑える。
インセンティブ設定で回収率を効率的に高める

アンケートにインセンティブ(謝礼)を用意することは、回収率を上げる上で非常に効果的です。
ここでは、インセンティブの種類や選び方について解説します。
インセンティブの種類
アンケート謝礼に活用できるインセンティブには、大きく分けて「デジタルギフト」と「現物の商品」の2種類があります。
回収率を最優先したい場合はデジタルギフトが最適です。一方で、特別感を演出したい場合やブランド訴求もしたい場合は、現物のインセンティブもおすすめします。
比較項目 | デジタルギフト | 現物の商品 |
|---|---|---|
配布スピード | 即時 | 数日〜数週間 |
配送コスト | なし | あり(送料・梱包費) |
事務処理の手間 | 少ない | 多い(発送・在庫管理) |
受け取り率 | 高い(95%以上) | 中程度 |
全員配布への適性 | ◎(最適) | △ |
デジタルギフト
デジタルギフトは、アンケート謝礼として優れたインセンティブです。
配送コストが不要で、全員配布にも対応しやすく、500〜1,000円程度の謝礼でも回収率を効果的に向上させられます。
メリット
- 配送不要で即時配布が可能
- メールやLINEで簡単に受け取れるため受け取り率が高い
- 住所確認や発送作業が不要で事務処理が簡単
- 個人情報の取得が最小限で済む
Amazonギフトカード、QUOカードPay、コンビニで使えるギフトなど、汎用性の高いものを選びましょう。
特に、複数のブランドから選べるタイプのデジタルギフトは、幅広い層に対応できるためおすすめです。
デジタルギフトについて詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご参照ください。法人活用の成功事例も紹介しています。
現物の商品
現物の商品とは、現金や商品券、ギフトカード、自社製品、カタログギフトなど、物理的に配送して受け取るタイプのインセンティブを指します。
メリット
- 高級感や特別感を演出できる
- 自社製品を提供すれば認知度を高められる
現物のインセンティブは、住所確認や配送手配が必要で、事務作業が増える点がデメリットです。受け取った人の好みに合わない場合のミスマッチも起こり得ます。
5,000円以上の高額商品を抽選で贈る施策は話題性を作れますが、全員配布には向いていません。
インセンティブの選び方
インセンティブを選ぶ際は、アンケートの目的と予算に応じて最適なインセンティブ選びが重要です。
目的 | 推奨のインセンティブ | 理由 |
|---|---|---|
回収率を最優先したい場合 | デジタルギフト (全員配布) | ・即時配布が可能で満足度が高い ・手続きが簡単で受け取り率が高い |
特別感や質の高い回答を重視する場合 | ・現物の商品 ・高額のデジタルギフト (抽選形式を含む) | ・高級感があり、回答のモチベーションが高まる ・回答者の労力と期待値に見合う報酬にできる |
自社製品の認知拡大を目的にする場合 | ・自社製品のサンプル ・割引クーポンなど | ・自社製品の利用促進や理解浸透につながる |
インセンティブ設計についての詳細は、以下の関連記事で解説しています。あわせて参考にしてください。
配布タイミングは即時配布が効果的
インセンティブを配布するタイミングは、回答率と満足度に大きく影響します。
即時配布
アンケート回答直後にデジタルギフトを送付
「回答したらすぐに受け取れた」という満足感が得られる
次回以降のアンケートにも協力してもらいやすくなる
後日配布
回答後、数日〜数週間後にギフトを配送
配送作業や管理の手間がかかる
受け取りまでに時間がかかるため、満足度が下がる可能性がある
デジタルギフトを使えば即時配布が可能なため、回答者の満足度を最大化できます。特に、回答完了画面でギフトコードを表示する方式は、最も効果的です。
インセンティブ設計を工夫することにより、アンケート回収率は向上させられるでしょう。
デジタルギフトを活用してアンケート回収率を向上させた企業の成功事例
ここでは、デジタルギフトをアンケート謝礼として活用し、実際に回収率を大幅に改善した企業の事例を紹介します。
えらべるギフトの採用で想定以上の回答数を獲得した事例
企業/ブランド名 | アイベックスエアラインズ株式会社 |
|---|---|
目的 | 顧客アンケートの回答率向上 仙台=広島線のPR施策検討のための顧客フィードバック収集 |
成果 | 想定以上の回答数を獲得 オペレーション工数の大幅削減 当選者数増加により顧客の回答意欲が向上 |
アイベックスエアラインズ株式会社様では、仙台=広島線のPR施策検討に向けて、顧客アンケートを実施されていました。
従来は航空券や産直品など単価の高い景品を提供していたため、当選者数を絞らざるを得ず、回答数が伸び悩む課題がありました。
そこで本施策では、デジタルギフト「giftee Box」200円分を抽選で200名にプレゼントする形式に変更。
「giftee Box」は、受け取った方が好きな商品を選べるデジタルギフトです。アンケートカードにも具体的な商品例を記載して訴求を強化しました。
その結果、機内Wi-Fi非搭載のため、降機後の回答が必要にもかかわらず、想定を超える回答数を獲得。
景品単価を下げて当選者数を増やしたことで、顧客の回答意欲を大きく引き上げ、さらには商品手配や住所確認が不要になり、業務負荷も大幅に軽減されました。
▼この事例の詳細はこちら
即時抽選で回答率120%を達成した事例
企業/ブランド名 | 株式会社LIFULL(LIFULL HOME'S) |
|---|---|
目的 | LINE公式アカウント友だち向けアンケートの回答数向上 ユーザーのサービス利用状況や満足度の把握 |
成果 | アンケート回答数が目標の120%を達成 開発工数の削減 問い合わせ窓口の負荷軽減 |
株式会社LIFULL様が運営する住宅情報サイト「LIFULL HOME'S」では、LINE公式アカウントの友だち登録ユーザーに向けてアンケートを実施されました。
アンケート回答後、即時で抽選が行われ、当選者にはその場でAmazonギフト券が発行されるキャンペーン形式を採用しました。
キャンペーン告知は、ウェルカムメッセージやメッセージ配信、リッチメニューのキャンペーンバナーを活用。回答すると「giftee for Business」のLINEインスタントウィンで回答者が識別され、そのまま抽選が始まるという仕組みです。
その場で抽選結果がわかり、当選者はすぐにギフトを受け取れるため、ユーザーの参加意欲を高め、回答数は目標の120%を突破。
また、「giftee for Business」のLINEインスタントウィンを活用することで、立案から短期間でキャンペーンを実施でき、プレゼント配送の手間や問い合わせ対応の負担も大幅に軽減できました。
▼この事例の詳細はこちら
展示場来場者向けアンケートでギフト配布した事例
企業/ブランド名 | セキスイハイム東北株式会社 |
|---|---|
目的 | 展示場・分譲住宅への来場促進 来場者アンケートの回答率向上 新規顧客の獲得 |
成果 | 新規顧客増を達成 運用負荷とコストの削減 その場でギフト配布が可能になり顧客満足度向上 |
セキスイハイム東北株式会社様では、お正月期間(2022年1月4日~1月31日)に、東北全エリアのセキスイハイム展示場や分譲住宅に来場し、アンケートに回答された方に抽選でgiftee Boxを含むさまざまなギフトをプレゼントするキャンペーンを実施されました。
従来は、来場時にアンケート回答を依頼し、後日メールでギフトを送付していましたが、「Direct(対面配布システム)」を活用することで、来場者にその場でギフトを配布。
これにより、商品管理や当選者への連絡・発送手続きが不要となり、運用コストが大きく軽減されました。
「giftee Box」は、1,000種類以上のデジタルギフトから選択できるため、幅広い顧客ニーズに対応できる点も好評でした。
また、告知テンプレートを活用することで、各ブランドの審査期間を短縮でき、短納期でのキャンペーンを開始できた点もメリットです。
年間施策として導入することで、時期やタイミングに合わせて「抽選」「スタンプラリー」などの企画内容に変化をつけながら、持続的な成果向上と潜在顧客の拡大を実現されています。
▼この事例の詳細はこちら
組合員向けアンケートで回答率110%を達成した事例
企業/ブランド名 | ニトリ労働組合 |
|---|---|
目的 | 組合員を対象とした働き方に関するアンケートの回答率向上 職場環境の実態把握と改善 |
成果 | 目標1万件に対し約1万1,000件を回収(回答率110%達成) 重複付与を防ぐ効率的なオペレーションを実現 回答直後にギフトを受け取れる仕組みで満足度向上 |
ニトリ労働組合様では毎年、組合員を対象に賃金や職場環境に対する満足度を調査するアンケートを実施されています。
アンケートの回答率を上げるために、初めてインセンティブとしてgiftee for Businessのサービスを導入。回答者全員に「giftee Box」500円分を付与した結果、目標回答数1万件に対し、約1万1,000件(110%)を回収することができました。
「Auth(認証配布システム)」を活用し、従業員番号リストを事前に登録することで、誰が受け取ったかを把握でき、重複受け取りを防止。これにより、ヒューマンエラーの少ない効率的なオペレーションを構築できました。
また、アンケート回答後、すぐにギフトコードが表示される導線により、回答者は即座にギフトを受け取れるため、満足度の向上につながりました。
▼この事例の詳細はこちら
製品サンプル請求者向けアンケートで顧客満足度向上を実現した事例
企業/ブランド名 | 株式会社LIXIL |
|---|---|
目的 | 製品サンプル請求者に対するアンケート回答率向上 請求動機や検討状況の把握 顧客満足度の向上 |
成果 | 幅広い顧客ニーズに対応し満足度向上 過去施策と比較してポジティブな反応を獲得 運用負荷をほとんど変えずに施策実施が可能に |
株式会社LIXIL様では、タイル建材のサンプルを請求した顧客に対してアンケートを実施し、回答者全員に「giftee Box」3,000円分をメールでプレゼントする形式を採用しました。
従来はカタログギフトや金券などのインセンティブを採用していましたが、全顧客の好みに対応しきれないという課題がありました。「giftee Box」は、1,000種類以上のギフトから顧客が自由に選べるため、幅広いニーズに対応できた点が評価されました。
また、抽選からギフト配布まですべてURLの先で完結できるため、メールにギフトのURLを記載するだけで施策を実施でき、運用負荷を増やさず実施できた点もメリットです。
▼この事例の詳細はこちら
アンケート回収率向上についてよくある質問集
アンケート回収率向上に取り組む際、多くの担当者が抱く疑問について、実務に役立つ回答を紹介します。
Q1.インセンティブなしで回収率を上げる方法は?
予算の都合でインセンティブを用意できない場合でも、回収率を向上させる方法はあります。
効果的な施策
パーソナライズ依頼文:担当者名や取引内容に言及し、特別感を演出する。
回答時間の短縮:質問数を10問以内に絞り、3分以内で回答できる構成にする。
結果共有の約束:「集計結果を〇月中にお知らせします」と具体的に伝える。
匿名性の保証:本音を話しやすい環境を整える。
ただし、インセンティブありのアンケートと比べると、回収率は低くなりがちです。可能であれば、少額でもインセンティブを用意することをおすすめします。
Q2.リマインドメールは何回まで送るべきですか?
リマインドメールは2回程度をおすすめします。
推奨スケジュール
1回目:初回配信の3日後
2回目:回答期限の前日
3回以上のリマインドは「しつこい」と感じられ、ブランドイメージに悪影響を及ぼす可能性があります。
また、頻繁にリマインドを送ることで、「あとで対応すればよい」という心理が働き、回答率が下がることも。
リマインドメールの件名は「【再送】」ではなく、「【あと〇日】」「【本日締切】」など、緊急性を伝える表現が効果的です。
Q3.回収率の目標値はどう設定すべきですか?
回収率の目標値は、アンケート対象者との関係性によって大きく異なります。
目標値の目安
既存顧客(関係性あり):30%以上
取引先(定期的な接点あり):20〜30%
新規接点(関係性なし):10〜15%
従業員アンケート:50%以上
初めてアンケートを実施する場合は、上記の数値を参考に目標を設定し、PDCAサイクルを回しながら徐々に改善していくとよいでしょう。業界平均との比較も有効です。
Q4.デジタルギフトの金額はいくらが適切ですか?
デジタルギフトの金額は、アンケートの対象者と回答にかかる時間によって決めると良いでしょう。
金額設定の目安
BtoB顧客向け:500〜1,000円
従業員向け:300〜500円
取引先向け:500〜1,000円
新規接点向け:500円以上
回答時間が5分程度のアンケートであれば500円、10分以上かかるアンケートなら1,000円を目安にするとよいでしょう。
重要性の高いアンケートや高品質な回答を求める場合は、金額を高めに設定することで、真剣な回答を得やすいです。
ただし、あくまで参考値なので、実際の運用にあたっては、自社基準に沿ってご判断ください。
まとめ|施策を見直してアンケート回収率を最大化しよう
アンケート回収率を向上させるために重要なのは以下3つです。
設計の最適化
インセンティブ設計
配信タイミング
アンケート回収率は、適切な施策を実行することで向上できます。
特に、デジタルギフトを活用したインセンティブ設計は即効性が高く、導入しやすい施策です。まずは小規模なアンケートで試し、効果を確認しながら本格導入を検討するとよいでしょう。
顧客の声を効率的に集められれば、より精度の高い意思決定につながります。ぜひ本記事の内容を参考に、アンケート施策の改善に取り組んでみてください。
アンケート施策の運用にお困りの方へ
アンケートの実施には、質問の設計や回答の収集、結果の集計・分析、そして謝礼の発送など、多くの手間がかかります。これらを手作業で行うのは非常に大変で、特に大量のデータを扱う場合は時間や労力がかかります。
そのため、アンケートの運用を効率化するためには、システムの活用が非常に効果的です。「Survey(アンケートシステム)」を使うことで、これらの手間を軽減し、スムーズに運用を進めることができます。
例えば、既にお使いのアンケートツールとも連携できるので、システムを大きく変更することなく、今の運用のままでアンケートの実施やギフト配布が可能です。
本資料では、アンケート実施から回答者へのギフト付与までをシステム上で完結させる方法や、料金プランについて詳しくご紹介しています。