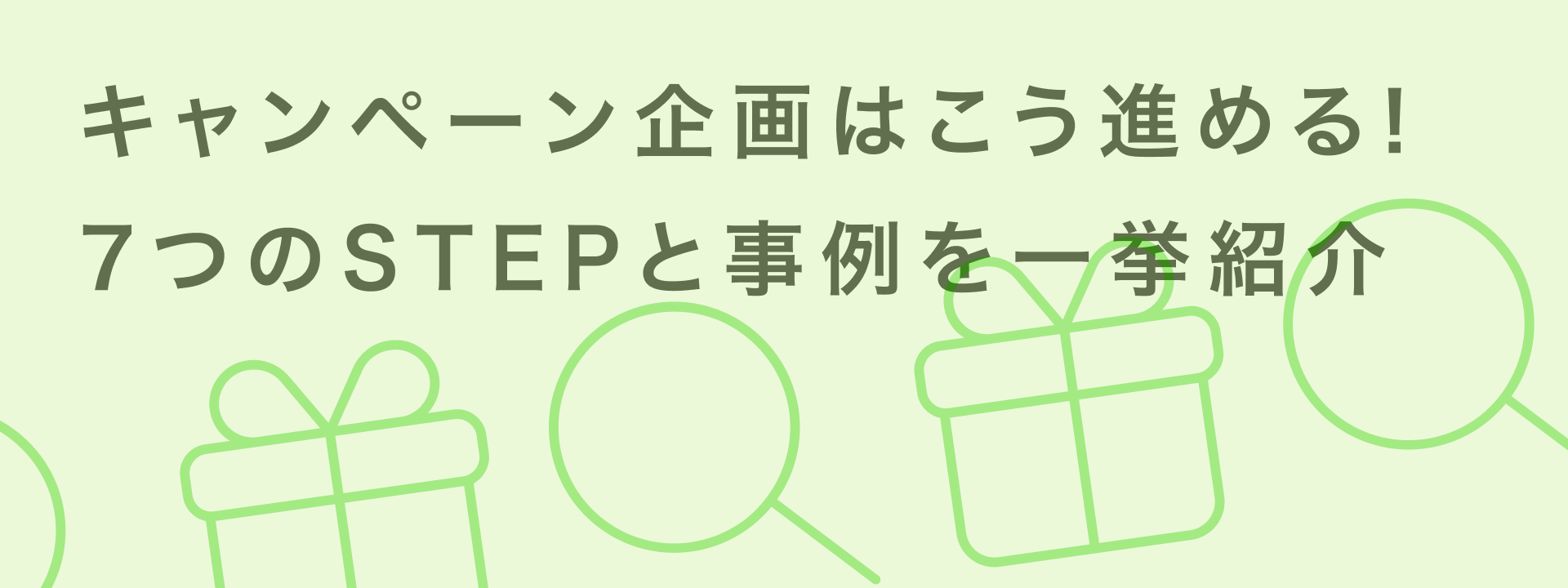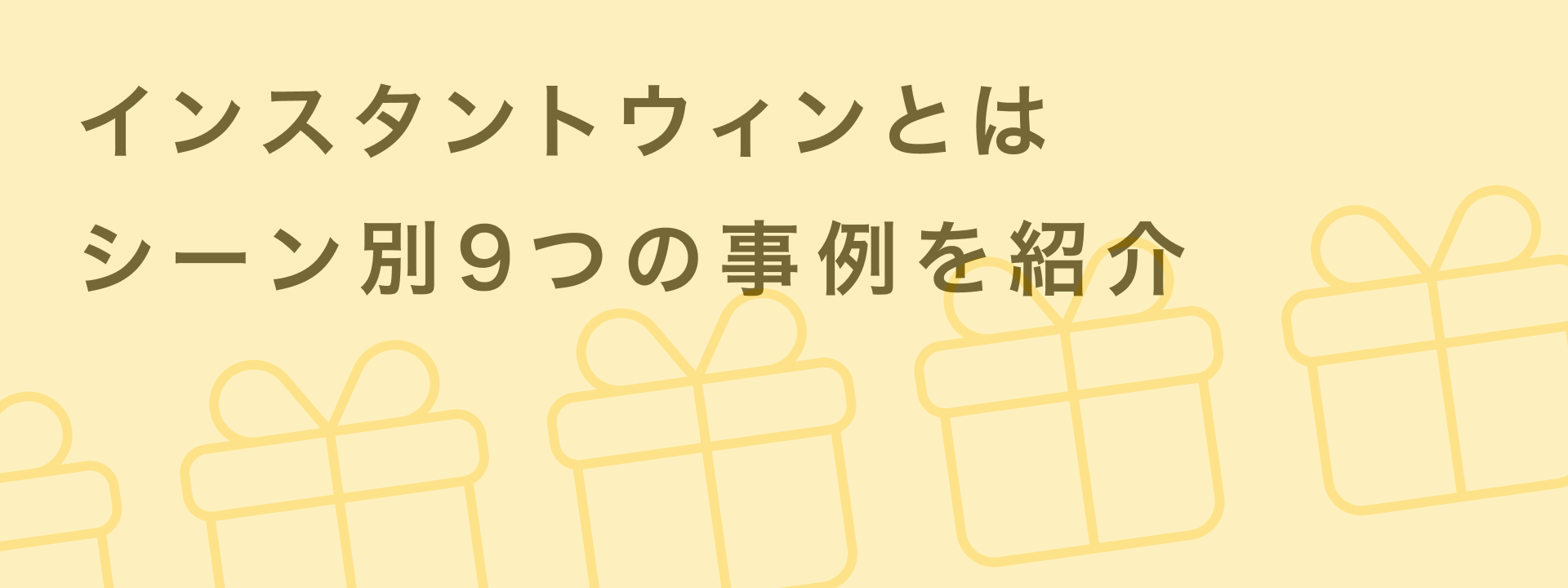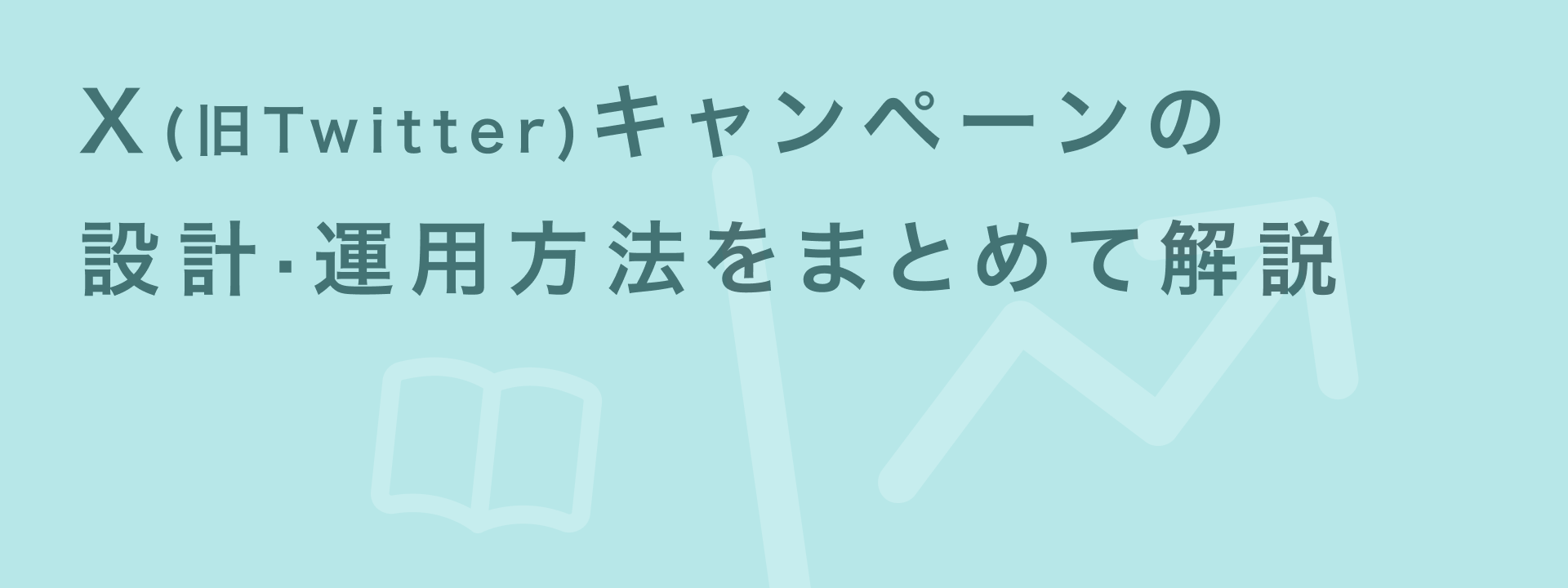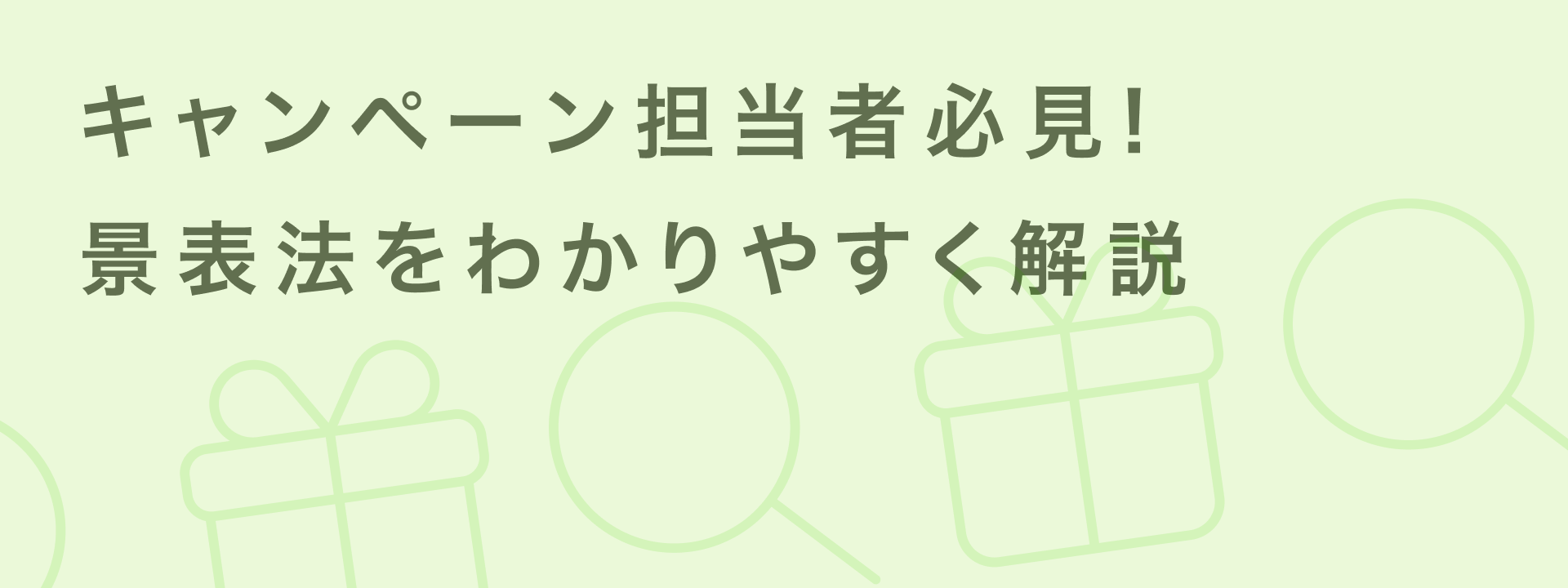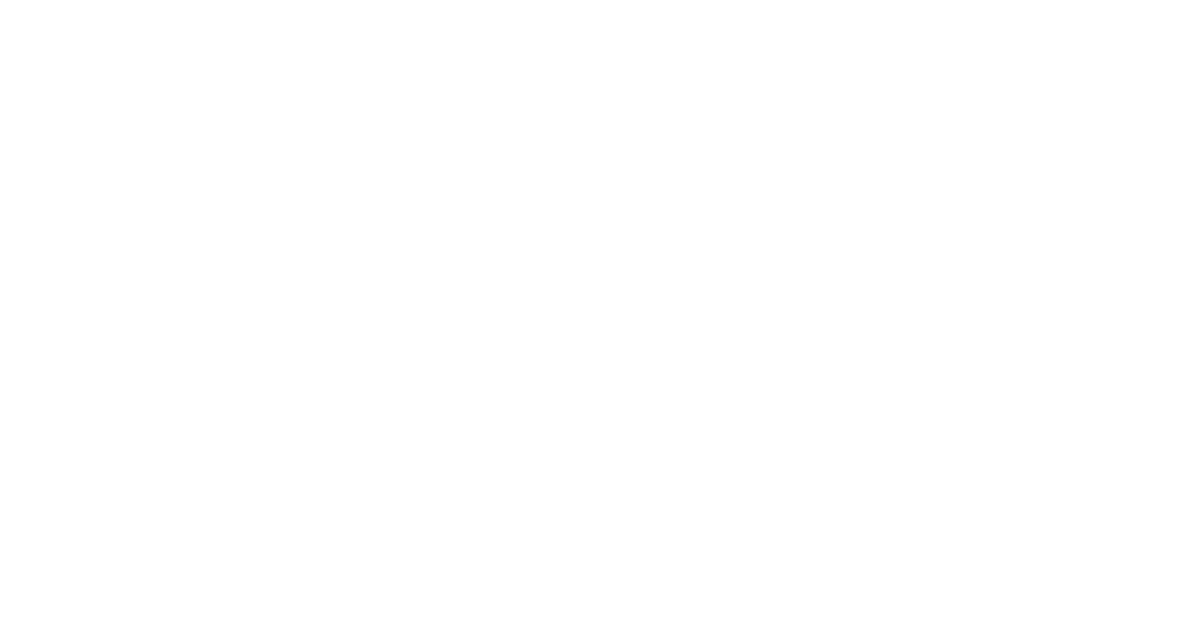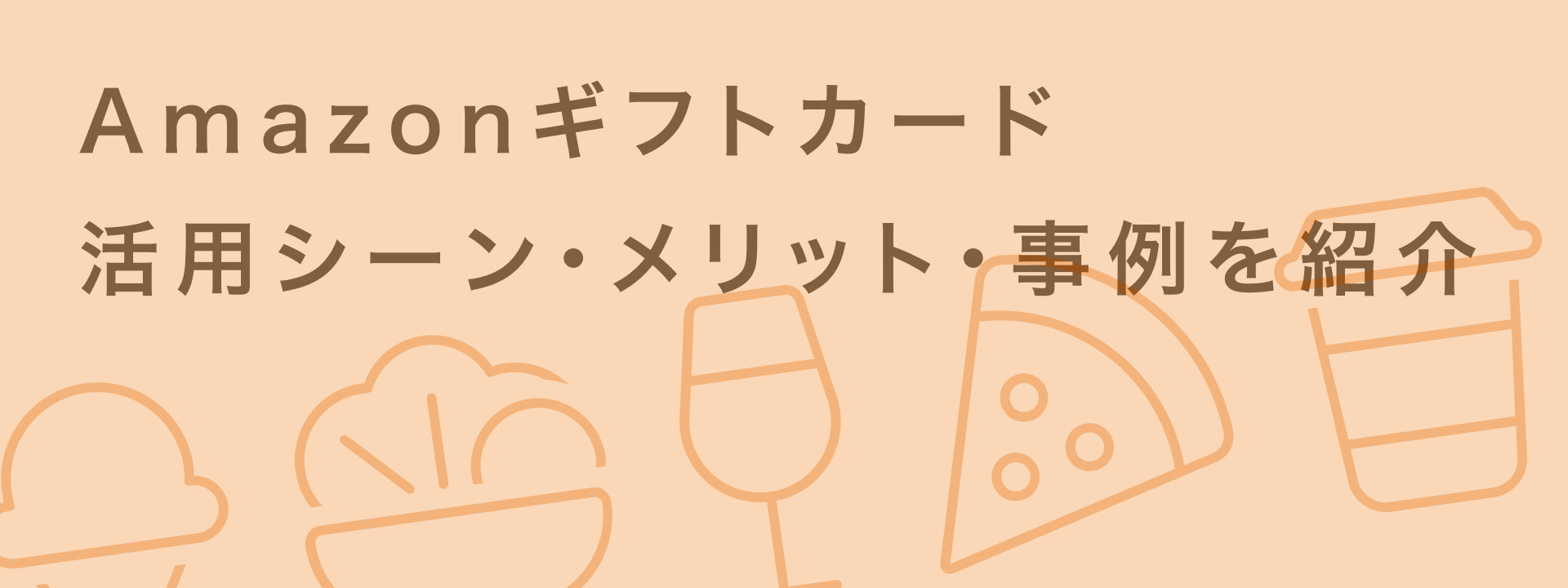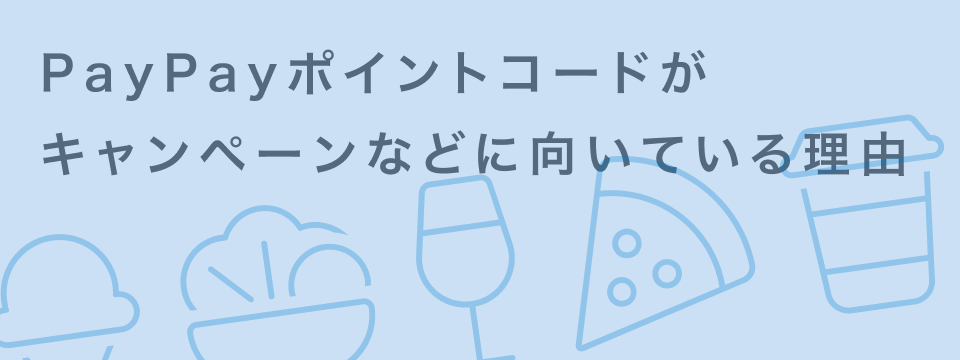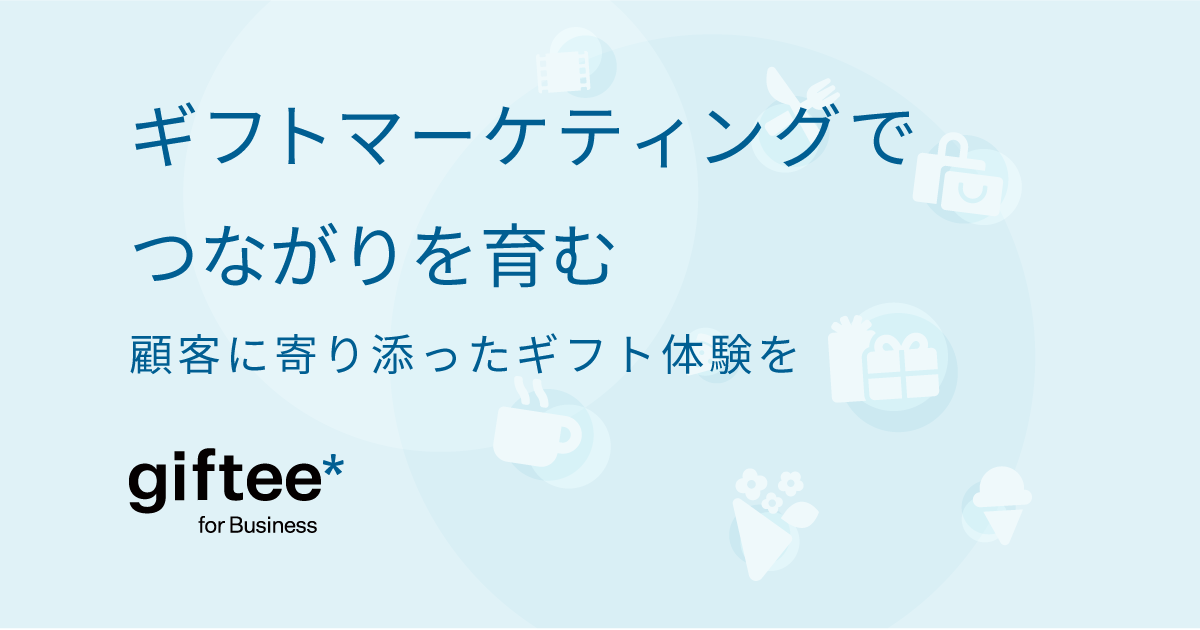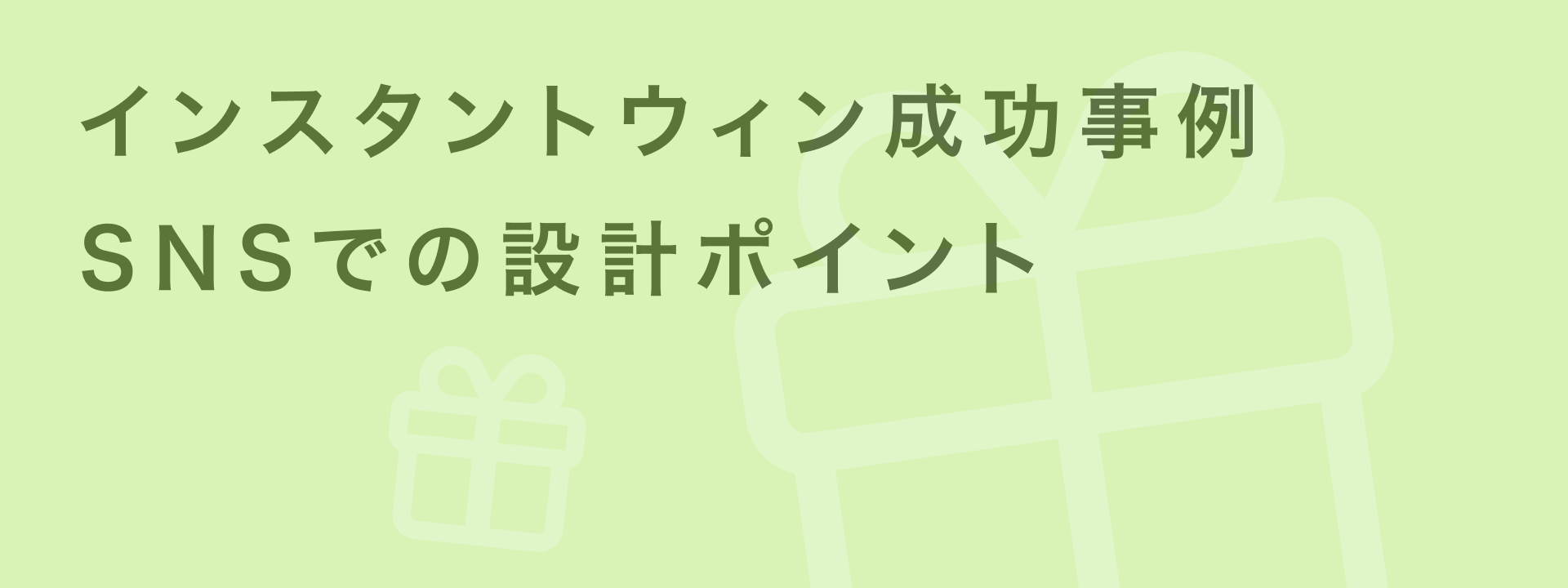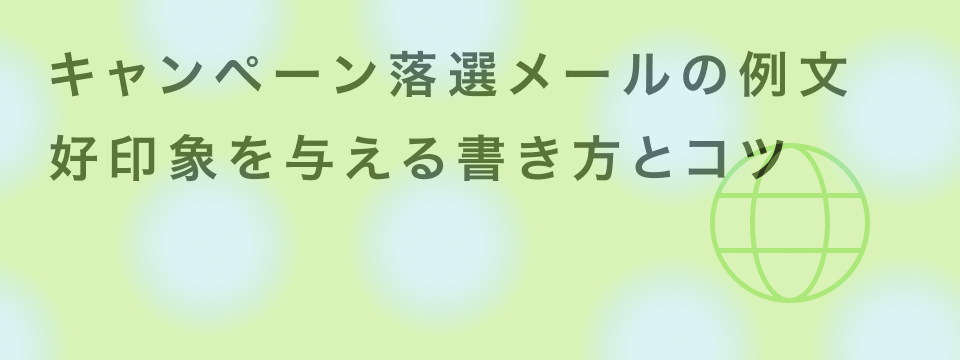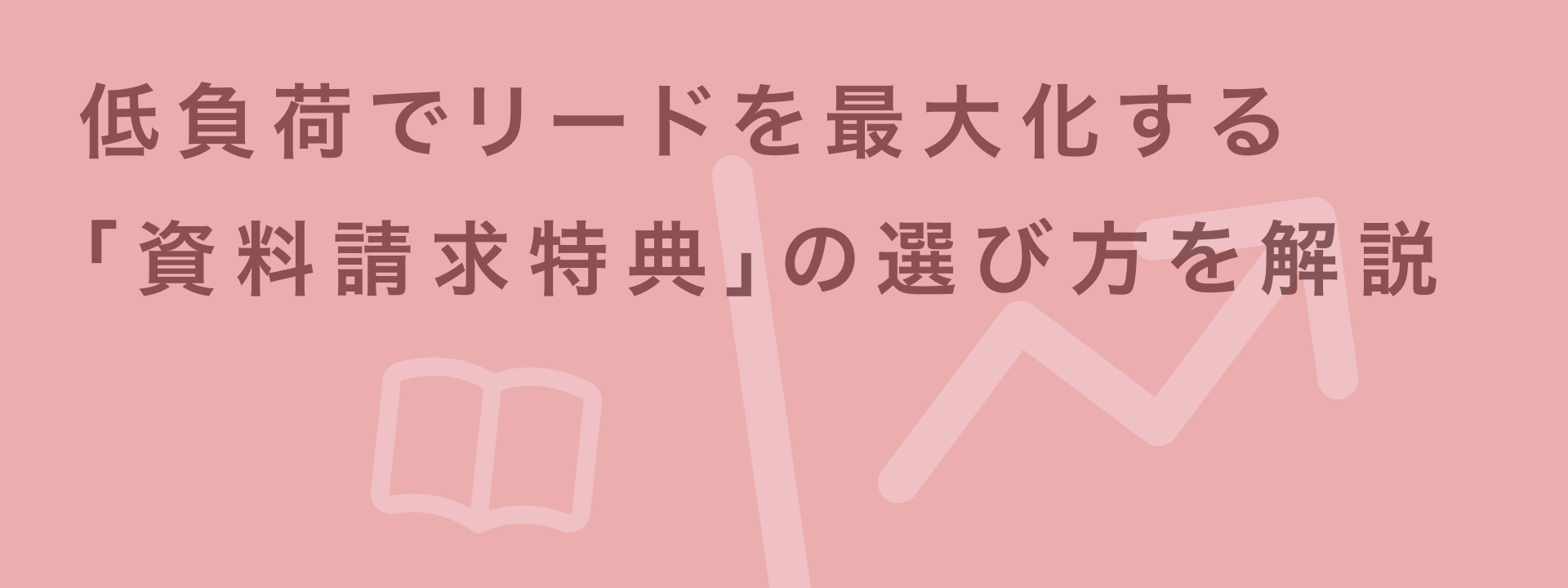マストバイキャンペーンとは?購買促進に直結する景品設定のコツを紹介
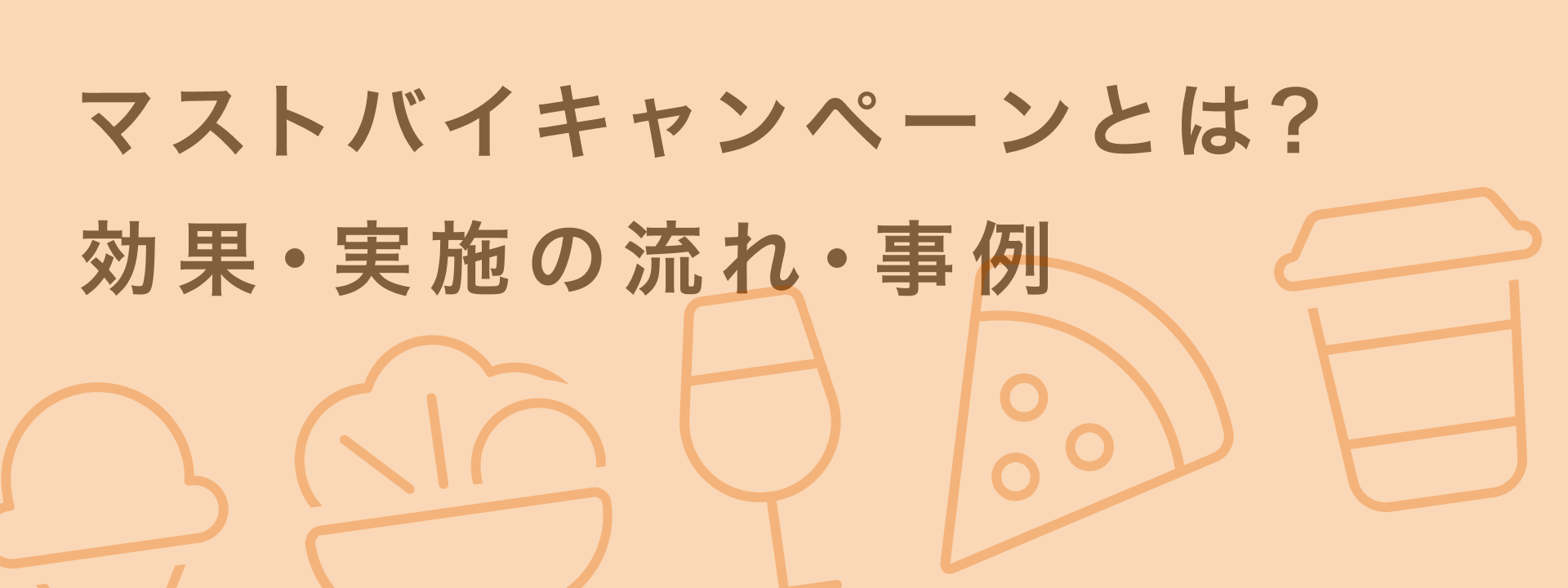
マストバイキャンペーンは商品の購入を参加条件とする販促キャンペーンのことです。成功すれば購買意欲の増加や新規顧客の獲得につながり、売上の向上が期待できます。
ただし、応募手続きを簡単にしたり、ゲーム要素を取り入れたりと、消費者が参加しやすい環境を整えなければ、マストバイキャンペーンを成功させるのは難しいでしょう。
また、商品の購入が条件となるため、「購買証明」が必要となります。購買判定を人の手で行うと多大な時間がかかり、ヒューマンエラーのリスクも高まります。キャンペーンを効果的に行うためには、キャンペーンに合わせた応募方法の検討や、購買判定を自動チェックできる「購買判定システム」の活用がおすすめです。
本記事では、マストバイキャンペーンの基礎知識や購買証明の種類、キャンペーンの効果、実施方法などを解説します。また、マストバイキャンペーンの成功事例も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
マストバイキャンペーンの設計でお困りのご担当者様へ
こんなお悩みはありませんか? ・マストバイキャンペーンを実施したいが、効果的な設計方法が分からない ・ターゲット設定やKPI設計など、キャンペーン設計の考え方が分からない ・効果的なギフト選定のコツを知りたい
購買情報をもとに参加条件を判定するマストバイキャンペーンでは、レシートの扱い方、不正防止、景品の設計など“マストバイ特有の要素”を押さえることが成功の鍵になります。
そこで累計導入件数7万件以上、法人向けデジタルギフト導入実績No.1のgiftee for Businessでは、購買証明の判定から抽選・ギフト付与までを自動化できる「Mustbuy(購買判定システム)」を提供しています。
さらに、同ソリューションの機能の紹介に加え、レシート解析によるリアルタイム判定の仕組み、不正応募を防ぐチェックロジック、継続購買を促すポイント設計など、マストバイ施策に必要なポイントを整理した資料もご用意しました。
マストバイキャンペーンをより効果的に実施したい方におすすめの資料です。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
マストバイキャンペーンとは?
マストバイキャンペーンは、参加条件として商品の購入が求められるプロモーション施策です。短期的な売上向上や新規顧客の獲得、リピート購入の促進に効果的なマーケティング手法となります。
マストバイキャンペーンにおけるユーザーの参加方法は主に以下の二つです。
特定の商品を購入することで応募できるケース | たとえば、キャンペーン対象の商品を購入した場合、その購入が応募資格となります。 |
|---|---|
一定金額以上の購入で応募できるパターン | この場合、たとえば1,000円以上の商品を購入することで応募資格が得られます。 |
これらの条件を満たした後、応募資格を証明するためにレシートや購入証明を提出することで、応募が完了する仕組みです。
応募完了後の流れとしては、後日抽選結果がわかる「後日抽選型」と、応募直後にその場で当選結果がわかる「即時抽選型(インスタントウィン)(※)」の二つの形式があります。
※即時抽選型のキャンペーンを行う場合、抽選ツールが必須となります。詳細は後述。
マストバイキャンペーンは、特定のショッピングモールで商品を購入するとプレゼントがもらえるキャンペーンや、人気の飲料や食品を購入するとポイントがもらえるキャンペーンなど、商業施設や食品・飲料メーカー、日用品メーカーといったさまざまな業界で活用されています。
マストバイキャンペーンで使われる購買証明の種類
商品の購入が条件となるマストバイキャンペーンでは、購入した証となる「購買証明」が必要となります。購買証明には複数の種類がありますが、主に以下の5つが挙げられます。
商品購入時のレシート
商品購入時のレシートを提示してもらう方法です。レシートをスマートフォンで撮影し、専用フォームやアプリ経由で送信するデジタル応募形式も一般的となっています。応募シールの製作や貼り付けが不要なため、手軽に実施できます。
ただし、消費者がレシートを紛失するリスクがあり、購入していても応募に至らないケースが発生しやすいとも言えます。そのため、応募方法をわかりやすく説明し、購入後すぐに応募を促す仕組みが必要です。
商品に貼り付けた応募シール
商品に貼られたシールを、はがきや専用の台紙に貼り付けて応募する方法です。シールの種類や枚数で景品を変えるなど、消費者に複数回の購入を促しやすい仕組みを作れる特徴があります。
また、実物のシールを集めるという行為自体が、コレクション感覚で消費者の参加意欲を高める効果も期待できます。そのため、食品・飲料・日用品などリピート購入が多い商材との相性が良い施策です。
ただし、消費者にとっては切り取り作業や郵送の手間がかかり、応募のハードルがやや高くなります。企業側にとってもシール製作や商品への貼付作業にコストがかかります。デジタル化が進む現代では、やや古い印象を与える場合もあるため、ターゲット層に合わせた施策設計が必要になるでしょう。
商品パッケージの一部(バーコード)
商品パッケージに印刷されているバーコード、マークといった商品パッケージの一部を切り取り、はがきに貼りつけて応募する方法です。既存のパッケージデザインをそのまま活用できるため、キャンペーン用の追加制作が不要で、コストを抑えてキャンペーンが行えます。
ただし、キャンペーン用追加制作を行わない場合、消費者がキャンペーンを認識しにくく、参加率が伸び悩む可能性があります。そのため、店頭POPやSNSを活用した告知が必要となってくるでしょう。バーコードの切り取りもまた、応募シールと同様にデメリットとなります。
二次元コード
商品に記載された二次元コードから応募する方法です。スマートフォンで撮影するだけで、簡単にWeb応募ができます。紙の応募シールやレシート送信と異なり、手間が少なくスムーズに参加できるため、消費者の応募率を高めやすいのが大きなメリットです。
Webサイトやアプリと連携することで、キャンペーンのバリエーションを広げやすく、応募者のデータを取得・分析しやすい点も魅力です。クーポンの発行や会員登録促進など、単なる応募以外のマーケティング施策とも組み合わせることができます。
ただし、二次元コードを商品パッケージに印刷する必要があるため、デザイン変更や印刷コストが発生します。特に、小ロット生産の商品ではコスト負担が大きくなる可能性があるため、事前の計画が重要です。
シリアルナンバー
商品に記載されたシリアルナンバーをWebサイトで入力して応募する方法です。スマートフォンやパソコンからの簡単なWeb応募が可能で、消費者の手間を減らしつつ、スムーズなキャンペーン運用が可能になります。
シリアルナンバーは一意のコードを付与できるため、不正応募を防ぎやすく、特定の商品購入者のみにキャンペーンを限定できる点が大きなメリットです。また、入力データを活用することで、応募者の傾向分析やCRM施策にも応用しやすくなります。
ただし、ナンバー管理のためのシステム構築や、コードを印刷するためのパッケージ制作コストが発生します。
購買証明の種類 | 初期コスト | 参加のしやすさ | 不正対策の強度 | 運用負荷 | 向いているキャンペーンやシーン |
|---|---|---|---|---|---|
レシート | 低 | ⚪︎ | 中 | 低 | 短期間のキャンペーン、スマートフォンユーザー向け |
応募シール | 中 | △ | 中 | 高 | リピート購入促進、コレクション要素を加えたい場合 |
バーコード | 低 | △ | 低 | 中 | 既存パッケージを活用したい場合、コスト重視 |
二次元コード | 中 | ◎ | 中 | 中 | スマートフォンユーザー向け、データ分析を重視する場合 |
シリアルナンバー | 高 | ◎ | 高 | 低 | 不正防止を重視する場合、高額景品のキャンペーン |
マストバイキャンペーンを効率的に運用するなら購買判定システムの利用もおすすめ
マストバイキャンペーンを実施する場合、購買判定を人の手で行うと以下のような課題が発生します。
レシートや商品パッケージの一部、シリアルナンバーなどを目視で確認する必要があり、非常に時間がかかる
レシート応募の場合、内容を即座に判定することが難しく時間がかかる
ヒューマンエラーのリスクが高い
キャンペーンを効果的に行ううえで、購買判定の作業を片手間で行うのは非常に大変です。大きなキャンペーンや申し込み数の多いキャンペーンほど時間がかかりますし、ヒューマンエラーのリスクも高まります。
これらのリスクを解消するためには、「購買判定システム」の活用がおすすめです。購買証明であるシリアルコードやレシート画像を自動判定できるため、マストバイキャンペーンの実施効率が格段に向上します。
また、景品をオンラインで贈れる「デジタルギフト」にすることで、判定から景品の付与までを全自動化できます。業務負担を大幅に軽減できるうえに、ユーザー側も簡単に受け取れるため満足度も高くなるでしょう。
マストバイキャンペーンの設計でお困りのご担当者様へ
こんなお悩みはありませんか? ・マストバイキャンペーンを実施したいが、効果的な設計方法が分からない ・ターゲット設定やKPI設計など、キャンペーン設計の考え方が分からない ・効果的なギフト選定のコツを知りたい
購買情報をもとに参加条件を判定するマストバイキャンペーンでは、レシートの扱い方、不正防止、景品の設計など“マストバイ特有の要素”を押さえることが成功の鍵になります。
そこで累計導入件数7万件以上、法人向けデジタルギフト導入実績No.1のgiftee for Businessでは、購買証明の判定から抽選・ギフト付与までを自動化できる「Mustbuy(購買判定システム)」を提供しています。
さらに、同ソリューションの機能の紹介に加え、レシート解析によるリアルタイム判定の仕組み、不正応募を防ぐチェックロジック、継続購買を促すポイント設計など、マストバイ施策に必要なポイントを整理した資料もご用意しました。
マストバイキャンペーンをより効果的に実施したい方におすすめの資料です。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
マストバイキャンペーンで期待できる効果
マストバイキャンペーンを実施すると、次のような効果が期待できます。
購買意欲の増加につながる
客単価向上につながる
新規顧客の獲得につながる
リピート購買を促進できる
ブランディング効果が期待できる
購買意欲の増加につながる
消費者は、自分が「お得」な買い物をしていると感じると、購買意欲が高まります。マストバイキャンペーンでは、条件を満たすことで「特典がもらえる」という期待感を醸成できます。この「お得感」が大きな魅力となり、特典が魅力的であればあるほど、購買意欲が強く引き寄せられます。
また、マストバイキャンペーンには「限定感」もともないます。特定の期間に行われるキャンペーンであれば、「今買わないと損をする」「この機会を逃すと次はない」といった心理が働き、急いで購入しようとする動機が生まれます。このように、限定的な条件が購買意欲をさらに強化し、通常のお買いもの以上の購入を促すことができます。
客単価向上につながる
特定の商品を購入することで応募資格が得られるマストバイキャンペーンでは、その商品を購入するために、いつもなら買わないような高額な商品を選んだり、必要以上に商品を購入したりする「まとめ買い」傾向が見られます。1回あたりの購入単価が増加し、客単価の向上につながります。
たとえば、「1,000円以上の商品を購入することで応募資格を得る」といった場合、「あと数百円でキャンペーンに参加できるなら」といった心理が働き、条件を満たすために必要な商品以外にも追加で購入することが多くなります。このように、キャンペーン期間中、消費者は普段よりも予算を超えた支出をする動きが見られることがあり、それにともない全体の売上や客単価が増加します。
新規顧客の獲得につながる
マストバイキャンペーンでは、「特典がもらえる」という魅力的な理由があるため、新しい顧客に対しても強いアピールになります。たとえば、普段自社ブランドを知らなかったり、利用したことがない人でも、キャンペーンの内容に惹かれて一度購入してみることがよくあります。特典を得るために「試しに買ってみよう」と思わせることで、新規顧客の獲得につながるのです。
さらにキャンペーンは通常、期間限定で行われるため、「今だけのチャンス」と感じる心理が働きます。この「限定感」が購買意欲を刺激し、キャンペーンに参加しようとする動機付けになります。
リピート購買を促進できる
マストバイキャンペーンがリピート購買を促進できる理由は、消費者が一度キャンペーンを通じて購入を経験し、その体験に満足することで、再度購入したいと感じる可能性が高くなるためです。
まず、キャンペーンを通じて商品を実際に手に入れることで商品自体を認識します。もしその体験がポジティブであれば、その商品に対する好感度が高まり、再度その商品やブランドを購入したいという気持ちが芽生えることがよくあります。
また、キャンペーン期間中に一度購入した顧客は、その後も再度キャンペーンの条件を満たすためにリピート購入をする可能性が高くなります。この繰り返しがロイヤリティを育むことにつながるのです。
他にも、「次のキャンペーンでは、さらにお得な特典があるかもしれない」といった期待感が生まれ、定期的にブランドや商品をチェックし続ける可能性もあります。
ブランディング効果が期待できる
マストバイキャンペーンは注目を集めやすいプロモーション手法です。キャンペーンが広く認知されることで、これまでブランドを知らなかった無関心層にもアプローチが可能だからです。また、SNSや口コミを通じて情報が拡散されることで、より多くの人にブランドの名前が伝わりやすくなります。
そして、キャンペーンを通じて初めて商品を購入した場合、その商品の品質が高ければ、実際に商品に触れることでブランドへの好感度や信頼感が高まるでしょう。
さらに、キャンペーン訴求の際、「希少性」や「特別感」も感じてもらえるように工夫すれば「特別な体験を提供するブランド」として認識され、他社との差別化要素となります。これにより、ブランドのプレミアム感や信頼性が強化され、長期的なブランディング効果が期待できます。
マストバイキャンペーンの実施方法

ここまで、マストバイキャンペーンの概要や効果について解説しましたが、どのように実施すればよいのかについても見てみましょう。
1.キャンペーンを設計する
まず、キャンペーンをしっかり設計しましょう。十分な設計ができていないと、期待していた売上や認知拡大の成果が得られない可能性があるからです。
はじめに「売上の向上」や「新規顧客獲得」などの、具体的な目標を設定しましょう。目標は『特定商品カテゴリの売上を20%向上させる』や『1回あたりの購入単価を10%引き上げる』といったように、数値で設定することで、結果を振り返る際の基準が明確になります。
目標を設定したら、年代や性別、生活スタイルなど、ターゲットを分析します。これは、プロモーション方法や景品選定に影響するため、憶測ではなく実際の顧客データなどから分析を行いましょう。
次に、「対象商品の購入」や「購入金額の指定」など、応募条件を設定します。応募条件は複雑すぎると参加しづらい原因になります。シンプルでわかりやすい条件を設定することが重要です。
キャンペーンの実施期間も、長すぎず短すぎないように決定しましょう。2週間〜1か月程度の期間が一般的です。
2.キャンペーンの訴求方法を選定する
キャンペーンを認知してもらうためのプロモーション方法を選びましょう。プロモーション方法は一つに絞る必要はありません。複数を組み合わせることでより効果的にプロモーションできる可能性があります。
代表的なプロモーションには、以下のような方法があります。
【SNSやWeb広告】
特に若年層に向けたキャンペーンの場合は、InstagramやXを活用したプロモーションが効果的です。SNS専用のハッシュタグを作成して話題性を高めたり、縦型動画を活用した短尺プロモーションを行うのもおすすめです。また、Web広告では過去に商品を閲覧した消費者にリターゲティングするのも有効です。
【店頭ポスターやPOP】
店頭にポスターやPOPを掲示することで、直接購入につながりやすい方法です。短くわかりやすいメッセージや視認性の高いデザインを心がけましょう。また、期間限定や特典内容を強調したキャッチコピーを使用すると良いです。
【商品パッケージのバーコードなど】
商品パッケージにキャンペーン情報を記載するのも良い方法です。たとえば、キャンペーンの説明文に加え、二次元コードと景品名を併記することで「このコードをスキャンすれば特典がゲットできるんだな!」といった明確なアクションの導線を敷け、キャンペーン参加率upにつながるでしょう。
SNS広告と店頭ポスターを連携させるなど、複数の方法を統合的に活用することで、より広範な消費者層にアプローチできます。自社のターゲット層にあわせて、最適なプロモーション方法を選びましょう。
3.応募方法(購買証明)を決定する
マストバイキャンペーンは、条件を満たしていることを確認するために、商品を購入したことを示す「購買証明」が必要です。購買証明には複数の種類があり、主に以下のような方法が挙げられます。
商品購入時のレシート
商品に貼り付けた応募シール
商品パッケージの一部(バーコード)
二次元コード
シリアルナンバー
自社の商品やキャンペーンに合わせて、適切な応募方法(購買証明)を決定しましょう。
4.景品を選定する
ターゲット層のニーズやライフスタイルに合った景品を選定することで、キャンペーンの効果を最大化できます。景品として用いられるものには、以下のような種類があります。
【デジタルギフト】
デジタルギフトは、電子マネーや食料品、商品引換券、体験ギフトなど幅広い種類があり、金額も数十円といったような少額から対応可能なため、キャンペーンやターゲットに合わせて適切な景品を選定できます。
当選者にメールやSNSなどを通じて配布できるので、梱包や発送、在庫管理の手間がなく、キャンペーンの実施を効率化できます。また、デジタルギフトサービスによっては、インスタントウィン(即時抽選)ツールを提供していることもあり、そのようなツールを活用することで、抽選を自動化することも可能です。
【自社商品】
自社商品を景品とするケースもあります。キャンペーンをきっかけに自社商品を試してもらうことで、商品の価値を認識してもらえる機会が増やせるというメリットがあります。
また、外部から景品を調達するよりも、コストを抑えられる可能性もあります。
【現物ギフト】
ギフトカード・食料品・家電・雑貨など、現物を用意する方法もあります。ただし、現物ギフトの場合は、在庫の管理や配送にかかるコストと手間が発生する点に注意が必要です。
5.キャンペーンを実施する
1~4まですべて決定したら、実際に告知や応募受付を実施します。その後、抽選・結果発表・景品の発送を行いましょう。
実施中は、進捗状況や応募状況をチェックし、問題があれば速やかに対応しましょう。また、キャンペーン終了後は、結果発表を迅速に行うことが大切です。
1~4まですべて決定したら、実際に告知や応募受付を実施します。その後、抽選・結果発表・景品の発送を行いましょう。
実施中は、進捗状況や応募状況をチェックし、問題があれば速やかに対応しましょう。また、キャンペーン終了後は、結果発表を迅速に行うことが大切です。
より詳しく知りたい方向け!キャンペーン企画の7STEP
マストバイキャンペーンの実施方法についての基本的な流れをご紹介しましたが、キャンペーン企画をさらに効果的に進めるためには、より詳細なステップに分けて計画します。キャンペーン全体は以下の7つのステップで構成されます。
目標・KPIの設定
ターゲット分析
キャンペーン内容の設計
景品選定
プロモーション計画
運用体制の構築
効果測定・分析
これらの各ステップについて詳しく知ることで、キャンペーンの成功確率を高めることができます。
さらに詳しく知りたい方は以下の記事にて、キャンペーン企画の手順を解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
マストバイキャンペーンを成功させる5つのポイント

マストバイキャンペーンを成功させるには、次のポイントを押さえて戦略を立てましょう。
参加しやすい仕組みを採用することで、エントリーの障壁を低くする
ゲーム要素を取り入れ、「楽しみ」を追加する
ターゲットに適した景品を選ぶ
キャンペーンの認知を促す施策を行う
SNSを活用して拡散力を高める
景品表示法に違反しない範囲での運用を行う
参加しやすい仕組みを採用することで、エントリーの障壁を低くする
応募方法は、消費者に負担のない方法を選ぶことが大切です。面倒で複雑な方法だと、せっかくキャンペーンを実施しても参加してもらえない可能性があるからです。
たとえば、20代向けのキャンペーンで「はがきにバーコードを貼り付けて応募」とした場合、はがきを購入して切り取ったバーコードを貼り付け、宛名を記載してポストに投函する、という手間がかかります。郵送が身近な方法ではない若者にとっては、手間や費用がかかり、参加してもらえないことが多いです。そのため、オンラインで応募できる方法が適していると言えます。
反対に、高齢者向けの場合はオンライン応募の勝手がわからず、抵抗感を持つ方もいるかもしれません。スマートフォンやPCを使いこなしている高齢者もいるため、オンラインでの応募の他に郵送でも応募を受け付けるなどすると、多くの人に応募してもらえる可能性が高いでしょう。
ゲーム要素を取り入れ、「楽しみ」を追加する
応募してただ結果を待つよりも、応募すること自体に楽しみを追加することで、興味を持ってもらえる可能性があります。たとえば、インスタントウィン(即時抽選)なら、その場で抽選結果がわかるため、以下のような効果が期待できます。
「今すぐ結果が知りたい」というユーザー心理を刺激できる
すぐに結果が分かることで、参加の心理的ハードルが下がる
繰り返し抽選に参加したくなる
ほかにも、落選してもさらに抽選に参加できる「ダブルチャンス」があれば、キャンペーンをより楽しめる要素が増えます。また、応募シールやスタンプを収集する方法なら、参加者に集める楽しさを味わってもらえます。
このような楽しみの要素を追加することで、より効果的にマストバイキャンペーンを実施できるでしょう。
マストバイキャンペーン × インスタントウィンで参加率を向上
マストバイキャンペーンにゲーム要素を加える方法として、インスタントウィン(その場で抽選結果がわかる仕組み)との掛け合わせがあります。インスタントウィンは応募後すぐに結果がわかる形式のため、ユーザーの期待感や興奮を最大化でき、キャンペーン参加率の向上が期待できます。
インスタントウィンの魅力は、応募後すぐに「あたり/はずれ」がわかる即時性です。このスピード感がユーザーのワクワク感や期待感を高め「また参加したい」という気持ちにつながります。また、当選確率の“さじ加減”や、当選時の演出を工夫したりすることでユーザー体験をさらに高められるでしょう。
さらに詳しく知りたい方は以下の記事にて、インスタントウィンの仕組みについて解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
ターゲットに適した景品を選ぶ
前述したように、ターゲットが魅力的に感じる景品を選べるかどうかは、キャンペーンの成功を大きく左右します。
たとえば、全国規模でキャンペーンを実施しているのに、使える店舗が限定された商品引換券を景品にしても、近くに店舗がない消費者には魅力的に感じられません。また、幅広い年齢層をターゲットにする場合は、限定された景品では適さない可能性もあります。
そのような場合は、受け取った人が好きな商品やサービスが選べるデジタルギフトを用意すると、幅広い顧客に参加してもらえる可能性が高まるでしょう。
キャンペーンの認知を促す施策を行う
マストバイキャンペーンはただ実施するだけではなく、より多くの人が参加してくれるように認知を促す施策を行いましょう。
たとえば、キャンペーンの認知を促す施策は以下のようなものがあります。
キャンペーンの詳細を掲載したWebページ
店頭や売り場にPOPを設置する
SNSでキャンペーンを告知する
キャンペーンの認知度を高めれば応募率もアップし、消費者の購買意欲を高めることが可能となります。
SNSを活用して拡散力を高める
マストバイキャンペーンの成果を最大化するには、SNSとの連携が効果的です。特にXキャンペーンでは「フォロー&リポスト」や「ハッシュタグ投稿」などの仕組みを活用することで、購入者自身が情報を拡散する仕組みを構築できます。
これにより新規顧客の認知拡大と既存顧客のエンゲージメント向上を同時に実現でき、キャンペーンの投資対効果の改善につながります。
実践のポイント
専用ハッシュタグを設定し、参加者の自発的な投稿を促す
リポストや投稿に追加特典を用意し、拡散インセンティブを高める
投稿内容を分析し、次回キャンペーンの改善点を把握する
X(旧Twitter)キャンペーンについてさらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、具体的な運用手法と成功事例を解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
景品表示法に違反しない範囲での運用を行う
キャンペーンを実施する際には、景品表示法(以下、景表法)に違反しないよう注意する必要があります。景表法には種類がありますが、マストバイキャンペーンは「一般懸賞」と「共同懸賞」に該当する場合があります。
一般懸賞
一般懸賞とは、購入を条件とした抽選方式の懸賞です。次のような方法が含まれます。
抽選券を用いる方法
レシートや商品パッケージを抽選券として使用する方法
宝探しやじゃんけんによる方法
そのため、マストバイキャンペーンも一般懸賞に当てはまるのです。一般懸賞の景品類は、以下のような制限があります。
懸賞に係る取引価額が5,000円未満:景品類限度額は取引価額の20倍まで
懸賞に係る取引価額が5,000円以上:景品類限度額は10万円まで
さらに、懸賞に係る取引の予定総額(懸賞販売実施期間中の対象商品の売上予定総額)の2%以内とされており、最高額及び総額の両方の制限内で行わなければいけません。
共同懸賞
共同懸賞とは、複数の事業者が共同で実施する懸賞のことです。以下のような場合に当てはまります。
一定地域(市町村など)の小売業者やサービス業者による共同実施
商店街やショッピングビルでの中元・歳末セールなどの実施
同業者による共同実施
たとえば、商業施設全体でマストバイキャンペーンを実施する場合は、共同懸賞となります。共同懸賞の景品類は、以下のような制限があります。
最高額:取引価額にかかわらず30万円まで
総額:懸賞に係る売上予定総額の3%以内
以下は「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品(ベタ付け景品)」の景品の上限額をまとめたものです。

景品表示法の詳細なルールについてさらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、実務で必要な知識を網羅的に解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
マストバイキャンペーンを実施した企業の成功事例

マストバイキャンペーンを実施した場合、具体的にどのような効果を得られるのかについて、弊社ギフティをご利用いただいた企業の事例を見てみましょう。
商業施設|マストバイシステム・即時抽選システムを活用した全国規模のイベントを実施
目的 | ・施設への来場頻度向上 ・施設内での買い上げ・買い回り促進 |
|---|---|
課題 | 新型コロナウイルス感染症の影響により主婦・若年層中心に来館者数が鈍化し、集客に苦戦していた |
成果 | ・オンラインのポイント蓄積・抽選システムを採用したことで運営工数の削減が実現できた ・デジタルギフトの採用によって、手間をかけずに当選賞品を増やすことができた ・「人生ゲーム」の世界観にあった企画を実現することができた ・シンプルなUI/UXにより、問い合わせやクレームを最小限に抑えることができた |
三井不動産商業マネジメント株式会社様では、全国の「ららぽーと」と「ラゾーナ川崎プラザ」の合計15施設合同で、「夏休みは、遊んで、買って、運試し! ららぽーと・ラゾーナ with 人生ゲーム」イベントを実施。その中の一企画である「あなたは貯めて応募派?今すぐチャレンジ派? LINEで『人生ゲーム』プレゼントキャンペーン」というマストバイキャンペーンを開催しました。
具体的なキャンペーン内容は、期間中に対象施設内の対象店舗で3,000円以上お買い上げの方に「Lドル」(シリアルコード付きの抽選補助券)を配布するというものです。キャンペーンサイトにLINEアカウントでログインしてシリアルコードを入力すると、マイページ上に「Lドル」が貯まっていき、貯まったLドルを使って好きなコースに応募でき、抽選で合計1,980名様に賞品が当たるという仕様でした。
貯まったLドルに応じて応募できるコースを選べるようにし、Lドル1枚で応募できるコースはその場で抽選結果がわかるようにしたことで、参加者のモチベーションアップにつながりました。また、ギフティの「MustBuy(購買判定システム)」と「Instantwin(即時抽選システム)」の2つのシステムもご利用いただき、運用工数も削減できました。
▼この事例の詳細はこちら
飲料メーカー|「えらべるPay」を活用して幅広いユーザーに喜んでもらえるキャッシュバックを実施
目的 | ・購買促進 ・「実質タダ」をうたうことでの話題化 |
|---|---|
成果 | ・オペレーションの負荷を軽減できた ・幅広いエリアや世代の人たちにも使い勝手がよい形でキャンペーンを実現できた |
ペプシ様では、対象商品に添付されたシールの二次元コードを読み取ると、好きなスマホ決済サービスのポイントと交換できる「えらべるPay」がもらえるキャンペーンを実施しました。具体的には、商品購入後に貼り付けられたシールの二次元コードを読み込み、LINEのトーク画面で応募するというキャンペーンです。
そのインセンティブとして「えらべるPay」を採用し、
80円分が必ずもらえるキャンペーン
140円分が抽選でもらえるキャンペーン
など、複数のキャンペーンを実施しました。
「えらべるPay」をインセンティブ・景品として選んだことで、利便性が高く幅広い属性のターゲットに喜ばれるインセンティブとなりました。また、デジタルギフトの活用により、オペレーションの負荷も軽減できました。
▼この事例の詳細はこちら
ガソリンスタンド|レシートを活用したマイレージキャンペーンを実施
目的 | ・新規顧客獲得 ・既存顧客の固定化 ・ブランド認知 |
|---|---|
課題 | ・店舗のPOSシステムが統一されていない影響で、マストバイキャンペーンなどが実施できない ・環境の制約から企画に幅が出ない |
成果 | ・応募数が前回実施時と比較して200%を達成 ・一定数の参加者が期間中に店舗を再訪 |
太陽石油株式会社様では、系列のガソリンスタンドで対象の油種を給油した方を対象に、抽選でデジタルギフトが当たる「レシートマイレージキャンペーン」を実施しました。参加者は給油料金1,500円ごとに1ポイントを獲得し、ポイントに応じて3コースから好きなコースを選択して応募すると、当選者はその場でプレゼントがもらえるというキャンペーンです。
ギフティの「マイレージシステム」を活用することで、ポイント付与・抽選・デジタルギフトの送付をリアルタイムで自動化しました。
ポイントを貯めるだけでなく、その場で抽選結果が分かるようにした結果、応募数が前回の実施時と比較して200%を達成しました。また、一定数の参加者が期間中に再訪してくれました。
▼この事例の詳細はこちら
キャンペーン景品におすすめのギフトカード3選
マストバイキャンペーンのポイントは、魅力的で誰もが使いやすい景品を用意することです。特に全国規模で展開する場合、地域を問わず利用できるデジタルギフトが最適です。ここでは、キャンペーン景品として高い満足度を誇るギフトカード3つをご紹介します。
1. Amazonギフトカード
世界最大級のECサイトAmazonで利用できるギフトカードです。15円〜50万円まで、1円単位で金額設定が可能で、豊富な商品ラインナップから自由に選べるため、キャンペーン景品として高い汎用性を誇ります。
Amazonギフトカードの特長
- 日用品から家電・書籍まで多様なニーズに対応
- デジタルタイプであれば、URLやコードで贈ることができる
- 有効期限は10年と長く、使い忘れのリスクが少ない
Amazonギフトカードについてさらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、法人活用のメリットと導入事例などを解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
2. PayPayポイントコード
スマートフォン決済の普及により急速に利用が拡大しているコード型のギフト。全国のPayPay加盟店で利用でき、日常的な買い物シーンでの実用性が極めて高いキャンペーン景品です。
PayPayポイントコードの特長
- コンビニ・飲食店・オンラインショップなど幅広い加盟店で利用できる
- 若年層から中高年まで年齢を問わず利用されている
- 100万円未満で自由に金額設定でき、キャンペーン予算に応じた調整が容易
PayPayポイントコードについてさらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、企業活用事例と合わせて詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
3. QUOカードPay
株式会社クオカードが提供するデジタル版のQUOカードです。主要コンビニエンスストアを中心とした全国の加盟店で利用でき、キャンペーン景品として高い実用性と利便性を両立します。
QUOカードPayの特長
- 主要コンビニで日常的に使える
- 50円〜10万円まで、1円単位で金額設定が可能
- URL配信による即時配布で、現物配送の手間なし
QUOカードPayについてさらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、具体的な導入事例などを解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q. マストバイキャンペーンとは何ですか?
マストバイキャンペーンとは、商品の購入を参加条件とするプロモーション施策のことです。特定の商品を購入した方や、一定金額以上を購入した方に応募資格が与えられ、抽選で景品が当たる仕組みです。
購入の証明として、レシートやシリアルナンバーなどの購買証明を提出してもらうことが多いでしょう。
Q. マストバイキャンペーンの主な効果は何ですか?
マストバイキャンペーンは、施策の位置づけとして「最終的な購買決定を後押しする」役割を担います。そのため、短期的な売上向上や客単価の引き上げに加え、新規顧客の獲得やリピート購買の促進といった点で効果が期待できる施策です。
加えて、設計次第ではブランディングへの寄与も見込めます。たとえばオリジナルグッズを景品とすることで、ブランドやサービスの世界観を体験させ、理解や好意形成を促すといった活用方法も多く見られます。
Q. どの購買証明を選ぶべきですか?
購買証明の選択は、ターゲット層・予算・キャンペーン規模によって適切な手法が異なります。
たとえば、若年層をターゲットとする場合は、スマートフォンで簡単に応募できる「レシート応募」や「二次元コード」が適しています。一方で、リピート購入を促進したい場合には、集める楽しさを提供できる「応募シール」が有効です。また、不正防止を重視する場合は、一意のコードを発行できる「シリアルナンバー」を用いた仕組みが適しています。
ただし、予算面や購買データ連携に伴う技術的制約といった課題から、「レシート応募」が最も多く採用されているのが実態です。
Q. 景品表示法(景表法)で注意すべき点は何ですか?
マストバイキャンペーンは、景品表示法の「一般懸賞」または「共同懸賞」に該当します。一般懸賞の場合、景品額の上限は取引価額が5,000円未満なら取引価額の20倍まで、5,000円以上なら10万円までです。また、景品総額は売上予定総額の2%以内とされています。
共同懸賞の場合、最高額は30万円まで、総額は売上予定総額の3%以内です。詳しくは以下の記事をご覧ください。
Q. 購買判定を効率化する方法はありますか?
購買判定システムの活用がおすすめです。レシート画像やシリアルコードを自動判定できるため、目視確認の手間やヒューマンエラーのリスクを大幅に削減できます。特に、応募数が多いキャンペーンや全国規模のキャンペーンでは、購買判定システムの導入が効果的です。
ギフティの「MustBuy(購買判定システム)」では、OCR(光学文字認識)を活用した判定機能により、購買証明からギフト付与までをデジタルで一気通貫できます。
MustBuy(購買判定システム)について詳しくお知りになりたい方は以下をご覧ください。
Q. おすすめのキャンペーン景品は何ですか?
全国規模でキャンペーンを実施する場合は、地域を問わず利用できるデジタルギフトを景品に選ぶのがおすすめです。特に、AmazonギフトカードやQUOカードPayは幅広い年齢層に利用されており、満足度の高い定番景品として多くのキャンペーンで採用されています。
デジタルギフトは、メールやSNSで即時に配布できるため、在庫管理や発送作業が不要です。その結果、運用負荷を抑えつつ、スピーディにキャンペーンを展開できる点も大きなメリットです。
一方で実務的な視点では、金券系の景品は応募率が高くなりやすい反面、ブランドによっては金券が「ばらまき施策」と受け取られ、ブランドイメージの毀損につながることを懸念する担当者が多いのも事実です。
そこでおすすめなのが、複数の景品を組み合わせた設計です。
たとえば
上位景品:体験型ギフトで上質な時間を提供する、QOLを高める家電など、ブランドやサービスのメッセージと親和性の高い景品
その他の景品:日常使いしやすく利便性の高い、500円程度のデジタルギフトを用意。これにより、応募のハードルを下げる
といった構成にすることで、ブランド訴求と応募数の最大化を両立しやすくなります。
なお、giftee for Businessではデジタルギフトに加え、家電なども選べるカタログギフトも提供しています。景品設計の幅を広げたい場合は、ぜひご検討ください。
まとめ
本記事では、マストバイキャンペーンの概要や効果、実施方法について解説しました。
マストバイキャンペーンを成功させることで売上の向上が期待できますが、効果的に行うにはさまざまな工夫が必要です。応募手続きを簡略化したり、ゲーム要素を取り入れたりなど、消費者が応募しやすい環境を整えましょう。
また、マストバイキャンペーンを効率的に実施したいのであれば、最も手間のかかる「購買判定」をシステム化することをおすすめします。また、景品をオンラインで贈れるギフトの「デジタルギフト」を選ぶことで、当選者にメールやSNSなどを通じて配布ができ、結果、梱包や発送、在庫管理の手間がなく、キャンペーンの実施をより一層効率化できます。受け取り手が好きなギフトを選べる仕組みもあるため、満足度も高くなるでしょう。
マストバイキャンペーンを成功させたい企業は、購買判定システムとデジタルギフトの組み合わせをぜひご検討ください。
マストバイキャンペーンの設計でお困りのご担当者様へ
こんなお悩みはありませんか? ・マストバイキャンペーンを実施したいが、効果的な設計方法が分からない ・ターゲット設定やKPI設計など、キャンペーン設計の考え方が分からない ・効果的なギフト選定のコツを知りたい
購買情報をもとに参加条件を判定するマストバイキャンペーンでは、レシートの扱い方、不正防止、景品の設計など“マストバイ特有の要素”を押さえることが成功の鍵になります。
そこで累計導入件数7万件以上、法人向けデジタルギフト導入実績No.1のgiftee for Businessでは、購買証明の判定から抽選・ギフト付与までを自動化できる「Mustbuy(購買判定システム)」を提供しています。
さらに、同ソリューションの機能の紹介に加え、レシート解析によるリアルタイム判定の仕組み、不正応募を防ぐチェックロジック、継続購買を促すポイント設計など、マストバイ施策に必要なポイントを整理した資料もご用意しました。
マストバイキャンペーンをより効果的に実施したい方におすすめの資料です。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。