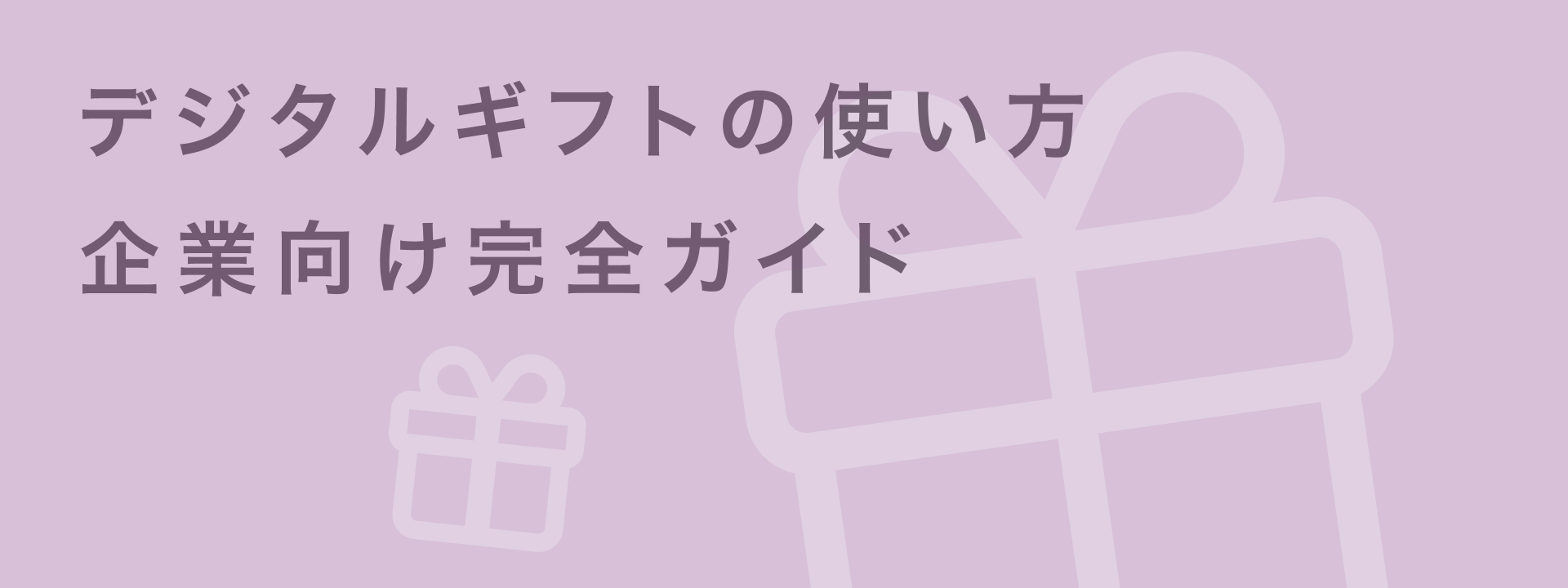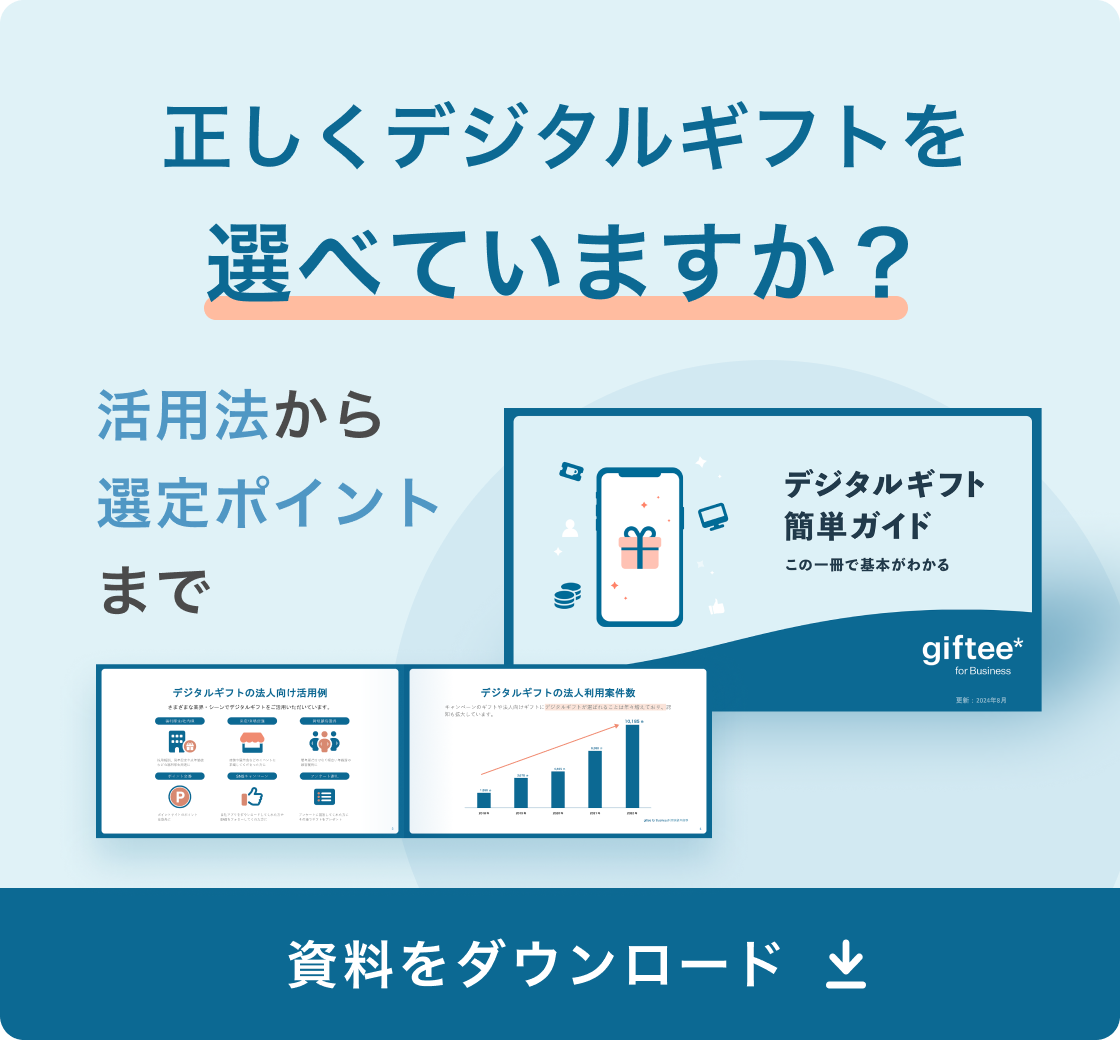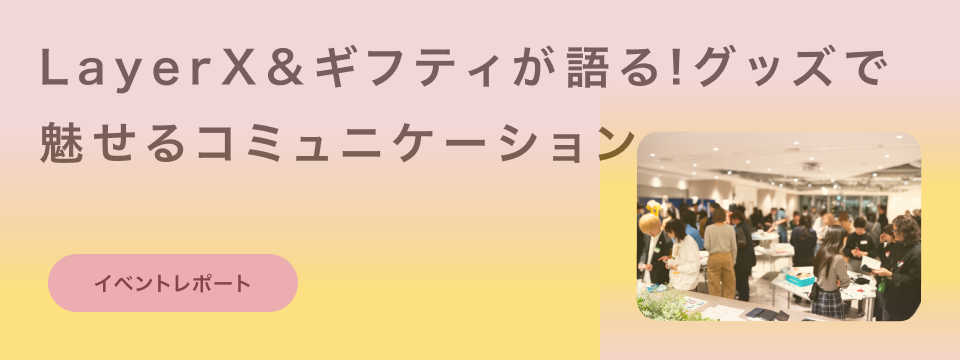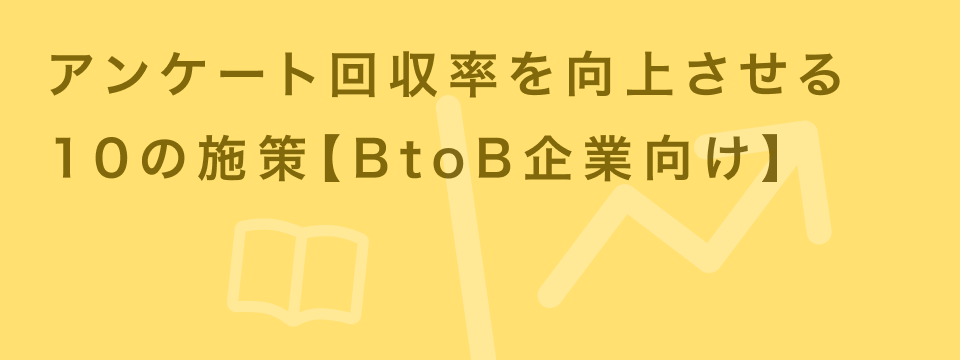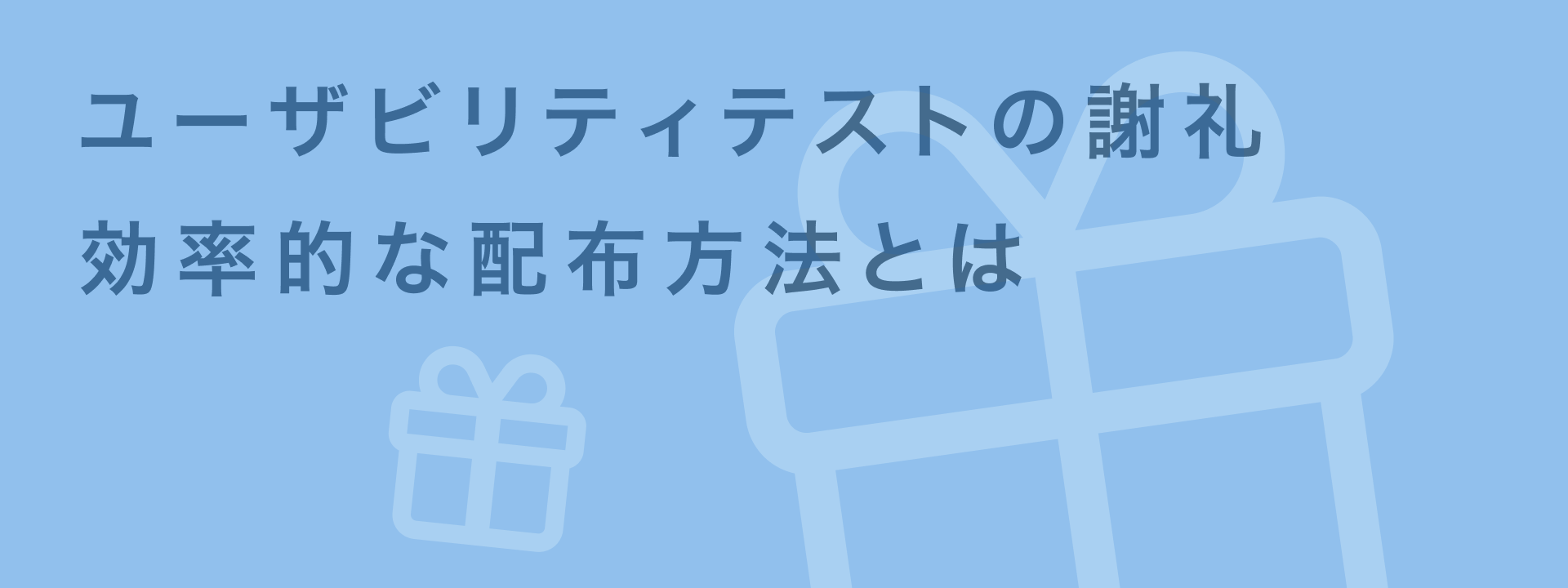デジタルギフトの種類、完全ガイド|BtoB企業が知っておくと良い「商品交換型」と「ポイント型」の違い
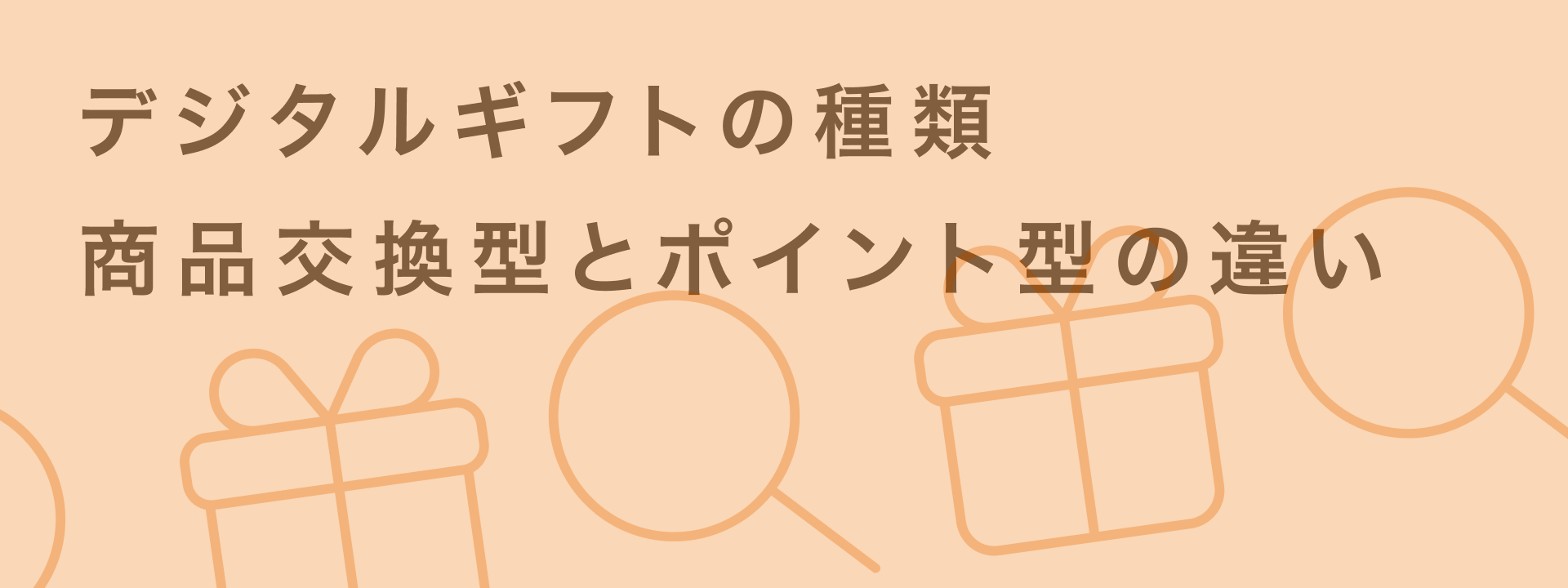
デジタルギフトの導入を検討する際に、最初に多くの担当者が直面するのが「種類が多すぎて、何を選べばよいのかわからない」という壁です。
まず、デジタルギフトは大きく分けて「商品交換型」と「ポイント型」の2種類があり、それぞれに異なる特徴と適した活用シーンがあります。この違いを理解することで、目的に合わせたギフトを効率的に選択できるようになります。
本記事では、デジタルギフトの2つの基本タイプとその特徴を整理した上で、BtoB領域で活用する際の選び方や判断基準を解説します。自社の課題や目的に合わせて、最適なデジタルギフトを見極めるためのヒントとして、ぜひご活用ください。
デジタルギフト導入で迷ったら、実績No.1の「giftee for Business」で
「giftee for Business」は、導入実績60,000件超(2025年6月時点)のデジタルギフトのサービスです。幅広い価格帯のギフトを取りそろえ、SNSキャンペーンや来店促進の景品、福利厚生など、幅広い法人利用シーンに対応しています。
▼こんなお悩みはありませんか? ・ユーザーを惹きつけるギフトの選び方が分からない ・キャンペーンを実施したいが、ギフトの手配や抽選業務の負荷が高い ・応募数の予測が難しく、在庫管理や余剰在庫処理に手間がかかる
これらの課題を解決できるのが「giftee for Business」です。170以上のブランド・約1,000種類のデジタルギフトに加え、抽選〜ギフト付与までをワンストップで支援する各種ツールも提供しています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
デジタルギフトの2つの基本タイプ
デジタルギフトは、大きく分けて以下の2つのタイプに分類されます。
商品交換型
ポイント型
どちらのタイプも、従来の物理ギフトに比べて配送費・在庫管理・人件費といったコスト削減が可能であり、即時配布できるという大きなメリットがあります。
それぞれの詳しい特徴や活用シーンについては、次の章で5つの種類に分けて解説します。
デジタルギフトの種類
デジタルギフトは、前述の「商品交換型」と「ポイント型」という2つの基本タイプをさらに細分化すると、5つの種類に分類できます。
この章では、BtoB企業が知っておくべきデジタルギフトの種類を5つに分けて、それぞれの特徴と適した活用シーンを詳しく解説します。自社の目的や予算、ターゲット層に合わせて最適な種類を選ぶための参考にしてください。
1. 各種ギフト券
各種ギフト券は、オンラインストアやアプリストアで利用できるお買い物券です。受け取った人が自由に商品やサービスを選べる高い汎用性が最大の魅力です。
Amazonギフトカード
Amazonギフトカードは、Amazon.co.jpで数億点以上の商品購入に利用できるデジタルギフトです。日用品から家電、書籍、食品まで幅広い商品を取り扱っているため、受け取る側の満足度が非常に高いのが特徴です。
主な特徴
- 数億点以上の商品から自由に選択可能
- 有効期限が10年と長く、使い忘れのリスクが低い
- 1円単位で金額設定が可能
- オンラインショッピングの利用頻度が高い層に最適
Google Play ギフトカード
Google Play ギフトカードは、Google Playストアでアプリ、ゲーム、映画、書籍などのデジタルコンテンツの購入に利用できます。スマートフォンユーザー、特にAndroidユーザーに人気のデジタルギフトです。
主な特徴
- アプリ、ゲーム、映画、音楽、書籍など幅広いコンテンツに対応
- Androidユーザーにとって利便性が高い
- デジタルコンテンツ好きな層に訴求力が高い
Apple Gift Card
Apple Gift Cardは、App Store、Apple Music、Apple TV+、iCloudストレージなど、Apple製品やサービス全般で利用できるデジタルギフトです。iPhoneやiPadユーザーにとって非常に利便性が高いのが特徴です。
主な特徴
- Apple製品・サービス全般で利用可能
- iOSユーザーにとって使い勝手が良い
- アプリ、音楽、映画、ストレージなど多様な用途
2. 各種ポイント・電子マネー
各種ポイント・電子マネーは、特定の店舗やサービス内で使えるポイントです。ユーザーが普段から使い慣れたポイントであれば、使用率が高く、無駄になりにくいのが特徴です。
PayPayポイント
PayPayポイントは、約1,000万か所超のお店やスポット(※)で利用できるデジタルポイントです。実店舗での利用が中心で、日常的な買い物で使いやすいのが特徴です。
主な特徴
- 約1,000万か所超の豊富なネットワーク
- 二次元コード決済の手軽さでユーザビリティが高い
- 少額決済から高額決済まで柔軟に対応
- 1円単位で金額設定が可能
楽天ポイント
楽天ポイントは、楽天市場をはじめ、楽天トラベル、楽天ブックス、楽天モバイルなど楽天グループの多様なサービスで利用できます。各種楽天サービスの利用頻度が高いユーザー層に特に人気です。
主な特徴
- 楽天グループの多様なサービスで横断的に利用可能
- 楽天ポイント制度との相乗効果で額面以上の価値を提供
- オンライン・オフライン両方で利用可能
dポイント
dポイントは、NTTドコモが提供するポイントサービスで、コンビニ、ドラッグストア、飲食店など全国の加盟店で利用できます。ドコモユーザー以外でも利用可能で、幅広い層に訴求できます。
主な特徴
- 全国の加盟店で利用可能
- ドコモユーザー以外でも利用できる汎用性
- 日常的な買い物で使いやすい
Pontaポイント
Pontaポイントは、ローソン、ゲオ、ホットペッパーなど多様な加盟店で利用できるポイントサービスです。コンビニでの利用頻度が高いのが特徴です。
主な特徴
- ローソンなどコンビニでの利用頻度が高い
- 多様な加盟店で利用可能
- 日常的な買い物で使いやすい
3. 商品交換型デジタルギフト
商品交換型デジタルギフトは、特定の商品やサービスと直接交換できるタイプです。贈るアイテムが明確で、受け取る側がすぐに利用できるのが特徴です。
カフェ・ドリンク系ギフト
カフェチェーンで利用できるドリンクチケットです。日常的に利用しやすく、手軽に喜ばれるのが特徴です。
主な特徴
- 全国のカフェチェーンで利用可能
- 少額(300円〜500円程度)から贈れる
- 日常的に利用しやすい
コンビニ・ファストフード系ギフト
ローソン、ファミリーマート、マクドナルド、サーティワンなどで利用できるギフトです。全国どこでも利用できる利便性の高さが魅力です。
主な特徴
- 全国のコンビニ・ファストフード店で利用可能
- 少額から贈れる
- 幅広い年齢層に喜ばれる
体験型ギフト
映画鑑賞券、温泉・スパ利用券、レストラン食事券など、特別な体験を提供するギフトです。特別感があり、記憶に残りやすいのが特徴です。
主な特徴
- 特別な体験を提供できる
- 記憶に残りやすく、ブランドイメージ向上に貢献
- 高額のインセンティブに適している
4. デジタルコンテンツ
デジタルコンテンツは、電子書籍、映画、音楽などのデジタル形式のコンテンツをプレゼントするギフトです。配送が不要で、即座に利用できるのが特徴です。
電子書籍
Kindle、楽天Kobo、BookLiveなどの電子書籍サービスで利用できるギフトです。読書好きな層に特に喜ばれるのが特徴です。
主な特徴
- 即座にダウンロードして読める
- 物理的な配送が不要
- 読書好きな層に訴求力が高い
映画・動画配信サービス
Netflix、Amazon Prime Video、U-NEXTなどの動画配信サービスで利用できるギフトです。エンターテインメント好きな層に人気です。
主な特徴
- 映画・ドラマ・アニメなど多様なコンテンツを楽しめる
- 自宅で気軽に利用できる
- エンターテインメント好きな層に訴求力が高い
音楽配信サービス
Spotify、Apple Music、LINE MUSICなどの音楽配信サービスで利用できるギフトです。音楽好きな層に特に喜ばれるのが特徴です。
主な特徴
- 数千万曲以上の音楽を楽しめる
- 通勤・通学時間に利用しやすい
- 音楽好きな層に訴求力が高い
5. 配送型デジタルギフト
配送型デジタルギフトは、オンラインで選んだ商品を、受け取る人が住所を入力することで実際に配送されるギフトです。デジタルの利便性と物理的なギフトの特別感を両立できるのが特徴です。
主な特徴
- オンラインで選択、物理的に配送される
- 住所を知らなくても贈れる
- 食品、雑貨、コスメなど多様な商品を選べる
シーン別|おすすめデジタルギフトの種類
ここまで紹介してきたデジタルギフトの種類を、実際のビジネスシーンでどのように使い分けるべきかを解説します。
自社の目的や予算、ターゲット層に合わせて、最適なデジタルギフトの種類を選ぶ際の参考にしてください。
キャンペーン・プロモーション向け
SNSキャンペーンや来店促進キャンペーンなど、不特定多数のユーザーに向けたプロモーション施策では、幅広い層に喜ばれる汎用性の高いギフトが適しています。
おすすめの種類
各種ギフト券
各種ポイント・電子マネー
商品交換型デジタルギフト
アンケート謝礼向け
アンケート調査の回答謝礼では、回答者の負担に見合った適切な金額設定と、受け取りやすさが重要です。
おすすめの種類
各種ギフト券
各種ポイント・電子マネー
商品交換型デジタルギフト
従業員向けインセンティブ
従業員向けのインセンティブでは、モチベーション向上につながる特別感と、実用性の高さが求められます。
おすすめの種類
各種ギフト券
体験型ギフト
配送型デジタルギフト
顧客ロイヤルティプログラム向け
既存顧客の継続利用を促進するロイヤルティプログラムでは、継続的に利用できる仕組みと、段階的な報酬設計が重要です。
おすすめの種類
各種ポイント・電子マネー
各種ギフト券
体験型ギフト
デジタルギフト選定の3つの重要ポイント
デジタルギフトを導入する際には、実際に運用を始めたあとの流れも視野に入れておく必要があります。
想定外のトラブルが発生しないよう、コスト効率性・運用のしやすさ・受け取る側の満足度の3つをバランスよく検討することが大切です。
この3つは相互に影響し合うため、どれか1つに偏ると、別の要素に支障が出る可能性もあります。デジタルギフトをインセンティブとして選ぶ際には、全体のバランスを意識して判断しましょう。
1. コスト効率性
コスト効率を見極めるには、ギフト単価だけでなく「導入費用・運用コスト・ROI(投資収益率)」まで含めて考える必要があります。
導入費用
初期設定費用やシステム連携費用、管理画面の利用料などがかかる場合があります。多くのサービスでは、ギフトのみの納品であれば月額固定費が不要なことも多いですが、キャンペーンシステムなども併用する場合は追加費用が発生することがあります。
また、既存のCRMやマーケティングツールと連携する場合は、技術対応費用の確認も必要です。
運用コスト
物理的なギフトと異なり、配送費・在庫管理費・人件費などは大幅に削減できます。ただし、配布や管理のための人的コストはゼロにはなりません。
とはいえ、URL送付で完結できる場合は、作業工数を大幅に減らせるため、中長期的な効率向上につながります。
ROI(投資収益率)
ROI(投資収益率)を把握するには、かけたコストに対してどれだけの成果が得られたかを数値で把握することが重要です。デジタルギフトでは、顧客獲得コスト(CPA)の改善、リピート率やブランド認知度、従業員満足度の向上など、効果が数字で可視化しやすいのが特徴です。
特に、従来の物理的ギフトに比べると配送コストを大幅に抑えられるためコスト効率が向上します。さらに、即時性による参加率の向上も加われば、より高いROIを実現できる可能性があります。
2. 運用のしやすさ
実際に業務で扱う担当者にとって、操作しやすいかどうかは日々の効率に直結します。導入前に、使いやすさにも着目しておくと安心です。
管理機能
たとえば、配布状況や未使用ギフトの確認、有効期限の管理などを一括で行えるダッシュボードが用意されているかを確認してください。なぜなら、リアルタイムで使用状況を把握できる管理画面があれば、効果測定や次回施策の改善にも活用できるからです。
また、CSV一括ダウンロードやメール・SMS配信機能があると、大量配布時にもスムーズに対応できます。
配布方法
メール、二次元コード、SMSなど、複数の配布手段が用意されているのが理想的です。個人情報を取得せずに配布できる二次元コードやURLの付与は、プライバシー保護の面でも安心で、BtoB施策に向いています。 アプリのインストールや会員登録なしで、届いたURLを開くだけでギフトを受け取れる仕組みは、受け取る側にとってもストレスが少なく、高い満足度につながります。
レポート機能の有無
配布数・使用率・使用タイミングといった基本情報に加え、受け取った人の行動や効果測定に役立つ詳細レポートが備わっているかも重要です。これにより、施策の成果を数字で把握し、ROIの算出や次回施策の改善点を明確化できます。
レポート機能を活用することで、継続的な運用の質を高められます。
3. 受け取る側の満足度
最終的にデジタルギフトの良し悪しを決めるのは、受け取った人が「もらってよかった」と感じるかどうかで決まります。満足度は、導入の成果を大きく左右する要素です。
交換先の豊富さ
日常的に利用しやすいECサイト、カフェ、ドラッグストア、ファストフードなどが揃っているかを確認しましょう。Amazon や各種コンビニ、有名カフェチェーンなど、全国で利用できる選択肢が多いほど喜ばれます。
利便性
ギフトの受け取りから利用まで何ステップ必要か、スマートフォンでの操作のしやすさ、有効期限の長さ(例:90日以上)など、受け取った人が「便利である」と感じられることも重要です。
年齢層やデジタル機器の扱いやすさを考慮し、できるだけシンプルに使えるものを選ぶことで、利用率と満足度の両方を高められます。
なお、デジタルギフトの納品までのステップなどについては、こちらの記事で詳しく解説しています。興味のある方はぜひご覧ください。
デジタルギフトの効果を最大化した企業・自治体の事例
本章では、商品交換型(giftee Box)とポイント型(えらべるPay)を活用してデジタルギフト施策を成功させた企業様の事例をご紹介します。
組合員アンケートで回答数目標110%を達成
企業/ブランド名 | ニトリ労働組合 |
|---|---|
目的 | 組合員への働き方アンケートにおける回答率向上 |
成果 | 目標(回答数1万件)に対し約1万1,000件を回収(110%達成) 1,000種類以上から選べる仕組みが高評価 Auth(認証配布システム)により重複付与を防止し効率的な運用を実現 |
ニトリ労働組合様では毎年、組合員を対象に働き方に関するアンケートを実施されています。賃金や職場環境に対する満足度を調査することで、働き方の改善を目指すものです。
今回、アンケートの回答率を上げるために、giftee Box 500円分をインセンティブとして活用されました。1,000種類以上のデジタルギフトから組合員が自由に選べる仕組みが功を奏し、結果として目標を10%上回る約1万1,000件の回答を獲得しました。
また、Auth(認証配布システム)を活用することで、従業員番号による個別管理を実現。重複付与を防ぎながら、効率的なオペレーションを実現されました。
▼この事例の詳細はこちら
ポイントサイトの交換商品拡充で利便性向上を実現
企業/ブランド名 | 株式会社インテージ |
|---|---|
目的 | ポイントサイトの交換商品拡充による顧客満足度向上と若年層の獲得 |
成果 | 低ポイント保有者、または既存交換商品を利用できない環境にいる会員に対して交換できる商品を拡充 giftee Boxを交換先に加えることで、複数種類の交換先を一気に増やすことが可能に |
株式会社インテージ様が運営するアンケートサイト『キューモニター』では、アンケート会員が回答して貯めたポイントの交換先としてgiftee Boxを導入されました。
ポイントサイトにおける課題の一つに、低ポイント保有者が交換できる商品がなく、ポイントが退蔵してしまうということがあります。giftee Boxを交換先に設定することで、1つの交換先を通じて1,000種類以上の商品を受け取れることになり、実質的に複数種類の交換先を一気に増やすことが可能になりました。
また、giftee APIを活用することで、開発工数を最小限に抑えられました。
▼この事例の詳細はこちら
デジタル化促進施策で1万5,000人超の市民が事業に参加
企業/ブランド名 | 静岡県焼津市 |
|---|---|
目的 | デジタルサービス利用促進による市民生活の質向上 |
成果 | 1万5,000人超の市民が参加 えらべるPayの多様な交換先が「今の時代に合っている」と好評 地域経済の消費活性化にも貢献 |
静岡県焼津市様は2023年10〜11月の期間中、「デジタルLifeサポート事業」を実施されました。xID(クロスアイディ)アプリにアカウントを登録の上、アプリ内に届いたデジタル通知から電子申請すると、先着2万名に3,000円分の「えらべるPay」が付与されるという施策です。
えらべるPayは、受け取った方がAmazonギフトカードや楽天ポイント、PayPayポイントなど、複数の人気サービスの中から自由に選んで使えるデジタルギフトです。「えらべるPay」のギフトとしての利便性も後押しとなり、最終的には1万5,000人を超える市民の方々にご参加いただきました。その結果、デジタル化の促進と地域経済の消費活性化を同時に実現することができたとのことです。
▼この事例の詳細はこちら
よくある質問(FAQ)
Q1: デジタルギフトの種類はどれくらいありますか?
デジタルギフトは大きく分けて「商品交換型」と「ポイント型」の2つの基本タイプがあり、さらに細かく分類すると以下の5種類に分けられます。
- 各種ギフト券
- 各種ポイント・電子マネー
- 商品交換型デジタルギフト
- デジタルコンテンツ
- 配送型デジタルギフト
それぞれに特徴と適した活用シーンがあるため、自社の目的や予算、ターゲット層に合わせて選ぶことが重要です。
Q2: 商品交換型とポイント型、どちらを選ぶべきですか?
商品交換型とポイント型の選択は、以下の基準で判断すると良いでしょう。
商品交換型が適しているケース
- 贈るアイテムを明確にしたい場合
- 受け取る側の好みやニーズを把握している場合
- ブランドイメージを重視したい場合
ポイント型が適しているケース
- 受け取る側に自由に選んでもらいたい場合
- 幅広い年齢層や嗜好の人に贈る場合
- 高い汎用性を重視したい場合
迷った場合は、Amazonギフトカードや楽天ギフトカードなど、選択肢が豊富なポイント型を選ぶと、受け取る側の満足度が高くなる傾向があります。
まとめ|この記事で伝えたかったこと
デジタルギフトの導入を検討するBtoB企業にとって重要なのは、まず基本となる2つのタイプの違いを理解することです。
商品交換型は、あらかじめ用意された商品との交換できる形式です。一方で、ポイント型は幅広い用途に対応できる柔軟さがあり、自由度の高い使い方が可能です。
どちらも従来の物理的ギフトと比べて、コスト削減や業務効率化が期待できますが、活用する場面や、受け取る側が体験する価値には大きな違いがあります。
効果的に導入するためには、次の3つの観点から総合的に判断することが欠かせません。
コスト効率性(導入費用・運用コスト・ROI)
運用の簡便性(管理機能・配布方法・レポート)
受け取り側の満足度(交換先の豊富さ・利便性)
これらの要素を、自社の課題や目的と照らし合わせながら検討することで、最適なデジタルギフトの種類の選定につながります。
ぜひ本記事の内容を、デジタルギフトの導入計画にお役立てください。
デジタルギフト導入で迷ったら、実績No.1の「giftee for Business」で
「giftee for Business」は、導入実績60,000件超(2025年6月時点)のデジタルギフトのサービスです。幅広い価格帯のギフトを取りそろえ、SNSキャンペーンや来店促進の景品、福利厚生など、幅広い法人利用シーンに対応しています。
▼こんなお悩みはありませんか? ・ユーザーを惹きつけるギフトの選び方が分からない ・キャンペーンを実施したいが、ギフトの手配や抽選業務の負荷が高い ・応募数の予測が難しく、在庫管理や余剰在庫処理に手間がかかる
これらの課題を解決できるのが「giftee for Business」です。170以上のブランド・約1,000種類のデジタルギフトに加え、抽選〜ギフト付与までをワンストップで支援する各種ツールも提供しています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。