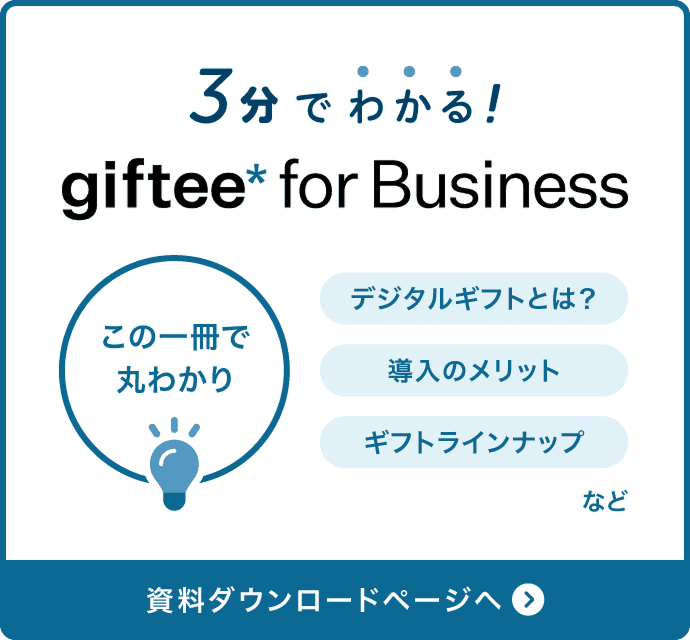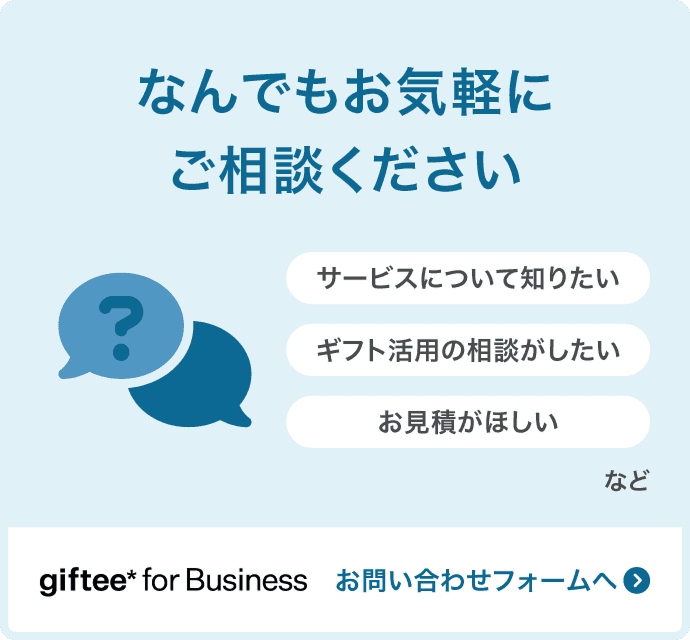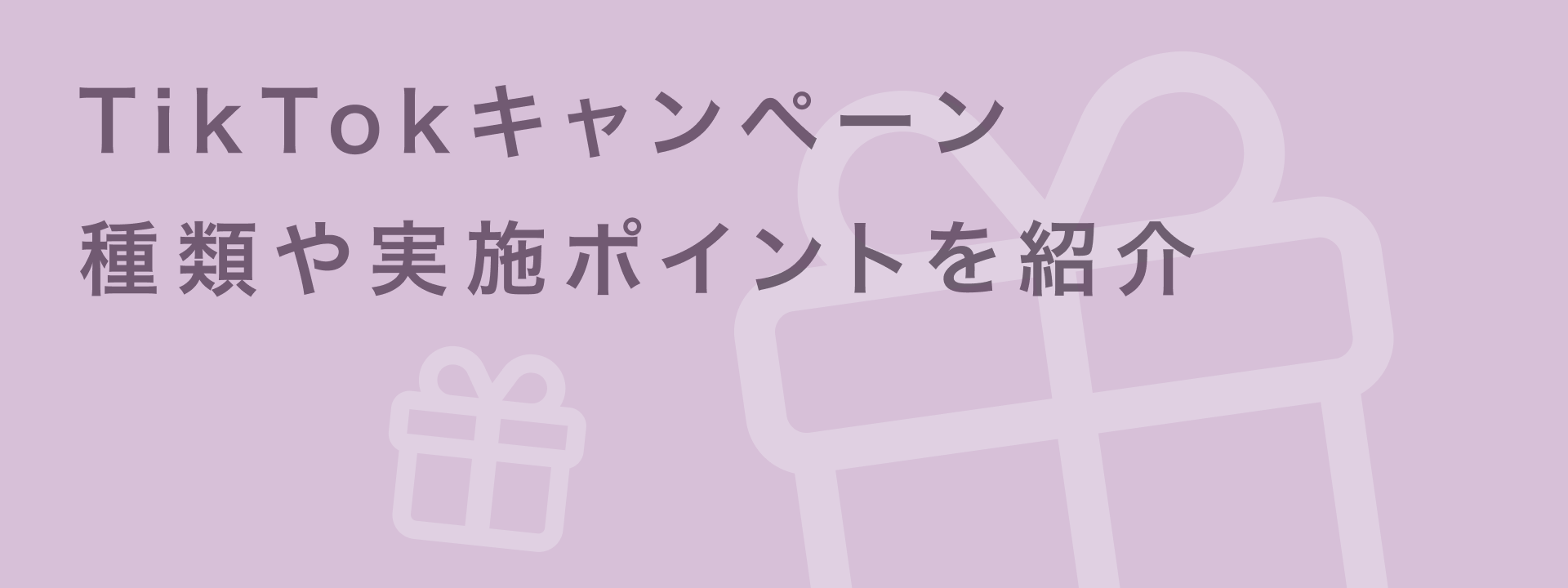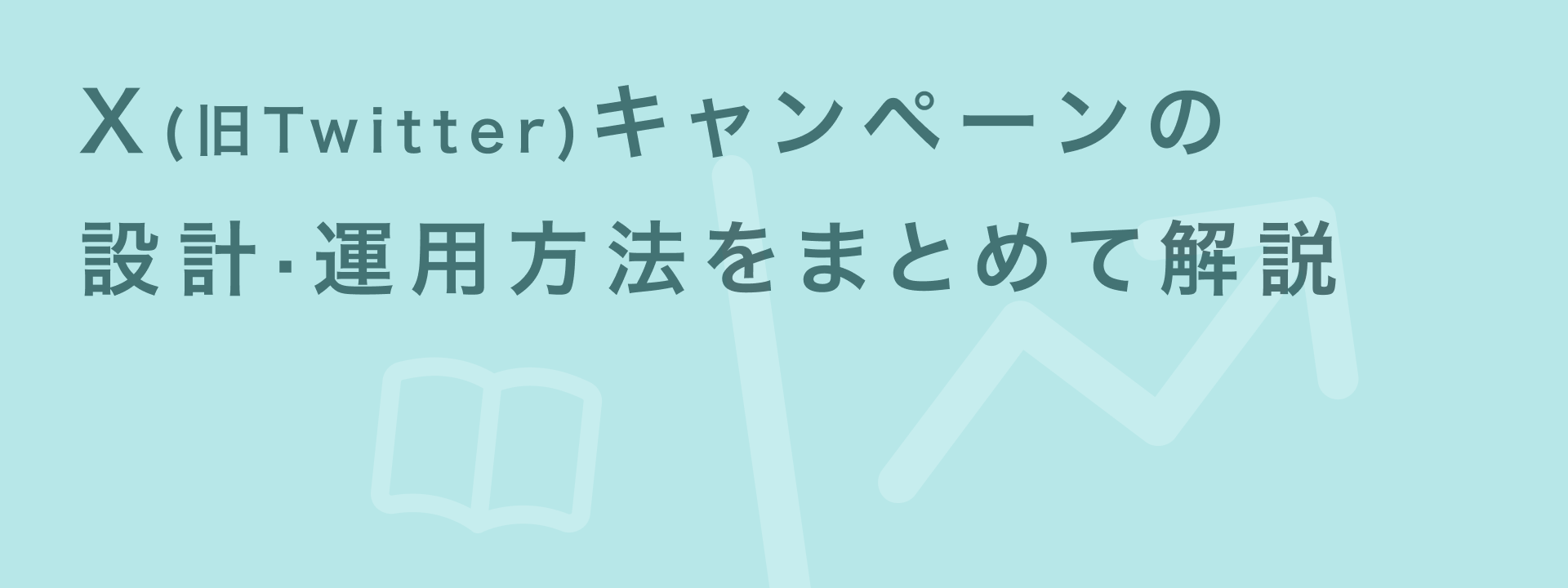QUOカードPayとは?法人活用のメリット・購入方法・導入事例を徹底解説
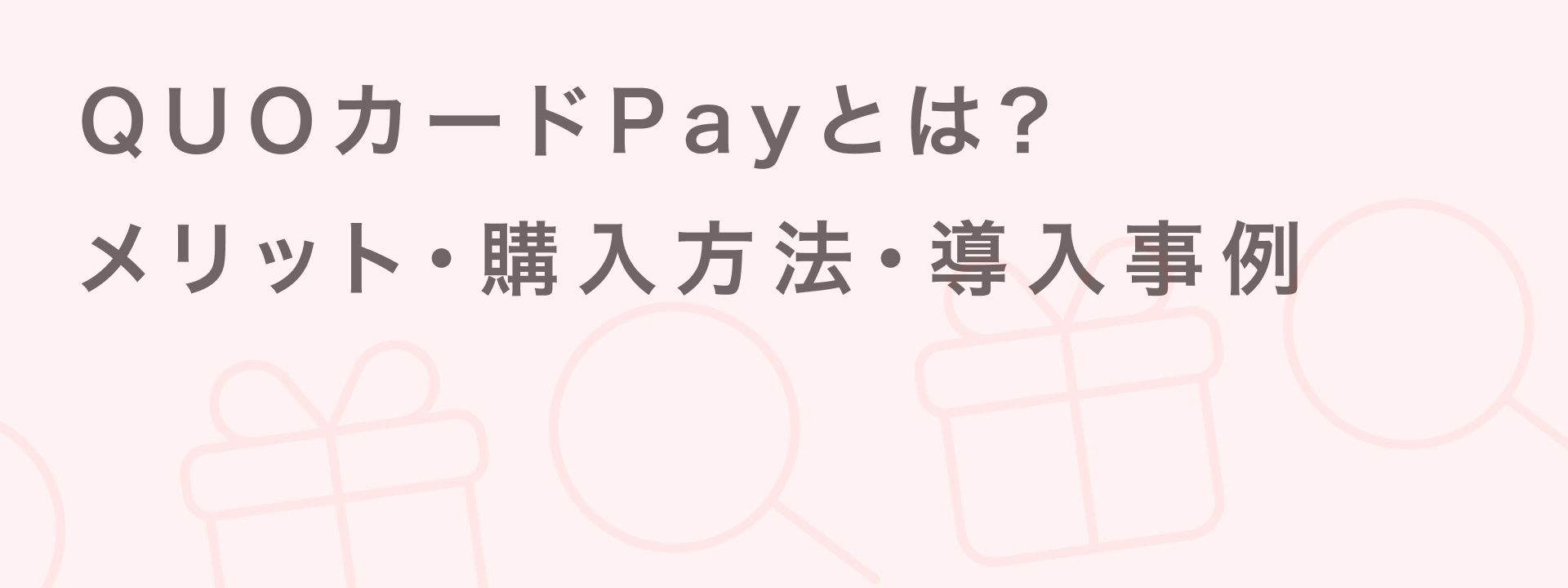
キャンペーンのインセンティブとしてよく使われるQUOカード。一般的によく知られているのは物理のカードであり、それだと現物を渡す必要があり、発送の手間や在庫管理が課題になることもありました。
一方で、QUOカードPayはスマートフォンさえあればすぐに使えるデジタルギフトです。郵送不要でスピーディーに配布できるため、キャンペーンやインセンティブ施策に適しています。もちろん、全国のQUOカードPay加盟店で使える利便性も魅力です。
この記事では、QUOカードPayの基本情報から具体的な使い方まで、個人・法人問わず活用しやすいポイントをわかりやすくご紹介します。さらに、他のデジタルギフトとの比較や、実際に企業や自治体で導入されている事例も取り上げ、導入判断のヒントとしてご活用いただける内容です。
QUOカードPayをインセンティブとしてご検討中の方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
QUOカードPayの活用でお困りのご担当者様へ
このようなお悩みをお持ちではありませんか? ・QUOカードPayで本当に喜ばれるのか不安がある ・他社のキャンペーンでも使われていて、もう少し差別化したい
こうした課題を解決するのが「giftee Box」です。
giftee Boxは、累計導入件数7万件以上、法人向けデジタルギフト導入実績No.1のgiftee for Businessが提供する、QUOカードPay含む1,000種類以上のラインナップの中から受け取った方が自由に選べるデジタルギフトです。
ギフトURLをメールやSNSで送るだけなので配布も簡単。受け取る側は自分の好みに合わせて商品を選べるため、満足度の高いインセンティブ施策を実現できます。
現在「giftee Box」の紹介資料をご用意しています。本資料では、giftee Boxをキャンペーン用途に合わせてどのように活用し、スムーズに配布・管理するか、その考え方や運用のポイントを詳しく解説しています。無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
QUOカードPayとは?
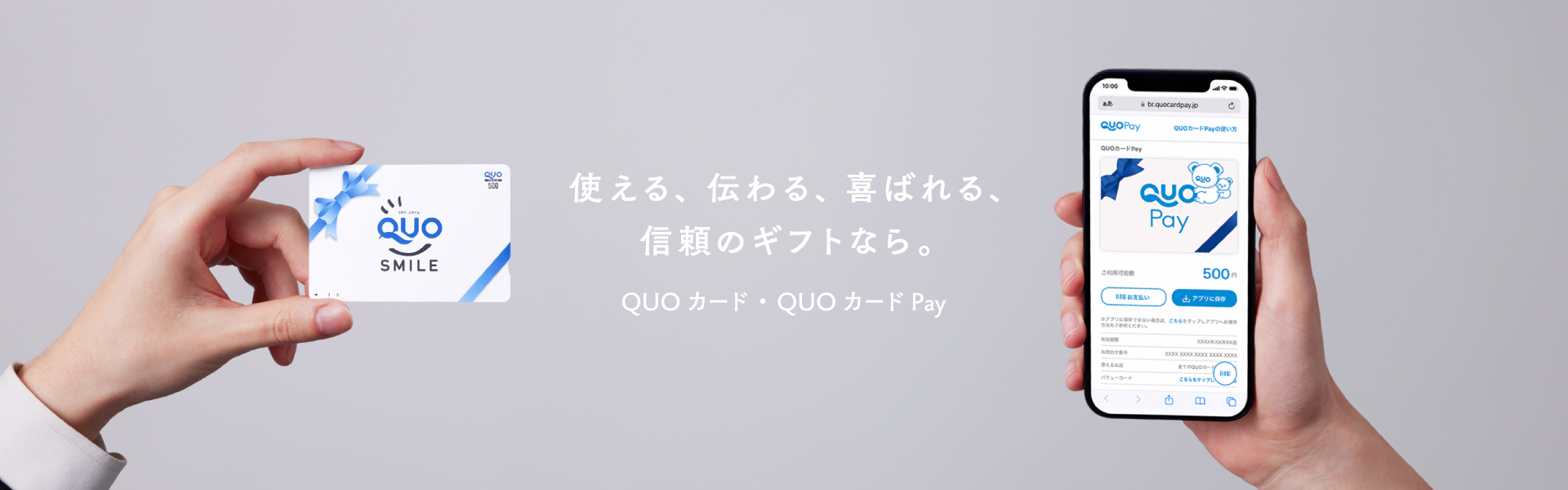
※引用:QUOカード公式
QUOカードPayは、株式会社クオカードが提供しているデジタル形式のギフトです。従来のプラスチック製のQUOカードとは違い、スマートフォンで使えるキャッシュレス決済型のプリペイドサービスとして設計されています。
ただし、QUOカードとQUOカードPayの使えるお店は異なっており、たとえばコンビニエンスストアでも次のように異なります。
QUOカードが利用できるコンビニエンスストア | QUOカードPayが利用できるコンビニエンスストア |
|---|---|
セイコーマート セブン‐イレブン※一部店舗除く タイエー デイリーヤマザキ※一部店舗を除く ハセガワストア ハマナスクラブ ファミリーマート※一部店舗を除く ポプラ/生活彩家/くらしハウス/スリーエイト もより市※一部店舗を除く リーベンハウス※一部店舗を除く ローソン | キヨスク※一部店舗のみ セイコーマート セブン‐イレブン タイエー デイリーヤマザキ※一部店舗を除く ナチュラルローソン ハセガワストア ハマナスクラブ ミニストップ もより市 リーベンハウス※一部店舗を除く ローソン ローソンストア100 |
企業のキャンペーン景品や福利厚生、自治体の給付事業など、法人の幅広いシーンでも活用が進んでいます。QUOカードPayはカードの印刷や郵送が不要で、すぐに渡せる手軽さも大きなメリットです。
仕組みは、贈る側が購入したデジタルギフトコードを、受け取る側に送信するだけ。受け取った人は、スマートフォンのアプリですぐに使えるようになります。さらに、金額を細かく設定できたり、オリジナルデザインを追加できたりと、柔軟なカスタマイズが可能なのもデジタルならではの魅力です。
QUOカードPayの使い道
QUOカードPayは、日々の生活でよく使うコンビニエンスストアでの買い物にとても便利です。セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンといった大手チェーンで利用できるため、食品や日用品の購入にぴったりです。
そのほかにも、ドラッグストアでの医薬品やコスメの購入、一部の飲食チェーンや書店、家電量販店など、利用できる店舗はどんどん広がっています。
ただし、すべての店舗で使えるわけではありません。QUOカードPayの公式サイトでは、最新の対応店舗が一覧で紹介されており、定期的に更新されています。
QUOカードPayの購入可能金額
QUOカードPayは、50円から最大10万円まで、1円単位で金額設定ができます。この柔軟さは、紙のQUOカードにはないデジタルならではの特徴です。公式サイトから購入すると、発行手数料が発行金額の6%上乗せされます。
※最小発注金額は1,000円です。
ちょっとしたお礼に使える少額から、特別な報奨にぴったりな高額まで、目的に応じた細かい調整が可能です。法人のキャンペーンなどでも、予算や配布対象に応じて最適な金額を設定できるので、使い勝手が非常に高いのもポイントです。
個人での利用でも、相手やシーンに合わせた金額設定がしやすいため、気軽な贈りものとしても活躍します。
QUOカードとQUOカードPayの違い
QUOカードPayの導入を検討する際、カードタイプのQUOカードとの違いを理解しておくことが重要です。以下の比較表で、主な違いをまとめました。
項目 | QUOカード(カードタイプ) | QUOカードPay(デジタルタイプ) |
|---|---|---|
形式 | プラスチックカード | デジタルコード(スマートフォンで利用) |
購入場所 | 公式オンラインストア、加盟店 | 公式オンラインストア、一部のデジタルギフトサービス |
配布方法 | 郵送・手渡し | URL送信(メール・SMS) |
配布スピード | 数日〜1週間 | 即時 |
有効期限 | なし(基本的に無期限) | あり(3年が一般的) |
残高確認 | カードの穴や使用時のレシートで確認 | スマートフォンで確認 |
在庫管理 | カードの保管 | ギフトコードの保管 |
発送コスト | あり(郵送料・梱包材) | なし |
このように、QUOカードPayはデジタルならではのスピード感と柔軟性を備えており、特に法人での大量配布やオンライン施策において大きなメリットを発揮します。一方、カードタイプのQUOカードは有効期限がなく、物理的な贈り物としての価値を重視する場合に適しています。
QUOカードPayの購入方法
QUOカードPayは、使う目的や規模に応じて、いくつかの購入方法が用意されています。個人で少額を贈りたいときと、企業で本格的に導入したいときとでは、購入手順が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
個人利用であれば、QUOカードの公式サイトから手軽に購入できます。希望の金額を入力してクレジットカードで決済すれば、すぐにデジタルギフトコードがメールで届きます。後はそのコードを相手に送るだけで、簡単にギフトとして贈ることができます。
法人でQUOカードPayの導入を検討している場合は、まず専用のオンラインストアでの会員登録からスタートします。これは初回購入時に必要な手続きで、紙タイプのQUOカードを過去に利用した企業であっても、QUOカードPay専用に再登録が必要です。
登録後は、オンラインストアから自由に額面・数量・デザインを指定して注文が可能です。
支払いは銀行振込またはクレジットカードに対応しており、決済完了後は最短当日でマイページにバリューコード(URL)が納品されます。その後は、このURLをメールなどで配布することで、受け取った方がQUOカードPayとして使用できる仕組みです。
問い合わせや営業担当を介さず、Web上でスムーズに完結できる点も、手軽に始めたい企業にとってのメリットです。
法人でのおすすめのQUOカードPay活用シーン
QUOカードPayは、手軽に贈れて柔軟に使える点から、法人においてもさまざまな場面で活用できるデジタルギフトです。業種や規模を問わず、目的に応じて幅広く対応できるのが大きな魅力です。
販促キャンペーンの景品やインセンティブに
販促キャンペーンの景品として、QUOカードPayはとても使い勝手の良いツールです。現物のギフトのような在庫を抱える必要がなく、発送コストもかからないため、運営の手間を減らしつつ効率的なキャンペーン展開が可能になります。
特にSNSキャンペーンとの相性は抜群です。たとえば、フォロー&リポストやハッシュタグ投稿キャンペーンの景品にすれば、参加のハードルが下がり、より多くの人にアプローチできます。デジタルであるからこそ、当選後すぐにギフトを配布でき、参加者の満足感も高められます。
また、アンケート回答やモニター参加の謝礼にもおすすめです。金額を自由に設定できるため、アンケートの内容や負担に応じて、ちょうどいい報酬を用意できます。これにより、参加率や継続率の向上も期待できるでしょう。
福利厚生や社内表彰に
社内の福利厚生やインセンティブにもQUOカードPayは便利です。たとえば、誕生日のお祝い、勤続年数に応じた記念品、成果を出した社員への報奨など、さまざまなシーンで活用できます。
テレワークが広がるなかで、直接の手渡しが難しいケースでも、デジタルギフトなら確実に従業員へ届けられます。全国に拠点がある企業でも、地域に関係なく同じサービスを提供できるのもメリットのひとつです。
社内イベントや研修・セミナーの参加特典、コンテストの賞品などとしても活用でき、従業員のモチベーション向上や社内のコミュニケーション促進にもつながります。年末年始のご挨拶や、チームでの目標達成時に贈るギフトとしても効果的です。
自治体の給付・助成・補助にも
QUOカードPayは、自治体による市民向けサービスでも広く使われています。子育て支援や高齢者支援、地域の活性化など、さまざまな目的での給付や助成に採用されており、その実績も年々増えています。
とくに新型コロナ対策として行われた経済支援では、非接触でスムーズに給付ができる手段として多くの自治体で導入されました。配布のスピードや安全性が高く、緊急時の対応策としても有効です。
また、地域イベントの参加者への記念品、住民アンケートの回答特典としても活用されており、市民の参加意欲や満足度を高めることに役立っています。デジタル化によって、給付事務の効率アップや透明性の向上にもつながる点は、行政側にとっても大きなメリットです。
BtoB営業・パートナーシップの強化に
QUOカードPayは、法人営業や取引先との関係づくりにも活躍します。たとえば、商談後のお礼や展示会でのノベルティ、セミナー参加者への特典など、さまざまなビジネスシーンで柔軟に活用できます。
とくにオンライン商談やウェビナーが定着している今、デジタルギフトを使ったコミュニケーションは新たな営業スタイルとして注目されています。商談後のフォローとして贈ることで、相手への印象アップや関係性の強化にもつながります。
また、パートナー企業とのつながりを深める場面でも効果的です。たとえば、プロジェクト終了時の感謝の気持ちとして、あるいは契約更新のタイミングでの記念品として活用することで、信頼関係の構築に役立ちます。贈る金額やタイミングも自由に調整できるので、相手企業との関係性やシーンに合わせた使い方がしやすいのもポイントです。
QUOカードPayを活用するメリット
QUOカードPayは、紙のギフト券では対応が難しかった「即時配布」や「オンライン完結」、「柔軟な金額設定」などを実現でき、法人利用においても大きなメリットがあります。
ここでは、企業でのキャンペーン施策や福利厚生にQUOカードPayを活用するメリットをご紹介します。
幅広い店舗で使いやすい
QUOカードPayの大きな魅力は、コンビニエンスストアをはじめとする多くのお店で使えることです。セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンなど、日常的に利用される主要コンビニチェーンで使えるため、受け取った人が迷わず使えて、喜ばれやすいギフトといえます。
実際に利用可能なコンビニエンスストアには、以下のような店舗があります。
セブン‐イレブン
ローソン
ローソンストア100
ナチュラルローソン
ミニストップ
デイリーヤマザキ ※一部店舗を除く
セイコーマート
タイエー
ハセガワストア
ハマナスクラブ
キヨスク ※一部店舗のみ
もより市
リーベンハウス ※一部店舗を除く
さらに、ドラッグストアや書店、一部の飲食店チェーンでも利用可能で、対応店舗は今も拡大中です。生活スタイルや好みに関わらず、誰にとっても実用性が高い点は、大きな強みです。
また、全国で使えるため、都市部と地方で利用格差が少なく、地域を問わず同じサービスを提供できるのもポイント。営業エリアが広い企業や、全国に拠点を持つ会社でも、統一感のあるギフト施策が展開できます。
柔軟な金額設定で予算調整しやすい
QUOカードPayは、50円から最大10万円まで、1円単位で自由に金額設定ができます。この自由度の高さは、キャンペーンの規模や目的に応じて細かく調整できる点で、大きなメリットです。
従来のギフトカードのように決まった金額から選ぶのではなく、配布対象や施策内容に応じて 最適な金額を設定できるため、コストの最適化にもつながります。
参加人数が多いキャンペーンでは少額設定に、成果を出した社員への報奨には高額設定にするなど、使い分けも簡単です。等級別インセンティブや、参加度に応じた段階的な報酬にも対応できるので、施策の幅がぐっと広がります。
オリジナルデザインでブランディングにも貢献
法人向けには、企業オリジナルのデザインや画像でQUOカードPayを作ることも可能です。会社のロゴやブランドカラーを使ったデザインで、ギフトそのものがブランディングの一部になります。

※引用:QUOカードPayとは?|QUOカード公式サイト
キャンペーンのテーマや季節感に合わせたデザインはもちろん、社内イベント用や周年記念向けの特別デザインなど、用途に応じて自由にカスタマイズできます。こうした演出は、受け取った相手の印象にも残りやすく、企業メッセージをしっかり届ける手段にもなります。
写真やイラスト、メッセージも入れられるので、ただの金券ではなく「想いを伝えるツール」として活用できるのがポイントです。
すぐに贈れるスピード感と効率性
QUOカードPayは、購入後すぐに贈れる手軽さも大きな魅力です。物理的なギフトと違い、印刷や配送の時間が不要なので、思い立ったらすぐに送ることができます。
このスピード感は、急なキャンペーン対応や、SNSでのリアルタイム施策において特に効果を発揮します。たとえば、その場で抽選してその場で贈るといった展開も可能なため、ユーザーの反応が冷めないうちに対応できます。
また、在庫管理や発送手配などの作業が不要になることで、運営側の負担も大幅に軽減されます。特に大規模な配布が必要なキャンペーンでは、こうした運用面の効率化がコスト削減につながり、戦略そのものにリソースを集中できる環境が整います。
QUOカードPayを活用する際の留意点
QUOカードPayは非常に便利なデジタルギフトですが、導入や活用を検討する際は、事前に留意しておくことも。あらかじめ想定されることを把握しておくことで、より効果的な活用が可能になります。
ギフトとしての“特別感”をどう演出するか
QUOカードPayはデジタル形式のギフトなので、手元に残る“モノ”としての存在感がありません。そのため、受け取った人に特別感や記憶に残る印象を与えるには、贈り方やデザインに一工夫加えることが大切です。
たとえば、重要な取引先へのお礼や、長年勤めた社員への記念品など、“特別感”が求められるシーンでは、デジタルギフトだけでは少し物足りなく感じられることもあります。そんな時は、オリジナルデザインの活用や、感謝のメッセージを添える工夫、他のギフトと組み合わせて贈るなどの対応が効果的です。
また、年齢層によっては「どうやって使うのかわからない」と感じる方もいるかもしれません。特にデジタルに不慣れな方には、わかりやすい使い方ガイドや問い合わせ先を用意しておくことで、安心して使ってもらえる環境が整います。対象となる相手の特性をしっかり理解したうえで、配布方法や内容を調整することが成功のポイントです。
利用できるお店に地域差があることも
QUOカードPayは、使えるお店が全国に広がっているとはいえ、地域によっては店舗数に差があることがあります。特に地方や郊外では、都市部に比べて対応店舗が少ないケースもあるため、注意が必要です。
全国規模のキャンペーンや、地方にも拠点を持つ企業が導入を検討する際は、事前に対象エリアでQUOカードPayがどの程度使えるかを確認しておくのがおすすめです。せっかく贈っても「近くで使えない」という状況になってしまっては、本来のギフト効果が半減してしまいます。
このようなリスクを避けるためには、QUOカード公式サイトで公開されている「利用可能店舗一覧」を活用し、エリアごとの対応状況をチェックしておくと安心です。また、必要に応じて他のギフト手段も検討するなど、地域性に合わせた柔軟な対応も視野に入れておきましょう。
法令や税務への配慮も忘れずに
QUOカードPayを法人で活用する場合、景品表示法などの法令にも注意が必要です。特にキャンペーンの景品として使用する際は、提供できる金額の上限やルールが定められているため、あらかじめ内容を把握し、ルールの範囲内で運用することが求められます。
業界によっては独自のガイドラインや自主規制が設けられているケースもあるので、自社が該当するかどうかを事前に確認しておくと安心です。
景品表示法(景表法)については、以下の記事で解説しています。違反のリスクなどにも触れているので、ぜひあわせてお読みください。
QUOカードPayと同時に検討したいデジタルギフトサービスの利用
QUOカードPayを導入する際には、他のデジタルギフトサービスとの比較もあわせて行うことで、より自社に合ったギフト施策を設計できます。目的やターゲットに応じて、複数のサービスを使い分けることで、より柔軟で効果的な活用が可能になります。
デジタルギフトの大きな魅力のひとつは、「もらう側が自分の好きな使い方を選べる」ことです。いくつかの選択肢を用意しておくことで、相手の好みやライフスタイルに合ったギフトとして機能し、満足度の高い贈り方が実現できます。
たとえば、オンラインショッピングに特化したサービス、デジタルコンテンツの購入に使えるもの、実店舗で利用できるタイプなど、それぞれ得意分野や利用シーンが異なります。こうした特性を活かして組み合わせることで、幅広いユーザー層にアプローチでき、キャンペーンやインセンティブ施策の訴求力もぐっと高まります。
また、複数のデジタルギフトを取り入れた「選べるギフト形式」にすることで、在庫リスクの軽減や運用コストの最適化にもつながります。受け取った人が実際に使った分だけコストが発生する仕組みなので、無駄が少なく、効率的な予算運用が可能です。
このように、それぞれ異なる特性を持つデジタルギフトをうまく組み合わせることで、単一サービスだけでは難しい、より幅広く、効果的なギフト戦略を実現できます。企業としての目的をしっかり達成しつつ、受け取る側にも喜ばれるバランスの取れた施策づくりに、ぜひ活かしてみてください。
QUOカードPayの活用でお困りのご担当者様へ
このようなお悩みをお持ちではありませんか? ・QUOカードPayで本当に喜ばれるのか不安がある ・他社のキャンペーンでも使われていて、もう少し差別化したい
こうした課題を解決するのが「giftee Box」です。
giftee Boxは、累計導入件数7万件以上、法人向けデジタルギフト導入実績No.1のgiftee for Businessが提供する、QUOカードPay含む1,000種類以上のラインナップの中から受け取った方が自由に選べるデジタルギフトです。
ギフトURLをメールやSNSで送るだけなので配布も簡単。受け取る側は自分の好みに合わせて商品を選べるため、満足度の高いインセンティブ施策を実現できます。
現在「giftee Box」の紹介資料をご用意しています。本資料では、giftee Boxをキャンペーン用途に合わせてどのように活用し、スムーズに配布・管理するか、その考え方や運用のポイントを詳しく解説しています。無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
デジタルギフトを活用した企業・自治体の成功事例
デジタルギフトの活用により、多くの企業や自治体が顕著な成果を上げています。本章では、弊社ギフティのデジタルギフトを活用した成功事例をご紹介します。これらの事例を参考にしていただくことで、自社での効果的な活用方法のヒントを得ることができるでしょう。
見積促進にデジタルギフトを活用した事例
企業/ブランド名 | TOTO株式会社 |
|---|---|
目的 | ・成約数の増加 ・金券の在庫管理や経理処理の手間削減 ・ギフトをお渡しする運用の効率化 ・キャンペーン効果の可視化 |
成果 | ・デジタルギフトの活用で、在庫管理や運用の手間を大幅に削減 ・リアルタイムで当選者数の可視化を実現 ・ギフトとユーザーを紐付けて管理 |
TOTO株式会社様では、ショールームでのフェア期間中に見積もり依頼をした方を対象とした抽選キャンペーンを実施されました。従来の金券管理の手間が課題でしたが、ギフティの「Instantwin(即時抽選システム)」を活用することで、抽選からギフト付与まで自動化を実現。お客様番号に紐付けた管理により、リアルタイムでの効果測定と成約までの効果検証が可能になりました。
▼この事例の詳細はこちら
若年層へのアプローチを強化した事例
企業/ブランド名 | 日本医師会 |
|---|---|
目的 | ・LINE公式アカウントの友だち数増加、特に若年層の獲得 ・国民の医療に関する認識や日本医師会に対する要望の把握 ・これまでアプローチが困難だった若手層からの意見収集 |
成果 | ・1か月という短い期間で約2,500人の参加を獲得 ・これまでアプローチできなかった若年層から直接意見や考えを聞くことに成功 ・アンケート回収効率の大幅改善 |
日本医師会様では、若年層へのアプローチが困難という課題を抱えていらっしゃいました。そこで、LINE友だち登録とアンケート回答を条件としたインスタントウィンキャンペーンを実施。その場で結果がわかる抽選で、オリジナルキャラクターグッズやギフティのデジタルギフト「giftee Box(※)」をプレゼントしました。結果として、1か月で約2,500人が参加し、これまでアプローチできなかった若年層から貴重な意見を収集できたそうです。
※1,000種類以上のラインナップの中から、好きな商品を自由に選べるギフト
▼この事例の詳細はこちら
多彩な交換先で高評価を獲得した事例
企業/ブランド名 | サントリー食品インターナショナル株式会社 |
|---|---|
目的 | 特茶の継続購入の促進 |
成果 | ・過去施策と比較して高い償還率を記録 ・参加者から「今の時代に合っているギフト」と高評価を獲得 |
サントリー食品インターナショナル株式会社様では、飲料ブランド「伊右衛門 特茶」において、2024年1月から3つのキャンペーンを展開されました。そこでご活用いただいたのが、弊社のデジタルギフト「えらべるPay(※)」です。そして、特茶の継続購入を促すため、一人のお客様に何度もキャンペーンに参加いただけるよう、ポイント単価を10〜90まで幅広く設定。通常「えらべるPay」は50ポイント以上からの引き換えとなっていましたが、今回のキャンペーンに合わせて「10ポイント」「20ポイント」の引き換えも可能にしました。
※様々なスマホ決済サービスのポイントを自由にえらべるギフト
また、「えらべるPay」の交換先の豊富さも大きなメリットとなり、参加者それぞれが日常的に使用しているキャッシュレス決済サービスに、任意の単価で引き換えられる点が好評でした。結果として、過去施策と比較して高い償還率を達成し、参加者からは「今の時代に合っている」といった感想が寄せられました。
▼この事例の詳細はこちら
「実質0円」キャッシュバック施策を実現した事例
企業/ブランド名 | ペプシ様 |
|---|---|
目的 | ・購買促進 ・「実質タダ」をうたうことでの話題化 |
成果 | これまでのオペレーション負荷を軽減 |
ペプシ様では、対象商品を購入して、商品に貼り付けられたシールの二次元コードを読み取ると、「えらべるPay」がもらえるキャンペーンを実施されました。「80円分が必ずもらえるキャンペーン」や「140円分が抽選でもらえるキャンペーン」など、複数の施策を展開しました。
「えらべるPay」を採用した理由として、受け取ったユーザーが好きなスマホ決済サービスやポイントを選んで交換できるため、利便性が高く多くの人に喜ばれるインセンティブが実現できることが挙げられます。また、抽選からギフト配布まで自動で実施されるため、運用負荷の軽減を図り、その分をユーザーへのギフトとして還元することができました。
▼この事例の詳細はこちら
よくある質問(FAQ)
Q. QUOカードPayの有効期限はどのくらいですか?
QUOカードPayの有効期限は、発行日から3年間です。
従来のカードタイプのQUOカードには有効期限がありませんが、デジタルタイプのQUOカードPayには有効期限が設定されています。受け取ったURLを開くと、画面上で有効期限を確認できるので、期限切れになる前に計画的に使用しましょう。
法人で配布する場合は、受け取った方が有効期限を把握できるよう、配布時のメッセージに有効期限の情報を記載しておくと親切です。
Q. QUOカードPayはチャージできますか?
いいえ、QUOカードPayにはチャージ機能はありません。
QUOカードPayは、あらかじめ設定された金額を使い切るプリペイド型のデジタルギフトです。残高がゼロになったら、新しいQUOカードPayを受け取る必要があります。ただし、複数のQUOカードPayを1つにまとめる機能はあるので、少額のギフトを複数受け取った場合でも管理しやすくなっています。
Q. アプリのダウンロードは必要ですか?
いいえ、専用アプリのダウンロードは不要です。
QUOカードPayは、スマートフォンのブラウザから利用できます。送られてきたURLを開くだけで、すぐに使えます。個人情報の登録も不要なため、受け取った方の手間が少なく、幅広い年齢層の方に利用していただきやすいデジタルギフトです。
Q. QUOカードPayが使えないお店はありますか?
はい、すべてのお店で使えるわけではありません。
QUOカードPayは、QUOカードPay加盟店でのみ利用可能です。主要なコンビニエンスストアやドラッグストア、書店などで使えますが、店舗によっては対応していない場合もあります。
最新の利用可能店舗は、QUOカードPay公式サイトで確認できます。
Q. 法人での大量購入は可能ですか?
はい。法人向けのオンラインストアから大量購入が可能です。
大規模なキャンペーンや福利厚生での活用を検討している場合は、事前にQUOカード公式サイトから問い合わせることで、より詳細な情報やサポートを受けられます。
まとめ|QUOカードPayで効果的なデジタルギフト活用を実現
QUOカードPayは、従来の物理的なギフトカードに比べて大幅に利便性を高めたデジタルギフトサービスです。企業のキャンペーン景品や福利厚生、自治体の給付事業など、さまざまなシーンで柔軟かつ実用的に活用できるのが特徴です。
50円から10万円まで、1円単位で自由に設定できる金額、主要コンビニを中心とした幅広い利用可能店舗、購入と同時にすぐに贈れるデジタルならではのスピード感、オリジナルデザインによるブランド訴求力、そして法人・個人両方に対応した購入方法などが特徴として挙げられます。
ぜひ本記事の内容をキャンペーン設計やインセンティブ選定にお役立てください。
QUOカードPayの活用でお困りのご担当者様へ
このようなお悩みをお持ちではありませんか? ・QUOカードPayで本当に喜ばれるのか不安がある ・他社のキャンペーンでも使われていて、もう少し差別化したい
こうした課題を解決するのが「giftee Box」です。
giftee Boxは、累計導入件数7万件以上、法人向けデジタルギフト導入実績No.1のgiftee for Businessが提供する、QUOカードPay含む1,000種類以上のラインナップの中から受け取った方が自由に選べるデジタルギフトです。
ギフトURLをメールやSNSで送るだけなので配布も簡単。受け取る側は自分の好みに合わせて商品を選べるため、満足度の高いインセンティブ施策を実現できます。
現在「giftee Box」の紹介資料をご用意しています。本資料では、giftee Boxをキャンペーン用途に合わせてどのように活用し、スムーズに配布・管理するか、その考え方や運用のポイントを詳しく解説しています。無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。