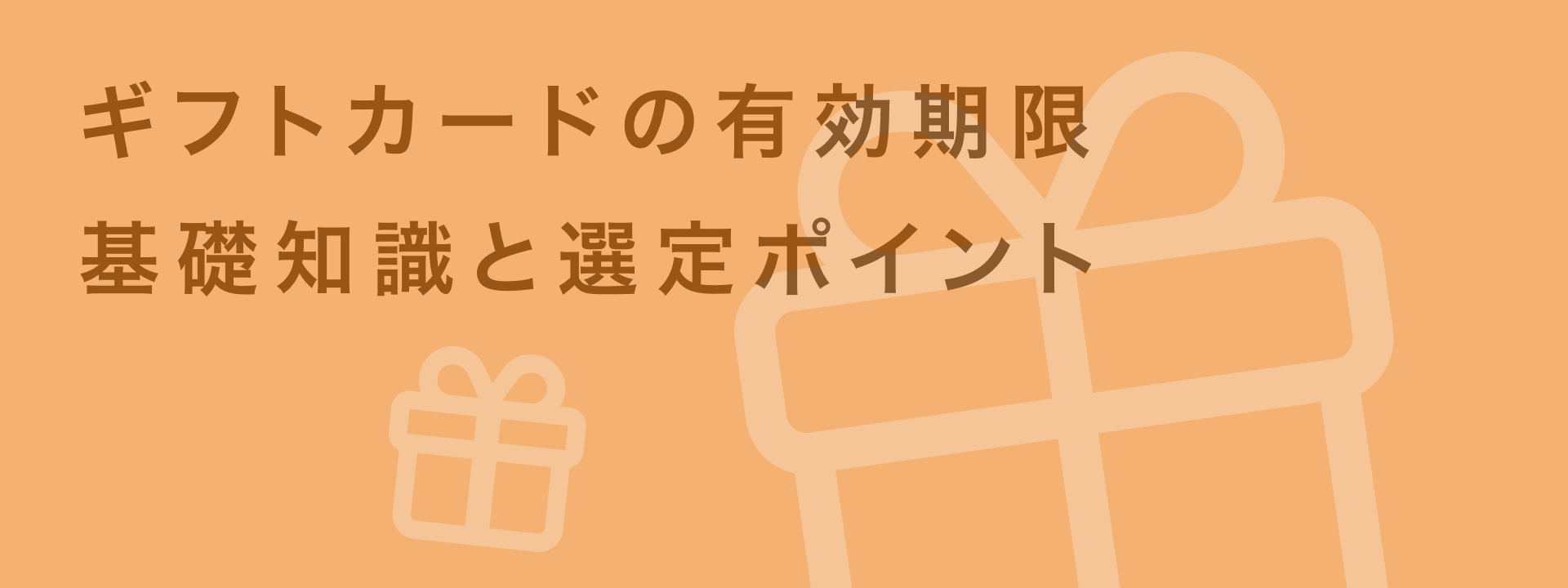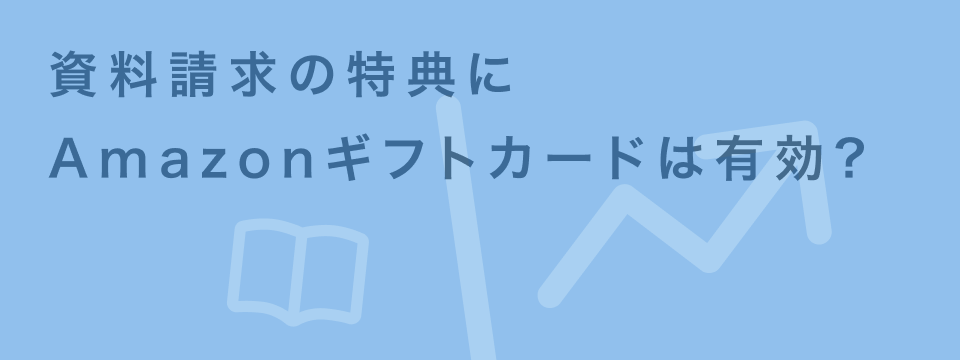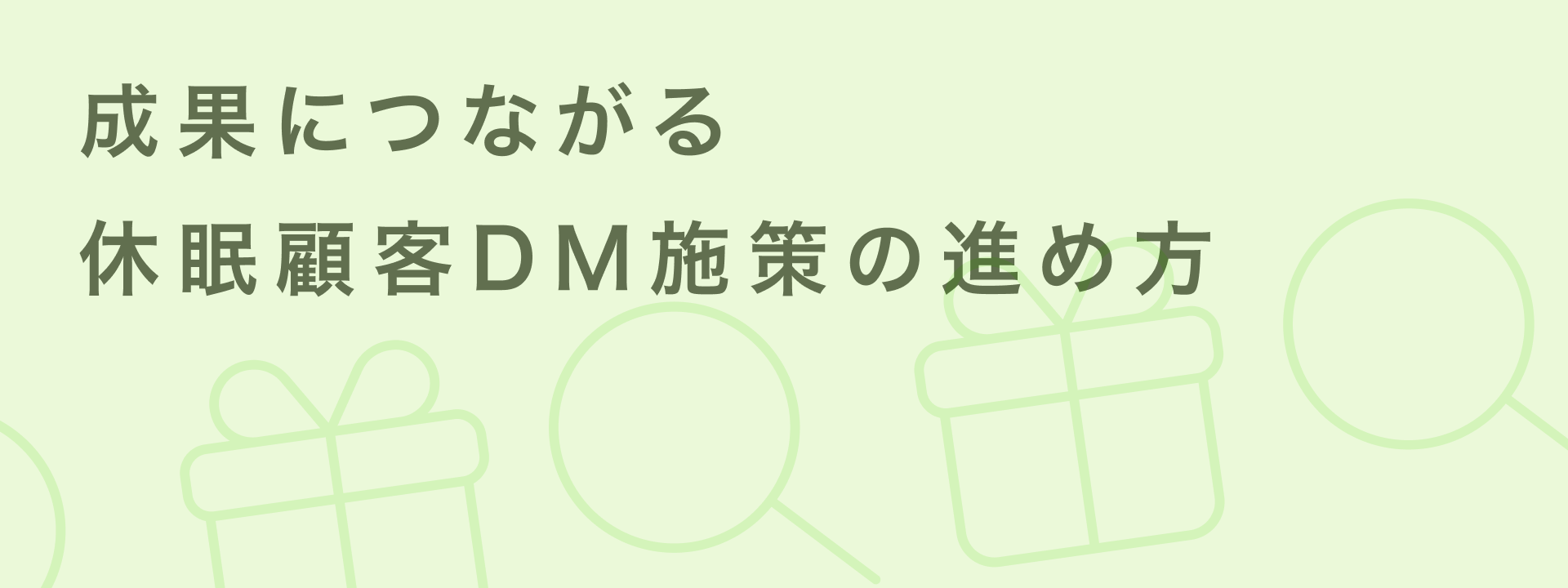保険キャンペーンのギフト規制|OK例やNG条件でルールをわかりやすく解説
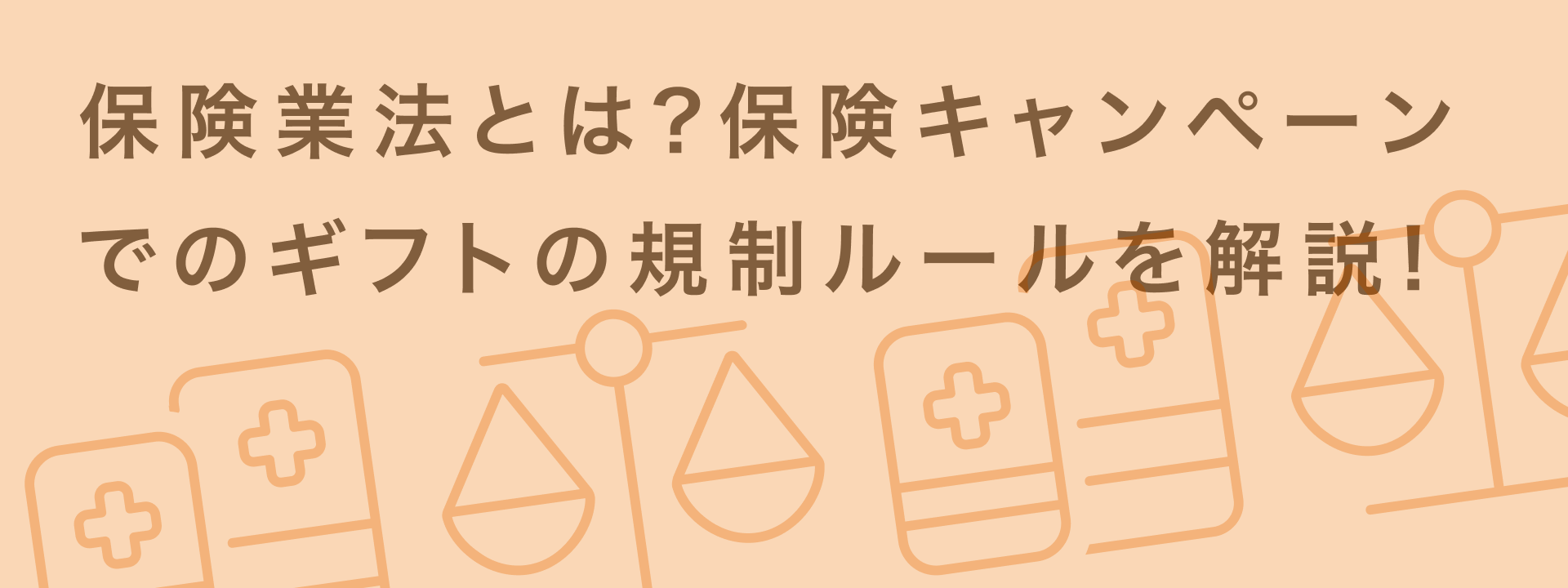
保険業界では、保険業法をはじめとした法令によってギフトのプレゼントが規制されています。ただ、成約・販売推進が目的でない場合や、前払い式支払い手段でない場合などは、プレゼントできる場合もあります。
そのため、実施するキャンペーンのギフトが保険業法に抵触していないか、渡してよいギフトの基準をクリアしているかなどを事前に確認することが重要です。判断に迷う場合は、法律の専門家や社内の法務部門に相談するのが確実でしょう。
とはいえ、企画を考えるためにも、どのようなケースが問題となるのか、大まかな判断基準は知っておきたいところです。
本記事では、保険業界のキャンペーンでプレゼントが禁止されるケースやギフトの使用が認められるケースについて解説します。保険業界のキャンペーン事例も紹介していますので、ぜひご参考ください。
※本記事の内容はあくまで株式会社ギフティ(以下、ギフティ)としての見解であり、本記事の内容が法令の解釈に適合していることを保証するものではなく、本記事の内容に基づいて被ったいかなる損害についてもギフティは一切責任を負いません。また、ギフトのプレゼントや使用に関する最終判断は、キャンペーン実施企業様に委ねています。
保険業界でのキャンペーン設計や、ギフト提供ルールにお悩みのご担当者様へ
もし現在、このようなお困りごとがありましたら、ぜひ「ギフトマーケティングの基本」 をご覧ください。
・そもそもギフトを活用したキャンペーンでどういった成果が得られるのか? ・景品表示法や業界ルールを守りつつ、魅力あるインセンティブ設計をしたい
本資料では、キャンペーン設計の考え方から、企画立案に役立つフレームワーク、成功へ導くポイントまでを体系的に解説しております。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
『保険相談で商品券をプレゼント』のキャンペーンはNG
保険業界のビジネスでは、契約成立に向けた情報提供のプロセスとして、保険相談が欠かせません。その一環として、集客のために商品券の配布を行いたい場合もあるかと思います。
しかし、2017年に金融庁や保険業界の団体から金券配布の自粛を求める通知が出された結果、保険勧誘において商品券をプレゼントする行為は原則禁止となりました。
商品券だけでなく、図書券やビール券などのプレゼントも不適切という見解が保険業界における共通認識となり、“金券は配布しない”という風潮が現場に広まり、現在に至っています。
「特別の利益の提供」に該当するキャンペーンは原則禁止
保険勧誘における商品券や図書券などのプレゼントは、「特別の利益の提供」に該当するとして、保険業法で禁止されています。
以下は、保険業法第300条(保険契約の締結等に関する禁止行為)の内容です。
“五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為”
保険業法の「特別の利益の提供」に該当する例は下記の通りです。
サービス等の経済的価値及び内容が社会相当性を超える
サービス等が換金性の程度と使途の範囲等に照らして実質的に保険料の割引、割戻しに該当する
サービス等の提供が保険契約者間の公平性を著しく阻害する
参考:保険募集人の体制整備に関するガイドライン 令和4年7月6日(生命保険協会)
商品券やクオカード、図書券などは「換金性が高い」とみなされ、実質的に現金と同じ扱いになります。そのため、保険料の割引や割戻しとみなされ、明確なルール違反となってしまうのです。
保険会社でも金券やギフトなどの使用が認められるケース

保険業界において金券のプレゼントは控えなければいけませんが、すべてのケースで禁止されているわけではありません。以下のケースは金券やギフト券の使用が認められることもあります。
成約・販売推進が目的でない
前払式支払手段でない
1.成約・販売推進が目的でない
保険の勧誘において、金券をプレゼントして成約や販売を促すことは禁止されています。そのため、「保険の見積もり実施で商品券1,000円分プレゼント!」と見込み顧客を募り、自社の保険への乗り換えを促すことは問題となります。
ただ、成約や販売推進が目的でなければ問題はありません。たとえば単なるお客様アンケートや満足度調査などは、「成約・販売推進を目的にしておらず、募集関連行為にはならない」と判断でき、金券類のプレゼントができる可能性があります。
2.前払式支払手段でない
先ほども触れた「特別の利益の提供」に該当するもので、「実質的に保険料の割引、割戻しに該当する」ものがあります。実質的に保険料の割引、割戻しに該当するものの例として挙げられるのが『前払式支払手段』のギフトです。
前払式支払手段とは、あらかじめお金を払っておいて、それを商品・サービスの購入の際に利用することができるものを指します。「資金決済法」では、次の4つの要件をすべて備えたものが前払式支払手段であると定義されています。
(1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
(2)証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
(3)金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
(4)物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。
これらの定義を踏まえると、具体的には商品券やカタログギフト券、IC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカードなどが前払式支払手段に該当します。そのため、ギフトには利用できません。
ただし、上記の4つの要件を満たしていても、使用期間が発行日から半年以内のものや社員食堂の食券、市町村が発行する商品券などは適用除外となるものもあります。
保険業界でキャンペーンを行う場合のポイント
保険業界では、保険業法の法令によってギフトのプレゼントが原則規制されています。しかし、ルールを守ればギフトをプレゼントできる場合もあるので、キャンペーンを行う際は以下のポイントを押さえて実施しましょう。
「使途の範囲」と「社会相当性」を考えてギフトを選定する
保険・金融業界のサポート実績が豊富なギフト提供会社を活用する
『使途の範囲』と『社会相当性』を考えてギフトを選定する
一般社団法人生命保険協会の「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」によれば、保険関連のキャンペーンで使用するギフトは下記の3点を満たし、「使途の範囲」と「社会相当性」の程度を踏まえて可否の判断を行います。
現金・電子マネーではない
現金・電子マネーに交換(チャージ)できない
前払式支払手段に該当しない
「使途の範囲」とはギフトで交換・購入できる商品の種類がどれだけ広いかを指し、「社会相当性」とはそのギフトが社会的に適切であるか、経済的にふさわしいかを指します。上図右下の通り、使途の範囲が狭く社会相当性が低いギフトはプレゼントとして活用可能です。その一方で、使途の範囲が広く社会相当性が高いギフトは認められません。
たとえば、複数のスイーツの種類から1つを選べる商品は使途の範囲が広く、ギフトとして適さないおそれがあります。また、優待券やお買物券などのギフトで前払式支払手段ではない場合でも、経済的価値が一般的に高ければ「社会相当性も高い」とみなされてしまい、ギフトとして活用できない恐れがあります。
使途の範囲と社会相当性の観点から明確にNGと判断できない場合もあるため、どのような目的で、どのように利用されるかによって判断が変わる点に注意が必要です。ギフトを利用する際は、各企業の法務やコンプライアンス部門に確認することをおすすめします。
保険・金融業界のサポート実績が豊富なギフト提供会社を活用する
保険業界でギフトをプレゼントする場合は、最終的には自社の判断で商品を選ぶ必要があります。そのため、実施するキャンペーンのギフトが保険業法に抵触していないか、「使途の範囲」と「社会相当性」の基準をクリアしているかなどをチェックした上で行わなければいけません。
自社のみで判断が難しい場合は、保険・金融業界での実績が豊富なギフト提供会社を活用するのがオススメです。法律やルールを遵守しつつ、自社に最適なキャンペーンを実施できるでしょう。
配布が認められる可能性のあるギフトの例
ここまでの説明で、保険関連のキャンペーンにおいて、ギフト全般がNGではないとおわかりいただけたと思います。配布が認められる可能性があるギフトの例についても確認してみましょう。
見積もりの謝礼にギフトをプレゼントする場合
ある保険会社様では、火災保険の見積もりを依頼した方にカフェチェーンで使用できるデジタルギフト数百円分をプレゼントするキャンペーンを実施したケースがあります。
この場合、ギフトを受け取るにあたって、参加者は対価を支払いません。ゆえに対価性を欠くことから、前払式支払手段には該当しません。
また、当該事案においては、経済的な価値も高いと評価されなかったため、社会相当性の観点からもプレゼントできる可能性が高いと考えられました。
LINE友だち追加の抽選プレゼント
LINE友だち追加でのギフトプレゼントではどうでしょうか。
保険会社の公式LINEアカウントにおいて、保険に関する情報を一律に配信したり、ユーザーの質問に対して設定された返信をしたりする程度にとどまるのであれば、 保険会社の公式アカウントをLINEの友だちとして登録させる行為は、直接的に保険契約を勧誘する行為と比較して、保険契約加入の契機となる可能性は低いと思われます。
ある保険会社様では、LINE公式アカウントを友だち追加して、簡単なアンケートに回答した方に対して、抽選でアイスクリームのデジタルギフトを贈るキャンペーンを実施した事例があります。
このような事例をふまえると、保険業界であっても、LINE友だち追加を条件とするギフトキャンペーンの実施は可能とご判断されることはありうるように思われます。
ただし、LINEの友だち追加を促す行為は、保険加入とまったく関係ない行為と言い切ることは困難であるため、最終的にはギフトの内容も含めて、各施策において具体的にご検討いただく必要があります。
事例|新規LINE公式アカウントの友だち登録増加を目的にデジタルギフトを活用
ここからは弊社の事例を参考に、保険業界でのキャンペーン実施事例を紹介します。
顧客へのサービス向上のためにLINE公式アカウントを新規開設し、その上で友だち登録者数の増加を目的としたキャンペーンを実施された保険会社様がいらっしゃいます。同社様はLINE友だち追加キャンペーンとアンケートキャンペーンの二つを実施。それぞれの対象者にえらべるデジタルギフトをプレゼントされました。
その結果、友だち登録者数の目標17万名を約4か月で達成。お客さまや代理店からも好評なキャンペーンとなり、保険業法を考慮したギフトで新規顧客獲得に成功されました。
まとめ
本記事では、保険に関するキャンペーンでギフトのプレゼントが禁止されるケースやギフトの使用が認められるケース、保険業界でキャンペーンを行う場合のポイントについて解説しました。
保険業界でギフトをプレゼントするときは、最終的に企業様の判断で商品を選ぶことになります。ルールに違反しないためにも、実施するキャンペーンのギフトが保険業法に抵触していないか、渡してよいギフトの基準をクリアしているかなどをしっかり精査するようにしましょう。
もし、自社のみでの判断では不安な場合は、保険・金融業界の実績が豊富なギフト提供会社を活用するのがおすすめです。法律やルールを遵守することはもちろん、自社のビジネスに効果的なキャンペーンが実施できます。
ぜひキャンペーンを活用して、自社の経営発展につなげていきましょう。