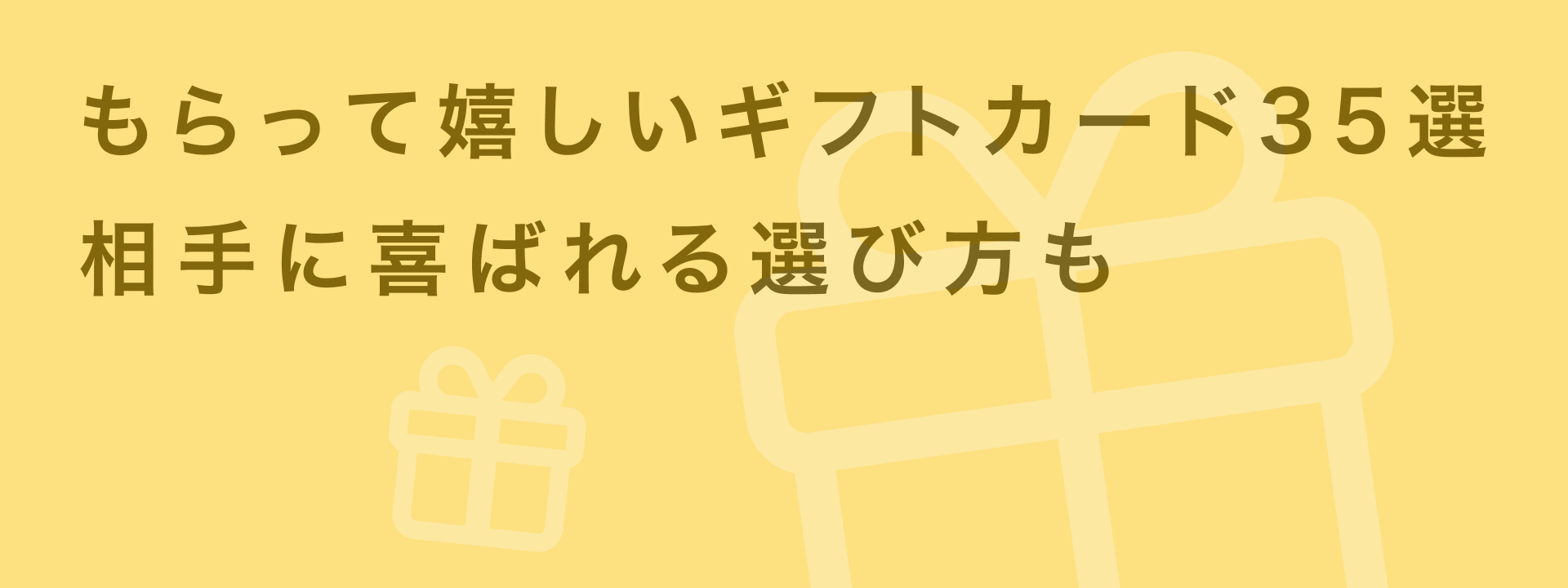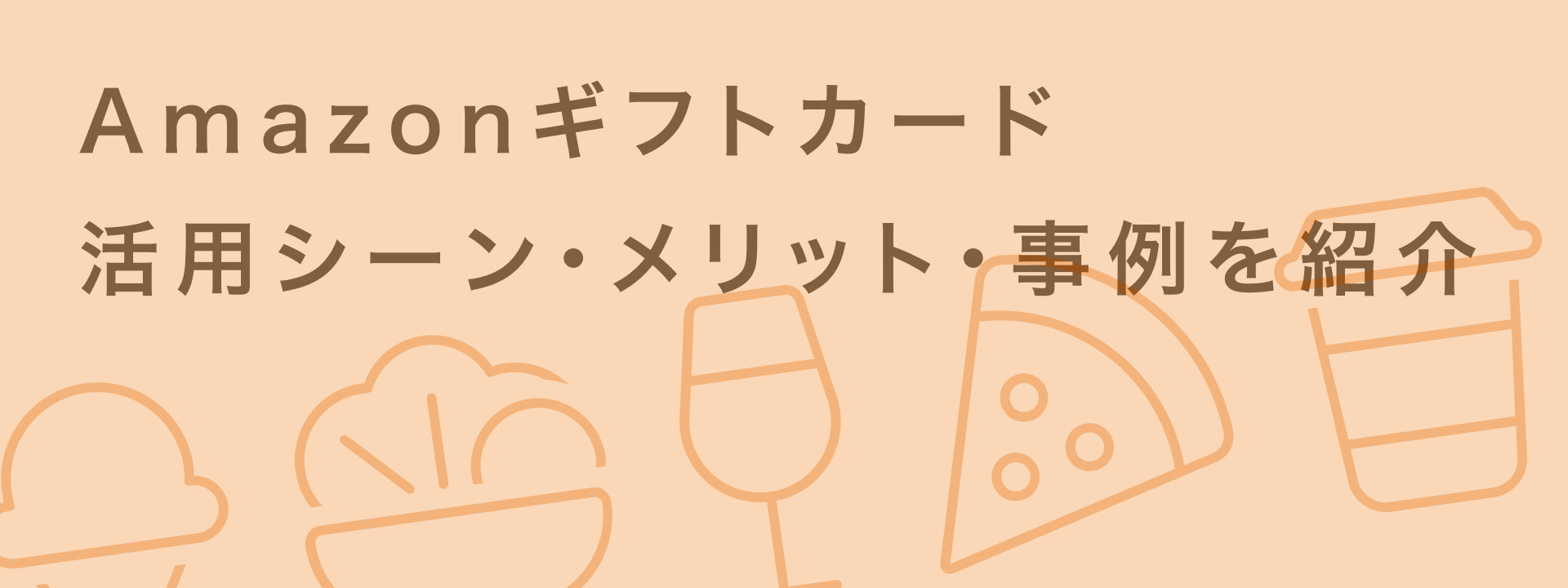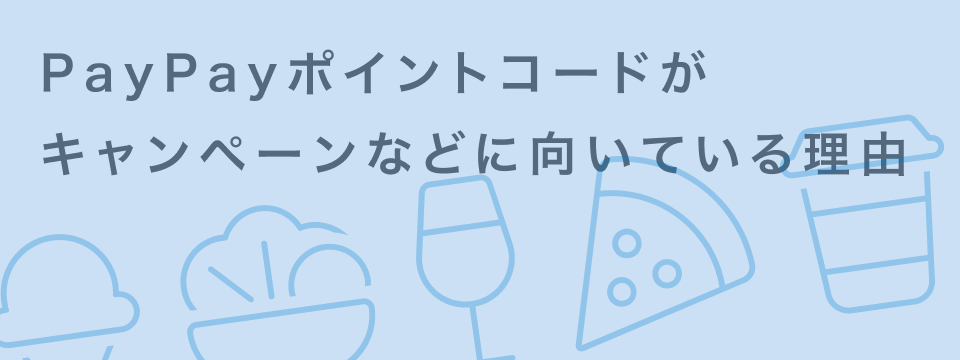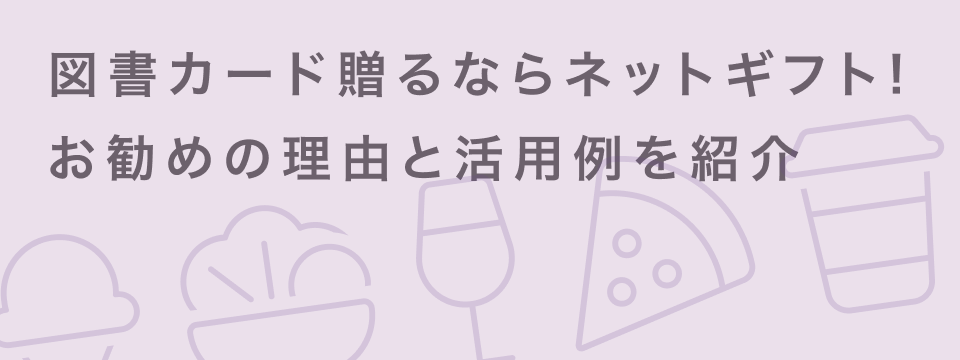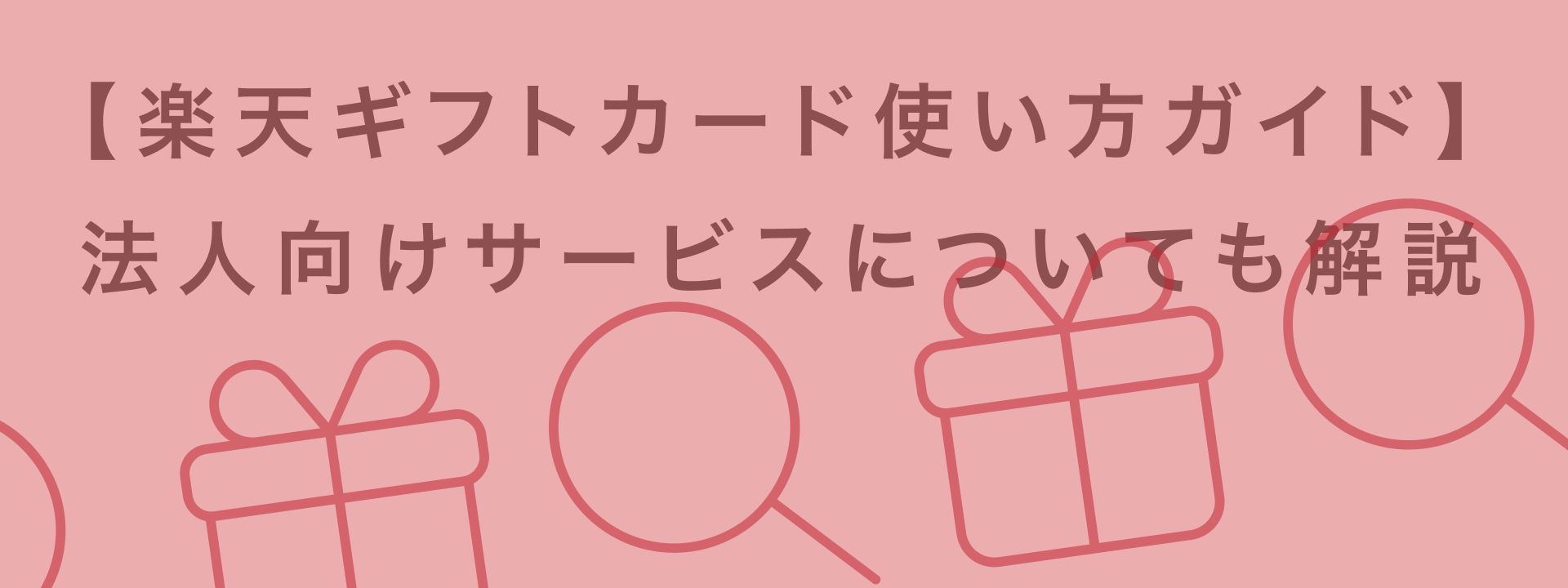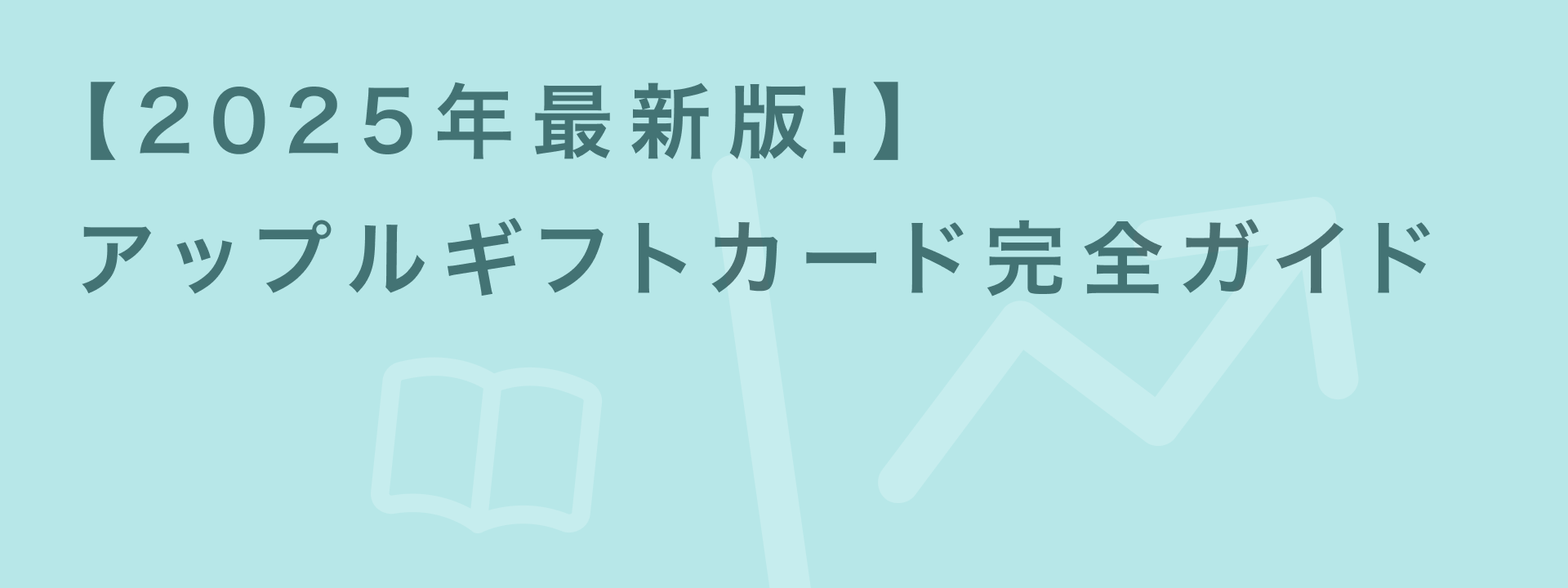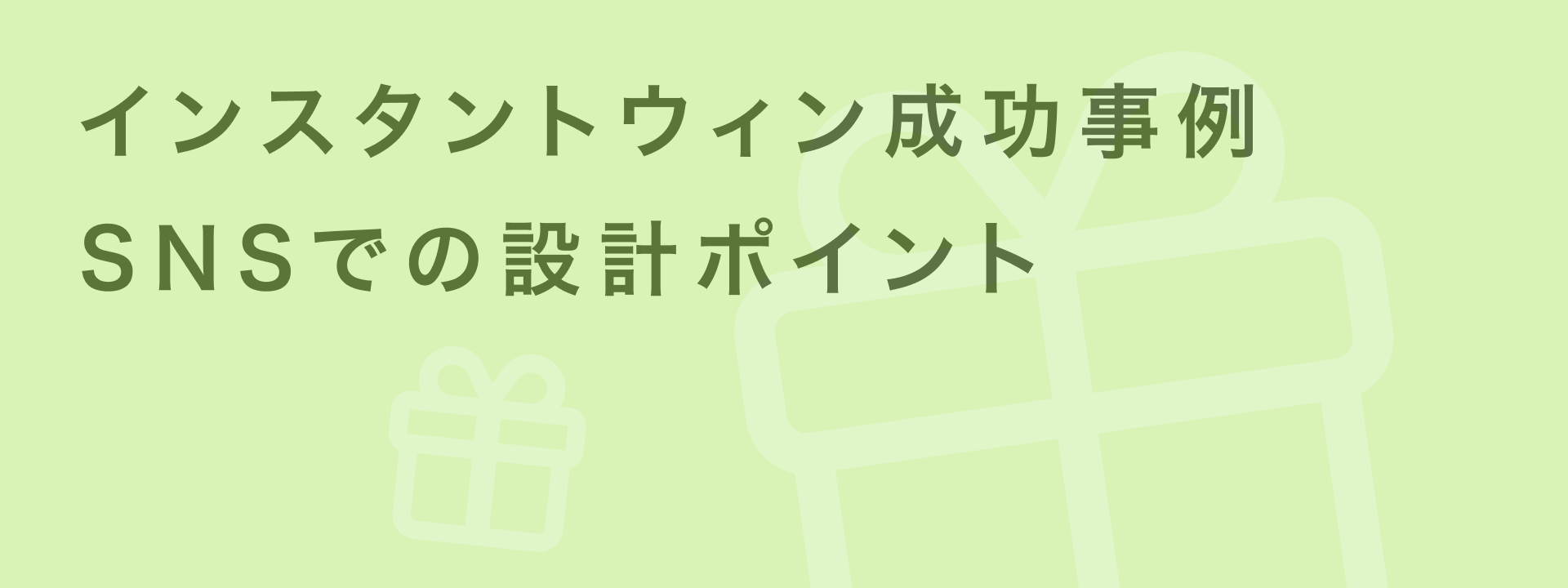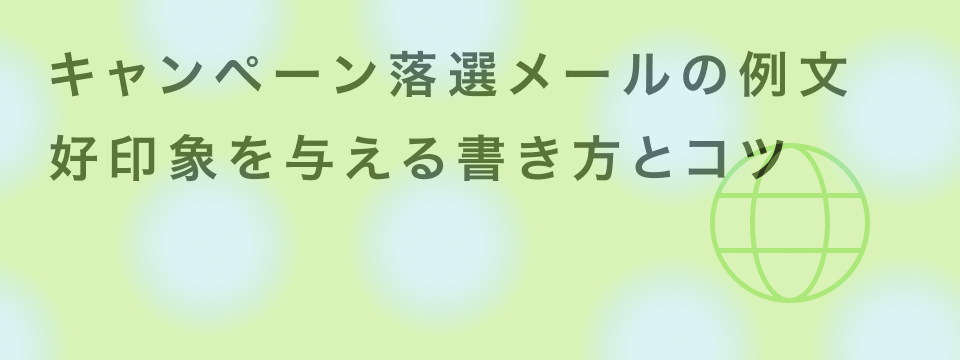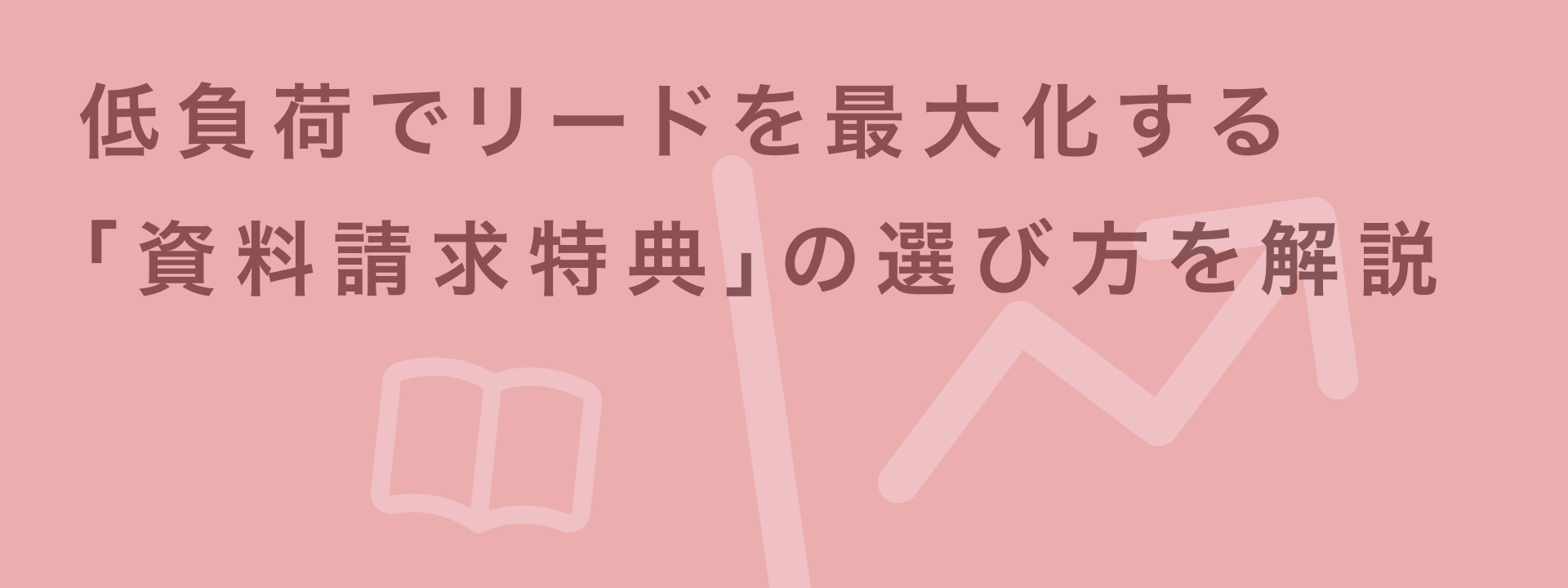ギフトマーケティングとは?基本概念や施策の流れをわかりやすく解説
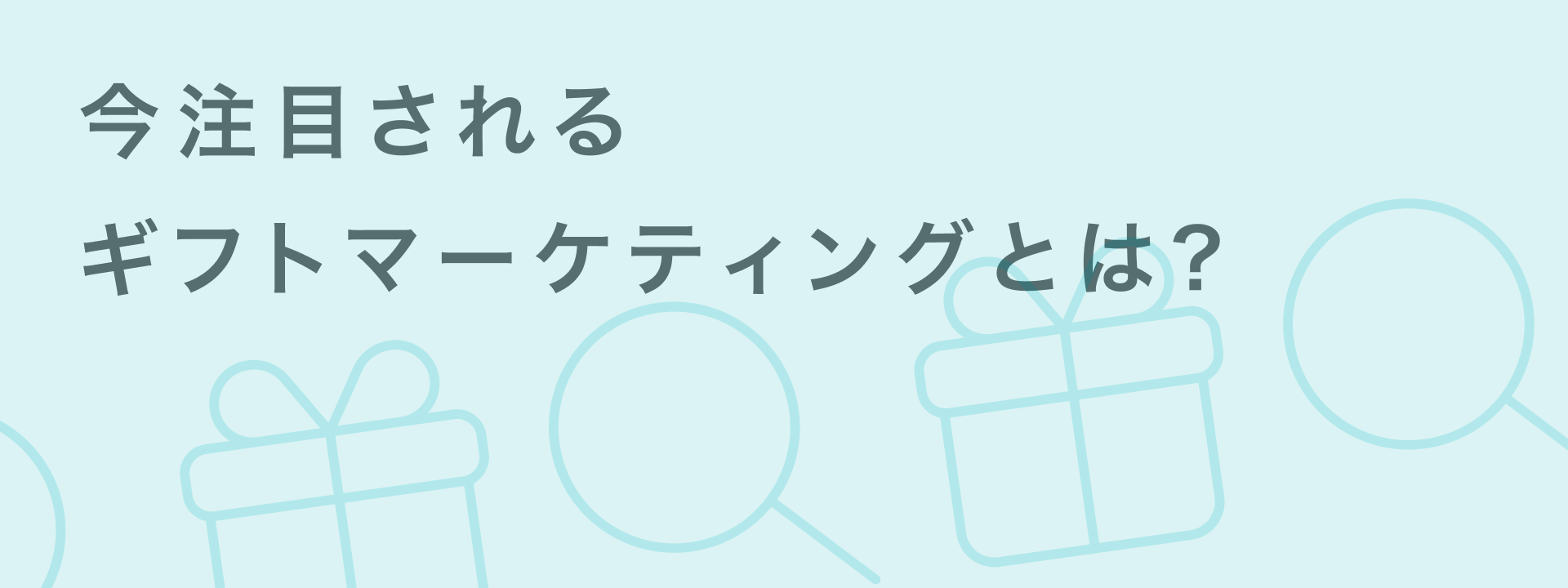
デジタルギフトの登場により、インセンティブ施策として、高額な「モノ」を景品として配送する時代から、少額なデジタルギフトを大量に贈れる時代となりました。しかし、やみくもにギフトを配って一時的に新規顧客の獲得ができたとしても、顧客のエンゲージメントまでを高めることはできません。顧客から他社と差別化してもらうには、「ギフトマーケティング(※)」の考え方を知る必要があります。
今回はギフトマーケティングの概要をおさらいしつつ、これからの時代に適したギフトや今後の展望を解説します。
※「ギフトマーケティング®」は株式会社ギフティの登録商標です。
ギフトマーケティングでお困りのご担当者様へ
こんなお悩みはありませんか? ・ギフトマーケティングを実施したいが、効果的な実践方法が分からない ・インセンティブ施策の最新トレンドを知りたい ・ターゲット設定やKPI設計など、キャンペーン設計の考え方が分からない
ギフトを活用したマーケティングは、顧客や従業員の行動を喚起する上で非常に有効ですが、効果を最大化するには、ギフトの価値や選び方、インセンティブ施策のトレンドを正しく理解しておくことが重要です。
そこでgiftee for Businessでは、ギフトマーケティングの基本概念から、インセンティブ施策の変遷、ギフト選定の考え方までを体系的にまとめた資料「ギフトマーケティングの基本」を用意しています。インセンティブの最新トレンドや、選べるギフトが求められる理由、データから見えるギフト利用傾向など、施策設計に役立つ知見を分かりやすく整理しています。
ギフトマーケティングの理解を深めたい方におすすめの内容です。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
ギフトマーケティングとは

ギフトマーケティングとは、顧客に最適なギフト体験を提供して、顧客とのつながりを育む考え方です。オンラインでのマーケティング手法が多様化した近年、顧客と接点を持つことは以前と比べて容易になりました。
しかし、やみくもに接点を持つだけでは購入や成約へ結びつけることはできず、せっかく得たチャンスを十分に活かすことができません。
そこで「ギフトマーケティング」の考え方をもとにインセンティブ施策をおこなうことで、ファーストコンタクトから購入・成約まで、顧客にとって自然な形でステップアップさせることが可能になります。
それではギフトマーケティングを理解するために、まずはインセンティブ施策の変遷から解説をしていきます。
インセンティブ施策の変遷
これまでのインセンティブ施策は下記の通り変化してきました。
- モノの景品時代
- デジタルギフトの登場
- ギフトマーケティングという考え方の登場
早速、インセンティブ施策の初期である、「モノ」の景品時代について解説していきます。
「モノ」の景品時代

初期のインセンティブ施策として主流だったのが、当選者に高額な「モノ」を景品として配送する方法でした。具体的には、キャンペーンに応募すると抽選で1名に豪華○○円相当のブランド牛が当たるなど、家電や食品、紙の金券といった高価格帯の「豪華商品」を目玉に参加者を集める手法のことです。
応募者は多数集まりますが、賞品の単価が高いため、高頻度での実施や大量配布が難しく、金銭面での課題がありました。また、商品の購入から配送までの在庫管理の手間や、当選者の抽選・配送業務など、間接コストも発生していました。
デジタルギフトの登場

近年になり、「デジタルギフト」が登場しました。デジタルギフトとは、コンビニやカフェの商品をURL化し、LINEやメールで送ることができるギフトで、「ソーシャルギフト」や「eギフト」とも呼ばれています。URLにアクセスするとチケットが表示され、画面を店頭で提示するだけで商品・サービスを提供してもらえる仕組みです。
デジタルギフトを活用した施策の例としては、X(旧Twitter)のフォローとリポストでデジタルギフトプレゼントや、アンケート回答でデジタルギフトが貰えるといったキャンペーンなどがあります。
デジタルギフトの登場により、配送料や在庫管理のコストや手間が削減され、予算内で当選者数を最大化することができるようになりました。ほかにも、キャンペーン参加後すぐに参加者へギフトを届けられるなど、企業側・参加者側双方にとってメリットのある施策を行えるようになりました。
ギフトマーケティングという考え方の登場

一方、デジタルギフトでは少額商品を大量に配布できてしまうため、顧客の満足度よりも配布効率が重視されるケースが目立ち、単発的な「バラマキ施策」が生まれやすくなりました。

こうした「バラマキ施策」のような画一的なコミュニケーションを受けた顧客の多くが、自分は企業から単なる数値として扱われていると感じたという調査結果も出ています。
このような背景から最近では、ギフトを顧客との関係構築・維持・強化の手段として捉え直す、ギフトマーケティングという考え方が求められるようになりました。
ギフトマーケティングで大切なポイント
インセンティブ施策の変遷について、おわかりいただけましたでしょうか。ここからはギフトマーケティングを行う上で大切なポイントを説明していきます。
ギフトマーケティングの考え方では、下記の点を意識してギフトを贈ることが重要です。
- ユーザーが欲しいものを渡す
- 最適なタイミングで渡す
- 特別感を出す
こうした点を踏まえてインセンティブ施策を行うことで、効果を一層高めることができます。それぞれのポイントについて詳しく見ていきます。
ユーザーが欲しいものを贈る

一般的に、個人間でギフトを贈るときは、相手が欲しいものを考えて選びます。
しかし、企業が行うキャンペーンでは、顧客に一律で同じギフトを配布するケースが多く、ユーザーのニーズを満たせないことも珍しくはありません。とはいえ配布対象が多い場合、ひとりひとりのニーズをヒアリングしてギフトを渡すのは現実的ではありません。
そのため、受け取り手が好きなものを選べるギフトなど、自由度の高いものをチョイスするのがおすすめです。
最適なタイミングで渡す
会員登録や購入にいたるには、最適なタイミングでギフトを段階的に配布して、徐々にエンゲージメントを高める設計を作ることが重要です。

具体的には、「資料請求」や「メールアドレス登録」、「アンケート回答」などの小さなコンバージョンポイントでは少額のインセンティブを付与し、「契約」や「申込み」など、大きなコンバージョンポイントでは高額なインセンティブを付与することで、初回のタッチポイントのハードルを下げ、無理なく段階的に最終目的のコンバージョンまで引き上げていくことが可能となります。
特別感を出す

受け取り手個人にフォーカスして満足度を高めるという観点から、ギフト付与のフェーズによってはギフトに特別感を演出することも重要です。
たとえば、家族や友人などからプレゼントをもらうとき、素敵なラッピングがされていたり、メッセージカードが同封されたりしていて、思い出に残ったことはありませんでしょうか。
法人ギフトでも同様で、ただギフトを渡すのではなく、オリジナルラッピングの活用やパーソナライズしたメッセージカードの同封などで特別感を演出することで、顧客の記憶に残るギフト体験を生み出すことができます。
ギフトマーケティングの具体的な流れ
ギフトマーケティングのイメージが湧くよう、新車販売のプロモーションを例に解説していきます。

認知拡大フェーズ<低価格帯&汎用的ギフト>
ギフト内容: 抽選で1,000名にデジタルギフト100円分
ギフト付与のタイミング: X(旧Twitter)のフォロー&リポスト
→ ひとりでも多くの方に商品の情報が広まるよう、低単価のギフトを使用し、拡散性の高いキャンペーンを実施します。
情報収集フェーズ<中価格帯&セグメントされたギフト>
ギフト内容: 人気アウトドアブランドとの限定コラボグッズ
ギフト付与のタイミング: 来店し、車を試乗したタイミング
→ まずは店頭へ来ていただけるよう、来店のフックとしてターゲット層が好むギフトをプレゼントするキャンペーンを実施します。
意思決定フェーズ<高価格帯&パーソナライズ・多様なニーズに応えうるギフト>
ギフト内容: 「車で出かけるオリジナル体験ギフト」2万円分
ギフト付与のタイミング: 車を購入するタイミング
→ 新しく買った車でどこへ行こうかイメージが膨らむような高価格帯のギフトをプレゼントすることで、購入の意思決定の後押しを行います。
このように、フェーズやシーンに適したギフト体験を提供することで、徐々に顧客との関係性を深めながら、意思決定を自然かつ段階的に促していきます。
ギフトマーケティングの成功事例
ここまで「ギフトマーケティング」の基本概念と運用の流れを見てきました。
次に、実際にこの考え方を活用して成果を上げた企業事例を紹介します。業界や目的の異なる5つの事例から、デジタルギフトをどのように戦略的に活用できるのかを見ていきましょう。
ゴディバジャパン株式会社
新商品発売記念キャンペーンとして、Xの公式アカウントをフォロー&リポストすることでギフト券またはトリュフ試食が当たるインスタントウィンキャンペーンを実施しました。
目的 | 新商品の認知拡大、Xアカウントの新規フォロワー獲得 |
|---|---|
課題 | Xキャンペーンと来店促進を組み合わせるキャンペーンが煩雑かつコストがかかりすぎていた |
成果 | 6万以上のリポストで新商品の認知拡大を実現、約4.3万の新規フォロワーを獲得 |
ハズレなしのキャンペーンにしたことで当選報告ポストが多数投稿され、効率的な拡散を実現。デジタルギフトをインセンティブとして活用することで、低コストかつ高いエンゲージメントを獲得できた好例です。
今回の施策におけるリポストの獲得単価は100円以下だったといい、従来のキャンペーンよりも圧倒的に効率的な拡散を達成しました。
▼事例の詳細はこちら
株式会社スクウェア・エニックス
FINAL FANTASY Ⅴとのコラボレーション記念として、公式Xアカウントのフォロー&リポストキャンペーンを実施。ゲームキャラクターをイメージした体験ギフトを景品として設定しました。
目的 | コラボレーション開催の認知拡大および集客 |
|---|---|
課題 | 事務局設置や商品発送など、キャンペーン実施において費用・オペレーション工数が大幅にかかる |
成果 | リポスト数約1.6万件(目標約1.0~1.2万件に対して160%達成) |
キャラクターに関連した「陸・空・海」をテーマに、乗馬体験・ヘリコプターフライト・クルージングチケットを景品として設定。ギフトマーケティングの「特別感を出す」原則に則り、キャンペーンの文脈に沿ったギフトでイベントを盛り上げ、高いエンゲージメントを獲得しました。
従来の商品発送と比較して、コストと工数を大幅に削減しながら、ユーザー満足度の高い画期的なキャンペーンを実現しました。
▼事例の詳細はこちら
サントリー食品インターナショナル株式会社
サントリー食品インターナショナル株式会社様では、「特茶」の継続購入促進を目的に、「特茶を飲んだら確実キャンペーン」「特茶クエスト」「特茶アドベンチャー」の3つの施策を展開しました。
目的 | 特茶の継続購入促進とブランドロイヤルティ向上 |
|---|---|
課題 | 継続購入を促すために複数回のキャンペーン参加を促したい 少額ポイントでも引き換え可能なインセンティブが必要 |
成果 | 過去施策と比較して高い償還率を達成 「えらべるPay」のポイント単価を10〜90まで柔軟に設定し、継続参加を実現 参加者から「今の時代に合ったデジタルインセンティブ」と高評価だった |
特に「特茶クエスト」では、ステージクリアに応じてポイントを貯められる形式を採用。そして、繰り返しキャンペーンに参加してもらえるよう、ギフティのデジタルギフト「えらべるPay」を活用していただきました。
さらに、ポイント単価を10〜90ポイントまでの幅広いレンジに設定。通常の「えらべるPay」は50ポイント以上からですが、今回は少額ポイントをユーザーにためてもらえるようにすることで、施策の限られた予算の中でも継続購入を促せるようにしました。
結果、過去施策を上回る償還率を達成。さらに参加者からは「今の時代に合ったデジタルインセンティブ」と高い評価を得ました。。
▼事例の詳細はこちら
イオンタウンユニオン
イオンタウンユニオン様では、組合内ツール「TUNAG for UNION」のリリース1周年を記念し、新規登録や投稿を促進するキャンペーンを実施しました。
目的 | 社内コミュニケーションツールの新規登録・ログイン率向上 |
|---|---|
課題 | 事業所が全国に複数あるため、ギフト配布が困難 組合員にツールの価値を実感してもらい、継続利用を促したい |
成果 | キャンペーン前後で比較し、アプリログイン率201%、Webログイン率344%向上 クローズドな抽選で組合員限定の特別感を演出 受け取り手が好きなギフトを選べる設計で満足度向上 |
イオンタウンユニオン様によると、全国に事業所が分散しているため、物理のギフト配布はあまり効率的ではなかったとのこと。そこで、メール記載のURLから抽選に参加できるオンラインの仕組みを採用。応募条件を満たした組合員のみに抽選IDを配信し、1,000円分・2,000円分・3,000円分の「giftee Box」のいずれかがその場で当たるクローズド抽選キャンペーンを実現しました。
この取り組みにより、キャンペーン前後で比較してアプリログイン率201%、Webログイン率が344%向上という顕著な成果を達成しました。
▼事例の詳細はこちら
ニトリ労働組合
ニトリ労働組合では、組合員を対象とした「働き方に関するアンケート」の回答率向上を目的に、回答者全員に「giftee Box」500円分を付与する施策を実施しました。
目的 | 組合員向けアンケートの回答率向上 |
|---|---|
課題 | アンケート回答率を上げるために効果的なインセンティブが必要 重複付与を防ぎヒューマンエラーのない効率的な運用が必要 |
成果 | 回答数1万件の目標に対し約1万1,000件(110%)の回答率を達成 Authシステムで従業員番号による認証を実現し、重複付与を防止 アンケート回答後すぐにギフトを受け取れる導線で満足度向上 |
従来は、アンケート施策におけるギフト配布時に重複付与や配布ミスのリスクがありましたが、Authシステム導入によってこれを解決。事前に従業員番号リストをインポートし、受け取り時に番号を入力することで、誰が受け取ったかを個別にトラッキングできる仕組みを構築しました。
また、アンケート回答後に組合専用アプリ内で即座にギフト受け取りページへ遷移できる導線を設計。回答から受け取りまでの体験をスムーズにすることで、参加者の満足度も向上しました。
その結果、目標を10%も上回る約1万1,000件の回答(回答率110%)を得たとのことです。
▼事例の詳細はこちら
デジタルギフトの選定と効果を最大化するコツ
前述の通り、ギフトマーケティングの効果最大化を目指すのであれば、目的とターゲットに適したデジタルギフトを選ぶことが肝要です。デジタルギフトには電子マネー、ポイント、商品引換券など様々な種類があり、それぞれに適した活用シーンが異なります。
たとえば、アンケート回答のインセンティブには少額でも即時性のある電子マネーや選べるギフトが適している一方、顧客の意思決定を後押しするには高額でパーソナライズされたギフトが効果的です。また、受け取る顧客層の年齢や生活スタイルによっても、最適なデジタルギフトは変わってきます。
デジタルギフト選定のポイント:
ユーザーの使いやすさを優先する:全国で利用できるか、有効期限は十分か、受け取った人が実際に使えるかを検討する
施策のフェーズに合わせて金額設定を調整する:認知拡大には低単価・大量配布、購入検討には中価格帯、成約促進には高価格帯と段階的に設計する
選べるタイプのギフトを活用する:受け取り手が自分の好みに合わせて選べるギフトは、幅広い顧客層に対応でき満足度も高くなる
適切なデジタルギフト選びとインセンティブ設計は、キャンペーン成功の鍵となります。顧客視点に立ち、本当に喜ばれるギフトを選ぶことで、ギフトマーケティングの効果を最大化できるでしょう。
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事でデジタルギフトの種類や活用方法、メリットや注意点などを詳しく解説しています。すでに導入している企業の事例も紹介していますので、キャンペーンの景品などでデジタルギフトを活用されたい方は、ぜひあわせてご覧ください。
キャンペーンで活用できるデジタルギフトと選び方のポイント
ギフトマーケティングの効果を最大化するには、ターゲット層の属性や嗜好に合わせたギフト選定が不可欠です。同じ金額のギフトでも、受け取り手のニーズとマッチするかどうかで満足度が大きく変わります。
効果的なターゲティングには、年齢・性別・ライフスタイル・消費傾向などの多角的な分析が必要です。また、選択肢の多いギフトや汎用性の高いギフトを活用することで、多様なニーズに対応できます。
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事で具体的なギフトの特徴と選び方などについて解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
では実際に、キャンペーンで活用できる代表的なデジタルギフトにはどのような種類があるのでしょうか。ここでは特に利用シーンが多いものを取り上げ、それぞれの特徴を解説します。
Amazonギフトカード
Amazonギフトカードは、段階的なエンゲージメント設計に最適なデジタルギフトです。ギフトマーケティングでは、認知拡大から購入検討まで各フェーズで一貫して活用でき、顧客の購買ジャーニーに寄り添った継続的な関係構築が可能です。特に「欲しいものを選べる自由度」が、個人の嗜好に合わせたギフト体験を実現し、企業からの一方的な押し付けではない顧客中心のマーケティングを展開できる点が魅力です。
こんな課題におすすめ
- 顧客ジャーニー全体を通して一貫したギフト体験を設計したい
- 個人の嗜好に合わせたパーソナライズドギフトマーケティングを実施したい
- 「選択の自由」を重視した顧客中心のギフト戦略を展開したい
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事で法人での活用方法などを詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
PayPayポイント
PayPayポイントは、登録ユーザー数が6,500万人を突破している(2024年発表、PayPay株式会社調べ)国内最大級のキャッシュレス決済サービスです。
そして、ギフトマーケティングの核心である「日常の接点づくり」において、PayPayであればさまざまな店舗やECモールで利用可能なので、その点もかないます。そして、特に小額から配布できる特性を活かし、顧客の行動データに基づいたリアルタイムなインセンティブ設計が可能で、従来の画一的なギフト配布から脱却した動的なギフトマーケティングを展開できるでしょう。
こんな課題におすすめ
- 顧客の行動データを活用した動的なギフトマーケティングを実施したい
- 日常の決済シーンでブランドとの接点を継続的に創出したい
- 小額・高頻度配布でエンゲージメント強化を図りたい
さらに詳しく知りたい方は以下の記事でキャンペーンでの活用方法などについて詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
QUOカードPay
QUOカードPayは、ギフトマーケティングにおける「特別感の演出」を最大化できるデジタルギフトです。オリジナルデザイン機能により、企業独自のブランドメッセージやキャンペーンテーマを視覚的に表現でき、受け取った瞬間から印象に残るギフト体験を創出できます。特に意思決定フェーズでの高価格帯ギフトとして活用する際、単なる金銭的価値だけでなく「企業からの特別な思い」を伝達できるため、感情的なつながりを重視するギフトマーケティング戦略に最適です。
こんな課題におすすめ
- ブランドストーリーを込めた感情的なギフト体験を設計したい
- 意思決定フェーズで印象に残る特別感のあるギフトを提供したい
- 視覚的ブランディングと実用性を両立させたギフトマーケティングを展開したい
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事で企業での活用方法などについて解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
図書カードNEXT
図書カードNEXTは、ギフトマーケティングにおける「知的価値の提供」を最大化できるデジタルギフトです。学習・自己啓発という長期的価値を提供でき、受け取る人の成長に寄与するため、単なる消費ではない意味のあるギフト体験を創出します。
特に「学び」や「教育」への投資という特別感を演出できるため、企業の社会的責任を重視するギフトマーケティング戦略に最適です。
こんな課題におすすめ
- 企業の社会的責任を重視した知的価値提供のギフト戦略を展開したい
- 「学び」や「教育」をテーマにしたギフトを提供したい
- 幅広い年齢層に対して長期的価値を提供するギフトマーケティングを実施したい
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、図書カードの詳細な活用方法などについて解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
楽天ギフトカード
楽天ギフトカードは、楽天市場をはじめとする楽天サービス内での豊富な選択肢の中から、受け取る人が自分の好みに合わせて自由に利用できるのが特徴です。
こんな課題におすすめ
- 楽天の各種サービスを活用した包括的なギフトマーケティングを展開したい
- オンラインと実店舗の両方で継続的な顧客接点を創出したい
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、楽天ギフトカードの詳細な活用方法などについて解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
Apple Gift Card
Apple Gift Cardは、ギフトマーケティングにおける「デジタルネイティブ層への訴求力」を最大化できるデジタルギフトです。App Store、iTunes、Apple製品などのサービス・製品の購入に利用でき、特に若年層や技術志向の顧客層にとって特に魅力的なギフトです。
スマートフォンやタブレットでの日常的な利用シーンが豊富で、ギフトを通じてブランドとの継続的な接点を創出できるため、デジタル世代をターゲットとしたギフトマーケティングに最適です。
こんな課題におすすめ
- デジタルネイティブ層に特化したギフトマーケティングを実施したい
- アプリやサービス利用を通じた継続的なブランド接触を創出したい
- 若年層・技術志向顧客へ提供したい
さらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、法人での活用方法について解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
なお、今回おすすめした以外にもさまざまなキャッシュレス決済サービスのポイントを自由にえらべるギフトとして、弊社ギフティのデジタルギフト「えらべるPay」があります。こちらもぜひご検討ください。
よくある質問(FAQ)
ギフトマーケティングを始める際によくある疑問について、Q&A形式で解説します。
Q1: ギフトマーケティングと従来のインセンティブ施策の違いは?
最も大きな違いは、「配布効率」から「顧客体験」へのシフトです。
従来のインセンティブ施策
- 一律で同じギフトを配布する「バラマキ施策」
- 配布数や配布効率を重視
- 単発的な施策が中心
ギフトマーケティング
- 顧客に最適なギフト体験を提供し、関係性を育む
- 顧客ジャーニーに合わせた段階的な設計
- 長期的な関係構築を重視
従来の施策では、顧客は企業から単なる数値として扱われていると感じることが多く、一時的な効果しか得られませんでした。一方、ギフトマーケティングでは、顧客一人ひとりに寄り添ったギフト体験を設計することで、中長期的に顧客との関係を深めていくことができます。
Q2: ギフトマーケティングを始めるには何から取り組めばいい?
以下の3ステップで始めることをおすすめします。
Step 1: 顧客ジャーニーマップを作成する
まずは、顧客が認知から購入・成約に至るまでの流れを整理しましょう。各フェーズでどのような接点があるのかを明確にすることが重要です。
Step 2: 各フェーズに適したギフトを設計する
認知拡大フェーズ:低価格帯(100円〜500円程度)の汎用的なギフト
情報収集フェーズ:中価格帯(500円〜5,000円程度)のセグメントされたギフト
意思決定フェーズ:高価格帯(5,000円以上)のパーソナライズギフト
Step 3: 小規模なテストキャンペーンから始める
いきなり大規模に展開するのではなく、まずは既存顧客向けの小規模施策から始めて、効果を検証しながら改善していくことが成功の鍵です。
Q3: ギフトマーケティングの効果測定はどうすればいい?
フェーズごとにKPIを設定し、定量・定性の両面から評価することが重要です。
定量指標
- エンゲージメント率:キャンペーン参加率、ギフト受け取り率
- コンバージョン率:資料請求率、購入率、契約率
- ROI(投資対効果):ギフトコストに対する売上・利益
- リピート率:再購入率、継続利用率
定性指標
- 顧客満足度:アンケートやNPS(ネットプロモータースコア)
- ブランドイメージ:ブランド好感度の変化
- 口コミ・SNS投稿:自発的な情報発信の増加
フェーズ別のKPI例
- 認知拡大フェーズ:リーチ数、エンゲージメント率
- 情報収集フェーズ:資料請求率、来店率
- 意思決定フェーズ:購入率、契約率
これらの指標を定期的にモニタリングし、PDCAサイクルを回すことで、ギフトマーケティングの効果を最大化できます。
Q4: 小規模な企業でもギフトマーケティングは実施できる?
はい、デジタルギフトを活用すれば、小規模な企業でも十分に実施可能です。
小規模企業でも始めやすい理由
1.少額から始められる
デジタルギフトなら100円から設定可能
予算に応じて柔軟に調整できる
2.必要な数だけ発注可能
従来の現物ギフトは最低発注数が設定されていることが多い
デジタルギフトなら必要な分だけ発注できる
3.在庫管理が不要
物理的な在庫を持つ必要がない
配送コストや保管コストがかからない
4.即時配布が可能
キャンペーン実施後すぐにギフトを届けられる
顧客の満足度を高めやすい
まずは既存顧客向けの小規模施策(例:アンケート回答謝礼、誕生日ギフトなど)から始めて、効果を検証しながら徐々に規模を拡大していくのが良いでしょう。
顧客との関係を育む「ギフトマーケティング」へ
ただインセンティブを配るのではなく、顧客体験を最大化するギフトマーケティング時代に突入したことがおわかりいただけましたでしょうか。
デジタルギフトの登場によって、メールやSNSなどで気軽にギフトをプレゼントできる時代となりました。しかし、やみくもにギフトを配っても顧客のエンゲージメントは高められません。中長期的に顧客との関係を深めていくためには、顧客一人ひとりに寄り添ったギフト体験を設計することが大切です。
ギフトマーケティングでお困りのご担当者様へ
こんなお悩みはありませんか? ・ギフトマーケティングを実施したいが、効果的な実践方法が分からない ・インセンティブ施策の最新トレンドを知りたい ・ターゲット設定やKPI設計など、キャンペーン設計の考え方が分からない
ギフトを活用したマーケティングは、顧客や従業員の行動を喚起する上で非常に有効ですが、効果を最大化するには、ギフトの価値や選び方、インセンティブ施策のトレンドを正しく理解しておくことが重要です。
そこでgiftee for Businessでは、ギフトマーケティングの基本概念から、インセンティブ施策の変遷、ギフト選定の考え方までを体系的にまとめた資料「ギフトマーケティングの基本」を用意しています。インセンティブの最新トレンドや、選べるギフトが求められる理由、データから見えるギフト利用傾向など、施策設計に役立つ知見を分かりやすく整理しています。
ギフトマーケティングの理解を深めたい方におすすめの内容です。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
※本記事は株式会社ギフティによる提供です。本記事についてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。株式会社ギフティ(03-6303-9318)までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 ※「au PAY」は、KDDI株式会社の商標です。 ※「nanaco(ナナコ)」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。本記事についてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしておりません。株式会社ギフティまでお願いいたします。