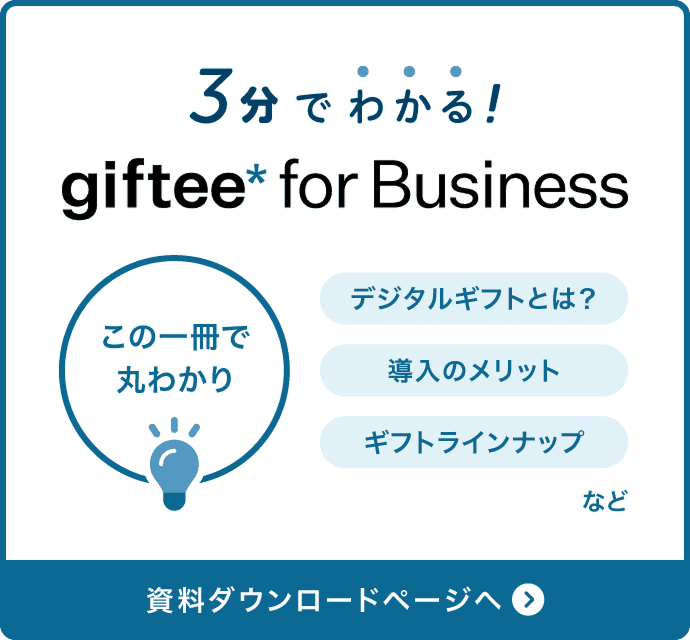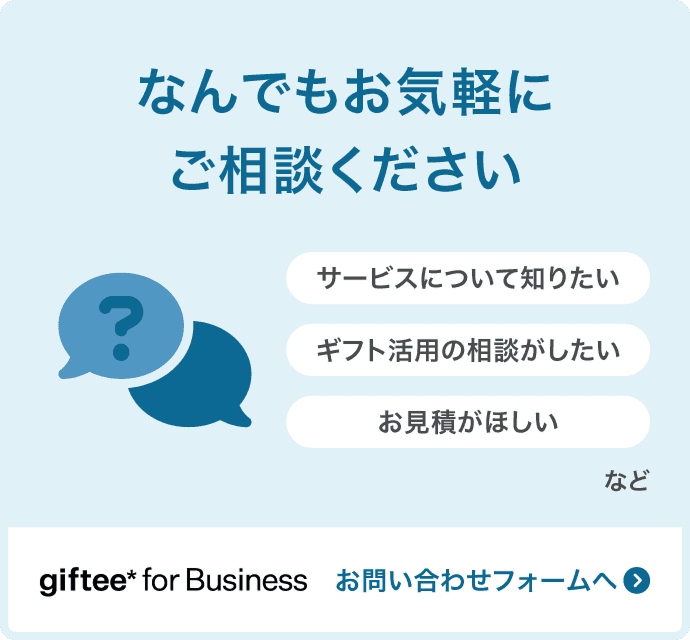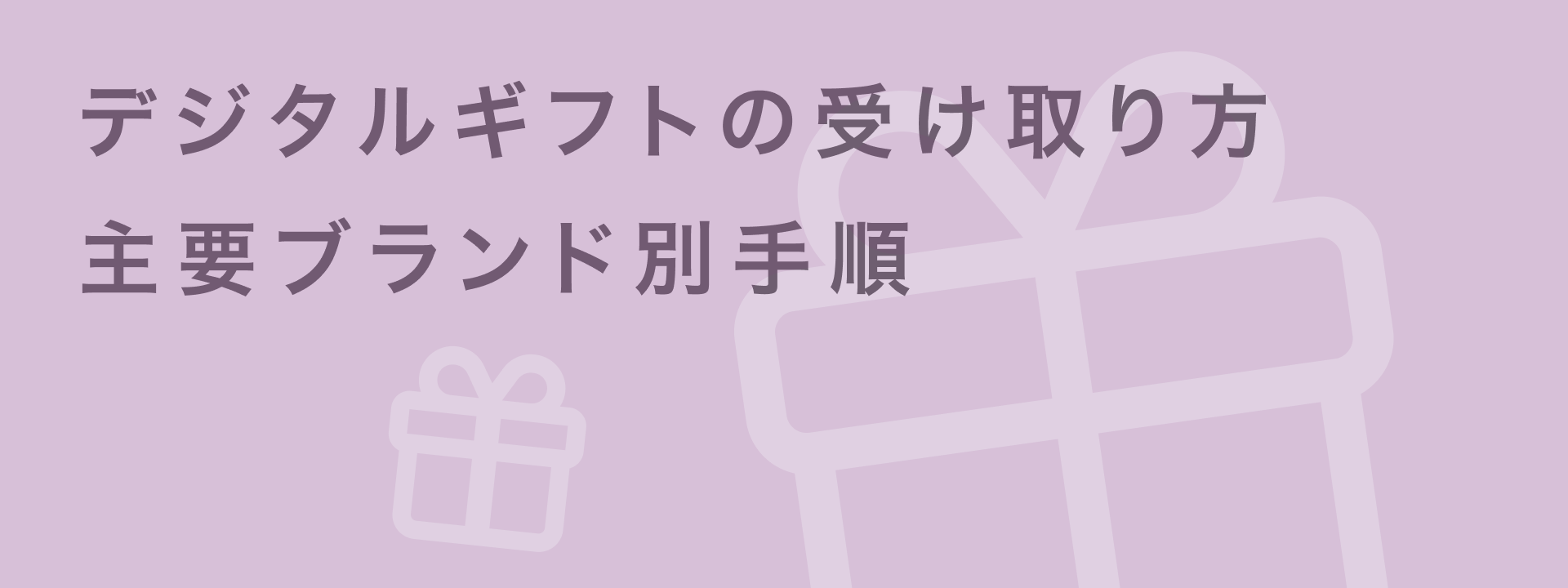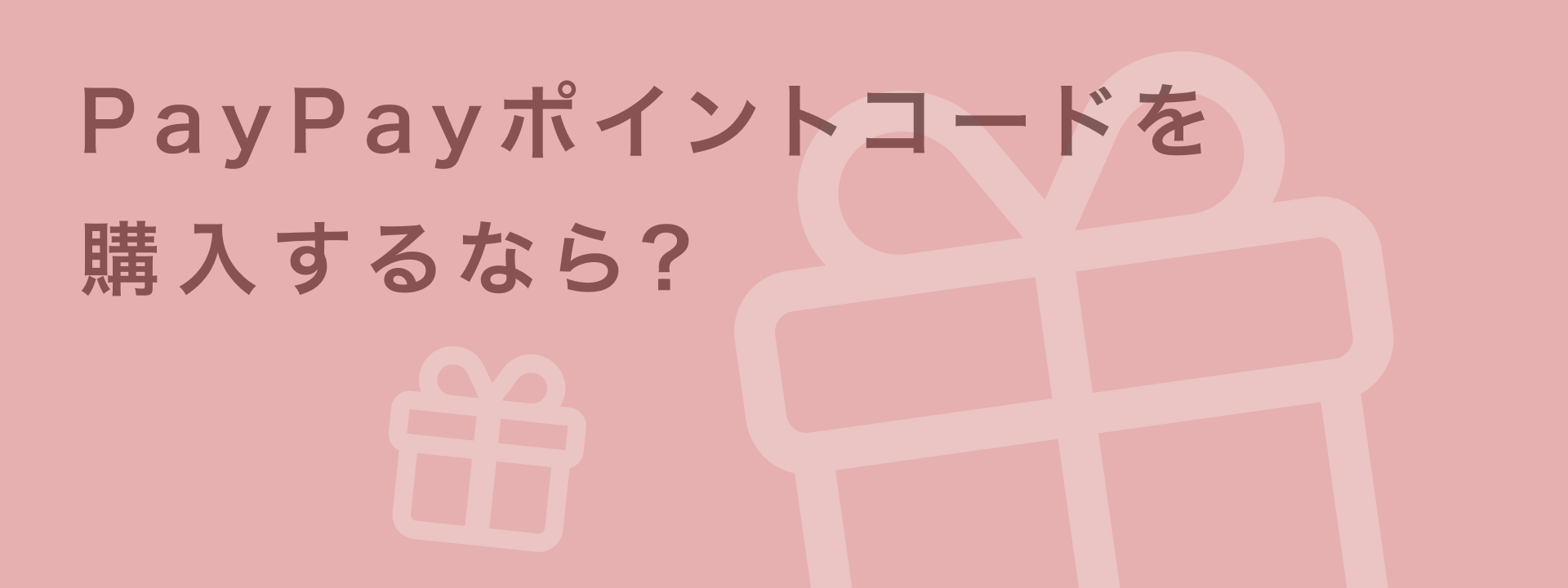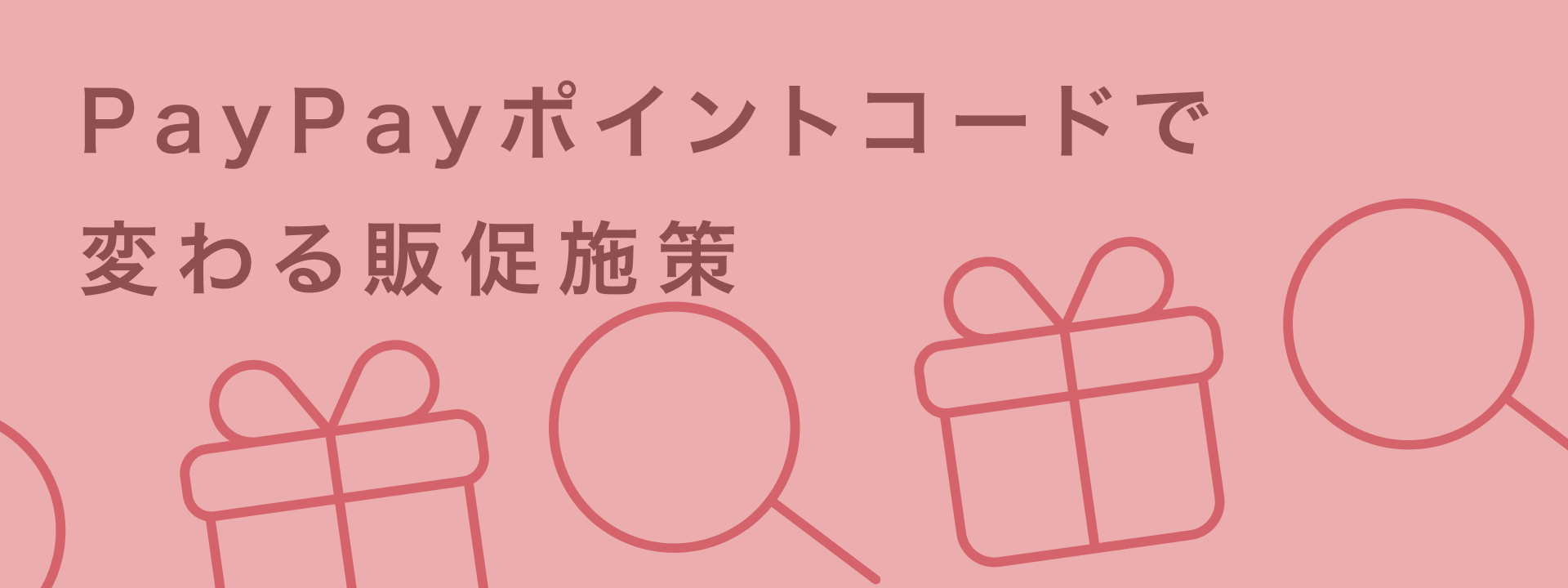【事例付き】 “贈る”が業務負担になっていませんか?ギフト運用の見直しヒント
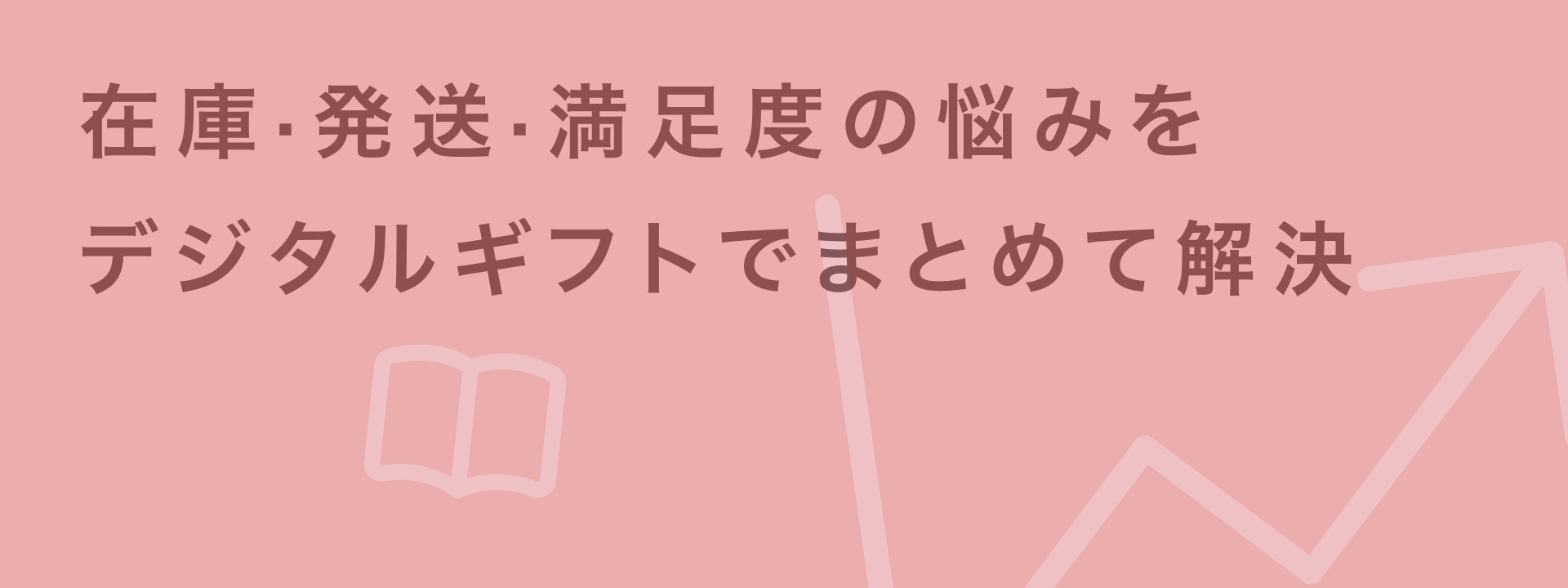
紙の商品券やギフトカードは、福利厚生や販促施策で長く利用されてきました。 しかし近年では、次のようなお悩みを抱える企業様からのご相談が増えています。
・社員表彰やキャンペーンで配布しているものの、「使える場所が限られて不便」という声が出ている ・住所収集や発送作業に多くの時間を取られ、担当者が本来の業務に集中できない ・在庫を抱える必要があり、余剰分の保管や廃棄が発生してしまう ・応募者や社員への配布が郵送中心となり、スピード感が出せない ・ギフトを贈る本来の目的よりも、手続きや管理業務に時間が割かれている
ギフトカードや紙カタログ、現物ギフトは長らく「定番」として活用されてきました。 しかし「便利なはずなのに、運用や利用の面で不便さを感じる」という声が目立つようになっています。
DXやペーパーレス化が進む今、多くの企業が「もっと簡単に、もっと自由にギフトを贈れる方法」を探し始めています。 実際にデジタルギフトを導入された企業からは、「工数が大幅に減った」「社員や顧客から“使いやすい”と好評だった」といった声が寄せられています。
本記事では、紙のギフトカード運用でよくある課題と、デジタルギフトに切り替えることで得られるメリットをご紹介します。
従来型ギフト施策が抱える課題とは?
紙のギフト券や現物商品は、企業や店舗で長年活用されてきましたが、実際の運用や体験面では以下のような課題があります。
在庫・廃棄リスク
管理の手間と個人情報対応の煩雑さ
利用体験の制約
DX・環境配慮への対応が困難
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
在庫・廃棄リスク
紙のギフト券や現物商品は在庫管理が必要で、余剰分の保管や廃棄にも手間がかかります。ギフト券の場合は金券としての性質上、不正利用や紛失のリスクもある一方で、在庫不足になればイベント進行に影響が出る可能性も。在庫管理そのものが大きな負担となります。
管理の手間と個人情報対応の煩雑さ
紙のギフト券や現物商品を郵送する場合には、住所の収集や郵送作業が伴い、個人情報の取り扱いにも注意が必要です。オフィスでの手渡しの場合にも、全国規模で配布する場合は社内展開も複雑化し、時間・コストともに負担が大きくなります。
利用体験の制約
受け取る側にとって、用途が限定された紙のギフト券や現物商品は必ずしも使いやすいとは限りません。利用できる店舗が限られていたり、すぐに使えなかったりするため、満足度が下がる要因になることがあります。
DX・環境配慮への対応が困難
社会全体ではDXやペーパーレス化、環境配慮が求められるようになっています。そうした流れのなかで、紙のギフト券や現物商品はこれまで多くの場面で役立ってきた一方、管理や配送といった面で課題が目立つようになってきました。
また、ECの拡大やライフスタイルの多様化により、ギフトの受け取り方や使い方にも変化が見られます。宅配便の取扱量が増加するなかで再配達による負担や環境への影響が社会課題となっていることもあり、よりスマートで持続可能な方法への期待が高まっています。
デジタルギフトへの切り替えメリット
紙のギフト券や現物商品が抱える課題を解消する手段として注目されているのが「デジタルギフト」です。主なメリットは以下の通りです。
即時性が高い
管理負担を軽減できる
受け取り手の自由度が高い
環境に配慮できるサステナブルな選択
即時性が高い
デジタルギフトは、メールやシステムを使ってすぐに贈ることができます。配送のタイムラグがないため、イベント当日やキャンペーンの締め切り直後など、「今すぐ贈りたい」というタイミングを逃しません。
紙のギフト券や現物商品を郵送する場合は、封入・発送・到着までに数日かかってしまいます。その間に熱が冷めてしまったり、受け取りのタイミングを逃したりすることも。 一方で、デジタルギフトならその場で即時に届けられるため、サプライズや感謝の気持ちもリアルタイムで伝えることができます。
管理負担を軽減できる
デジタルギフトは、在庫の保管や郵送の手配、住所情報の収集といった作業が不要です。住所情報の収集も必要なく、個人情報の取り扱いを最小限に抑えられるため、セキュリティ面でも安心です。
また、数量の変更や宛先の修正などにも柔軟に対応できるため、「間違って多く発注してしまった」「名前の入力ミスで届かなかった」といったトラブルも起こりにくくなります。
紙のギフト券や現物商品では、どうしても人手による管理やチェックが多くなりがちですが、デジタルギフトならすべてオンラインで完結。結果、全体の管理工数を大幅に削減することができます。
受け取り手の自由度が高い
選べるタイプのデジタルギフトであれば、受け取った人が自分の好みやライフスタイルに合った商品やサービスを自由に選ぶことができます。 「何が届くか分からない」受け身のギフトではなく、「自分で選べる楽しさ」がある点が、大きな魅力です。
たとえば、食べ物が好きな方はグルメ系を、忙しい方は日用品やデジタルサービスを選ぶなど、贈る側がすべてを決めるのではなく、受け取り手の自由を尊重した設計ができます。
この「自分に合ったものを選べる」という体験自体が、ギフトを受け取る喜びをより深いものにしてくれます。
環境に配慮できるサステナブルな選択
デジタルギフトは、紙や梱包資材を使わずに贈れる環境にやさしいギフトです。印刷や封入、郵送といった物理的な工程が不要なため、資源の使用を抑えられるだけでなく、CO₂排出の削減や再配達の回避にもつながります。
とくに最近では、企業活動におけるサステナビリティの意識が高まっており、環境配慮は無視できないテーマになっています。 その点、デジタルギフトは「贈ること」と「環境配慮」の両立を実現できる選択肢として、多くの企業に注目されています。
事例で見るデジタルギフト活用の広がり
配送や在庫管理の負担は、紙の金券だけでなく、ボールペンやオリジナルグッズといったモノのノベルティでも共通する課題です。ここでは、従来の手法からデジタルギフトに切り替えた企業の事例をご紹介します。
幅広い世代に喜ばれる福利厚生を実現
目的 | ・幅広い世代に喜ばれる福利厚生を実現したい ・在庫管理や発送作業などの事務局負担を軽減したい |
|---|---|
課題 | ・幅広い世代に喜ばれるギフトを検討していた ・紙のギフト券の場合には盗難や紛失対策を行う必要があり、管理方法が煩雑だった |
成果 | ・「便利に使える」「好きなサービスに交換できる」など幅広い世代から喜ばれた |
全国の会員に向けて福利厚生制度を提供する一般社団法人リブドゥ共済会様では、新規入会キャンペーンのインセンティブや誕生日ギフトとして「giftee Box」を導入。
もともとは紙のギフト券も検討されていましたが、「管理のしやすさ」や「利用者の多様なニーズへの対応力」を重視し、デジタルギフトの導入を決定されました。
▼この事例の詳細はこちら
幅広い世代に喜ばれる福利厚生制度を目指し、ギフトラインナップが豊富な「giftee Box」を採用
展示会ノベルティをデジタルギフトに切り替え
目的 | ・WEB会員登録とアンケート回答の促進 |
|---|---|
課題 | ・使用先が限られたギフトを配布していたため、ユーザーの多様な好みに対応しきれないことがあった ・ギフトの配布数が想定を下回ってしまった場合のコストを減らしたかった |
成果 | ・「giftee Box」にはコンビニやECサイトなど使えるギフトが豊富なため、ユーザーから好評を博した |
工作機械や切削工具の展示会「メカトロテックジャパン2023(MECT2023)」にて、WEB会員登録とアンケート回答を促す施策として「giftee Box」を活用。来場者特典として、その場で使えるデジタルギフトを配布する形に切り替え、従来の物理ノベルティからの転換を図りました。
▼この事例の詳細はこちら
展示会でのWEB会員登録促進にデジタルギフトを活用し、ノベルティの在庫管理の煩雑さを解消
会員ポイント交換を即時化し、満足度を向上
目的 | ・会員サービスの拡充 |
|---|---|
課題 | ・少額のポイントで交換できる商品の選択肢が少ない ・商品交換から商品到着までに時間がかかる ・商品ラインナップの確保やオペレーションに手間を感じていた |
成果 | ・お客様への商品送付に2週間程度かかっていたのが、即時で送付できるようになった |
北海道ガス株式会社様が運営する会員サイト「TagTag」内でのポイント交換施策の利便性向上を目的に、デジタルギフトを導入。API連携により、ポイント交換確定後すぐにギフトをメールで送付できる仕組みを構築しました。
▼この事例の詳細はこちら
ポイントサイトとAPI連携させ、リアルタイムにギフトを送付。運用コストを下げつつ、お客様満足度の向上につなげる
ギフト業務の手間を減らし、喜ばれる形へ
紙のギフト券や現物商品は長年にわたり活用されてきましたが、業務効率化・DX・環境配慮の流れのなかで、その課題が顕在化しています。
対してデジタルギフトは、業務の効率化と利用体験の向上を両立できる新しい選択肢として、福利厚生や販促など多くの現場で導入が進んでいます。
実際の導入担当者からは「もっと早く切り替えればよかった」という声も。 手間を減らし、受け取る人に喜ばれる体験を届けるーーその両立を叶える手段として、デジタルギフトが選ばれています。
ギフト施策を「手間なく喜ばれる」かたちへ
まずはオンライン相談で、運用の見直しから始めてみませんか?
紙のギフトやノベルティに手間がかかりすぎている、満足度が思うように上がらない—— そんなお悩みをお持ちの企業様が、いまデジタルギフトに切り替えはじめています。
「使いやすいと社員から好評だった」 「発送や在庫の管理が不要になり、工数が大幅に削減できた」 など、導入企業様からは嬉しいお声も多数。
業務効率化と、もらって嬉しい体験の両立。 その第一歩として、ぜひオンラインでお気軽にご相談ください。