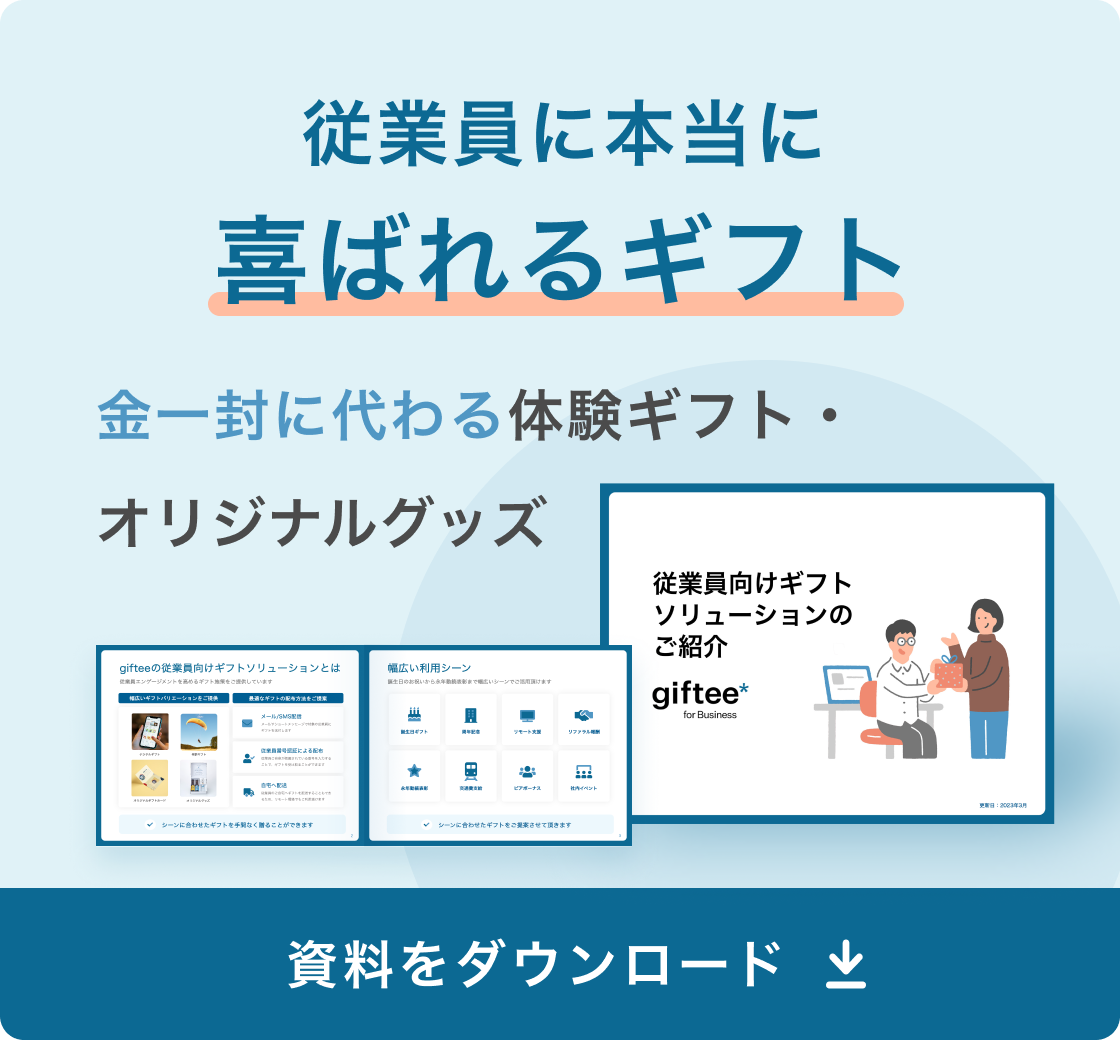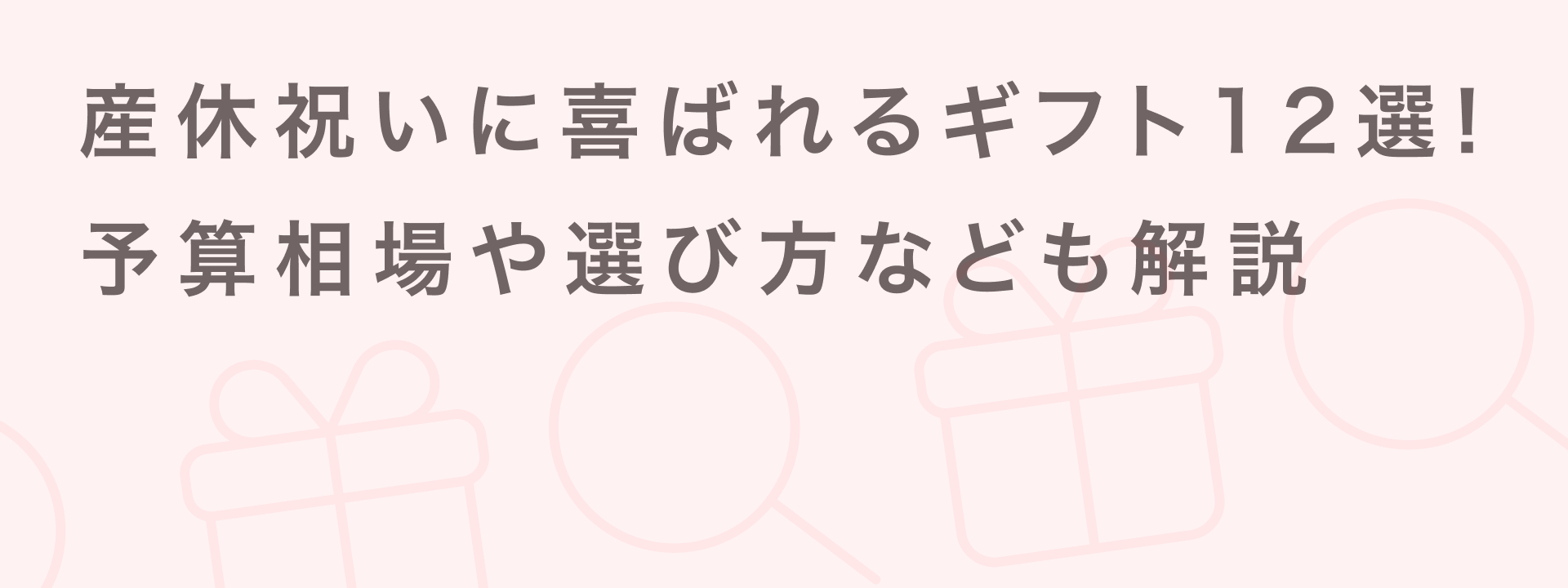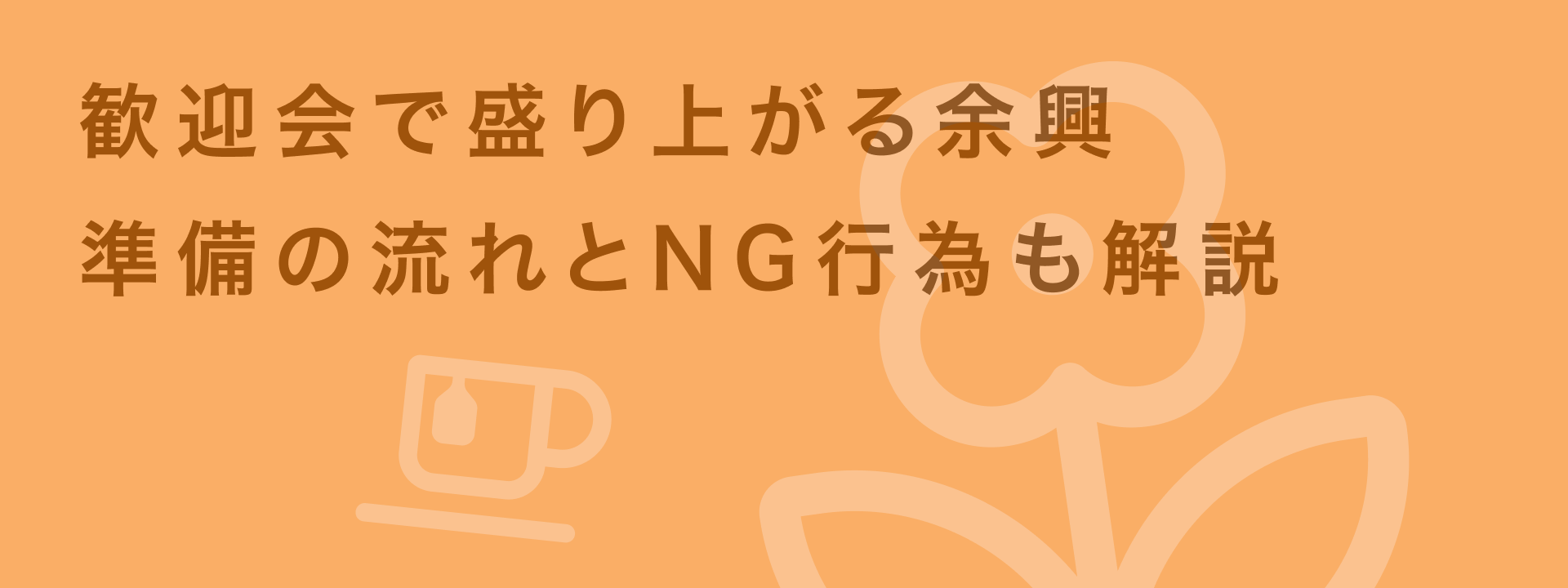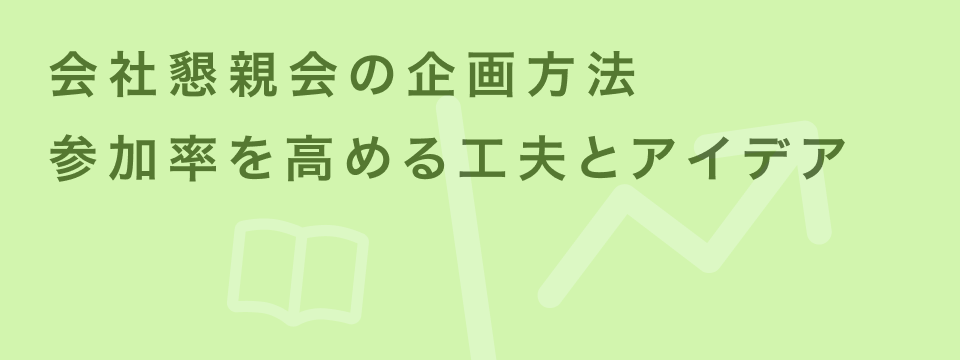会社スポーツ大会におすすめの種目12選|参加率を高める種目選定と運営のコツ
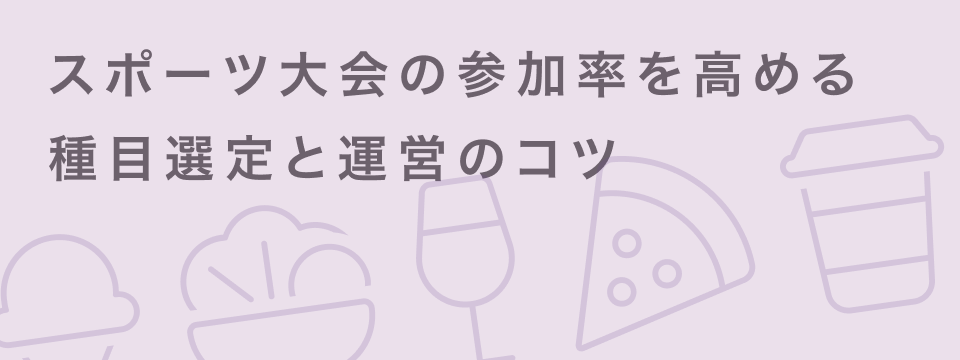
社内のスポーツ大会は、部署や世代を超えた交流を生み、チームワークや一体感を育む貴重な機会です。
一方で、企画担当者のなかには「参加してもらえるだろうか」「景品の準備が大変そう」「ケガをしたらどうしよう」と不安を抱く方も少なくありません。
本記事では、会社でのスポーツ大会を成功に導くための準備・運営・事後フォローのポイントをわかりやすく解説。参加率を高める工夫や盛り上がる競技の選び方、景品設計のコツ、労災・保険の基礎知識まで、実務に役立つ情報をまとめています。初めて企画を担当される方などは、ぜひ最後までご覧ください。
社員に喜ばれる景品を準備したいけれど、手間はかけられない…
そんな総務・人事ご担当者の声にお応えするのが、ギフティのデジタルギフトのサービスです。 用途や予算をお伝えいただくだけで、最適なギフトをセレクトしてご提案します。
さらに、ギフトの手配から配布方法の設計まで、すべてをワンストップで対応可能です。 煩雑になりがちな景品準備の工数を大幅に削減できるので、イベントの企画や当日の進行といった“本来注力すべき業務”に時間を使えるようになります。
まずは、デジタルギフトの基本や活用のポイントがわかる「デジタルギフト簡単ガイド」をご覧ください。
会社でスポーツ大会を開催する効果とは?
社内スポーツ大会は、単なるレクリエーションではなく、組織の活性化や定着率向上にもつながる重要な社内イベントです。
部署や役職を超えた交流が信頼関係を生み、チームワークや一体感の醸成にも寄与します。社員が会社への愛着を深めるきっかけとなり、健康づくりやモチベーション向上にもつながるでしょう。
ここでは、主な効果を3つ紹介します。
社員エンゲージメントと帰属意識の向上
競技では、普段あまり接点のない仲間とも声を掛け合い、協力し合う場面が生まれます。自分の行動がチームの成果につながる体験は、会社への信頼や誇りを育て、前向きな姿勢を引き出すでしょう。
スポーツ大会のような社内イベントは、「会社に大切にされている」と感じられる機会となり、モチベーションや帰属意識の向上が期待できます。
チームワーク強化と組織の一体感醸成
力を合わせて競技に取り組む経験は、チームワークの大切さを再確認する好機です。
勝敗よりも、互いに声を掛け合いながら目標を目指す過程にこそ、協力する喜びがあります。その体験は、日常業務でも助け合える関係や、前向きに挑戦できる雰囲気を生み出すきっかけになるでしょう。
役職や年齢を超えてフラットに関わることで、普段の上下関係とは異なるつながりも生まれます。立場にとらわれず意見を交わせる環境は、心理的安全性の向上と風通しのよい企業文化の形成につながります。
その積み重ねが、組織全体の一体感を強める力となるでしょう。
健康経営の推進と離職率低下への貢献
従業員に運動の機会を提供すると、健康意識が高まり、生活習慣の改善にも結びつきます。
経済産業省が推進する健康経営の観点からも、社内スポーツ大会は効果的な施策です。
健康経営優良法人の認定では、従業員の健康支援が評価対象となるため、社内スポーツ大会は取り組みの一例として位置づけられます。
心身のリフレッシュはメンタルヘルスや職場満足度の向上にも寄与し、結果として離職率の低下にもつながるでしょう。
参加率を高める5つの工夫と「嫌がられない」設計
社内スポーツ大会を成功させるには、社員が気持ちよく参加できる環境を整えることが欠かせません。どれほど内容が充実していても、参加者が少なければ交流の効果は十分に発揮されないでしょう。
参加のハードルを下げ、自然に盛り上がる大会を実現するための工夫を5つ紹介します。
1. 参加者が嫌がる理由を知る
社内スポーツ大会の参加率が伸びない背景には、いくつかの理由があります。
たとえば、「運動が苦手で恥ずかしい思いをしたくない」「休日の参加が負担」「強制されるのが嫌」「勝敗でプレッシャーを感じる」など、心理的な抵抗感です。
こうした不安を取り除かない限り、どれほど内容を工夫しても参加率の向上は期待できないでしょう。
まずは社員がなぜ参加をためらうのかを理解し、安心して参加できる雰囲気を整えることが大切です。
2. 任意参加を基本にし、魅力的なインセンティブで意欲を高める
参加を強制すると不満や反発を招き、イベント全体の雰囲気が悪くなるおそれがあります。
そのため、まずは任意参加を基本にし、社員が「出てみたい」と思える工夫を取り入れましょう。
たとえば、豪華な景品や多彩な表彰制度を設けるのも効果的です。優勝チームだけでなく、敢闘賞やチームワーク賞、ベストパフォーマンス賞など、さまざまな角度から称賛できる仕組みにすれば、より多くの社員が達成感を得られます。
楽しみながら挑戦できる環境づくりが、意欲を引き出すポイントです。
3. 運動レベルに配慮した種目選定
運動が得意な人だけが活躍できる種目ばかりでは、参加のハードルが高くなります。誰もが気軽に参加できる内容にしましょう。
たとえば、ドッジボールや玉入れのように、ルールがシンプルで特別な技術を必要としない競技は、運動経験に関係なく楽しめます。
また、チーム対抗形式にすれば個人へのプレッシャーが分散され、協力し合うなかで自然と盛り上がる雰囲気が生まれます。
4. 事前アンケートでニーズを把握する
社員が「参加したい」と思える企画にするには、事前の意見収集が欠かせません。
やってみたい競技や参加しやすい曜日・時間帯、欲しい景品などをアンケートで確認し、その結果を企画に反映するとよいでしょう。
「社員の声をもとに内容を決めました」と社内告知で伝えれば、自分たちの意見が反映されている実感が生まれ、参加への意欲もいっそう高まります。
5. 応援・サポート役など多様な参加形態を用意する
全員が競技に出る必要はありません。
応援や撮影係、審判やタイムキーパーなど、体を動かさずに関われる役割を設けると、より多くの社員が参加しやすい環境をつくれます。
目安として、全社員の50%以上が関われる体制を目標にしましょう。無理に全員参加を求めるよりも、自然と関わりたくなる雰囲気をつくることが大切です。
強制ではなく、参加したくなる魅力で引きつける設計こそが、結果的に高い参加率を生み出します。
会社のスポーツ大会におすすめの種目12選
参加者全員が楽しめる社内スポーツ大会にするためには、種目選びがポイントです。ここでは、屋内・屋外・運動が苦手な人向けの3つのカテゴリに分けて、おすすめの12種目を一覧にまとめました。
会場や参加者の特徴に合わせて柔軟に組み合わせれば、誰もが無理なく楽しめる大会を企画できます。
種目名 | カテゴリ | 難易度 | おすすめ人数 |
|---|---|---|---|
ドッジボール | 屋内 | 低 | 10〜20名 |
バドミントン | 屋内 | 低〜中 | 4〜8名 |
綱引き | 屋内 | 低 | 10〜30名 |
玉入れ | 屋内 | 低 | 10〜20名 |
ソフトボール | 屋外 | 中 | 10〜20名 |
サッカー | 屋外 | 中 | 10〜20名 |
リレー | 屋外 | 低〜中 | 8〜40名 |
障害物競走 | 屋外 | 低 | 5〜30名 |
大縄跳び | 屋外 | 低 | 8〜15名 |
ボウリング | 運動苦手向け | 低 | 3〜6名 |
ダーツ | 運動苦手向け | 低 | 2〜8名 |
チーム対抗クイズ | 運動苦手向け | 低 | 4〜30名 |
屋内種目なら天候を気にせず実施でき、屋外は開放感が魅力です。
運動が得意でない社員も参加しやすい種目を織り交ぜると、全体の参加率が上がります。
労災・保険の扱い方と事故発生時の対応
社内スポーツ大会では、転倒や接触によるケガなど、思わぬトラブルが発生する可能性があります。
安全に開催するためには、労災保険の適用範囲や、加入が必要な保険の種類を事前に把握しておくことが大切です。
労災保険の適用範囲
労災保険が適用されるかどうかは、開催の形態や参加の性質によって異なります。
業務時間内に会社の指示のもとで実施される場合は、労災保険が適用されるケースが多いでしょう。一方で、休日や業務時間外に行う任意参加のイベントは、原則として労災保険の対象外です。別の保険で補償できるよう備えておくと安心感が高まります。
企業が加入すべき保険
休日や時間外に開催する場合は、レクリエーション保険や傷害保険への加入を検討しましょう。これらの保険は、参加者全員を対象に、ケガや事故による治療費などを補償するものです。保険料は参加人数や内容によって異なりますが、一般的な保険料と比べ低コストで加入できるのが特徴です。
加入前に複数社の補償内容を確認し、最適なプランを選ぶとより納得して進められます。
事故発生時の対応フロー
万が一事故が起きた場合は、まず応急処置を行い、必要に応じて医療機関へ搬送します。軽傷に見えても、念のため医師の診察を受けるよう促しましょう。
次に、事故報告書を作成し、発生時の状況や対応内容を記録します。その上で、保険請求に必要な書類を整え、速やかに保険会社へ連絡します。
再発防止のためには、原因を分析し、改善策を共有しておくことも重要です。
こうした取り組みを積み重ねることで、社員が安心して参加できる大会運営につながります。
企画から実施までの流れ

社内スポーツ大会を成功させるには、企画段階から当日運営、事後フォローまでの全体像を把握し、計画的に進めることが重要です。ここでは、各フェーズで押さえるべきポイントを時系列で解説します。
企画フェーズ(3〜6か月前)
開催の目的・予算の決定
役割分担
日時と会場の決定
初めに、大会を開く目的を明確にしましょう。
社員同士の交流、チームビルディング、健康促進など、目的によって競技内容や運営方針は変わります。方向性を定めておけば、その後の準備がスムーズです。
続いて、会場費・景品費・保険料・レンタル費など、必要な経費を洗い出し、予算を確保します。限られた予算内で進める場合は、優先順位をつけて調整すると効率的です。
準備を一人で抱えるのは大きな負担になるため、複数名で実行委員会を結成します。総括責任者、競技担当、広報担当、景品担当などの役割を分担しましょう。担当を明確にすれば、作業の抜け漏れを防ぎ、全体を円滑に進められます。
最後に、日程と会場を決定します。参加率を高めるには、アクセスしやすい会場と、社員が参加しやすい日程を選ぶことが大切です。業務時間内の開催を検討すれば、より参加しやすい雰囲気をつくれます。
会場の予約は早めに行い、キャンセルポリシーも事前に確認しておきましょう。
準備フェーズ(1〜3か月前)
社内スポーツ大会の開催に向けて、ここからは具体的な準備を進める段階です。開催当日までに行う主な準備は、次の6項目です。
種目の決定
備品のリストアップ
チーム編成
保険の加入
インセンティブの準備
社内告知
事前アンケートで社員の意見を取り入れながら、種目を決定し、必要な備品をリストアップします。
チーム編成は部署をまたいで行うと、自然な交流が生まれやすくなります。運動経験者の偏りを避け、どのチームも平等に楽しめるよう配慮しましょう。
保険の手続きは、開催日の数週間前までに完了させておくのが安心です。特にレクリエーション保険などは申し込み期限が早い場合があるため、余裕を持って対応しましょう。
景品にはデジタルギフトを活用すると、準備の手間を減らせます。表彰枠ごとに内容を設定すれば、社員のモチベーション向上にもつながります。
社内告知では、メールやポスター、イントラネットなど複数のチャネルを活用します。任意参加であることと、参加方法を明確に伝えることで、誰もが気軽に参加できる雰囲気をつくれます。
当日運営
当日は、あらかじめ作成したタイムテーブルに沿って進行します。
開会式や各競技、表彰式などの時間配分を明確にし、受付や審判などの役割もあらかじめ決めておくと、運営を円滑に進められます。
開会式では、大会の目的やルールを共有し、安全に参加できる雰囲気を整えましょう。競技中は、スタッフ同士の連携を意識し、トラブルやタイムロスを防ぐことも大切です。閉会式では、感謝の言葉とともに表彰式を行い、温かい空気のなかで大会を締めくくります。
事後フォロー
イベント終了後は、参加者アンケートを実施し、満足度や改善点を把握します。結果を集計・数値化して経営層や関係部署へ共有すれば、次回の予算確保や協力体制の強化につながります。
また、振り返りミーティングを行い、良かった点や課題を整理しましょう。得られたノウハウを共有することで、次回の運営をさらにスムーズに進められます。
よくある質問(FAQ)
Q. 会社スポーツ大会の予算はどのくらい?
予算には、会場費、備品レンタル費、景品代、保険料、飲食代などが含まれます。規模や開催場所によって大きく変動するため、まずは必須項目から見積もりを出し、優先順位をつけて調整するとよいでしょう。
外部の会場を借りる場合は施設利用料が大きな割合を占めますが、社内スペースや近隣の公園を活用すれば、コストを抑えることも可能です。
Q. 外部のイベント会社に依頼すべき?
初めて開催する場合や、担当者の負担を軽減したい場合は、外部のイベント会社への依頼を検討する価値があります。
イベント会社を利用するメリットは、企画立案から当日運営まで一括で任せられる点です。経験豊富なスタッフがサポートしてくれるため、トラブル対応もスムーズになります。
一方、費用は自社運営よりも高くなる傾向があります。予算に余裕がない場合は、備品レンタルや会場手配など、一部の業務だけを外注する方法もあります。
まとめ|成功の鍵は「参加者視点の設計」と「効率的な運営」
社内スポーツ大会を成功させるには、社員が楽しめる内容と、スムーズな運営体制の両立が欠かせません。
強制ではなく、誰もが関われる仕組みを整えることが高い参加率につながります。
インセンティブやデジタルギフトを取り入れれば、準備の負担を減らしつつモチベーションを高められます。また、事前アンケートや安全対策を取り入れて、安心して参加できる環境を整えましょう。
そして何より、社員が「楽しかった」「また参加したい」と感じる時間をつくることが大切です。その一体感こそが、社内スポーツ大会成功の最大の証といえます。
得た知見を次回に活かし、より魅力的なイベントづくりにつなげましょう。