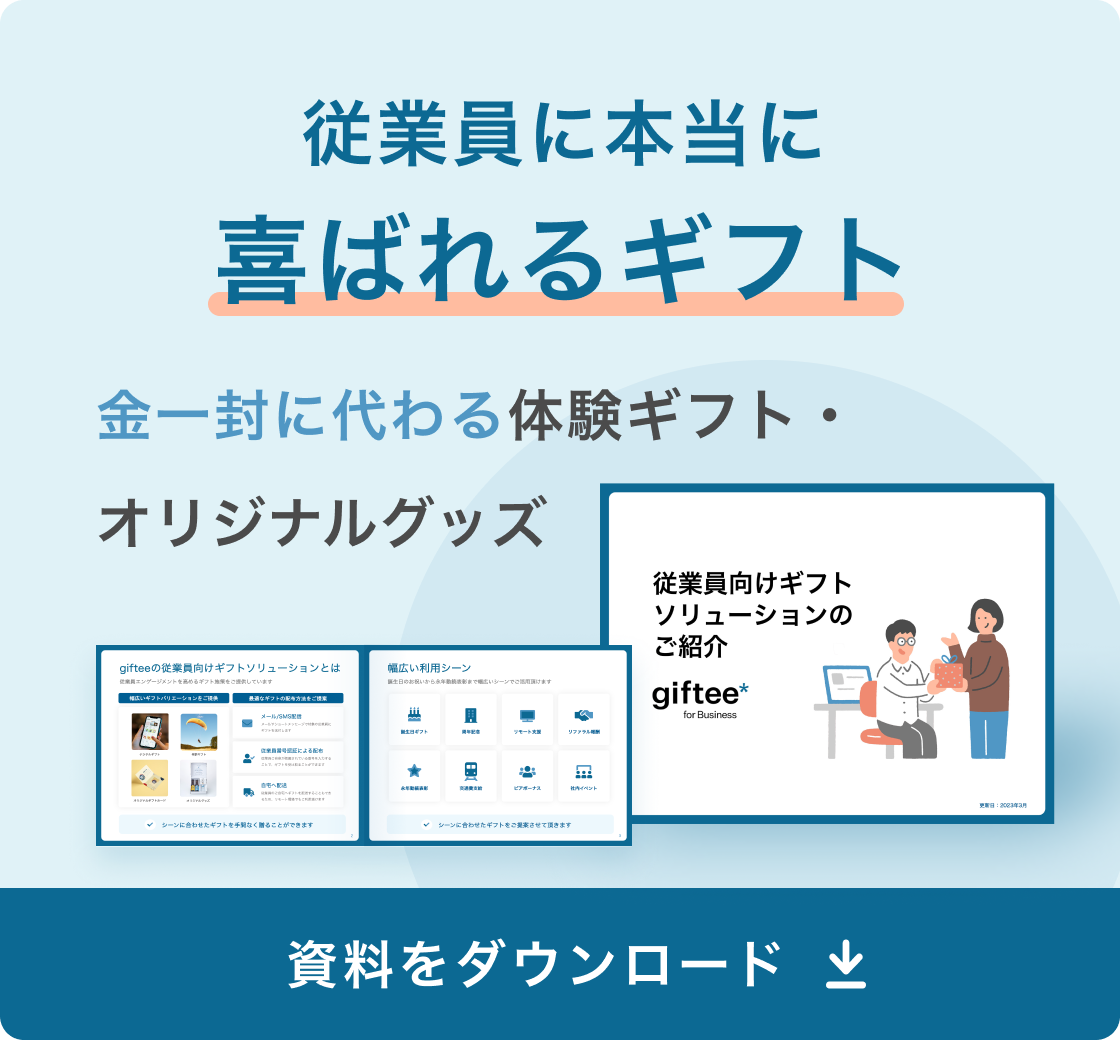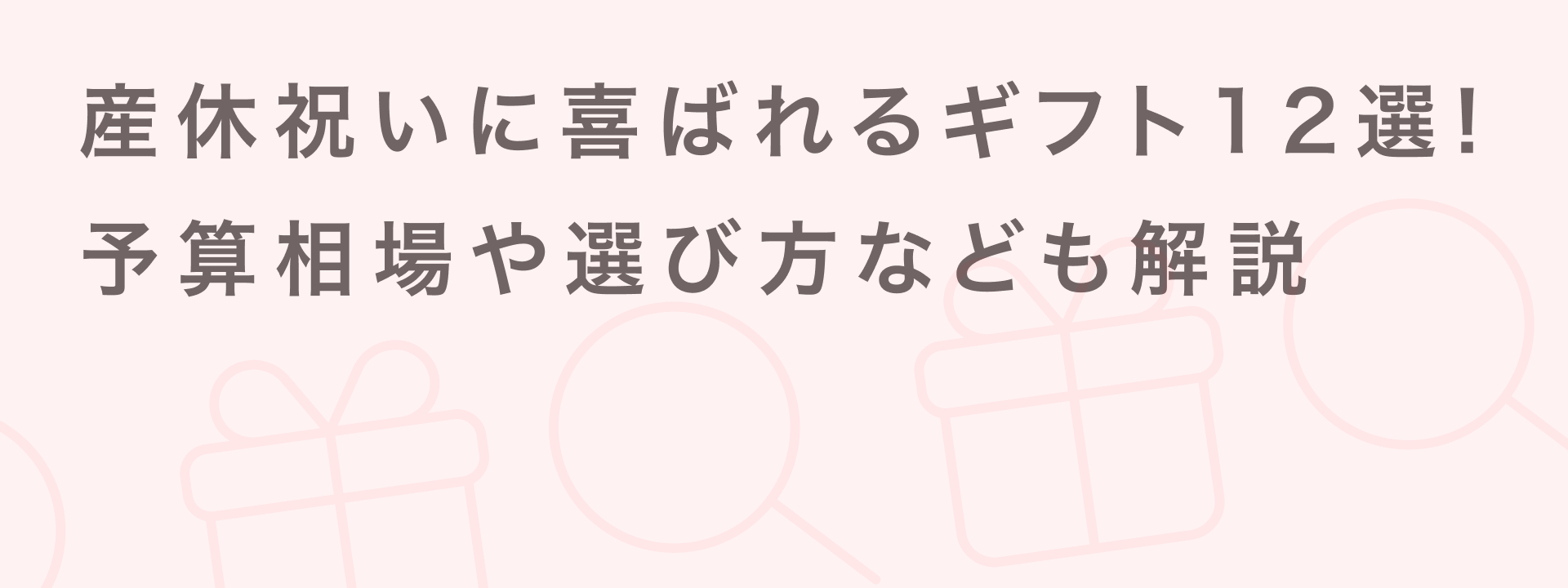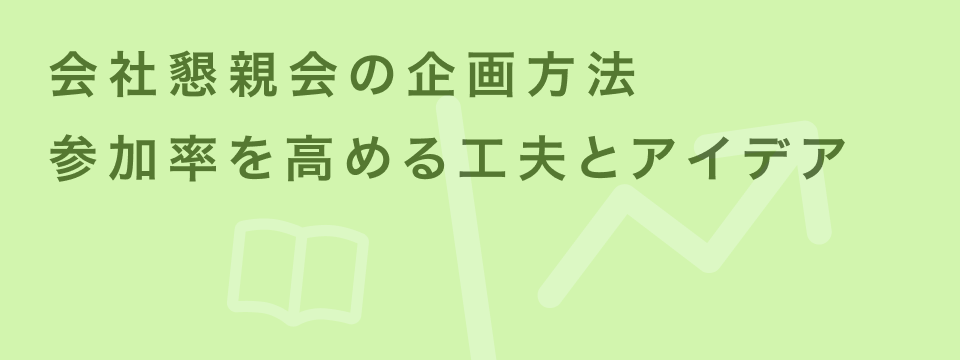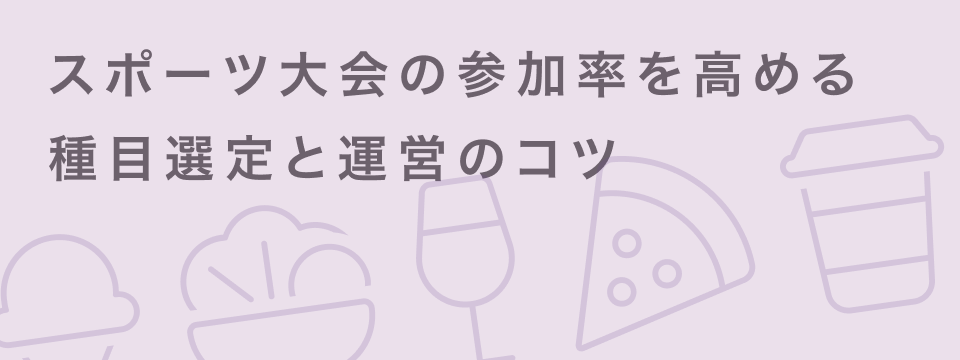歓迎会で盛り上がる余興15選|準備の流れとNG行為も解説
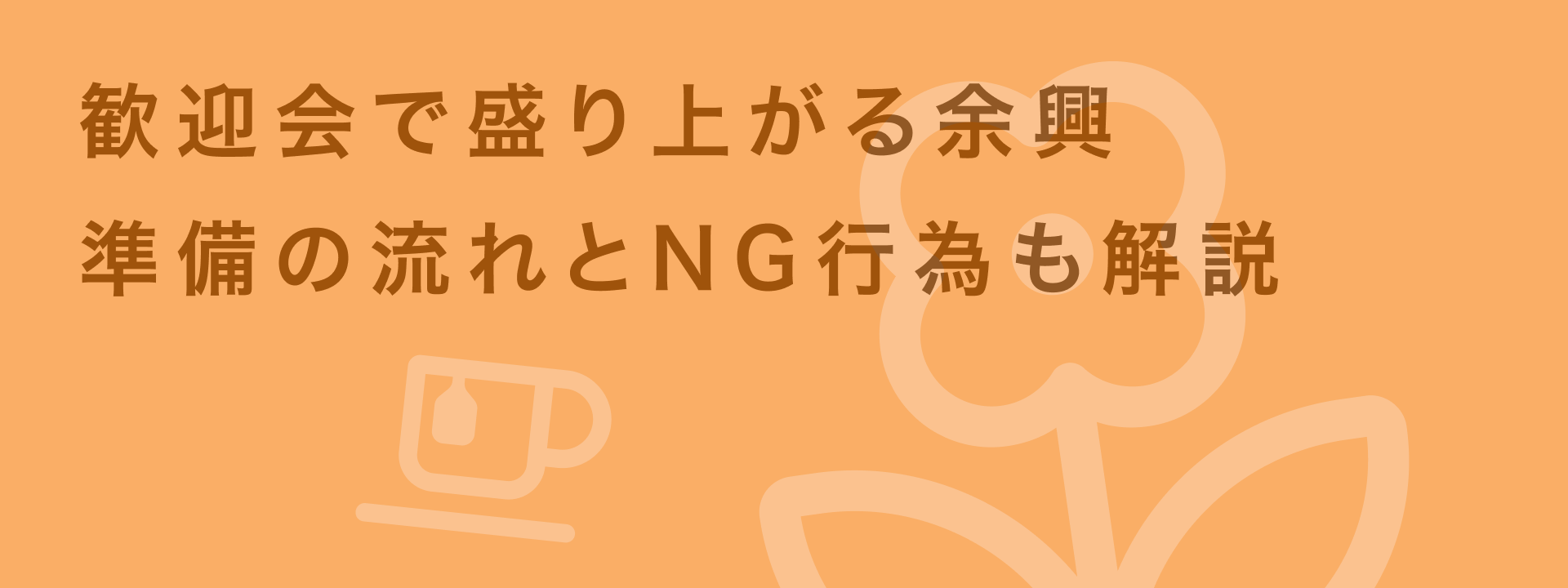
新入社員が最初に体験する社内イベントの一つが、歓迎会です。しかし、企画担当者にとって、新入社員が気兼ねなく参加できる雰囲気をつくるのは簡単ではありません。上下関係や立場の違いに配慮しつつ、全員が心地よく過ごせる場づくりに悩む方も多いでしょう。
本記事では、ハラスメントに配慮しながら、新入社員と既存社員が自然に打ち解ける歓迎会づくりのコツをわかりやすく整理しました。成功のための3つの基本原則、準備の流れ、すぐに活用できる余興アイデア15選を実務目線でまとめています。この記事を参考に、新入社員に「この会社に入って良かった」と感じてもらえる歓迎会を企画しましょう。
社員に喜ばれる景品を準備したいけれど、手間はかけられない…
そんな総務・人事ご担当者の声にお応えするのが、ギフティのデジタルギフトのサービスです。 用途や予算をお伝えいただくだけで、最適なギフトをセレクトしてご提案します。
さらに、ギフトの手配から配布方法の設計まで、すべてをワンストップで対応可能です。 煩雑になりがちな景品準備の工数を大幅に削減できるので、イベントの企画や当日の進行といった“本来注力すべき業務”に時間を使えるようになります。
まずは、デジタルギフトの基本や活用のポイントがわかる「デジタルギフト簡単ガイド」をご覧ください。
歓迎会で余興を成功させる3つの基本原則
歓迎会の盛り上がりを左右するのは、余興の内容だけではありません。何を意識して準備するかによって、参加者が楽しめるかどうかが変わってきます。
ここでは、歓迎会を成功に導くために意識しておきたい3つの基本を紹介します。
全員が参加できるシンプルさ
余興は、ルールが簡単で誰でも気軽に参加できるものを選びましょう。
複雑なルールや特定のスキルが必要な内容では、一部の人しか楽しめず、新入社員が居づらさを感じてしまいます。初めて聞く人でもすぐ理解でき、特別な準備や経験を必要としない内容が理想的です。
たとえば、ビンゴ大会やジェスチャーゲームなど、誰もが楽しめるシンプルなゲームがおすすめです。
また、全員が参加できる形式にすれば、会場全体に一体感が生まれます。見ているだけの人をつくらないように、自己紹介を兼ねた質問タイムや、チーム対抗のクイズ大会など、全員が自然に関われる仕掛けを意識しましょう。
新入社員の心理的安全性を最優先
歓迎会の主役は新入社員です。主役が不安なく参加できるよう、心理的安全性を保つ配慮が欠かせません。
初対面の上司や先輩の前では、誰でも緊張するものです。新入社員がプレッシャーを感じてしまうと、その後の関係づくりに悪影響を及ぼすおそれがあります。
強制的な参加や恥ずかしい思いをさせるような余興は避けましょう。特に、一発芸やお酒の一気飲みなどは、ハラスメントとみなされる可能性があります。
代わりに、新入社員が自己紹介できるアイスブレイクや、先輩が新入社員を紹介する他己紹介形式がおすすめです。
新入社員が「この職場は安心できる」と感じられる雰囲気づくりは、信頼関係の第一歩です。長く働きたいと思える職場づくりにもつながるでしょう。
準備の手間と盛り上がりのバランス
仕事と並行して行う余興の準備は、担当者にとっては大きな負担です。業務の合間に進行を考えたり、備品を手配したりするのは想像以上に手間がかかります。
準備に時間をかけすぎると本業に支障が出る一方で、十分な準備がないまま当日を迎えれば進行が滞り、参加者の満足度が下がってしまいます。
準備に時間をかけなくても盛り上がる余興を選ぶことが大切です。
たとえば、ビンゴゲームなら事前にカードと景品を用意するだけで簡単に楽しめます。会社にまつわるクイズも、質問をまとめておけば当日の進行がスムーズです。
準備の手間を減らしたい場合は、外部サービスやデジタルツールの活用も検討しましょう。オンラインビンゴやクイズアプリを使えば、モノを用意する必要がなく、ハイブリッド開催にも対応できます。
さらに、景品をデジタルギフトにすれば、当日にすぐ配布できて幹事の負担も減るのでおすすめです。
【ステップ別】歓迎会の準備の流れ

直前になって慌てないよう、段階的に準備を進めることが大切です。計画的に進めれば、担当者の負担を減らし、スムーズに運営できます。
ここでは、歓迎会の1か月前から当日までの準備の流れを時系列で整理し、各時期に行うべき内容を解説します。
1か月前にやること
歓迎会の準備は、開催日の1か月前から始めましょう。早めに全体の流れや方針を固めておけば、スケジュール調整や備品の手配を円滑に進められます。
具体的には、次のような項目を順に決めていきます。
日程、会場、予算の決定
会場の予約
余興の決定
まず、日程や会場、予算などの骨組みを決めます。
日程が決まったら、参加予定の人数や予算のバランスを考慮して会場を予約しましょう。会場の広さや、多少盛り上がっても問題ない環境かどうかの確認も大切です。オンライン参加の希望がある場合は、ハイブリッド開催にも対応できるよう整える必要があります。
次に、余興の大まかな内容を決定します。
全員参加のシンプルなゲームにするのか、パフォーマンスを取り入れるのかなど、会社の雰囲気や参加者の年代に合わせて選ぶとよいでしょう。
準備に必要な物や協力者も、この段階でリストアップしておくと後で慌てずに済みます。
さらに、新入社員に事前に話を聞いておくことも大切です。
趣味や出身地などを把握しておけば、自己紹介タイムやクイズの内容を充実させられます。当日の会話も弾みやすくなるでしょう。
2週間前にやること
2週間前になったら、余興や進行の具体的な準備を進めます。細かい部分を整理しておけば、当日の混乱を防ぐのに役立ちます。
具体的には、次のような項目を進めます。
余興の詳細を決定、進行表の作成
景品の手配
司会進行役の決定
まず、余興の内容を決定してから進行表を作成します。進行表には、各プログラムの開始時間・所要時間・担当者・準備物を明記しておきましょう。
たとえば、乾杯後に自己紹介タイム(15分)、ビンゴ大会(20分)、チーム対抗クイズ(15分)という形で構成すると、全体の流れを把握しやすくなります。
余興全体は、30分〜1時間程度に収めるのが目安です。
景品の準備もこの時期に進めましょう。ビンゴやクイズの景品は、世代を問わず喜ばれるアイテムを選ぶのがポイントです。買い出しの時間が取れない場合は、オンラインで完結するデジタルギフトを活用しましょう。URLや二次元コードを共有するだけで配布できるため、担当者の負担を大幅に減らせます。
また、司会進行役を決め、事前に台本を共有しておくことも大切です。司会者が流れを把握していれば、自然な進行ができ、突発的なトラブルにも落ち着いて対応できます。
1週間前にやること
1週間前は、最終チェックとリハーサルの時期です。準備が整っているか、進行がスムーズに行えるかを事前に確認しておきましょう。
具体的には、次のような項目を進めます。
参加者の最終人数の確認
準備物の最終チェック
司会者とのリハーサル
まず、参加者の最終人数を確認します。飲食店で開催する場合は、人数変更の締切日を守って調整しましょう。
オンライン参加がある場合は、使用する会議ツールのアクセス情報を事前に共有し、接続テストを行っておくと安心です。
次に、余興で使用する道具や資料を揃えます。
ビンゴカードやクイズの問題リスト、景品やマイク、スピーカーなど必要なものはリスト化してチェックしましょう。デジタルツールを使う場合は、ネット環境や機材の動作確認も忘れずに行います。
時間に余裕があれば、司会者と簡単なリハーサルを実施します。進行表に沿って流れを確認し、時間配分や内容に問題があれば調整しましょう。
この段階で細かい部分まで確認しておけば、進行や内容の微調整にも十分対応できます。
当日にやること
いよいよ開催日です。開始前に最終確認を行い、スムーズに進行できるよう整えましょう。開催後のフォローも忘れずに行います。
当日に実施する主な内容は、次のとおりです。
会場設営と最終チェック
新入社員や司会進行役への声掛け
終了後のフォロー
会場には早めに到着し、テーブルの配置や音響設備、プロジェクターなどを確認します。特に機材は、不具合があった場合でもすぐ対応できるよう、余裕を持ってチェックしておくと安心です。
余興で使う道具や景品は手に取りやすい場所に置き、スムーズに進行できる環境を整えましょう。
次に、司会者と最終の打ち合わせを行います。進行表を見ながら時間配分や開始タイミングを確認し、互いの役割をすり合わせておきましょう。
新入社員が会場に到着したら、緊張をほぐす声掛けをして、余興の流れを簡単に伝えておくと安心感を高められます。
余興中は、全体の雰囲気や参加者の様子を観察します。
盛り上がりが足りないと感じたら、司会者がコメントで場を温めたり、短時間のミニゲームを追加したりして柔軟に対応しましょう。状況に応じて流れを微調整できる余裕を持つことがポイントです。
終了後は、会場の忘れ物や機材の片付け状況を確認します。特に景品を用意した場合は、配布漏れや持ち帰り忘れがないよう注意しましょう。
また、新入社員に感想を聞き、次回の改善につなげます。参加者の反応や運営上の課題を記録しておくと、次回の企画に活かせます。
歓迎会で盛り上がる余興アイデア15選
歓迎会の余興は、準備にかける手間と当日の盛り上がりのバランスを考えて選ぶことが大切です。
ここでは、準備がほとんど不要ですぐにできる余興10個と、少し準備が必要な余興5個を表形式で紹介します。
準備不要ですぐできる余興(10個)
特別な準備をしなくてもすぐに始められる余興は、その場の雰囲気で気軽に楽しめるのが魅力です。
余興名 | 内容 | 所要時間 | 人数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
自己紹介プレゼン | 新入社員が3分程度で自己紹介を行う 趣味や学生時代の話、仕事への意気込みなどを共有する | 15〜20分 | 全員 | 新入社員の緊張をほぐすため、先輩社員が質問を投げかけると話しやすくなる |
他己紹介ゲーム | 先輩社員が新入社員について紹介する形式 事前にヒアリングした情報をもとに、ユーモアを交えて紹介する | 15〜20分 | 全員 | 新入社員がプレッシャーを感じにくく、先輩社員の温かさが伝わる |
新入社員への質問コーナー | 参加者が新入社員に自由に質問できる時間 趣味や休日の過ごし方など、軽い話題を中心に進行する | 10〜15分 | 全員 | 質問内容を事前にいくつか用意しておくと、沈黙を避けられる |
共通点探しゲーム | 参加者同士で共通点を探し、最も多く見つけたペアが優勝 趣味や出身地、好きな食べ物などをテーマにする | 10〜15分 | 全員 | 自然に会話が生まれ、新入社員と既存社員の距離が縮まる |
新入社員クイズ | 新入社員に関するクイズを出題 趣味や特技、出身地などを三択形式で出題し、参加者が答える | 10〜15分 | 全員 | 新入社員のことを知るきっかけになり、会話のネタが生まれる |
会社に関するクイズ | 会社の創業年や社員数、商品名などに関するクイズを三択形式で出題 全員参加型にすると盛り上がる | 10〜15分 | 全員 | 新入社員が会社のことを楽しく学べる機会になる |
ビンゴゲーム | 数字を読み上げ、ビンゴカードが揃った人から景品をもらう定番ゲーム オンラインツールを使えば準備不要 | 15〜20分 | 全員 | 景品があると盛り上がりが格段に上がる デジタルギフトを活用すれば、当日に配布できて幹事の負担も軽減される |
ジェスチャーゲーム | お題を身振り手振りで表現し、他の参加者が当てるゲーム 動物や職業、映画のタイトルなどがお題として人気 | 10〜15分 | 4〜6人チーム | 笑いが生まれやすく、場の雰囲気が一気に和む |
イントロクイズ | 曲のイントロを流し、曲名やアーティスト名を当てるクイズ スマートフォンの音楽アプリを使えば実施できる | 10〜15分 | 全員 | 幅広い年代の曲を混ぜると、全員が楽しめる |
あいこで勝ち抜きじゃんけん | 全員で一斉にじゃんけんを行い、「あいこ」を出した人だけが勝ち残るゲーム 最後まで残った人が優勝 | 5〜10分 | 全員 | ルールが単純で盛り上がりやすく、短時間で実施できる |
少し準備が必要な余興(5個)
時間に余裕がある場合は、以下の5つの余興がおすすめです。ちょっとした準備で、より特別感のある雰囲気や一体感を演出できます。
余興名 | 内容 | 準備期間 | 必要なもの | ポイント |
|---|---|---|---|---|
歓迎ムービー | 新入社員へのメッセージや職場の雰囲気を伝える動画を作成し、歓迎会で上映する | 2〜3週間 | カメラ、動画編集ソフト、プロジェクター | 先輩社員からの温かいメッセージが新入社員の心に残る |
ダンスパフォーマンス | 社員数名で流行のダンスを披露する TikTokなどで人気の簡単な振り付けを選ぶと練習しやすい | 2〜3週間 | 音響設備、スペース | 完璧を目指さず、楽しむ姿勢が大切
失敗しても笑いが生まれる |
替え歌・合唱 | 流行の曲や定番ソングの歌詞を、会社や新入社員にちなんだ内容に変えて歌う | 1〜2週間 | 音響設備、歌詞カード | 歌詞を会場のスクリーンに映すと、全員で一緒に歌えて一体感が生まれる |
チーム対抗クイズ大会 | 参加者をチームに分け、会社クイズや一般常識クイズで競う 得点制にして優勝チームに景品を贈る | 1〜2週間 | クイズの問題リスト、得点ボード、景品 | チーム対抗にすることで一体感が生まれ、新入社員と既存社員の交流が深まる。 |
お絵描き伝言ゲーム | お題を絵で伝えていくゲーム 最初の人が見たお題を次の人に絵で伝え、最後の人が答える。 | 1週間 | スケッチブック、ペン | 画力は関係なく、下手な絵ほど笑いが生まれて盛り上がる |
歓迎会の余興でやってはいけないNG行為
歓迎会の余興は、楽しければよいわけではありません。選び方を誤ると、思わぬトラブルやハラスメントの原因になることがあります。
ここでは、特に注意が必要なNG行為を3つのカテゴリーに分けて整理します。
事前に避けるべきポイントを把握し、新入社員も既存社員も心地よく楽しめる歓迎会を目指しましょう。
ハラスメントにつながる余興
相手が不快だと感じた時点で、それはハラスメントにあたる可能性があります。たとえ悪気がなくても、受け手の感じ方によっては問題となるため注意が必要です。
特に、飲酒の強要は避けましょう。一気飲みを促したり、飲酒を罰ゲームにしたりする内容は、アルコールハラスメント(アルハラ)に該当します。お酒が苦手な人や体質的に飲めない人にとって大きな負担となるだけでなく、健康被害を招くおそれもあります。
また、身体に触れるゲームや、外見・体型をネタにした演出は行わないのが適切です。肩を組んで踊ることや、相手の体に触れる仕草を含むゲームなどは、セクシュアルハラスメント(セクハラ)やパワーハラスメント(パワハラ)と見なされる可能性があります。
さらに、一発芸やカラオケの強要も控えましょう。たとえ盛り上げのつもりでも、本人にとっては大きなストレスになることがあります。希望者だけが自発的に参加できる仕組みを整え、誰もが安心して楽しめる会を目指しましょう。
特定の人に負担をかける余興
余興は、全員が楽しめることが大前提です。
特に新入社員だけに過度な負担がかかる内容は避けましょう。入社したばかりの新入社員は、まだ職場の雰囲気に慣れていません。たとえば、新入社員だけがステージに立ってパフォーマンスを披露する形式は、強い緊張やプレッシャーを与えるおそれがあります。
先輩社員と一緒に参加できる形式や、全員が気軽に楽しめるゲームを企画すれば、新入社員もリラックスして参加できるでしょう。
また、会の担当者や司会者に準備や進行の負担が集中しやすい点にも注意が必要です。
準備に時間がかかりすぎる内容や、進行が複雑な企画は避け、運営側の負担を軽減しやすい余興を取り入れるとよいでしょう。
さらに、景品はできるだけ多くの参加者に行き渡るよう配慮が大切です。一部の人だけが豪華な景品を手にすると、不公平感を生むおそれがあります。少額の景品を多めに用意したり、全員に参加賞を配ったりすれば、みんなが気持ちよく楽しめる歓迎会になります。
身内ネタ・世代間ギャップのある余興
歓迎会では、新入社員が楽しく交流できる雰囲気づくりが大切です。そのため、限られた人にしかわからない身内ネタや、世代間ギャップのある余興は避けましょう。
過去の社内イベントの話や特定部署でしか通じない話題をネタにすると、新入社員が会話に入りづらく、疎外感を覚えます。余興は、初めて参加する人でも楽しめる内容にすることがポイントです。
また、年代によって好みが分かれる音楽やクイズにも注意が必要です。
たとえば、1980年代の曲だけを使ったイントロクイズは若手社員が楽しめず、逆にZ世代の話題ばかりではベテラン社員が置いていかれます。幅広い世代が一緒に楽しめるよう、バランスを意識して企画を立てましょう。
さらに、宗教や文化に関わるテーマにも配慮が必要です。たとえば、クリスマスやハロウィンをモチーフにした内容は、信仰上の理由で参加しにくい人がいるかもしれません。
多様性を尊重し、誰もが気兼ねなく参加できる余興を選ぶことが、現代の職場にふさわしい歓迎会のあり方です。
歓迎会の余興に関するよくある質問
Q. 余興の時間はどのくらいが適切?
余興全体の時間は、30分〜1時間程度が目安です。長すぎると参加者が飽きてしまい、短すぎると盛り上がりに欠けてしまいます。
歓迎会全体の時間が2時間であれば、乾杯・挨拶(10分)→歓談(30分)→余興(30〜40分)→締めの挨拶(10分)という構成がバランスよくまとまります。余興内で複数のゲームを行う場合は、1つあたり10〜20分を目安に組み立てましょう。
Q. 景品の予算はいくらが目安?
景品の予算は、1人あたり500〜1,000円程度が一般的です。全体の景品予算は参加人数や会社の規模によって異なりますが、目安として以下を参考にしてください。
参加人数 | 景品総予算の目安 |
|---|---|
10〜20人 | 5,000〜10,000円 |
20〜50人 | 10,000〜30,000円 |
50人以上 | 30,000〜50,000円 |
景品は豪華な1等賞よりも、参加賞を含めて多くの人に行き渡るようにすると、全員が楽しめる歓迎会になります。デジタルギフトを活用すれば、少額でも喜ばれる景品を手軽に用意できます。
Q. オンライン・ハイブリッド開催でもできる余興はある?
オンラインやハイブリッド開催でも、以下の余興は問題なく実施できます。
オンラインビンゴ
クイズ大会
自己紹介・他己紹介
イントロクイズ
ポイントは、全員が同じ画面を見ながら参加できる形式を選ぶことです。身体を動かすゲームや、物理的な道具が必要な余興は避け、デジタルツールで完結できる内容を選びましょう。
Q. 新入社員に余興をさせてもいい?
新入社員に余興を強制することは避けるべきです。入社直後で職場に慣れていない新入社員にとって、人前でパフォーマンスをすることは大きなプレッシャーになります。
もし新入社員に参加してもらう場合は、以下の点に配慮しましょう。
3分程度の簡単な自己紹介程度に留める
希望者のみにする
先輩社員と一緒に参加する
歓迎会の主役は新入社員です。主役が居心地よく過ごせることを最優先に考え、企画を進めましょう。
まとめ|歓迎会の余興で大切なのは「全員が笑顔になれること」
本記事では、全員が参加しやすく心から楽しめる余興づくりの基本と、準備の流れ、すぐに実践できるアイデアを紹介しました。
大切なのは、誰もが楽しめて、新入社員が気兼ねなく参加できることです。ハラスメントにつながる行為や特定の人に負担をかける内容、世代や社内事情に偏ったネタは避け、全員が笑顔になれる企画を意識しましょう。
担当者の負担を減らすには、デジタルツールの活用も効果的です。特に景品配布にデジタルギフトを取り入れれば、買い出しや準備の手間を減らし、スムーズな運営につなげられます。
会社の文化や参加者の雰囲気に合った余興を選び、新入社員が「この会社に入って良かった」と感じられる温かい歓迎会を実現しましょう。