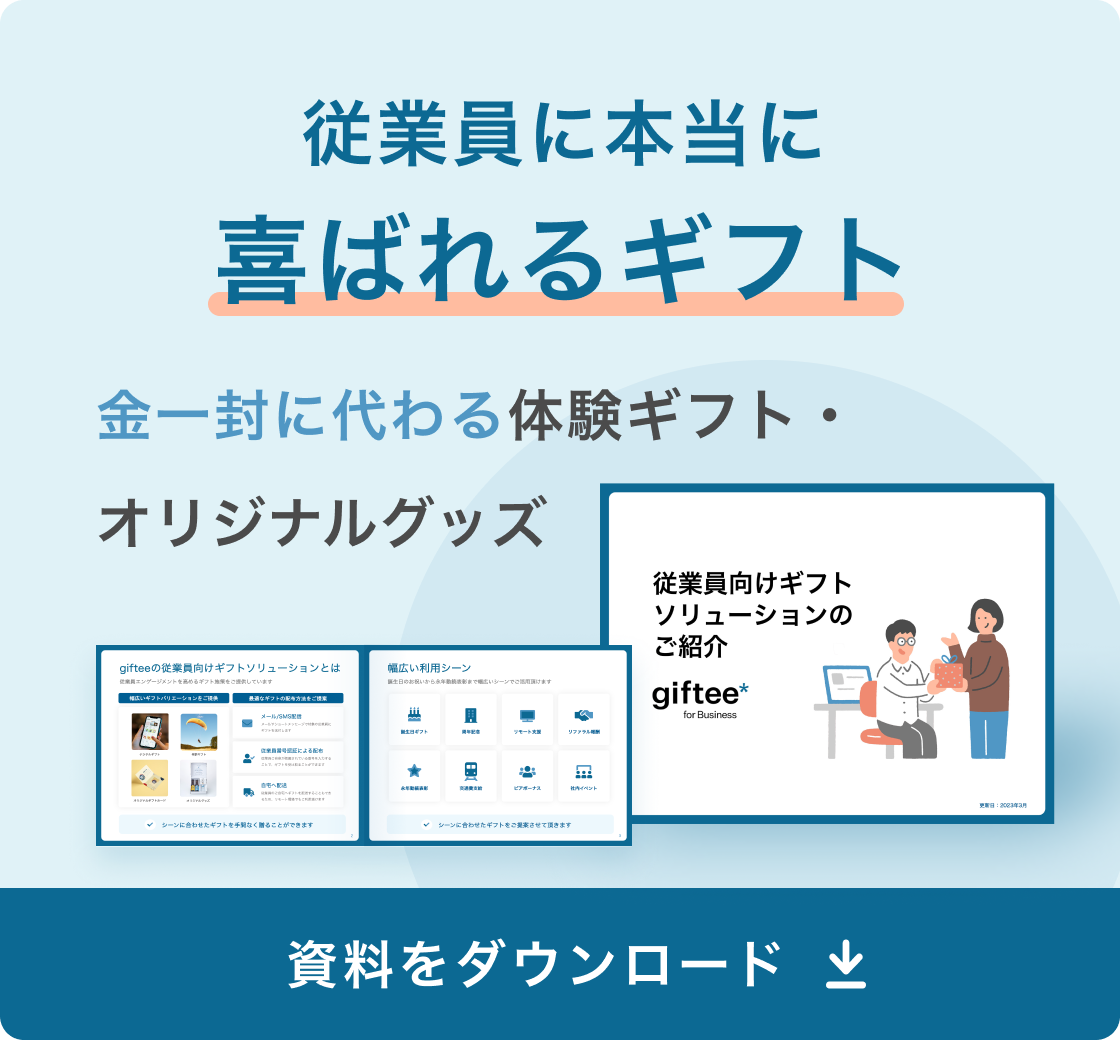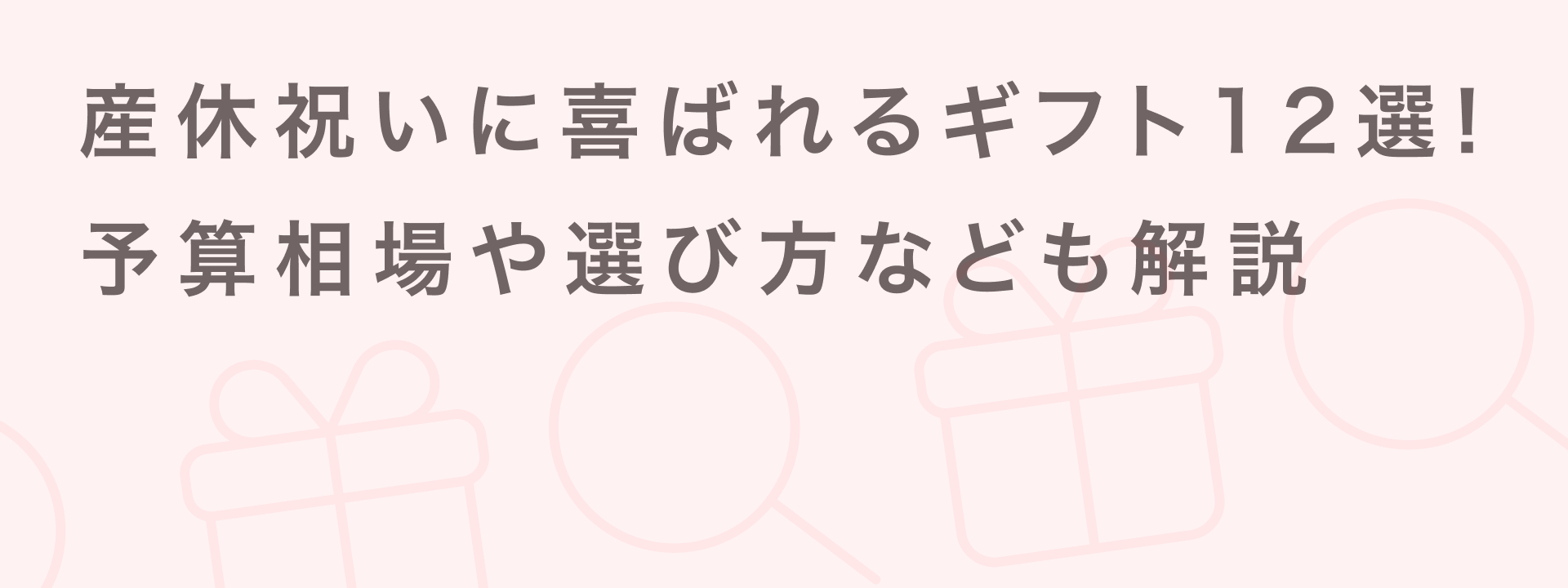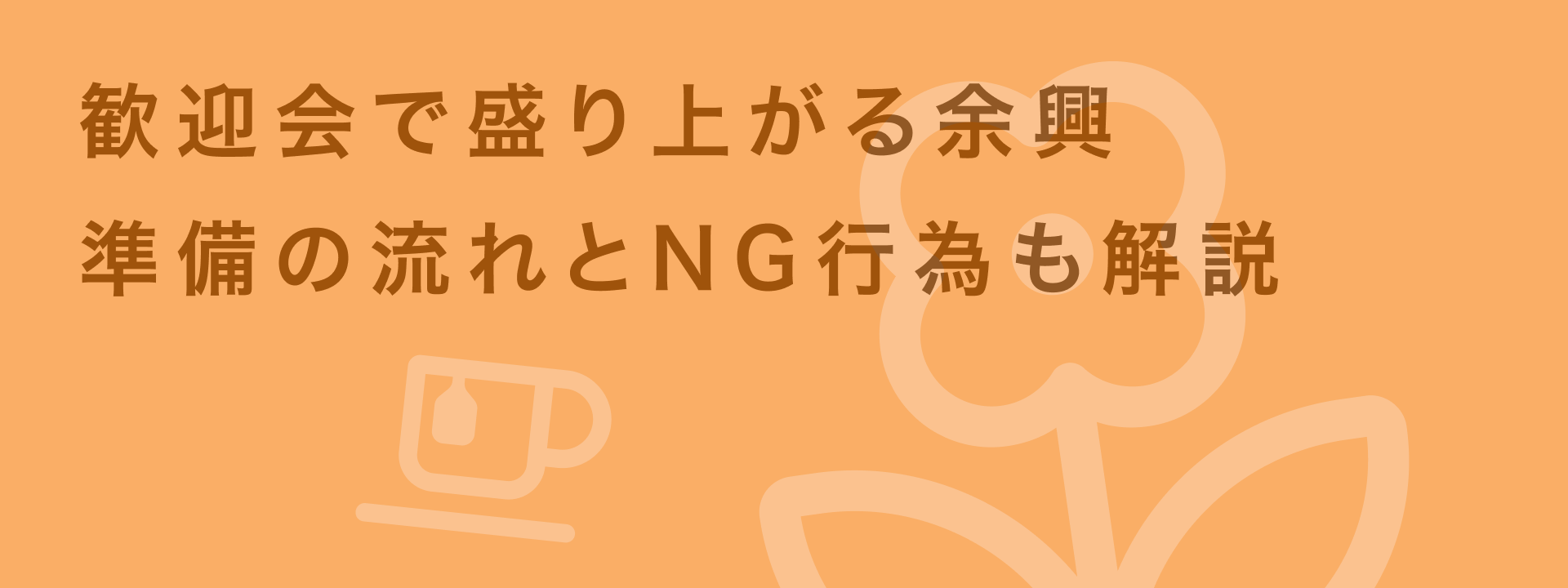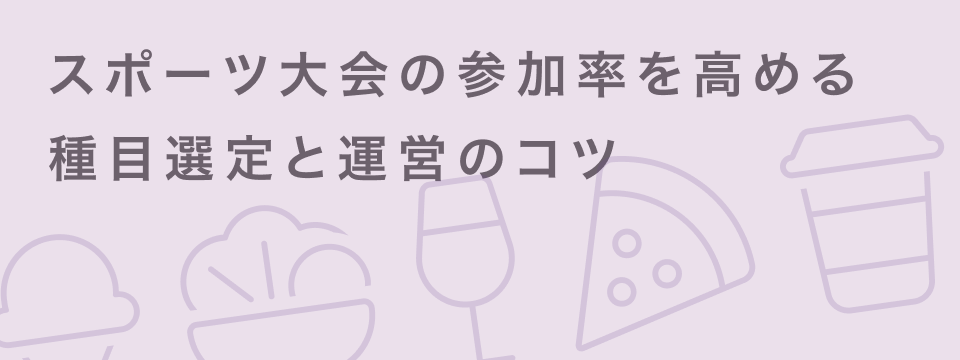会社懇親会の企画方法|参加率を高める3つの工夫とアイデアを紹介
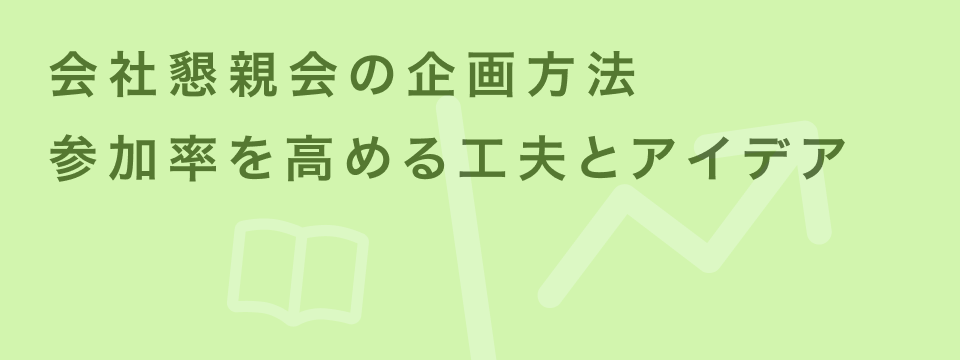
会社懇親会の企画担当として「何から手をつければよいのだろう……。」と悩んでいませんか。
予算設定、オンラインか対面かの形式選定、そして参加率を高めるための具体的なアイデアなど、検討すべき事項は多岐にわたります。過去の経験から「今度こそ成功させたい」とプレッシャーを感じる方もいるでしょう。
本記事では、会社懇親会を成功に導くための基本手順と成功のコツを解説します。企画の基本的な流れや実務に直結するアイデア、参加率を高める施策、さらによくある失敗と対策を、体系的にまとめました。
懇親会は組織の一体感を高め、社員エンゲージメントを向上させる大切な機会です。適切な企画設計と準備を通じて、限られたリソースでも効果的な懇親会を実現しましょう。
社員に喜ばれる景品を準備したいけれど、手間はかけられない…
そんな総務・人事ご担当者の声にお応えするのが、ギフティのデジタルギフトのサービスです。 用途や予算をお伝えいただくだけで、最適なギフトをセレクトしてご提案します。
さらに、ギフトの手配から配布方法の設計まで、すべてをワンストップで対応可能です。 煩雑になりがちな景品準備の工数を大幅に削減できるので、イベントの企画や当日の進行といった“本来注力すべき業務”に時間を使えるようになります。
まずは、デジタルギフトの基本や活用のポイントがわかる「デジタルギフト簡単ガイド」をご覧ください。
会社の懇親会の意味とは?目的と重要性
懇親会を企画する前に、そもそもなぜ会社の懇親会が重要なのかを理解しておきましょう。
ここでは、懇親会の基本的な定義や種類、開催形式を整理した上で、組織にとって懇親会が果たす役割とその意義を確認します。
懇親会の定義と種類
懇親会が重要な理由と達成すべき目的
懇親会の定義と種類
会社の懇親会とは、社員同士のコミュニケーションを深め、組織の一体感を高めることを目的に開催される社内イベントです。通常は業務時間外に行われ、目的や規模に応じてさまざまな種類があります。
たとえば全社的な大規模な懇親会や、部署・チーム単位の小規模な懇親会、そして歓迎会や送別会など節目のイベントに合わせたものが一般的です。
開催形式には、対面・オンライン・ハイブリッドの3種類があります。対面は交流の深まりや一体感を得やすく、オンラインは場所を問わず参加できるのが魅力です。
両方を組み合わせたハイブリッドは柔軟に運営できますが、オンライン参加者との温度差が生まれやすいため、進行や演出に工夫が必要です。
企画の目的や参加者の状況に合わせて、適切な形式を選びましょう。

懇親会が重要な理由と達成すべき目的
懇親会は、仕事の枠を越えて人と人とのつながりを広げる大切な時間です。
仕事中は立場や役割によって会話が形式的になりがちですが、懇親会では部署や役職を問わず気軽に話せる雰囲気が生まれます。お互いの人柄や価値観を知れば、新しい発見や信頼関係が育まれるでしょう。
会社が期待する懇親会の目的は、主に次の3つです。
1.社員同士の信頼関係の構築
リラックスした雰囲気のなかで互いの理解が深まり、業務上のコミュニケーションも円滑になります。日常では話す機会の少ないメンバーともつながりが生まれ、結果としてチームワークの強化につながります。
2.組織へのエンゲージメント向上
会社が社員同士の交流を大切にする姿勢を示すことで、安心感や帰属意識を持てます。仕事への意欲向上に加え、離職率の低減や生産性向上にもつながるのが利点です。
3.情報共有とナレッジの交換
部署を越えた交流によって新しい視点やアイデアが生まれるだけでなく、経営層と現場社員が直接対話できる場ともなります。こうした機会を通じて、組織の透明性や活性化が一層進むでしょう。
これらの目的を意識して企画を立てれば、懇親会の意義がより明確になります。
懇親会企画の基本的な流れ
懇親会を成功させるには、開催の1〜2か月前から計画的に準備を進めることが大切です。ここでは、企画立案から事後フォローまで、4つのステップに分けて流れを解説します。
1.企画立案(開催1〜2か月前)
懇親会の成功は、最初の企画段階で方向性をしっかり定められるかどうかにかかっています。ここでは、開催目的や形式、予算など、計画の土台となる要素を整理していきましょう。
開催の目的の明確化
開催日時と形式の決定
参加対象者の選定と予算設定
懇親会の企画は、目的を明確にすることから始まります。
新入社員の歓迎や部署間の交流促進、年度の打ち上げなど、目的によって企画の方向性は大きく変わります。明確な目的を設定すれば、全体の雰囲気や内容、準備の優先順位が整理しやすくなるでしょう。
次に、実施時期と開催形式を検討します。対面・オンライン・ハイブリッドのいずれにするかを決め、できるだけ多くの社員が参加しやすい日時を選びます。勤務形態や繁忙期を考慮すれば、参加率の向上が期待できます。
参加対象の明確化も大切です。全社員を対象にするのか、部署単位にするのかを決めておくと、会場規模や費用の見積もりが立てやすくなります。
予算の設定も欠かせません。一般的な相場は一人あたり3,000〜10,000円で、飲食付きなら5,000〜8,000円が目安です。オンラインの場合は、1,000円〜3,000円のデジタルギフトを活用するケースも増えています。
参加対象や予算が固まったら、経営層や関係部署へ早めに報告し、承認を得ましょう。計画段階から情報を共有し、承認ルートを明確にしておくと、運営全体がスムーズに進みます。
2.企画詳細設計(開催1か月前〜2週間前)
懇親会の骨組みが整ったら、次は詳細設計に移ります。開催形式に合わせて、内容や進行の流れを詰めていく段階です。具体的には、以下の2点を中心に準備を進めましょう。
会場選びやツールの選定
プログラムの詳細決定と進行表作成
対面開催では、アクセスの良さや収容人数、飲食内容、予算とのバランスを踏まえて会場を選びます。会場の広さや交通の便、設備を確認し、事前に下見や担当者との打ち合わせを行うことが重要です。
オンライン開催の場合は、社内で使用するビデオ会議システムを選定し、事前に接続テストを実施します。クイズやゲームを組み込むと、コミュニケーションが活発になりやすいでしょう。
通信環境や操作に不安がある社員にはサポート体制を整え、デジタルギフトの受け取り方法も明確にしておきます。
ハイブリッド形式では、音響やカメラの配置、画面の表示方法など技術面の準備が大切です。事前リハーサルを行い、現地とオンラインの双方が快適に参加できる環境を整えましょう。
どの形式でも、プログラム内容と進行表を事前に整理しておけば、当日の想定外のトラブルにも落ち着いて対応できます。
3.実施準備と当日運営(開催2週間前〜当日)
懇親会の詳細が固まったら、いよいよ実施に向けた最終準備です。参加者への案内や備品の確認など、抜け漏れのないよう整理しておきましょう。
案内の送信と出欠確認
会場の最終確認
設営と機材チェック・打ち合せ
少なくとも2週間前には参加者全員に案内文を送付し、開催日時や場所、オンラインの場合は接続先のURL、参加方法、服装や持ち物などの詳細を伝えます。案内には返信期限を明記し、最終的な参加者数を確定します。
また、会場や飲食の最終手配も重要です。人数の変更が生じた場合は速やかに連絡し、運営スタッフ間で当日の流れや必要事項を共有しておきましょう。景品やノベルティを準備する場合は数量や配布方法を再確認し、必要な備品のチェックリストを作成しておくと安心です。
当日は、開始前に会場の設営や機材の動作チェックを行います。スタッフの役割分担を明確にし、受付や司会進行、写真撮影など、各担当がスムーズに動けるよう準備を整えましょう。初参加の社員や緊張している様子の参加者には特に目を配り、受付で丁寧に案内を行うことも大切です。
プログラムは予定に沿って進めつつ、会場の雰囲気を見ながら柔軟に対応します。参加者が気兼ねなく楽しめる空気をつくることが、運営側の大きな役割です。懇親会終了後は速やかに片付けと会場の原状回復を行い、備品や忘れ物の確認も忘れないようにしましょう。
4.実施後のフォロー
懇親会の実施後には、参加者へのフォローが欠かせません。以下の3つを中心に対応を進めましょう。
参加者へのお礼や開催報告
アンケートの実施
報告書の作成
まず、懇親会に関わった全員へお礼や開催報告を行い、感謝の気持ちを伝えます。社内ポータルやメールで当日の写真や参加者の感想を共有すると、参加できなかった社員にも雰囲気が伝わり、次回への期待感を高められます。
次に、今後の懇親会をよりよくするためのアンケートを実施します。設問は「参加してどう感じたか」「良かった点」「改善してほしい点」「次回の希望」などを簡潔にまとめ、回答しやすい形式にすることがポイントです。匿名回答にすると率直な意見を得やすく、実のある声が集まります。
最後に、費用の精算や報告書の作成を忘れずに行いましょう。実際の支出や予算との差異、参加人数、当日の様子、参加者からの意見や今後の改善点などを整理しておくと、経営層や関係部署への報告もスムーズです。
こうした記録やフィードバックを積み重ねることで、懇親会の質が向上し、継続的な組織の活性化につながります。
【カテゴリ別】盛り上がる懇親会の企画アイデア
懇親会を成功させるには、目的や参加者に合う企画選びが重要です。以下では、目的に応じて活用できる代表的な企画アイデアをカテゴリ別にまとめました。
カテゴリ | 企画名 | 特徴・ポイント | 適した形式 |
|---|---|---|---|
アイスブレイク・交流促進 | 自己紹介ゲーム | 「最近ハマっていること」など個性が見える質問で、会話のきっかけをつくる | 対面/オンライン |
アイスブレイク・交流促進 | 人間ビンゴ | 条件に合う人を探してサインを集める形式で、自然な会話が生まれる | 対面/ハイブリッド |
アイスブレイク・交流促進 | クイズ大会 | 会社や社員に関するクイズで組織理解が深まる。チーム対抗で一体感も生まれる | 対面/オンライン |
チームビルディング | 謎解きゲーム | チームで協力して謎を解くことで、コミュニケーション力が高まる | 対面/オンライン |
チームビルディング | 料理・ものづくり | 寿司やピザ作り、陶芸など。共同作業を通して自然な交流が生まれる | 対面/オンライン |
チームビルディング | スポーツ・アクティビティ | ボウリングやゴルフ、ボルダリングなど。体を動かしてリフレッシュできる | 対面 |
リラックス・エンタメ | カラオケ大会 | 替え歌や歌当てクイズなど、歌が苦手な人も参加しやすい工夫ができる | 対面/オンライン |
リラックス・エンタメ | ビンゴ抽選・くじ引き | 参加者全員が楽しめる定番企画。デジタルギフトを使えばオンラインでも実施可能 | 対面/オンライン |
リラックス・エンタメ | 映画鑑賞・ゲーム大会 | 会話が苦手な人も参加しやすく、協力型で自然な交流が生まれる | 対面/オンライン |
アイスブレイク・交流促進系
懇親会の冒頭や、初対面の参加者が多い場面におすすめの企画です。参加者同士の緊張をほぐし、心理的な距離を一気に縮める効果があります。
自己紹介や簡単なゲームを取り入れれば会話のきっかけが生まれ、その後の交流や会自体の盛り上がりにつながるでしょう。
特に、新入社員歓迎会や他部署合同の会合など、まだ関係性が浅い参加者が集まる場で効果的です。短時間で実施できるため、他のプログラムと組み合わせやすい点も魅力です。
チームビルディング系
チームの一体感を高めたいときに最適な企画です。協力して課題に取り組んだり、共同で何かを作り上げたりするなかで自然と役割分担が生まれ、メンバーの意外な一面も見えてきます。
活動を通じてコミュニケーションが活性化し、普段の業務にも良い影響が期待できます。企画時にはある程度まとまった時間を確保し、懇親会のメインコンテンツとして実施するのがおすすめです。
業務では見えにくい個々の強みや性格を知るきっかけとなり、チームワークの向上にもつながるでしょう。
リラックス・エンタメ系
誰もが気軽に参加できる雰囲気をつくりたいときに向いています。会話が得意でない人や積極的な交流が苦手な人でも参加しやすく、堅苦しさを感じさせないリラックスした空気を演出できます。年度末の打ち上げや目標達成の祝賀など、成果を共有しながら楽しむ場面にぴったりです。
気軽さと楽しさを両立できるため、初めて懇親会を企画する担当者にも取り入れやすいでしょう。
参加率を高めるための3つの工夫
ただ懇親会を企画するだけでなく、社員が参加したくなる仕掛けづくりが大切です。どんなに内容を充実させても、参加者が集まらなければ本来の目的や効果を十分に発揮できません。
ここでは、企画段階から当日の運営まで、参加率向上を実現する3つの工夫を紹介します。社員が自然と「参加したい」と思えるような雰囲気と仕組みを整えていきましょう。
具体的には、以下の3つの工夫を取り入れると効果的です。
企画段階での工夫
告知・コミュニケーションの工夫
インセンティブ設計の工夫
企画段階での工夫
企画するときは「誰もが参加しやすい環境づくり」を意識することが大切です。まずは、社員が集まりやすい日時を選びましょう。金曜の夕方や休日前の開催は人気が高く、参加しやすい時間帯です。
家庭やライフスタイルに合わせた柔軟な時間設定を意識すると、より多くの人が参加しやすくなります。
次に、事前アンケートで企画内容や食事の希望、避けてほしい事項などを把握しましょう。アレルギーや食事制限の確認も大切です。
こうした意見を反映することで、「社員の声を大切にしている」という会社の姿勢が伝わり、自然と参加意欲が高まります。
また、オンライン参加やハイブリッド形式を取り入れるのも効果的です。遠隔勤務や家庭の事情で会場に来られない社員にも参加機会をつくれるため、全体の参加率向上につながります。
告知・コミュニケーションの工夫
懇親会への参加を促す上で重要なのが、早めの告知とこまめなコミュニケーションです。
案内はできれば1か月以上前から始め、社内メールや掲示板など複数のツールを使って繰り返し周知しましょう。
過去の懇親会の写真や感想を共有すると雰囲気が伝わり、初参加の社員の不安をやわらげられます。新入社員や中途入社の社員もハードルが下がり、参加しやすくなります。
インセンティブ設計の工夫
参加者の満足度と次回への参加意欲を高めるには、「参加してよかった」と感じられる仕掛けづくりが欠かせません。
たとえば、参加者全員へのギフトや抽選会など、気軽に楽しめる特典を用意すると効果的です。近年は、オンラインでも簡単に贈れるデジタルギフトを導入する企業が増え、場所や時間を問わずスムーズにインセンティブを提供できるようになっています。
ただし、インセンティブが主目的になると交流という本来の目的が薄れてしまうおそれがあります。バランスを保つためには、参加者の声を取り入れながら、当日の交流やプログラムの質を高める工夫が大切です。
インセンティブをうまく活用すれば、社員が楽しみながら参加でき、次の懇親会にも積極的に参加してもらえるでしょう。
社員に喜ばれる景品を準備したいけれど、手間はかけられない…
そんな総務・人事ご担当者の声にお応えするのが、ギフティのデジタルギフトのサービスです。 用途や予算をお伝えいただくだけで、最適なギフトをセレクトしてご提案します。
さらに、ギフトの手配から配布方法の設計まで、すべてをワンストップで対応可能です。 煩雑になりがちな景品準備の工数を大幅に削減できるので、イベントの企画や当日の進行といった“本来注力すべき業務”に時間を使えるようになります。
まずは、デジタルギフトの基本や活用のポイントがわかる「デジタルギフト簡単ガイド」をご覧ください。
懇親会企画でよくある失敗と対策
懇親会の準備を整えても、思わぬトラブルや想定外の失敗が起こることは珍しくありません。
ここでは、企画段階から開催後のフォローまで、懇親会で起こりがちな失敗例とその対策を紹介します。あらかじめリスクを把握し、トラブルを防いでスムーズな運営につなげましょう。
企画段階での失敗と対策
運営当日の失敗と対策
事後フォローの失敗と対策
企画段階での失敗と対策
企画段階で多いのが、目的が曖昧なまま進めてしまうケースです。「とりあえず懇親会を開く」という姿勢では、方向性が定まらず、参加者にも意図が伝わりません。
これを防ぐには、目的を明確に言語化し、関係者全員で共有することが大切です。目的がはっきりすれば、判断基準が明確になり、企画全体に一貫性をもたせられます。
また、予算の見積もり不足もよくある失敗です。会場費や飲食費はもちろん、景品や人件費、予備費まで見越して設定しましょう。
過去の実績を参考に現実的な金額を算出し、不足時の対応も事前に決めておくと安心です。
また、参加者のニーズを把握せず、企画者の独断で内容を決めるのも避けたいところです。参加者の期待とのずれは満足度を下げるため、事前アンケートやヒアリングで希望を把握し、求められる懇親会のスタイルを反映させましょう。
運営当日の失敗と対策
懇親会当日に起こりやすいのは、進行の遅れや現場の混乱です。
プログラムの詰め込みすぎや連携不足が原因のため、余裕を持ったスケジュールと詳細な進行表を用意し、スタッフの役割を明確にしておきましょう。事前リハーサルで流れを共有しておくと安心です。
進行面だけでなく、参加者の孤立にも注意が必要です。新入社員や他部署の社員が孤立しないよう、スタッフが積極的に声をかけることが大切です。さらに、アイスブレイクの時間を設けて、自然に交流が生まれる雰囲気をつくりましょう。
オンライン懇親会では、接続トラブルや音声不具合など技術的な問題が起こりがちです。事前のテストや予備機材の準備を行い、参加者には簡単な操作マニュアルを共有しておくとスムーズです。
事後フォローの失敗と対策
懇親会後のフォローを怠ると、次回以降の参加意欲が下がるだけでなく、せっかくの満足感も薄れてしまいます。終了後はできるだけ早くお礼メールを送り、アンケートでフィードバックを集めることが大切です。
得られた意見を分析して次回の企画や運営に反映すれば、会を重ねるごとに参加者の満足度が高まり、懇親会の目的も達成しやすくなります。結果を社内で共有することで、透明性や一体感の向上にもつながるでしょう。
また、費用精算や報告書の作成を後回しにすると、記録が曖昧になり、ノウハウとして蓄積しにくくなります。領収書整理や支出記録は当日中に済ませ、報告書も早めにまとめておくと安心です。
よくある質問(FAQ)
Q. 懇親会の適切な開催頻度は?
四半期に1回(年4回)程度が一般的な目安です。ただし、組織の規模や文化、予算によって最適な頻度は異なります。
全社規模の大きな懇親会は年1〜2回、部署やチーム単位の小規模な懇親会は月1回など、規模に応じて使い分けるのが効果的です。頻度が高すぎると負担が増え、低すぎると交流の機会が不足するため、社員の声を聞きながらバランスを取りましょう。
Q. 参加を強制しても問題ない?
親会への参加強制は避けるべきです。 業務時間外に開催される懇親会への参加を強制すると、パワーハラスメントと捉えられるリスクがあります。
厚生労働省が定める「職場におけるハラスメントの防止のために」では、パワハラの典型例として「個の侵害」(私的なことに過度に立ち入ること)が挙げられています。参加しない社員への不利益な扱いや、繰り返しの参加要請は問題となる可能性があります。
参加率を高めたい場合は、強制ではなく「参加したくなる仕掛け」を工夫しましょう。魅力的なプログラムの企画、参加しやすい日時の設定、インセンティブの用意など、本記事で紹介した方法を活用することをおすすめします。
まとめ|会社の懇親会企画で組織を活性化させよう
懇親会は、社員が立場を越えて交流し、チームとしての一体感を深める大切な場です。目的を明確にし、参加者の声を反映した企画設計を行えば、誰もが楽しく参加できる懇親会を実現できます。
また、事前準備から当日の運営、事後フォローまでを丁寧に進めれば、懇親会は単なるイベントではなく、会社全体のコミュニケーションを活性化させる仕組みとして機能するでしょう。
社員が「また参加したい」と思える場づくりは、会社全体の活気やつながりを生み出すきっかけになります。懇親会を通じて、一人ひとりの成長と組織の発展を目指しましょう。