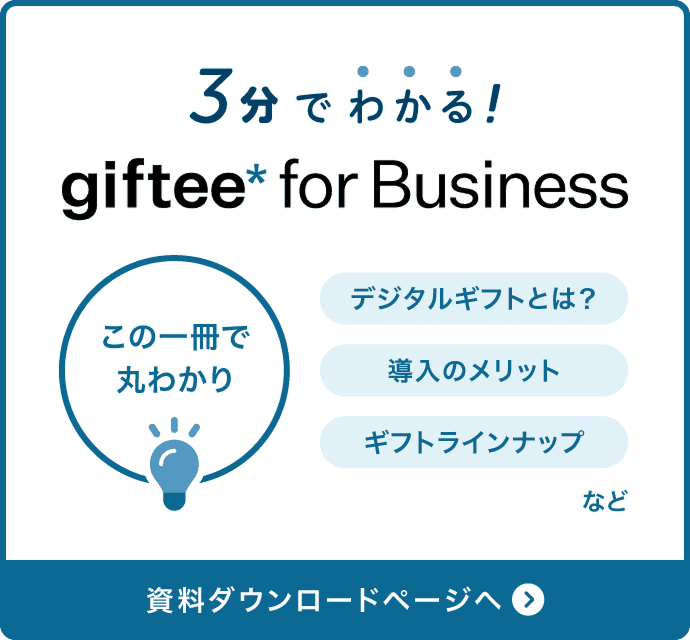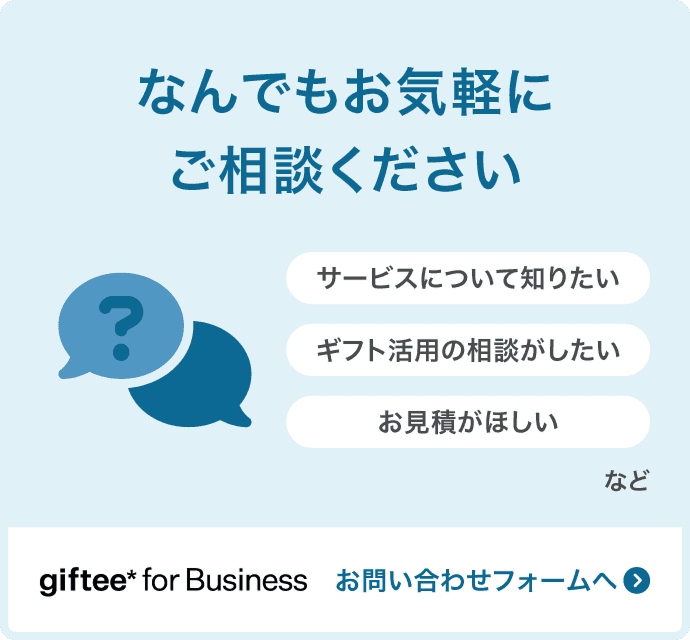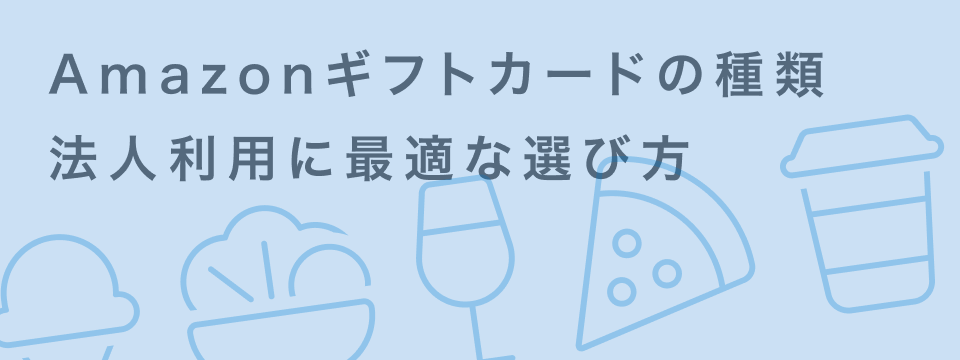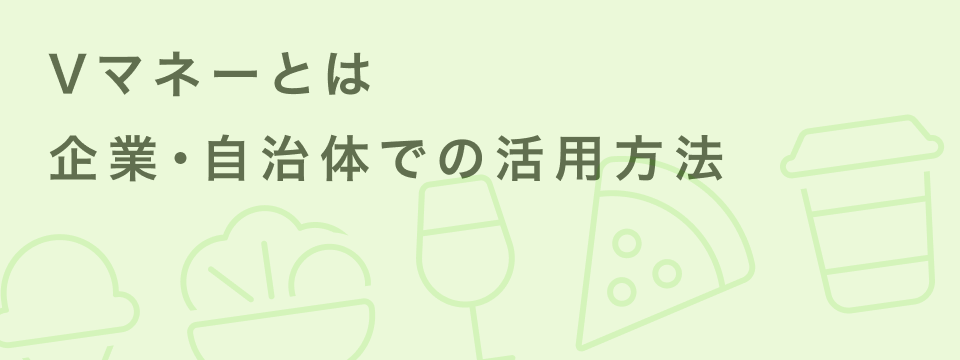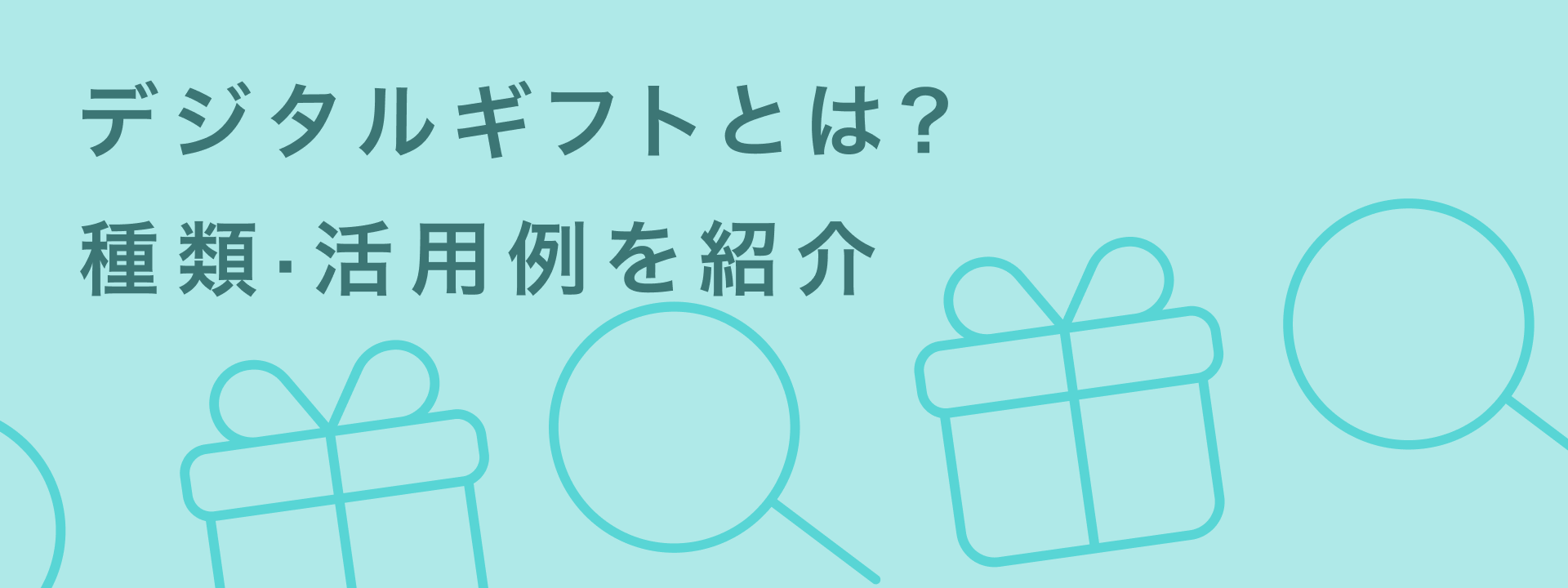健康経営を成功させるには?福利厚生とインセンティブを活用した事例集
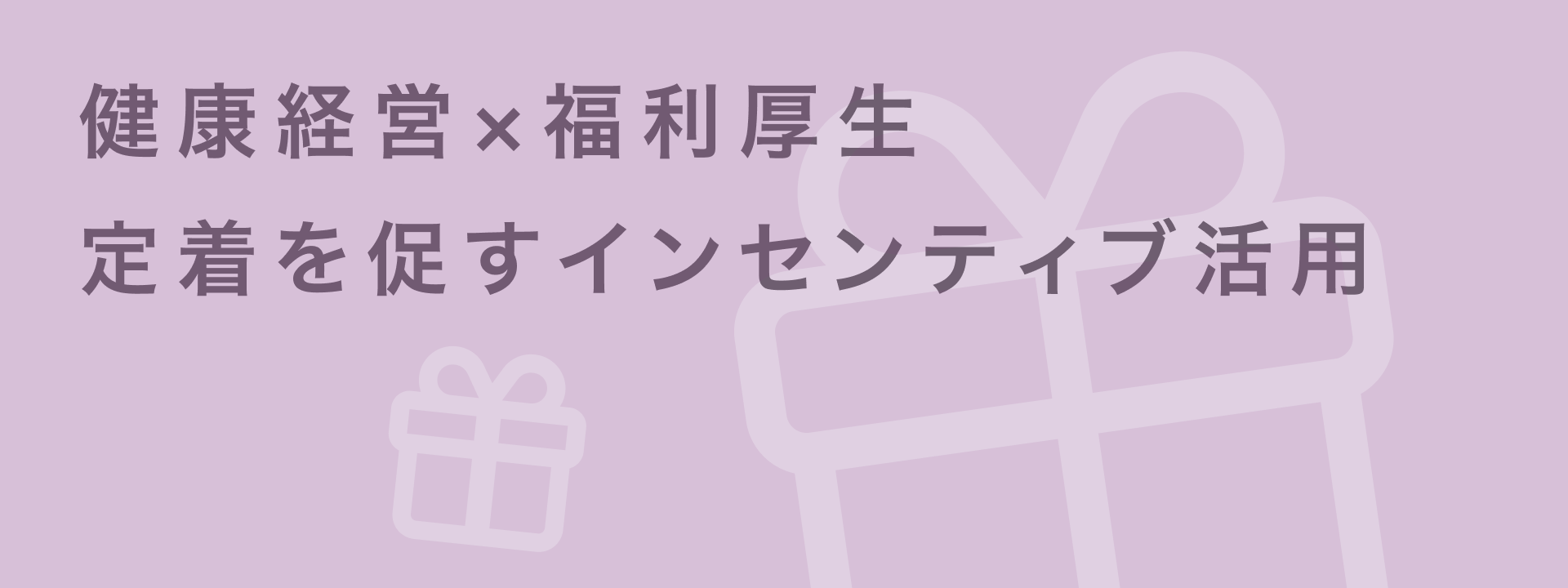
健康診断の受診や運動イベント、知識向上のためのセミナーやeラーニング。 多くの企業が「健康経営」に取り組んでいますが、その成果が見えづらく、形骸化してしまうという声も少なくありません。
また、せっかく導入した福利厚生制度も「利用率が低い」「存在を知られていない」といった理由で活用されず、費用対効果を問われて悩む担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、そうした課題を解決するヒントとして「健康経営 × 福利厚生」の組み合わせによる取り組みをご紹介します。 実際の企業・健保組合の事例をもとに整理した 4つのインセンティブ活用パターンを中心に、参加率向上や行動の継続、制度利用率アップにつながった工夫を解説します。
健康経営の取り組み、もっと“続けたくなる・使われる”設計に。
まずはオンライン相談で、インセンティブ設計の見直しから始めてみませんか?
「せっかく施策を打っても、定着しない…」 「制度は整っているのに、利用されていない…」
そんなお悩みを持つ企業が、いまデジタルギフトの活用を進めています。
参加率・継続率の向上と、業務負荷の軽減を両立。 まずはお気軽にオンラインでご相談ください。
なぜ“健康経営と福利厚生の組み合わせ”が重要なのか
従業員の健康を支える施策として、「健康経営」と「福利厚生」は重要です。しかし、現場では両者が別々に運用され、十分に連動していないケースもあります。
健康経営とは、従業員の健康を経営課題のひとつとして捉え、戦略的に推進していく考え方です。健康診断やメンタルヘルス対策といった取り組みを通じて、生産性の向上や組織活力の強化を目指すものです。
本来、両者は相互に補完し合う関係にあります。健康経営が戦略的な枠組みとして機能し、福利厚生がその実行手段となることで、施策全体に一貫性が生まれ、従業員の参加意欲や取り組みの継続につながります。健康意識の定着や制度利用の促進は経営成果としても可視化されやすく、人的資本経営の観点からも有効です。
こうした背景から、健康経営と福利厚生を「別々の施策」として捉えるのではなく、「組み合わせる」ことで実効性を高めようとする動きが注目されています。
単体施策での限界とよくある課題
健康経営に取り組んでいるものの、その成果が実感できず、取り組み自体が形骸化していると感じている企業は少なくありません。健康診断の受診率やストレスチェックの実施といった「実施した事実」はあるものの、従業員の行動変容や組織の生産性といった成果につながっているかどうかは見えづらいという声も多く聞かれます。
一方で、福利厚生についても、せっかく制度を整えても「利用されない」「何のためにあるのかわかりにくい」といった課題が浮上しがちです。特に、使いこなすために手間や知識が求められる制度は、導入しても実際の利用率が伸びないケースも。また、運動イベントや食生活改善などの健康施策を実施しても、一時的な盛り上がりで終わり、継続や定着につながらないという悩みもあります。
こうした課題に対して、効果的な解決策となるのが「健康経営 × 福利厚生」の組み合わせです。健康経営を“理念”にとどめず、福利厚生という“手段”と組み合わせることで、従業員の行動を促し、参加率や継続性を高める施策へと進化させることができます。
健康経営 × 福利厚生:4つのインセンティブ活用パターン
健康経営と福利厚生を連動させた施策を実施する際、インセンティブの設計は重要な要素です。とくに、「どのような行動を促したいか」「誰に届けたいか」によって、適切なインセンティブの種類や仕組みは異なります。
企業や健保組合の事例を整理すると、インセンティブ活用は大きく次の4つに分類できます。
パターン名 | 特徴と狙い |
|---|---|
習慣化支援型 | ログイン・歩数記録・体重入力など、“日常的な継続行動”に対してギフトを付与。小さな行動を積み重ねる仕組みを通じて、健康習慣の定着を促進。 (例:ウォーキングイベント、健康アプリログイン、週次体重入力 など) |
知識定着型 | 健康に関する動画の視聴やクイズの正答といった“学びの行動”にインセンティブを設定。知識と意識の底上げを狙う。 |
成果報酬型 | 健診の受診、保健指導の完了、体重や腹囲の変化など、“実施+成果”を評価軸とし、結果に対してギフトを提供。数値での説明がしやすく、経営報告にも有効。 |
文化醸成・表彰型 | 社内での健康行動を可視化・共有し、投票や表彰を通じて“健康に取り組むことを称える空気”を醸成。参加者の満足度向上やエンゲージメント向上につながる。 |
このように分類することで、施策の目的や対象者に合わせたアプローチが明確になり、企画・実行の精度が高まります。
健康経営 × 福利厚生の活用事例
健康経営と福利厚生を効果的に組み合わせることで、従業員の参加意欲を高め、取り組みの継続や成果の「見える化」につなげることができます。ここでは、実際の社内施策に取り入れやすいアイデアをご紹介します。
いずれも、日常の行動にインセンティブを設けることで、自発的な参加を促し、組織全体の健康意識を高めていく工夫がされています。
習慣化支援型:毎日の行動に、続けたくなる仕掛けを
継続的な健康行動に対してインセンティブを設計することで、行動の“習慣化”を促すのがこのタイプです。記録の負担を減らしつつ、参加し続けたくなる工夫がポイントです。
事例①|ウォーキングキャンペーン × 参加賞+達成賞
社内コミュニケーションと健康増進を目的に、2カ月間のウォーキングイベントを実施。歩数に応じて達成賞を、参加者全員に参加賞を用意し、日々の行動を後押ししました。 参加者の約9割が「また参加したい」と回答するなど、楽しみながら継続できる仕組みが高評価を得ました。
▼この事例の詳細はこちら
“また参加したいイベント”へ転換。社内ウォーキングイベントの賞品にデジタルギフトを活用
事例②|アプリ連携型 健康行動ポイントプログラム
歩数、体重、食事、睡眠といった毎日の健康行動を記録することでポイントを付与。貯まったポイントはデジタルギフトと交換可能とし、「少しずつ続けること」に価値を持たせました。ギフトの自由度や低額交換のしやすさが継続率向上に貢献しています。
知識定着型:健康について学ぶことが行動につながる設計に
健康に関する知識を深めることも、意識づけには欠かせません。ここでは、動画視聴やクイズ参加などの学びの行動に対してインセンティブを設計した事例をご紹介します。
事例③|健康教育動画 × 先着ギフト
健康保険組合の会員を対象に、特定の健康動画を視聴した先着600名に対してデジタルギフトをプレゼント。動画は数分から10分程度と短時間で完結する設計とし、学びやすさと“もらえる楽しみ”の両方を実現しました。
事例④|クイズ参加 × 抽選プレゼント
動画やコラム内容をもとにした健康クイズを毎週配信。全問正解者の中から抽選でギフトを進呈する仕組みで、反復学習と参加率向上を両立しました。
成果報酬型:行動+成果を“見える化”し、報いる
「受診しただけ」「参加しただけ」ではなく、行動の完了+成果(減量・改善)に対してインセンティブを付与するのが成果報酬型。人的資本経営の報告にも有効です。
事例⑤|健診完了 × 自己申請式ギフト提供
被扶養者向けに健診受診後の申請フォームを用意し、受診完了者に対して1,000円〜2,000円のギフトをプレゼント。自己申請式にすることで、受診の主体性と申請率の向上を両立しました。
事例⑥|特定保健指導完了 × 体重・腹囲の改善でポイント付与
一定期間の保健指導プログラムを完了し、かつ体重−2kg/腹囲−2cmの成果を達成した方にポイントを進呈。行動+成果の両軸で評価される設計が、離脱防止と改善意欲の向上につながっています。
文化醸成・表彰型:健康を称える雰囲気を、組織の中に
健康経営を単なる制度で終わらせず、“みんなが参加することが当たり前”な雰囲気をつくるのが文化醸成・表彰型です。称賛や共有を通じて、継続率だけでなくエンゲージメントも高まります。
事例⑦|社内表彰制度 × 健康行動投票
個人・チームの健康に関する取組みを社内で公募し、従業員による投票で上位者を選出。表彰者にはインセンティブとしてギフトを贈呈。「頑張っていることが見える」「称え合える」文化が育まれました。
事例⑧|健康セミナー × アンケートギフト
従業員向けの健康セミナー終了後、アンケート回答者の先着にギフトを提供。セミナー参加後のアクションにも報酬を設けることで、参加意欲の喚起と満足度向上を両立した事例です。
このように、「継続させたいのか」「知識を定着させたいのか」「成果を出したいのか」「文化をつくりたいのか」など、目的ごとに施策の設計を明確にすることで、健康経営と福利厚生はより実効性を持った取り組みに進化します。
健康経営の取り組み、もっと“続けたくなる・使われる”設計に。
まずはオンライン相談で、インセンティブ設計の見直しから始めてみませんか?
「せっかく施策を打っても、定着しない…」 「制度は整っているのに、利用されていない…」
そんなお悩みを持つ企業が、いまデジタルギフトの活用を進めています。
参加率・継続率の向上と、業務負荷の軽減を両立。 まずはお気軽にオンラインでご相談ください。
健康経営 × 福利厚生の効果とメリット
制度を整備するだけでは、従業員の健康行動や満足度の向上にはつながりません。健康経営と福利厚生を連動させることで、戦略と仕組みの両面から実効性を高めることができます。
従業員の参加率・健康意識の向上
日常の行動にインセンティブを組み込むことで、従業員の参加率が高まります。たとえばウォーキングイベントや健康診断が、“義務”ではなく“楽しめるもの”となることで、健康意識そのものも向上し、企業全体のリテラシー向上にもつながります。
人的資本経営としての外部評価に活用可能
健康経営優良法人の認定や人的資本開示においても、福利厚生と連携した施策は有効です。IRや採用広報などで、「従業員の健康を戦略的に支えている企業」として企業価値を高める要素になります。
エンゲージメント向上と離職防止
会社が従業員の健康や働きやすさに本気で取り組んでいるというメッセージは、信頼感や安心感として届きます。こうした積み重ねが、従業員エンゲージメントの向上に寄与し、離職の防止にもつながります。特に若手や中堅社員の定着を課題とする企業にとっては、重要なポイントです。
健康経営に、ギフトという選択肢を。
健康経営や福利厚生の取り組みを、もっと“やってよかった”と思える施策に変えていくには、「ギフト」という小さなきっかけが意外と効いてきます。
続けたくなる仕掛けに、ちょっとしたご褒美を。 学びや成果に、気持ちの伝わるありがとうを。 頑張っている人を、みんなで称え合う雰囲気づくりにも。
そんな場面にぴったりなのが、デジタルギフトです。
日々の健康行動に、気軽に・柔軟にインセンティブを組み込むことで、健康経営はもっと“ひとごとじゃない”取り組みに変わります。
健康経営の取り組み、もっと“続けたくなる・使われる”設計に。
まずはオンライン相談で、インセンティブ設計の見直しから始めてみませんか?
「せっかく施策を打っても、定着しない…」 「制度は整っているのに、利用されていない…」
そんなお悩みを持つ企業が、いまデジタルギフトの活用を進めています。
参加率・継続率の向上と、業務負荷の軽減を両立。 まずはお気軽にオンラインでご相談ください。