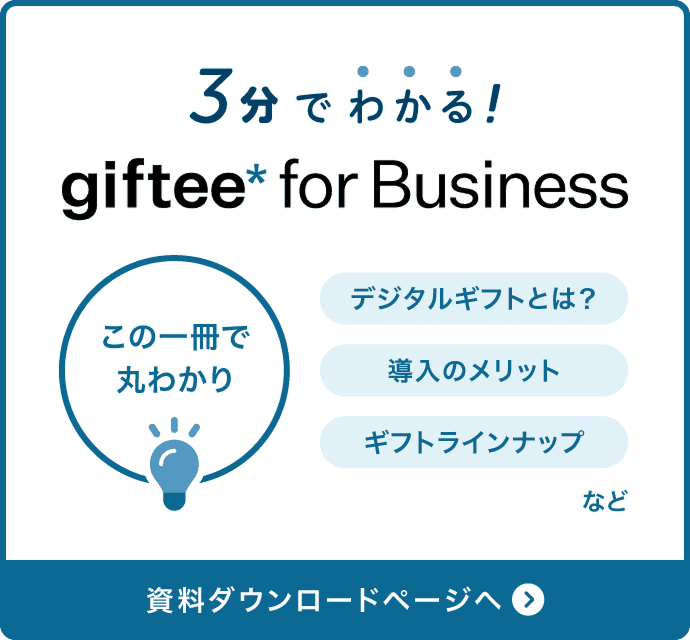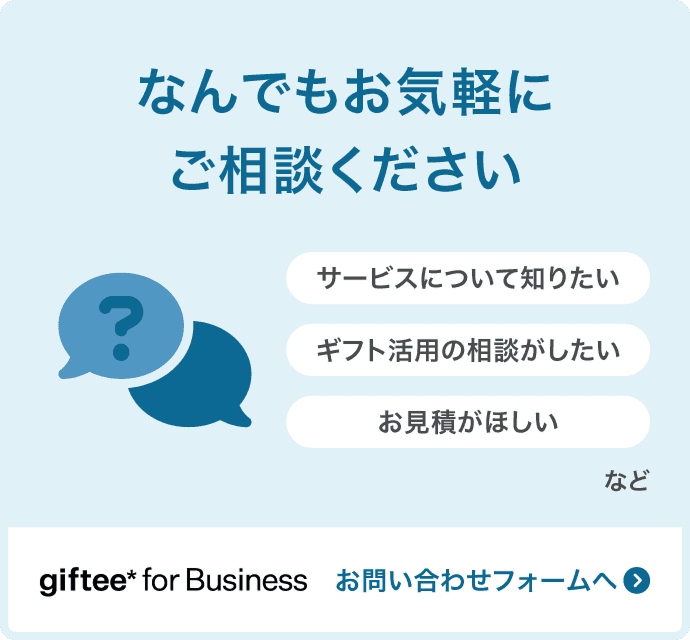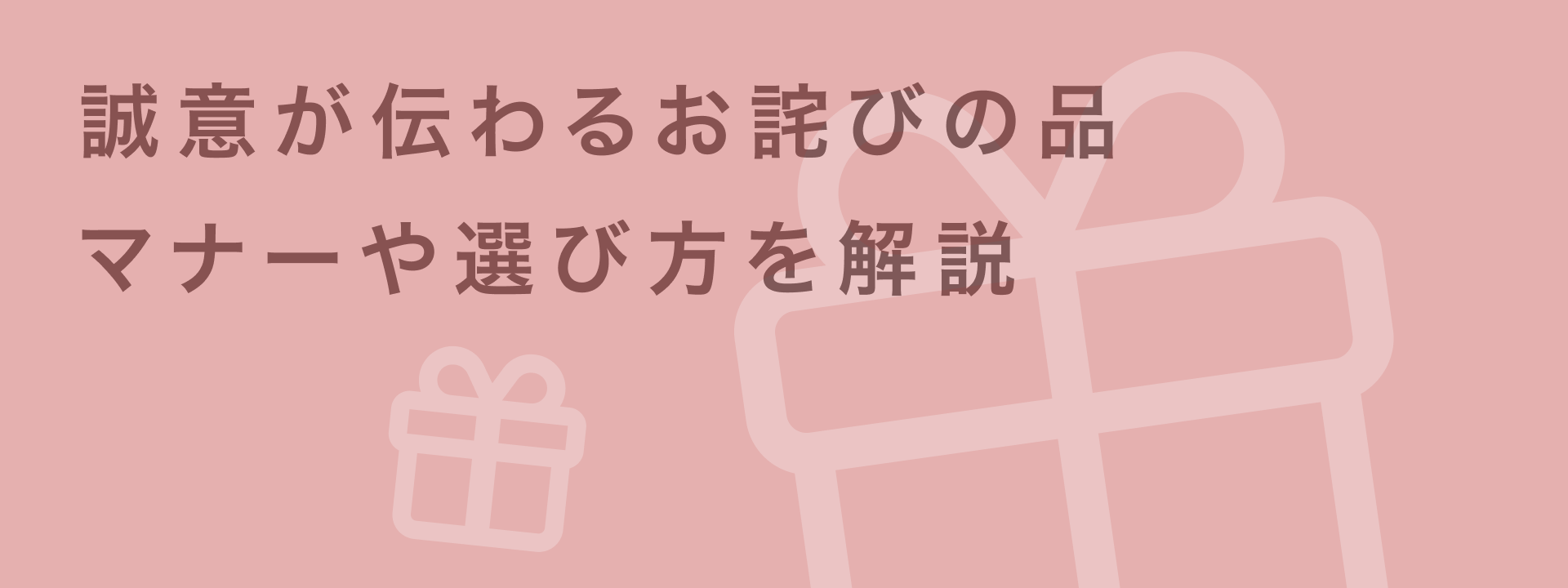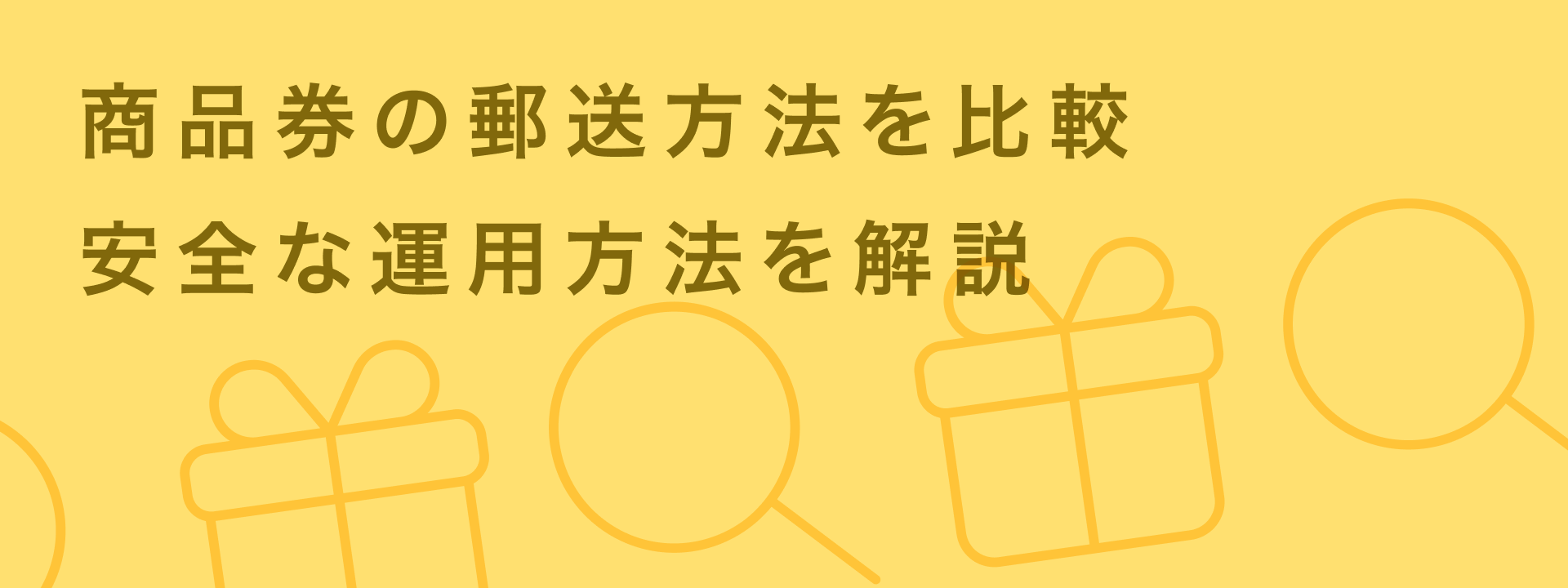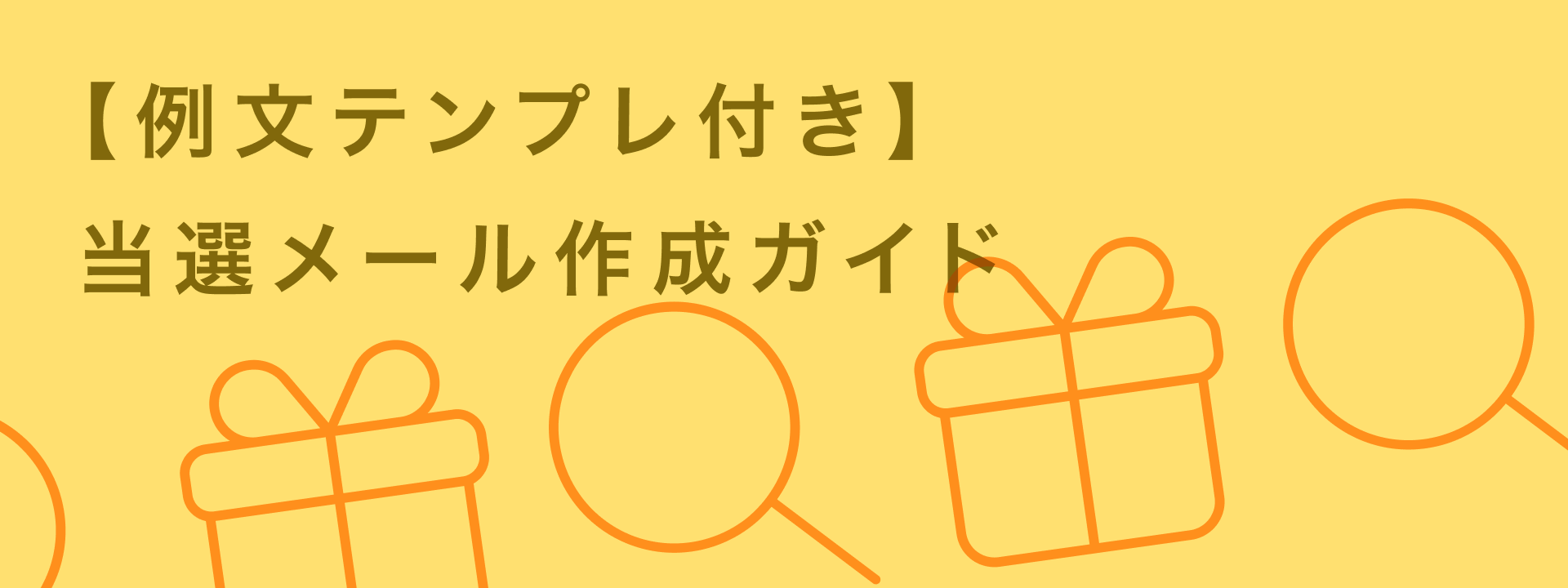デジタルギフトの受け取り方|主要ブランド別手順とBtoB&BtoE活用のポイント
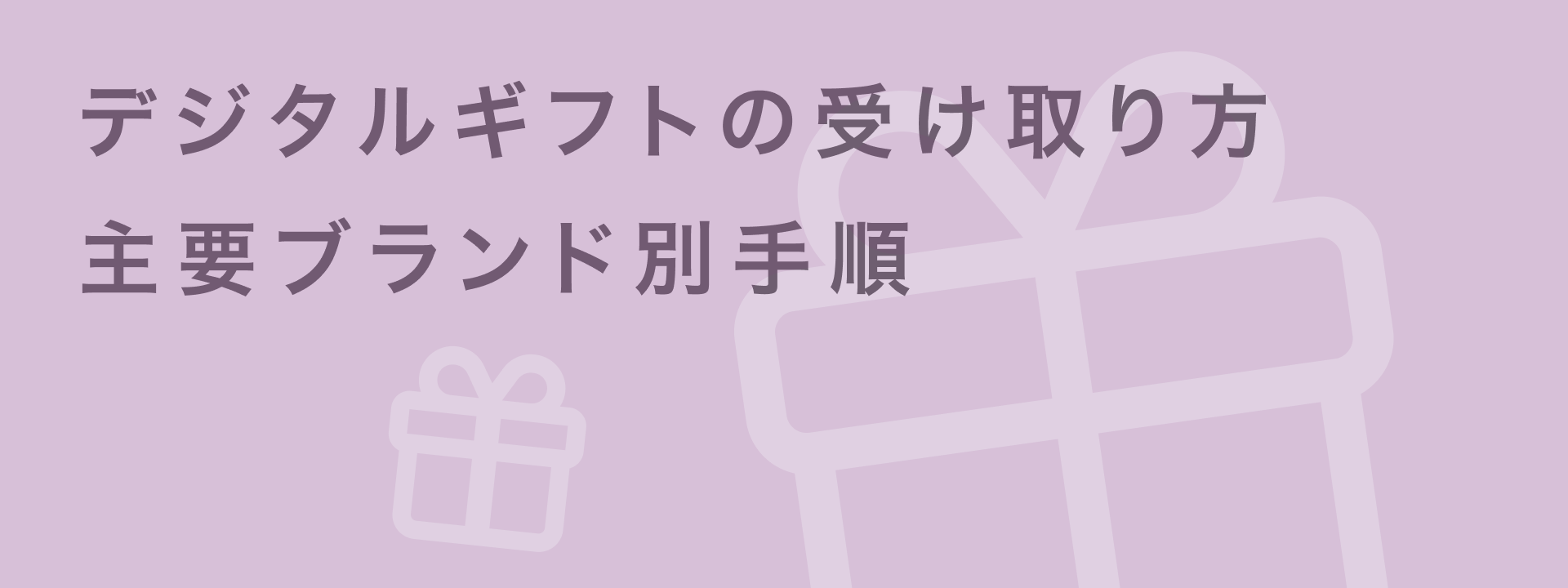
インセンティブや福利厚生の場面で幅広く利用されるようになったデジタルギフト。一方で、PayPayやAmazonギフトカード、コンビニ系のデジタルギフトなどは、ブランドごとに受け取り方法が異なるため「どうやって使えば良いの?」と戸惑うケースも少なくありません。その結果、従業員への案内や運用に頭を悩ませる担当者も多いのが実情です。
本記事では、主要ブランドごとの受け取り手順を整理し、BtoBとBtoE(Business to Employee)シーンで活用する際に押さえておきたいポイントをわかりやすく解説。デジタルギフトをインセンティブとしてご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
デジタルギフトの受け取り方でお困りのご担当者様へ
こんなお悩みはありませんか? ・デジタルギフトの受け取り方がブランドごとに異なり、従業員への案内が大変 ・受け取り時のトラブル対応に時間がかかる ・デジタルギフトを効果的に活用し、運用負担を軽減したい
デジタルギフトの受け取り方は、URL受け取り方式、ギフトコード入力方式、アプリ経由方式の3つに大きく分けられます。企業担当者にとっては、配布するギフトがどの方式なのかを事前に把握しておくことが大切です。キャンペーンの案内などにその情報をわかりやすく盛り込めば、受け取り時の混乱を防ぎ、スムーズな運用につながります。
こうしたデジタルギフトに関する疑問については、累計7万件以上の法人導入実績を持つgiftee for Businessの担当者がご相談を承ります。導入検討段階のご質問から具体的な運用設計まで対応していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
デジタルギフトの受け取り方法
本記事は、デジタルギフトの基礎知識と、エンドユーザーのギフト受け取り手順を理解することで、キャンペーン担当者や、企業の福利厚生の担当者の業務負担軽減を目指します。
本章では、まずデジタルギフトとは何か、受け取りの4ステップ、そして各ブランドで異なる受け取り方の違いについて整理していきましょう。
デジタルギフトとは
「デジタルギフト」とは、紙やカードのように現物で配布するのではなく、電子データとして送られる商品券やポイントのことです。受け取った人は、専用のユニークURLやギフトコードを使い、店舗では店員に提示したり、ECサイトではコードを入力するなどして商品やサービスに交換できます。
友人間で贈り合ったりする他、法人ギフトとしてはキャンペーンのインセンティブや福利厚生用途として使われるケースが多いです。
受け取り方法の種類
デジタルギフトの受け取り方は、大きく3つに分けられます。
以下に、各受け取り方法の特徴をまとめました。
方式 | 操作方法 | メリット | 代表的なサービス |
|---|---|---|---|
URL受け取り方式 | メールやSMSのリンクを開く | 操作が簡単、手間がかからない | giftee Box、QUOカードPay |
ギフトコード入力方式 | 公式サイトやアプリにコードを入力 | セキュリティが高い | PayPayポイントコード、Amazonギフトカード |
アプリ経由方式 | 専用アプリで操作 | 残高や利用履歴を管理しやすい | PayPay、コンビニ系アプリ |
企業担当者にとっては、配布するギフトがどの方式なのかを事前に把握しておくことが大切です。
キャンペーンの案内などにその情報をわかりやすく盛り込めば、受け取り時の混乱を防ぎ、スムーズな運用につながります。
主要ブランド別|デジタルギフト受け取り手順
デジタルギフトの受け取り方は、ブランドごとに手順が異なります。ここでは、以下の3カテゴリーに分け、それぞれの具体的な受け取り手順と注意点を詳しく説明します。
PayPayポイントコード系
Amazon・楽天などのECモール系
コンビニ・店舗系
それでは順に見ていきましょう。
PayPayポイントコード系デジタルギフト
PayPayポイントコード系のデジタルギフトは、スマートフォンのPayPayアプリを通じて受け取ります。
事前にアプリをインストールし、アカウントの登録が必要です。その上で、企業から届いたギフトコードやユニークURLを入力すれば、受け取り手続きが完了します。
具体的な手順は以下の通りです。
PayPayアプリを開く
ホームの「+(チャージ)」をタップ
「その他のチャージ方法」内にある「ポイントコード」をタップ
「ポイントコードからのチャージ」画面で16桁のコードを入力
認証が完了すると指定金額がPayPayマネーライトとして付与される
付与された残高は全国のPayPay加盟店で利用可能です。
福利厚生としてギフト付与するのであれば、配布前に従業員のPayPayアプリ利用状況を確認し、PayPayを使ったことがない人にはダウンロード方法から説明するとスムーズに進みます。
Amazon・楽天などECモール系デジタルギフト
Amazonや楽天といったECモール系のギフトは、それぞれのアカウントを通じて受け取ります。
Amazonギフトカード:ログイン後、「アカウントサービス」から「ギフト券を登録する」画面でコードを入力すると残高に反映されます。
楽天ギフトカード:楽天会員ページの「楽天ギフトカード受け取りページ」でコードを入力すると「楽天キャッシュ」として追加されます。
このタイプのギフトは有効期限が比較的長いのが特徴で、コード発行日からAmazonは10年間、楽天は6か月間有効です。
福利厚生としてギフト付与するのであれば、従業員がアカウントを保有しているかを事前に確認し、未登録なら会員登録の方法まで案内しておくと受け取りがスムーズになります。
コンビニ・店舗系デジタルギフト(セブン-イレブンなど)
セブン-イレブンのデジタルギフトは、アプリ経由と店頭受け取りの2通りがあります。
アプリ利用:アプリをダウンロード後、会員登録を行い、コードを入力すると受け取り完了。
店頭利用:レジでギフトコードを提示すれば、その場で商品と交換できます。
このようなコンビニ・店舗系ギフトは、アプリと店頭の両方に対応しているのが強みです。アプリ操作が苦手な人でも、店頭で直接交換できるため幅広い層に適しています。
ただし、利用は店舗の営業時間に依存するため、ギフトを受け取る人に事前に営業時間を確認するよう案内しておくと安心です。
キャンペーン担当者は、ギフトを受け取る人のデジタルリテラシーに合わせて、どの受け取り方を選ぶべきか提示しておくと良いでしょう。
受け取り時のよくある質問(FAQ)
Q: デジタルギフトを受け取るのにアカウント登録は必要ですか?
ブランドによって異なります。
区分 | ブランド例 | 利用方法の概要 |
|---|---|---|
登録が必要 | PayPayポイントコード | アプリにログインしてポイントを受け取る |
| Amazonギフトカード | ギフトコードをAmazonアカウント上で登録 |
| 楽天ギフトカード | 楽天IDでログインして受け取り |
登録が不要 | コンビニ系ギフト(ローソン、ファミマなど) | URLを開いて店頭でバーコードを提示 |
| QUOカードPay | URLを開くだけで利用可能(アプリ不要) |
従業員や顧客にギフトを配布する際は、アカウント登録の有無を事前に案内しておくことが大切です。
特に、PayPayやAmazonなどアカウント登録が必要なブランドでは、「受け取る前にアカウントを作成しておいてください」と伝えておくと、受け取りがスムーズになります。
Q: 受け取ったギフトはいつまで使えますか?
ギフトの種類によって有効期限が異なります。
主なデジタルギフトの有効期限例
Amazonギフトカード:発行から10年
PayPayポイントコード:特に期限の記載なし
QUOカードPay:発行から3年
コンビニ系ギフト:発行から数ヶ月〜1年程度(ギフトによる)
Q: スマートフォンがなくても受け取れますか?
ギフトの種類によって異なります。
基本的にスマートフォンでの受け取りを前提にUI/UXは設計されていますが、たとえばAmazonギフトカード(メールタイプ)のように、ECでの購入に使われることを想定したデジタルギフトの場合、PCで受け取ることも可能です。
企業で配布する際は、受け取る人のデバイス環境を考慮し、PCでも利用可能なギフトを選ぶか、複数の選択肢から選べるタイプを活用すると、より多くの人に受け取ってもらえます。
受け取り時のトラブル対処法
デジタルギフトを受け取る際には、さまざまなエラーが発生することも少なくありません。ここでは特によく起こるトラブルとその解決方法、さらに企業側で対応が必要になるケースを具体的に紹介します。
よくある受け取りエラーと対処法
デジタルギフトの受け取りでよく起こるトラブルは以下3つです。
ギフトコードの入力ミス
有効期限切れ
重複入力によるエラー
もっとも多いのは入力の間違いです。O(オー)とQ(キュー)、1(イチ)とI(アイ)など、似た文字を打ち間違えるケースが目立ちます。
これを防ぐには、手入力ではなくコピー&ペーストを推奨すると効果的です。大文字と小文字の区別が必要な場合もあるため、その点も案内しておくと安心でしょう。
有効期限切れは、配布から受け取りまで時間が空いてしまうことで発生するトラブルです。多くのデジタルギフトには期限が設定されており、過ぎてしまうと無効になります。
対策としては、配布時に期限を明示しておくこと、さらに期限が近づいたらリマインド通知を送ることが効果的です。企業側では受け取り状況を定期的にチェックし、未利用の人がいたらフォローを入れることも有効です。
重複入力によるエラーは、同じコードを複数回入力すると発生します。キャンペーン対象者などには「受け取り完了画面をスクリーンショットしておくと安心」と伝えると、あとから確認できるためトラブル予防につながります。
企業側での対応が必要なケース
企業としてサポートが必要になるのは以下の3つのケースです。
システム障害
配布情報の誤送信
退職者への処理
システム障害が発生した場合は、提供元へ速やかに問い合わせ、ギフトを受け取った人には状況をわかりやすく説明することが不可欠です。復旧の見込みや代替手段があればあわせて共有し、不安を和らげる対応を心がけましょう。
配布情報の誤送信には、宛先の誤りや金額・期限の記載ミスなどがあります。正しい情報を再送するだけでなく、誤って送ったデータを無効化することが必要です。特に金額を間違えた場合は、既に受け取りを完了した人との調整も必要になるため、公平性を保つルールを事前に定めておくと安心です。
福利厚生としてギフト付与するのであれば、退職者への対応については、未受け取りのデジタルギフトが残っていないか確認することが重要です。多くの場合は個人アカウントに紐づくため権利移行は難しいですが、提供元によっては企業側で無効化できる場合もあります。
労務担当者と連携して、退職手続きに「デジタルギフトの受け取り状況確認」を組み込んでおくと、無駄なコストを防げます。
BtoE活用時の運用ポイント
企業がデジタルギフトを特に福利厚生(Business to Employee)として活用する場合、運用上のポイントがいくつか存在します。本章では、そのポイントを詳しく解説します。
従業員への配布・サポートの工夫
デジタルギフトを社内で配布する際には、タイミングと方法をあらかじめ決めておくことが大切です。
たとえば、四半期の成果発表や年末のインセンティブで一斉配布する場合は、事前に説明会を開き、受け取り方を周知しておくと混乱を防げます。
個別配布であれば、上司から直接渡すスタイルを取り入れると、確実に届けられるうえに「特別感」も演出できます。
サポート体制では、社内ヘルプデスクやFAQの整備が役立ちます。
アプリの使い方、コードが見つからないときの対応、受け取り確認の方法など、よくある質問をまとめておけば、人事や総務がスムーズに対応できます。
さらに電話だけでなく、チャットやメールなど複数の窓口を設けると、従業員の状況に合わせた柔軟なサポートが可能です。
また、従業員のデジタルリテラシーには差があるため、段階的なサポートも欠かせません。慣れている人には簡潔な手順書を、操作が苦手な人には図解入りのマニュアルを用意するなど、必要に応じてサポートの方法を切り替えると安心です。
注意点とコンプライアンス対応
デジタルギフトを企業で活用する際には、税務・個人情報への配慮が必要です。
まず税務面では、場合によっては「現物給与」とみなされ課税対象になる可能性があります。金額や配布頻度によって処理が変わるため、その点については、貴社の人事や経理のご担当者に直接お問い合わせください。
次に個人情報の取り扱いです。受け取り履歴や利用状況は個人情報に当たるため、アクセス権限を制限し不要な閲覧を防ぎましょう。情報漏洩のリスクを最小限に抑えられます。
まとめ|デジタルギフトの受け取りをマスターしてBtoB活用を成功させる
デジタルギフトの受け取り方の基本は、「通知を受け取る → コードを入力する → 本人確認 → 受け取り完了」という4ステップです。
PayPayポイントコードはアプリ経由、Amazonや楽天はWebサイトから、コンビニ系はアプリまたは店頭受け取りなど複数の方法に対応しており、それぞれの仕組みに特徴があります。
BtoEで効果的に活用するには、従業員がスムーズに利用できるようなサポート体制を整えることが欠かせません。また、受け取りエラーが発生した際に迅速にフォローできる仕組みや、運用ルールを決めておくことも重要です。
デジタルギフトはキャンペーンの景品や社内報奨など、さまざまなシーンで活用できます。キャンペーン対象者や従業員が安心して受け取れる環境を整えれば満足度の向上につながり、最終的にはモチベーションを高め、企業全体の成長にも寄与していくでしょう。ぜひ本記事の内容をデジタルギフトのBtoB&BtoE活用にお役立てください。
デジタルギフトの受け取り方でお困りのご担当者様へ
こんなお悩みはありませんか? ・デジタルギフトの受け取り方がブランドごとに異なり、従業員への案内が大変 ・受け取り時のトラブル対応に時間がかかる ・デジタルギフトを効果的に活用し、運用負担を軽減したい
デジタルギフトの受け取り方は、URL受け取り方式、ギフトコード入力方式、アプリ経由方式の3つに大きく分けられます。企業担当者にとっては、配布するギフトがどの方式なのかを事前に把握しておくことが大切です。キャンペーンの案内などにその情報をわかりやすく盛り込めば、受け取り時の混乱を防ぎ、スムーズな運用につながります。
こうしたデジタルギフトに関する疑問については、累計7万件以上の法人導入実績を持つgiftee for Businessの担当者がご相談を承ります。導入検討段階のご質問から具体的な運用設計まで対応していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。